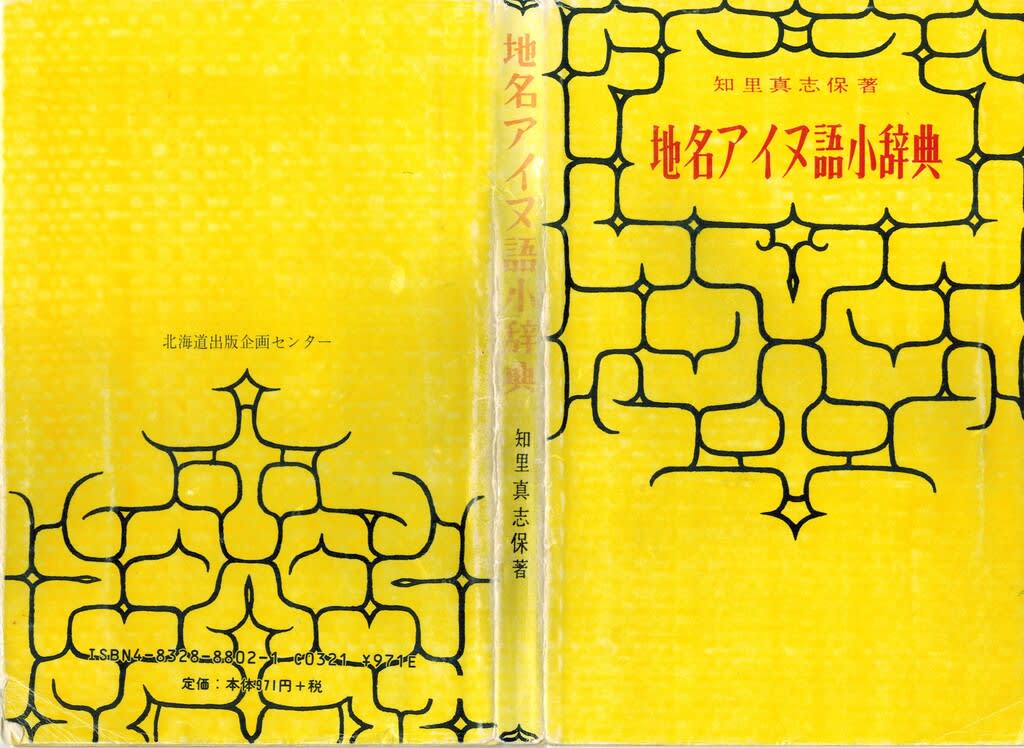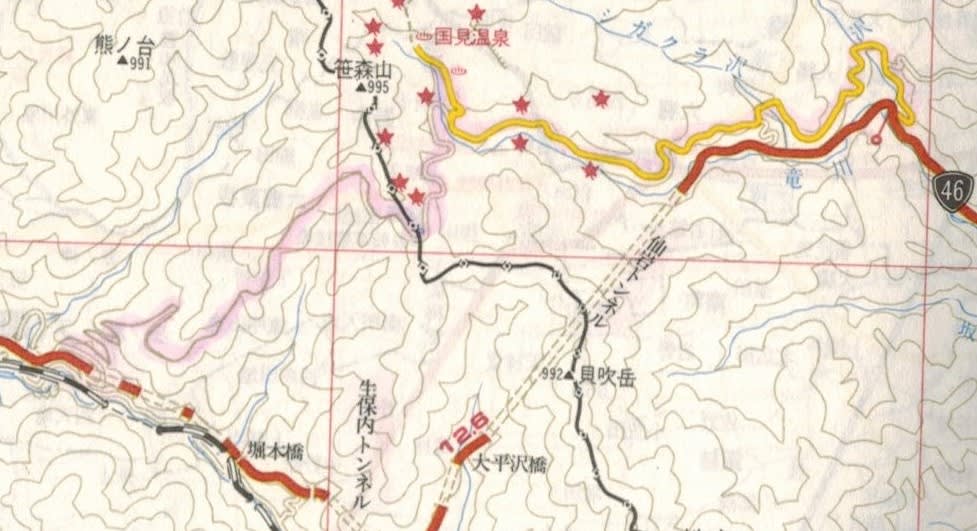今日は、神吉翕次郎〔かんき・きゅうじろう〕についてのお尋ねです。

しずかな朴:
『御料局測量課長 神足勝記日記 ―林野地籍の礎を築く―』日本林業調査会(J-FIC)の「人名録」643ページ上に神吉翕次郎氏のことを書いておきました。
「内科医。徳川慶喜主治医。日光で内科医を開業していた時に神足が治療を
受ける。津田季穂(画家)は5男。」
このうち、「徳川慶喜主治医」と「津田季穂」の件はネット検索で知ったことですが、「内科医」については『神足日記』に次のように出てきます。
「昭和9年7月1日 四十余年前、牛込矢来町住居当時係り医として懇意に
せし医学士神吉翕次郎来訪」
神足が牛込矢来町に住むのは明治25年11月30日からです。このころ神吉氏もこの近くにいたものと見られます。
その後、明治33年7月に、神足は岩村通俊局長らに従って日光の中禅寺湖付近の調査に出ますが、その折の13日の項に「神吉〔翕次郎〕医学士を訪ふ」と書いています。
この後はしばらく音信はなかったようですが、昭和9年になって神足が陸軍と海軍に各5000円ずつ「国防費献金」を行ったことが新聞に掲載されると、それを見た神吉氏が7月1日に訪ねてきたというわけです。
神足とは、この時の来訪があって後、11年までの間に時候挨拶などのやり取りが見られますが、12年7月に勝記が亡くなりますから、詳しいことはわからないまま終わってしまいます。
なお、神吉翕次郎という人は矍鑠〔かくしゃく〕とした人で、勝記のご子息勝孝氏の『日記』の昭和18年10月24日に「神吉翕次郎翁来宅」と出てきます。神吉氏は勝記よりも5歳ほど年下です。
画家・津田季穂の父ということでもあり、できれば知りたいと思っています。このルート〔経路〕を手掛かりにいくらか情報入手方法を試みたこともましたが、力及ばず、これまでのところ手掛かりを得られておりません。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただければ幸いです。

もう一つ:
神足勝孝氏の日記の件でお願いがあります。
勝孝氏は、海軍中将にまで昇進した火薬・爆薬の研究者〔研究職の軍人〕でした。
勝記と同様に、ご子息の勝孝氏についても、ミカン箱3箱分ほど、日記ほかの文書を残されています。これについても、私はご遺族の神足勝文様からお借りして全部を拝読しました。
そのうち、日記については『神足勝孝日記』と題してパソコンに入力整理しました。
簡単に概要を書きますと、A4判・横長ファイルを使って、裏表印刷で打ち出したものをファイルしてあります。それが、
ファイル1 昭和12~15年
ファイル2 昭和16~22年
ファイル3 昭和23~29年
ファイル4 昭和30~35・38年
ファイル5 昭和39~42・50・52・53年
となっています。ざっと30年余分あります。
内容からは戦時中の軍港・舞鶴のようすや、戦後の追放令の中での動向など、さらにお住いの鎌倉・藤沢近辺のようすがわかります。
これについて、「原本は〔当面〕寄託」、「大澤の作業成果は寄贈」、ということで相談できる図書館・公文書館・大学・研究機関などございましたら、ぜひお知らせいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。