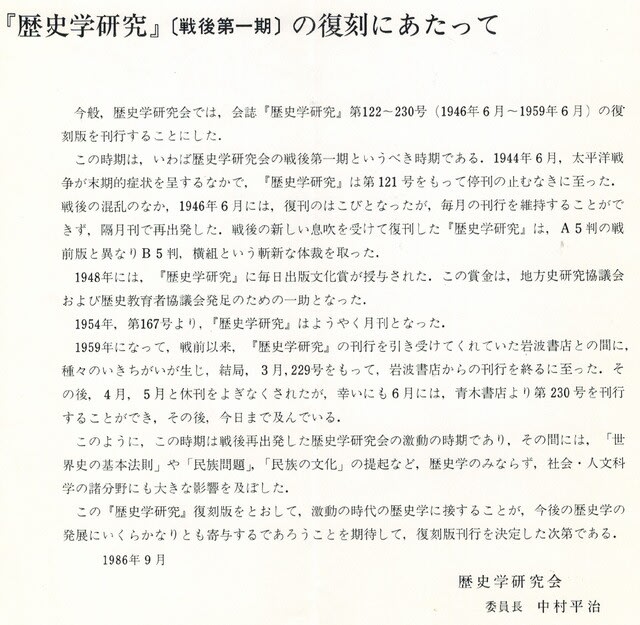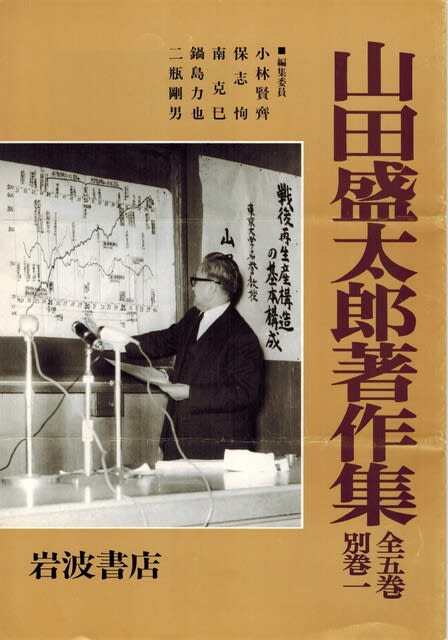(1)きょうは、下に『近世地方経済史料』を載せました。
各分野とも、先行研究者になっている人は(その中でも草分けといわれるような研究者)は、たいがいなにがしかの苦労をして史料発掘をしているものです。それも1点や2点ではなく、その分野の研究が広く注目されるようになる数量、そして、それなりの質のものであるということがあります。
(2)これは、たとえば、疑問をもって研究を始めてみたものの、手掛かりになる史料や研究材料が見当たらない、いったいあるのかないのか、それもわからない。暗中模索で取り組んでいるうちに、次第に光明が見え始め、手探りでたどっていったところ、ようやく出てきて、しかもそれが結果としてその分野の確立につながるようなきっかけになったというようなことです。
(3)これに対して、ちょっとおこがましいですが、私が『戦前期皇室財政統計』(法政大学日本統計研究所、1995年)を作った時は、少し違いました。
No.472で紹介した香田徹也氏インタビューで答えていましたが、史料は「富士見櫓」にリンゴ箱か何かに入れて保管されていました。しかし、当時は、情報公開法制定前で、香田さんのような林業関係の役人をやっていたような人でも簡単には近づく機会を得られませんでした。ですから、私は、株主名簿、株式年鑑、社史などから一つ一つ数字を拾って、当時としてどこまで接近できるのかをやったわけです。
(4)つまり、私の場合は、元の資料がないのではなくて、あるけど「内部資料」として「秘匿」されていて閲覧できなかったわけです。
もちろん、いまは情報公開法制定によって元の資料を見ることができます。ですから、私は、さっそく作り直しに取り組んで、すでにコロナ蔓延の前に原稿を仕上げ終えました。もっか未公開ですが、公開もやぶさかではありませんから、大学や公的機関なら、提供可です。
(5)繰り返しになりますが、言いたいのは、史料があるのはわかっていたけど、見られなかったから、迂回して「苦労して作った」ということです。
どのくらい苦労したか? それはもう、いいことにしましょう。
(6)おっとっと!毎度の脱線です。
要するに、先行研究、中でも開拓者は、想像できないくらい苦労はしている、ということです。
もっともね、「苦労の跡がわかるようではたいしたことない」、ということも大事なことです。
そういうのは、電車の中で化粧をしている・・・みたいなことです。

バラが公園の藪の中で首をもたげて咲いてました。
【コレクション 244 近世地方経済史料】
このパンフは、B5判8㌻です。B5判4枚分の横長の用紙を二つ折りし、それを再度二つ折りしてできています。ですから、広げるとまず6・7㌻が現われ、さらに広げると2~5㌻が現われます。下には、このうちの1・6(の一部)・8㌻を載せました。
このほかのページは次のようになっています。
2~5㌻ 全10巻の収載書目と解題
6㌻の一部~7㌻ 本文組方見本
6ページに児玉幸多氏の推薦文、8㌻に刊行案内・編者略歴・全冊の装丁見本が出ていますから、残余の説明は略します。
1㌻

6㌻(一部)

8㌻

以上です。
きょうはここで。あす28日(水)の分はお休みです。
なお、このブログはNo.500をもって終了とします。
(とりあえずのお断りですが、苦情やご意見などがある場合は早めにお寄せください。)

白い点の🐞さんです。
きょうは、久しぶりに、懐かしい人からお電話を頂戴しました。