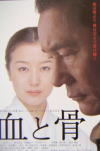
原作は1920年代から1980年代までの日本を舞台に、
朝鮮半島から日本に渡ってきた在日1世の半生を描く大河ドラマです。
映画では戦前戦中のエピソードを割愛して、
主人公とその周辺の人々が戦後日本をどう生き抜いたかをひたすら追いかけて
います。
こうして主人公の青春期を切り捨ててしまうことで、
強烈な個性を持つひとりの“父親”と、
家族や息子の関わりというテーマを描くことに専念しています。
しかし、まったく戦中の話が出てこないかというとそうでもなく、
断片的に登場して、それをナレーションで繋いでいるのですが、少し分かりに
くい…。
蛇足ながら整理すると、こんな風になります。
大阪の蒲鉾工場で働く金俊平は、
幼い娘を抱えて飲み屋を営み、必死で生きている李英姫(鈴木京香)にひと目
惚れ、
英姫を強姦し、強引に結婚。
その後二人の間には花子と正雄が生まれる。
戦況が厳しくなると金俊平は失踪するが、むしろ家族は安堵の生活をおくる。
戦争が終わると金俊平は舞い戻り、呆然とする李英姫を挨拶代わりに再び襲っ
て、
家族を一度見捨てたことを恥じるどころか、暴力亭主として君臨する。
大酒を飲んでは牙をむき、家財道具を破壊して外へ放り出して荒れ狂う俊平
に、
家族は無論、近所の住人すべてが怯えて暮らす毎日がやってくる。
戦時中に親日を貫いて、終戦の時、朝鮮学校の校庭でつる仕上げを食う
大山こと金成寛(塩見三省)はのちに俊平の金貸し業の顧客として再登場しま
す。
李英姫が結婚前、紡績工場を追われる場面が唐突に挿入されています。
英姫は16歳のときに10歳の相手と結婚させられて逃げ出し離婚、
工場で働いていたが、監督者と不倫、妊娠して工場を追われる。
そのときの子が、“幼い娘を抱えて”の長女になります。
当時の父権絶対の朝鮮社会で女性の生き難さを語っているのか、
英姫という人のバイタリティを語っているのか、
たぶん両方なのでしょうが、
金俊平と結婚後は終生彼の呪縛から逃れられなかった女性なので、
外向的な強さを誇示されても、後のエピソードとの繋がりが良くなくなりま
す。
原作どおりなのかもしれませんが、
鈴木京香さんが熱演の割には、映画の掲示板で「精彩を欠く」といった批評が
目立つのは、
脚本構成上、李英姫の人物像が冒頭で伝わりにくいためではないでしょうか?
むしろ中盤以降、陰で子供たちを支える姿などを強調したほうが、
忍従の女の一生が伝わったかも…。
いや、李英姫という人は、単純に“耐える妻”というわけではないので、
やっぱりそれでは不味いか。
「血と骨」は崔洋一監督が6年の歳月をかけて映画化に漕ぎ着けた作品で、
主人公・金俊平には当初から北野たけしをイメージしていたといいます。
たけし監督も数々の暴力映画を監督してますが、
北野ブルーに象徴される透明感はなくて、もっと暑苦しい世界観です。
6年というと長い気がしますが、監督に言わせると『月はどっちに出ている』
は、
12年かかったそうですから粘着質なのですね、崔監督は。
一方で「クイール」のようなプログラムピクチャーを、しれっとして演出して
います。
「刑務所の中」はうちのメーリングリストのオフ会でみんなで見てますが、
「塀の中の懲りない面々」のような浪花節はないです。
ナレーションも長ぜりふも必要なら使うけど、能書きで
映画を見せるタイプの演出ではないです。
時は流れ、英姫の連れ子である春美(唯野未歩子)は、
俊平の弟分の高信義(松重豊)と結婚。
俊平は蒲鉾工場を立ち上げ、信義、元山(北村一輝)らを従えて事業を動か
し、
小金を得ていた。そんな折、「俊平の息子」と名乗る、朴武(オダギリジョ
ー)が現れる。
済州島で俊平が15才の時に人妻を寝取った際に生まれた実の息子だという。
武は俊平の家に転がり込むと女まで呼び寄せ、好き勝手に振舞うようにな
る。
複雑な思いを抱く英姫とは対照的に、
恐ろしい父親にびくともしない武に羨望の眼差しを向ける正雄。
しばらくして武は、俊平から金をもらって出て行こうとするが、
家族にはビタ一文使う気のない俊平と大乱闘になる。
映画では特に触れられてませんが、俊平はもともと蒲鉾職人としての下地が
あります。
俊平が職人に鉄拳制裁をふるって、労働基準法無視の搾取でこがねをため込ん
だように
見えてしまいますが、当時は戦後の物資統制下にあって、蒲鉾が庶民には手に
入りにくい
希少価値があったという背景が在ります。
プロダクション・ノートなどを見ますと、当時の大阪の蒲鉾工場の様子を今に
伝える資料が
皆無に近く、スタッフは大いに苦労させられたようです。
ここまで書けばおのずと気が付かれると思いますが、
俊平が起こす嵐を描けば自然と大阪の朝鮮長屋の風俗史を語ることとなり、
一家一族のごたごたを活写すれば、おのずとサーガを描きあげることとなりま
す。
崔監督の狙いはまさしくその一点にあるようで、
2時間半近い映画でありながら、それ以外の余分なものが一切ありません。
オダギリジョーが演ずる武という馬鹿息子はあっという間に死んでしまいます
が、
作中では魅力的に描かれています。
雨の中の俊平との最後の乱闘は彼が勝ったように見えませんが、
別れ際に英姫から金を貰っていることや、弟の正雄に「勉強せいや」と最後の
言葉を
かけていること、そして俊平に対して常に「アボジ(親父)よ」と呼びかけて
いることからも、武が…
この続きはhttp://www.cam.hi-ho.ne.jp/la-mer/Pic-chitohone.htmlにて「血と骨」脚本レビュー公開

朝鮮半島から日本に渡ってきた在日1世の半生を描く大河ドラマです。
映画では戦前戦中のエピソードを割愛して、
主人公とその周辺の人々が戦後日本をどう生き抜いたかをひたすら追いかけて
います。
こうして主人公の青春期を切り捨ててしまうことで、
強烈な個性を持つひとりの“父親”と、
家族や息子の関わりというテーマを描くことに専念しています。
しかし、まったく戦中の話が出てこないかというとそうでもなく、
断片的に登場して、それをナレーションで繋いでいるのですが、少し分かりに
くい…。
蛇足ながら整理すると、こんな風になります。
大阪の蒲鉾工場で働く金俊平は、
幼い娘を抱えて飲み屋を営み、必死で生きている李英姫(鈴木京香)にひと目
惚れ、
英姫を強姦し、強引に結婚。
その後二人の間には花子と正雄が生まれる。
戦況が厳しくなると金俊平は失踪するが、むしろ家族は安堵の生活をおくる。
戦争が終わると金俊平は舞い戻り、呆然とする李英姫を挨拶代わりに再び襲っ
て、
家族を一度見捨てたことを恥じるどころか、暴力亭主として君臨する。
大酒を飲んでは牙をむき、家財道具を破壊して外へ放り出して荒れ狂う俊平
に、
家族は無論、近所の住人すべてが怯えて暮らす毎日がやってくる。
戦時中に親日を貫いて、終戦の時、朝鮮学校の校庭でつる仕上げを食う
大山こと金成寛(塩見三省)はのちに俊平の金貸し業の顧客として再登場しま
す。
李英姫が結婚前、紡績工場を追われる場面が唐突に挿入されています。
英姫は16歳のときに10歳の相手と結婚させられて逃げ出し離婚、
工場で働いていたが、監督者と不倫、妊娠して工場を追われる。
そのときの子が、“幼い娘を抱えて”の長女になります。
当時の父権絶対の朝鮮社会で女性の生き難さを語っているのか、
英姫という人のバイタリティを語っているのか、
たぶん両方なのでしょうが、
金俊平と結婚後は終生彼の呪縛から逃れられなかった女性なので、
外向的な強さを誇示されても、後のエピソードとの繋がりが良くなくなりま
す。
原作どおりなのかもしれませんが、
鈴木京香さんが熱演の割には、映画の掲示板で「精彩を欠く」といった批評が
目立つのは、
脚本構成上、李英姫の人物像が冒頭で伝わりにくいためではないでしょうか?
むしろ中盤以降、陰で子供たちを支える姿などを強調したほうが、
忍従の女の一生が伝わったかも…。
いや、李英姫という人は、単純に“耐える妻”というわけではないので、
やっぱりそれでは不味いか。
「血と骨」は崔洋一監督が6年の歳月をかけて映画化に漕ぎ着けた作品で、
主人公・金俊平には当初から北野たけしをイメージしていたといいます。
たけし監督も数々の暴力映画を監督してますが、
北野ブルーに象徴される透明感はなくて、もっと暑苦しい世界観です。
6年というと長い気がしますが、監督に言わせると『月はどっちに出ている』
は、
12年かかったそうですから粘着質なのですね、崔監督は。
一方で「クイール」のようなプログラムピクチャーを、しれっとして演出して
います。
「刑務所の中」はうちのメーリングリストのオフ会でみんなで見てますが、
「塀の中の懲りない面々」のような浪花節はないです。
ナレーションも長ぜりふも必要なら使うけど、能書きで
映画を見せるタイプの演出ではないです。
時は流れ、英姫の連れ子である春美(唯野未歩子)は、
俊平の弟分の高信義(松重豊)と結婚。
俊平は蒲鉾工場を立ち上げ、信義、元山(北村一輝)らを従えて事業を動か
し、
小金を得ていた。そんな折、「俊平の息子」と名乗る、朴武(オダギリジョ
ー)が現れる。
済州島で俊平が15才の時に人妻を寝取った際に生まれた実の息子だという。
武は俊平の家に転がり込むと女まで呼び寄せ、好き勝手に振舞うようにな
る。
複雑な思いを抱く英姫とは対照的に、
恐ろしい父親にびくともしない武に羨望の眼差しを向ける正雄。
しばらくして武は、俊平から金をもらって出て行こうとするが、
家族にはビタ一文使う気のない俊平と大乱闘になる。
映画では特に触れられてませんが、俊平はもともと蒲鉾職人としての下地が
あります。
俊平が職人に鉄拳制裁をふるって、労働基準法無視の搾取でこがねをため込ん
だように
見えてしまいますが、当時は戦後の物資統制下にあって、蒲鉾が庶民には手に
入りにくい
希少価値があったという背景が在ります。
プロダクション・ノートなどを見ますと、当時の大阪の蒲鉾工場の様子を今に
伝える資料が
皆無に近く、スタッフは大いに苦労させられたようです。
ここまで書けばおのずと気が付かれると思いますが、
俊平が起こす嵐を描けば自然と大阪の朝鮮長屋の風俗史を語ることとなり、
一家一族のごたごたを活写すれば、おのずとサーガを描きあげることとなりま
す。
崔監督の狙いはまさしくその一点にあるようで、
2時間半近い映画でありながら、それ以外の余分なものが一切ありません。
オダギリジョーが演ずる武という馬鹿息子はあっという間に死んでしまいます
が、
作中では魅力的に描かれています。
雨の中の俊平との最後の乱闘は彼が勝ったように見えませんが、
別れ際に英姫から金を貰っていることや、弟の正雄に「勉強せいや」と最後の
言葉を
かけていること、そして俊平に対して常に「アボジ(親父)よ」と呼びかけて
いることからも、武が…
この続きはhttp://www.cam.hi-ho.ne.jp/la-mer/Pic-chitohone.htmlにて「血と骨」脚本レビュー公開











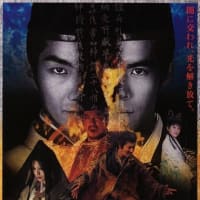


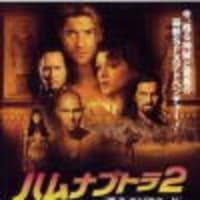

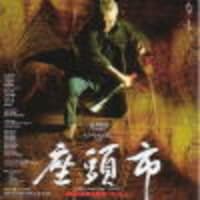
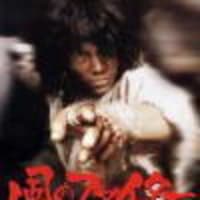



やはり、時間の関係もあってか、
前半がはしょっているので、
わかりにくい部分がありました。
原作を読んでみようと思います。
「血と骨」ではないですが、原作と映画のあらすじを比較したレビューがhttp://www.cam.hi-ho.jp/la-mer/にあります。お暇なとき是非、ごらんくださいまし。