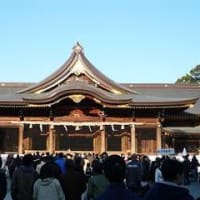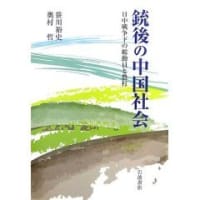「分餐制は決して『舶来品』ではない」
新华网 http://www.xinhuanet.com/politics/2020-04/04/c_1125814471.htm
新型コロナ肺炎の感染拡大の期間、分餐制が再び公衆の視野に入り込み、人々の間で議論の的となっている。分餐制は西洋由来の「舶来品」であると言う人もいるが、資料によれば、分餐制はわが国の昔から存在してきたものである。歴史の大きな流れを経て、わが国はいかにして分餐から合餐へと向かったのだろうか?
その実、われわれが常に使用している「筵席」(宴会の席)という言葉は、もともと分餐の意味を含んでいた。史料の記載によれば、「筵」と「席」は全て古代の宴会の時の地上の座具であり、昔の人の食事で「席」を用いて座る習慣があり、目の前に低い食卓を置いて、筵と席は一人ずつ設けられ、みんながそれぞれ分かれて食事をして。
中国古代の飲食方法の変化は、高いテーブルと大きな椅子の出現と密接不可分である。記載によると、唐宋時期に、高いテーブルと大きな椅子は一般的に民衆の生活の中に適用されはじめ、絶対多数の中国人は席に座る方法を放棄し、座り方の変化が完成した。これも、中国の飲食方法の分餐から合餐への転換に直接影響与えた。
アジア食学論壇主席の趙栄光は次のように語る。「中国には昔から分餐制が存在していて、これまで絶えたことはありません。例えば今のカクテルパーティ(鳩尾酒会)や、バイキング形式など、「一人食」などは、全て分餐の形式の体現です。ただ、合餐が主流になるにしたがって、分餐が古代のように一般的ではなくなっているに過ぎません」。
趙栄光は、分餐制と似たものとして、中国史上で「双筷制」による食事が流行していたことを紹介している。まず、一つの箸や匙を用いて、食べたい料理を自分の碗や皿に取り分け、さらにもう一つの箸と匙を用いて食事をする。「早くも宋の高宗時期には、二つの箸で食べる形式が出現していました。100年ほど前、中国現代医学の先駆者である伍連徳がペストと闘っている時にも、双筷制で食事をとる方法を真剣に検討していたことがあります。」趙栄光によると、その他の様々な食事の方法と比べて、双筷制は中国料理という芸術品の鑑賞と中華の食卓マナーの感受性により適っており、箸を使用することでより文化的に優雅なると考えていたという。
趙栄光によると、「中国料理のメニューの中には、魚の煮付け(清蒸鱼)など分餐の形式に合わないものもあります。分餐は魚全体の皿の美観を損ねてしまうので、双筷による食事方法により適しています」という。
2003年のSARSの期間は、分餐制と双筷制が再び提起された。合餐が様々な疾病の拡大をもたらした可能性があるということで、関連する業界や公益組織などは分餐制と双筷制の提唱に力を入れた。しかし社会認知度の不足と、住民の長い間形成されてきた合餐の習慣で改革することが難しいなどの原因のために、分餐制と双筷制を効果的に広めることが全くできなかった。
食卓は中国人にとって、食事する場所というだけではなく、様々な社会関係と人情の礼儀と密接に関係している。中国人は食事には非常にこだわりが強く、圧倒的多数の家庭にとって、合餐は団欒、幸福を象徴しており、お互いの間の感情の交流に有利である。このように、多くの人は分餐制が隔たりの感覚をもたらし食事の雰囲気を壊してしまうと考えている。
中国飯店協会会長韓明は次のように語っている。「実際は、『分』と『合』の間は絶対的に矛盾するものでは全くありません。私たちも共用の箸と匙を置くことや、双筷などの形式で食事ができます。和気藹々の雰囲気にも影響しないだけではなく、食事用具を通じて病気の拡大を避けることもできますし、より健康な文明の食卓の習慣をもたらします。」
新华网 http://www.xinhuanet.com/politics/2020-04/04/c_1125814471.htm
新型コロナ肺炎の感染拡大の期間、分餐制が再び公衆の視野に入り込み、人々の間で議論の的となっている。分餐制は西洋由来の「舶来品」であると言う人もいるが、資料によれば、分餐制はわが国の昔から存在してきたものである。歴史の大きな流れを経て、わが国はいかにして分餐から合餐へと向かったのだろうか?
その実、われわれが常に使用している「筵席」(宴会の席)という言葉は、もともと分餐の意味を含んでいた。史料の記載によれば、「筵」と「席」は全て古代の宴会の時の地上の座具であり、昔の人の食事で「席」を用いて座る習慣があり、目の前に低い食卓を置いて、筵と席は一人ずつ設けられ、みんながそれぞれ分かれて食事をして。
中国古代の飲食方法の変化は、高いテーブルと大きな椅子の出現と密接不可分である。記載によると、唐宋時期に、高いテーブルと大きな椅子は一般的に民衆の生活の中に適用されはじめ、絶対多数の中国人は席に座る方法を放棄し、座り方の変化が完成した。これも、中国の飲食方法の分餐から合餐への転換に直接影響与えた。
アジア食学論壇主席の趙栄光は次のように語る。「中国には昔から分餐制が存在していて、これまで絶えたことはありません。例えば今のカクテルパーティ(鳩尾酒会)や、バイキング形式など、「一人食」などは、全て分餐の形式の体現です。ただ、合餐が主流になるにしたがって、分餐が古代のように一般的ではなくなっているに過ぎません」。
趙栄光は、分餐制と似たものとして、中国史上で「双筷制」による食事が流行していたことを紹介している。まず、一つの箸や匙を用いて、食べたい料理を自分の碗や皿に取り分け、さらにもう一つの箸と匙を用いて食事をする。「早くも宋の高宗時期には、二つの箸で食べる形式が出現していました。100年ほど前、中国現代医学の先駆者である伍連徳がペストと闘っている時にも、双筷制で食事をとる方法を真剣に検討していたことがあります。」趙栄光によると、その他の様々な食事の方法と比べて、双筷制は中国料理という芸術品の鑑賞と中華の食卓マナーの感受性により適っており、箸を使用することでより文化的に優雅なると考えていたという。
趙栄光によると、「中国料理のメニューの中には、魚の煮付け(清蒸鱼)など分餐の形式に合わないものもあります。分餐は魚全体の皿の美観を損ねてしまうので、双筷による食事方法により適しています」という。
2003年のSARSの期間は、分餐制と双筷制が再び提起された。合餐が様々な疾病の拡大をもたらした可能性があるということで、関連する業界や公益組織などは分餐制と双筷制の提唱に力を入れた。しかし社会認知度の不足と、住民の長い間形成されてきた合餐の習慣で改革することが難しいなどの原因のために、分餐制と双筷制を効果的に広めることが全くできなかった。
食卓は中国人にとって、食事する場所というだけではなく、様々な社会関係と人情の礼儀と密接に関係している。中国人は食事には非常にこだわりが強く、圧倒的多数の家庭にとって、合餐は団欒、幸福を象徴しており、お互いの間の感情の交流に有利である。このように、多くの人は分餐制が隔たりの感覚をもたらし食事の雰囲気を壊してしまうと考えている。
中国飯店協会会長韓明は次のように語っている。「実際は、『分』と『合』の間は絶対的に矛盾するものでは全くありません。私たちも共用の箸と匙を置くことや、双筷などの形式で食事ができます。和気藹々の雰囲気にも影響しないだけではなく、食事用具を通じて病気の拡大を避けることもできますし、より健康な文明の食卓の習慣をもたらします。」