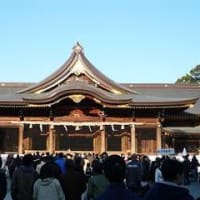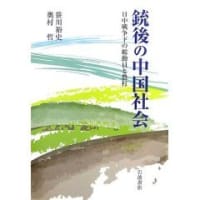王娟『近代北京慈善事業研究』(人民出版社、2010年)
第4章 近代北京地区の慈善組織
第4節 救助効果
・・・・・・・・・
1 困窮者の「福音」と怠け者(懒汉)の「温床」(181)
慈善事業の基本的な機能からみれば、貧困人員および様々な弱体集団を救助することは、慈善活動家および慈善組織がつとめて求めてきた目標であり、これは近代国家政府が進んでなすべき(当仁不让)神聖な職責である。生死の境でもがいでいる近代の貧窮人民に対して、形式的に多様な慈善活動は実際に救いの星と福音というだけではない。しかし、近代的な救助の手段は施しから教育に至る過渡的な特徴のために、これらは貧し弱い人々に生活の希望という「福音」を与えたが、同時にまた容易に社会の寄生分子を生み出す土壌となり、怠け者の「温床」となったことは、もともと救済範囲が狭く、救済の水準も低かった近代慈善事業の救助効果は、さらに小さなものとしてしまった。
積極的な点から見れば、官制の救済機関であろうと民間の慈善組織であろうと、それらの最も直接的な目標と客観的な作用は、大規模な貧民・弱者の人口を救い出し、貧民・弱者の集団の生存能力を引き上げることであった。清末から民国に至るまで、慈善活動家集団から単独の善人・善士に至るまで、政府が全面に出て運営している救済機構から社会の力量で組織された慈善団体に至るまで、数えきれないほどの貴重かつ脆弱な生命が救われ、千万を数える家庭が維持され得たのであり、大規模な貧苦の無業人員が簡単な生計の技能が与えられ、これらは慈善事業の弱者集団を救う強力な機能を十分に明らかにするものだった。
・・・・・
民国年間には粥の配給所(粥厰)が依然と林立し、直接にして迅速な救助の効果を発揮していた。たとえば民国18年から21年の間には、北京の数十か所の粥厰ではどの配給所も季節ごとに粥を受け取る人数は二十万人は下らず、全市は季節ごとに516.7万人、平均毎日5万人、毎年粥厰を運営・設立する費用は20万元を下らなかったことは、表4-8が示している通りである。これらの粥の施しを受けた貧苦人民は、これによってかろうじて余命を保つ(苟延残喘)ことができ、彼らは「家族ぐるみで(扶老携幼)、まさに熱々の粥を手に持って、しばしば手づかみでこれを食べた。帰る途中には、お互い笑って語らい、微笑ましい雰囲気にあふれていた。粥厰の門前には露店で漬物野菜が売られており、家が比較的遠い粥民は争って買い求め、夜明けの朝日(晨光熹微)の下でそれを食べていた」(張金陔「北平粥厰之研究」『社会学界』7巻、1933年)。
民国時期の北平千二百貧戸の調査が明らかにしているところでは、約67.42%の家庭が様々な救済を受けたことがあり、救済の状況はだいたい表の4-9のように示されている。しかし粥を受ける以外は、その多くはそのほかの救済を得ることはできず、これは救済形式が単一化している状況を表わすものである。
教育・訓練(教養)の手段については、貧民と流民に対して生計技能を伝授する新しいタイプの慈善機構が、教育・訓練の人員がきわめて限られていると言っても、こうした救助モデルはかえって長い目で見て意義のあるものとなっている。教育・訓練の救済方式をとる工芸局が若くて体力のある貧苦・無業の人々多く受け入れていることによって、社会の生産力と労働力を保存し、富の持続的な創造を可能にしている。たとえば京師習芸所は光緒32年の4月初1日から開設され、閏4月30日に閉鎖されているが、全部で軽犯罪者2750人、貧民646人、全部で3396人で、かつ収容・養成している貧民も次第に増えている。そのなかには、貧民の任連貴のように舅舅(母方のおじ)に身柄を引き取ってもらったのち、まだ習芸所にとどまることを望んで送還したといった例は少数ではなく、こうした小さなエピソードの戯劇性はこうした教育・訓練機構の実際の積極的な効果を反映したものである。また清末以来二十あまり創設されている龍泉寺の孤児院のように、「教養を図って18年、事業は既に成年になり、各種の技術・知識を備えさせて、自立して生を治めることができ、前後して孤児院を出て社会に奉仕する者は、既に三千余名に達している。
しかし多くが依然として初歩的な施しであり、単に収容効果を重視するだけの事前救済機関について言えば、それらは往々にして救助を実施すると同時に、実際上は不可避的に一群の社会救済機関に依存して生計を維持するような社会的に寄生した人々を生み出すことは避けられず、それによって実際の救助の効果が大きく引き下げられた。たとえば清末の、貧民の収容と流民の犯罪人の習芸所、一つは徳勝門外の習芸所、一つは広寧門外の教養局は、「両所であわせて600余名を数えるが、技能(芸事)は極めて乏しく、事実技能を身につけた者(習芸者)は百人に満たず、そのほかは飽食に安んじており、苦労して働く者もなく、毎年経費が不足している。いたずらに金銭を浪費(靡)し、享受してばかりであるが(价其享受)、これは乱を推奨して盗を勧めることと何が異なるだろうか。こうした消極的な施しの慈善事業に対して、梁啓超はかつて激しい攻撃を行っている。「慈善事業は、人を懶惰に導き、その依存心を生み出し、その廉恥の心を滅ぼすものである。このように言うのも、こうした事業が日に盛んになっているのに、貧民窟の現状はますますひどくなっているからである」(『新大陸游記』)。
2 焼け石に水(杯水車薪)と模範の機能
全体的に言えば、清末時期に設立された職業訓練所(工藝厰所)の救済の効果は焼け石に水であり、結局のところ北京社会の秩序悪化と貧困の深刻化の時代趨勢を阻止することは困難であった。これは一方では、慈善救済機関の資金の調達がずっと相当に逼迫(緊張)していて、投入された管理人員も不足かつ素質もより低く、屈辱を与えて虐待を行い、私服を肥やすなどの自ら克服できない現象が頻繁に見られたためであり、他方では、首都北京(京城)の数十万の旗漢貧困人口と数え切れないほど次々と流入してくる流民に比べると、これらの救済機構の教育・養成の対象は常に限られたものであり、多くて二三千、少なくて数十人であり、周辺の州・県の習芸救済機構にいたってはわずか数人で、薊州習芸所は部屋はたったの三間であり、習芸者は三人だけであった。光緒32年に拡充・修建された後も、習芸人員はやはり14名増えただけで、このように救助の力量は微々たるものであったと言うことができる。
しかし、慈善組織の評判と救済機構の社会的な効果は、決して一時一事の具体的な効果によるものではなく、さらにその潜在的な社会的影響を見なければならない。北京の慈善救済事業の積極的な影響は、その土地およびその土地に流れ着いた弱者集団におけるのみではなく、さらに「首善」の区である北京が全国に生み出している強大な規範性と・・
3 社会進歩の体現と社会的危機の暴露
時代の環境と制度的制約のために、伝統型でも教育型でも慈善組織と救済組織には、等しく多くの自ら克服できない古い弊害と新しい弊害が存在している。一方では、こうした弊害は慈善組織の救済機能の有効な発揮を妨げているだけではなく、事前救済組織が受ける社会制度的な制約の本質の所在を反映しており、近代社会の危機の深化および社会の弱体集団の増加によって、弊害にあふれている慈善組織は既に社会の需要を満たすことがまったくできなくなっている。他方では、人々の慈善組織と救済手段の弊害が、認識の上で次第に前面に深く入っており、不断に伝統的な慈善組織の立ち遅れと不合理を暴露・攻撃し、大きな力で慈善事業の転換を大きな力で呼びかけ、人々の主観的な意識の点から慈善組織の新陳代謝を加速させ、社会救済事業の進歩と時代の進歩を体現している。このような慈善組織の弊害に対して、弁証法的な程度で分析かつ扱わなければならない。
清末時期、官営の救済が当時の慈善救済事業の主要な特徴であったため、事前救済機構の弊害は主に管理と経費の両面に集中していた。
「新政以来、往々にして効果は著しくないのに弊はすでに深い。旧時と比べてみると、悪習でしかも理解されていないのは、一つには無駄な費用、二つには無駄な人員である。そもそも自分勝手に遣いすぎること(浮销)を無駄な費用と言うのであるが、収入に応じて支出を決めても、その全てが見た目を立派にすることに使われて全く効果を挙げないことも、無駄な費用という。凡庸で乱れた者を無駄な人員と言い、高い才能を持った時代の俊英で、肩書をあって給料を得ているが、責任がどこにあるのかを知らない者は、やは無駄な人員である。・・・・・」「各省は新政を実行し、その土地で資金集めを行っており、・・・その地方の財政に用いて、その土地の公益を運営している。・・・ただ一省の中にも、州県の貧富には差があり、富貴もまた異なる。・・・・・つまりうまく行っていない州県は、普段から上下の隔たりがあり、行政の資金調達などの仕事にも携わることなく、地方の紳士・董事に委ねている。紳士で賢い者は、面倒なことに関わることを避けようとしている。あるいは公益に熱心で、事業に力を尽くす者もいるが、官の力に頼って輿論の実情を理解できず、さらには籍端抑勒(?)、私服を肥やす者もいる。民衆(百姓)は己のことしか考えず、恨みや屈辱が沸き起こり、流言が至る所に広まり、事変を醸成している」。こうした総括と暴露は、慈善救済組織の中に対しても適用されると言うことができる。慈善的な性質をもった閲報社にも、管理が散漫になる現象が存在していた。
これらの弊害は深刻な消極的結果を導いている。一方では、政府が扶植かつ依拠すべき社会的な救助の力を大きく挫折させ、「紳士の賢者、あるいは身を清めて引き下がり、あえて関わろうとしない者もあれば、公益に熱心で、事業に力を出し、官の勢力に頼り、輿論を理解できなくなる者、さらには籍端抑勒(?)、私服を肥やす者もいる。民衆(百姓)は己のことしか考えず、恨みや屈辱が沸き起こり、流言が至る所に広まり、事変を醸成している」という厄介な(尴尬)局面を作り出していた(『宣統政紀』巻37、661頁)。他方では、援助を受ける者について言うと、遅れた慈善救済モデルと管理は容易に依存の心を形成するものであった。これは慈善事業の発展の歩みを維持困難にし、救済効果の発揮を非常に大きく制約するものであり、そして実際の救助の効果が、これによってさらに大きく削がれることになった。このように、「一杯の水、何ぞよく群生を普済せん」という、こうした感慨は珍しいものではなく、また非常に的を得た(所言極是)ものであった。結局のところその原因は、「(慈善行政は)名目は多くないということはなく、用意も周到でないということはないのだが、表面ばかりで内容がなく(徒有其表)、範囲は狭くて設置は広くなく、焼け石に水で効果をあげることが難しいだけではなく、弊害を生み出している」。(周成『地方慈善行政讲义』4頁)。
民国に入って以降は、慈善救済組織内部の弊害が克服されていないだけではなく、かえってますますひどくなっている。1923年、『益世報』は慈善組織内部の弊害に対する暴露を行っている。
慈善機関の内幕は様々である。最もはっきりしているのは、以下のものである。一つには、職員の採用は世襲制であり、父は子に伝え、子は孫に伝え、私人による運営になっている。二つには、警庁および各警区は乞食を収容し、表口から収容して、裏口から追い出しているが、これは慈善の本旨とは違うものである。この院の巡捕は乞食に対して勝手気ままに(任意)虐待して、実に残虐極まりない(惨無人道)ものである。四つには、少数の理事長が長期にわたって掌握し、誰も責任を負ったり立て直したりする人がいないことである。(「慈善機関黒幕重重」『益世報』1923年10月28日。)
ここで言われている、公の名のもとに私服を肥やす(因公肥己)、いい加減に対応する(敷衍塞責)、勝手気ままにでたらめに振舞う(任意妄為)などの弊害は、慈善救済の領域の中で普遍的に存在している。有識の士は慈善組織の弊害に対して深い憂慮を表わし、「近年、水害と旱魃による災害と飢饉が全国に遍く広がっており、中外の慈善家で救済を施す者は決して少なくなく、特に外国人の設けている救済機関は信用が明らかに高く、成績が最もよい。中国人(華人)の方面では、もとより熱心な従事者は多数を占めているが、救済に名を借りてそこから利益を得ようとする者も、やはり免れ難い。ゆえに救済の業務の前途に、影響がなくはない」。救済活動の中の弊害は、外来の救済の力量の信頼と賛助を失わせており、たとえば駐華美国賑済会は「何があろうとも、この資金は華人が行う災害救済の用には渡さない」と決定している(「美人処分賑余之計劃」『益世報』1921年10月25日)。
具体的な救済組織について言うと、管理の不備によって、育嬰堂の子供の死亡は非常に多く、そのため「社会では取りざたされていた(人言嘖嘖)」(「育嬰堂小孩死亡何多」『益世報』1923年5月19日)。粥配給所(粥厰)は救済対象を見分ける力がないため、「小康の家が粥配給所で粥を受け取って鶏や犬を飼育する」という現象が常に見られた(張金陔「北平粥厰之研究」『社会学界』第7巻、1933年)。各慈善救済機関の援助を受ける者に対する待遇も往々にして悪く、いい加減に放置されており、きわめて冷酷な待遇であった。たとえば北京の貧民教養院は、「80歳余りの老人に対して、冬の夜は地面に寝かせていた。さらに衣服の薄さや飲食の劣悪さは、状況がますますひどくなるばかりである(每况愈下)」(周震鱗「北平市社会局救済事業小史・北平特別市社会局第一習芸工厰」)。各地に設立された学校は、「過半は前代の旧制を踏襲し、民国十年以来、名目は変わっているものの、その精神の所在は、なお多くは従前のものと変わらない」(「天津急賑会開会紀」『益世報』1922年4月4日)。
民国時期には昆明市の救済機関に対して調査を行う人もおり、昆明市の男子感化院について、「受刑者(犯人)は豚小屋に住んでいるがごとくで、ベッドも布団もなく、集団で地面に臥し、窓や戸は開けっ放しで、暴風雨による痛みを味わっていた。疾病が流行し、医療・薬の設備はきわめて粗末なものであった。着てる服も全く洗濯されておらず、退院の時は入院の時と同じ服で、ひどいものだと数年あまりも服を着替えておらず、虱・蚤が集まって怪しげな臭いを発する人もいた」。「院長は一度も牢に入って見回ったことがなく、獄吏や巡警は日夜大声で叱り、受刑者は虎のように恐れていた」。40人余りが獄中で老いて死ぬよりも、連名で日本鬼子と前線で戦うことを要求したが、数十日たっても院長に会えなかったので、どうしようもなかった。受刑者は毎月死者が2、30人と自ら語っている。昆明市の救済事業の過半は消極の傾向があり、当然ながら経費が欠乏するところとなったが、しかし政府は真剣に運営せず、専門的な人材の訓練もなく、方法の多くは理に適ったものではなく、弊害は免れ難いものであった(許志致「昆明市救済事業調査」李文海・夏明方・黄興涛主編『民国時期社会調査叢編・社会保障巻』)。事実、これは決して昆明という一地域の救済の状況なのではなく、民国時期の全国的な範囲の救済組織に広く存在していた病弊の一つの典型的な代表例であった。北平市社会局局長が指摘していたように、北平の救済組織は、「職員が官僚化し、役人の地位を守ることが事業となっていて、救済を事業となっていない」「施設が粗末であるために、混乱して無秩序である(凌乱无章)。規約は不備で、初めは規約を具えていたが、きちんと成文化していたが、実際は依然として旧態依然であり、全体として放任されている」「要するに、形式があって精神がなく、名義があって実質がないのである」(周震鱗「北平市社会局救済事業小史・北平特別市社会局第一習芸工厰」)。さらに、「極めて苦しい生活(水深火热)に置かれた被災民たち」は、「老人も幼児も関係なく、誰もが黄色い顔色で瘠せており、表情は悲しげである」「戦争の前は400余りあった部屋が半分しかなくなってしまい、41頃あった田地は28頃に減ってしまった」が、「災害調査の人を歓迎するために、川を渡って十里あまりの隣の鎮に行って粗塩を買って焼飯を作った」というのも(善後救済総署『冀熱平津文署一年来的振務』4頁)、よくあることであった。
政府が主体となって運営する救済事業と民間の慈善事業の中に含まれている近代社会保障のシステムは、既に西洋の先進的な慈善思想と救済制度を参考にし、体系的な建設の道を歩み始めたものの、社会制度の制約によって依然として多くの弊害と不合理な要素を充満させていた。このように、清末の民国時期の北京地区の慈善組織と救済機関に対する考察は、一方ではこうした機関や組織の管理の点での弊害をはっきりと暴露し、当時の社会的な危機が深刻である歴史事実を表すものであったが、他方では慈善組織の具体的な運営やその発展・変化は、社会救済事業の進歩と希望を反映するものでもあった。こうした二重の考察の経路は、我々が近代の慈善組織が歴史発展の規律の正確な標準に合致していると評価すべきものである。
第4節 救助効果
・・・・・・・・・
1 困窮者の「福音」と怠け者(懒汉)の「温床」(181)
慈善事業の基本的な機能からみれば、貧困人員および様々な弱体集団を救助することは、慈善活動家および慈善組織がつとめて求めてきた目標であり、これは近代国家政府が進んでなすべき(当仁不让)神聖な職責である。生死の境でもがいでいる近代の貧窮人民に対して、形式的に多様な慈善活動は実際に救いの星と福音というだけではない。しかし、近代的な救助の手段は施しから教育に至る過渡的な特徴のために、これらは貧し弱い人々に生活の希望という「福音」を与えたが、同時にまた容易に社会の寄生分子を生み出す土壌となり、怠け者の「温床」となったことは、もともと救済範囲が狭く、救済の水準も低かった近代慈善事業の救助効果は、さらに小さなものとしてしまった。
積極的な点から見れば、官制の救済機関であろうと民間の慈善組織であろうと、それらの最も直接的な目標と客観的な作用は、大規模な貧民・弱者の人口を救い出し、貧民・弱者の集団の生存能力を引き上げることであった。清末から民国に至るまで、慈善活動家集団から単独の善人・善士に至るまで、政府が全面に出て運営している救済機構から社会の力量で組織された慈善団体に至るまで、数えきれないほどの貴重かつ脆弱な生命が救われ、千万を数える家庭が維持され得たのであり、大規模な貧苦の無業人員が簡単な生計の技能が与えられ、これらは慈善事業の弱者集団を救う強力な機能を十分に明らかにするものだった。
・・・・・
民国年間には粥の配給所(粥厰)が依然と林立し、直接にして迅速な救助の効果を発揮していた。たとえば民国18年から21年の間には、北京の数十か所の粥厰ではどの配給所も季節ごとに粥を受け取る人数は二十万人は下らず、全市は季節ごとに516.7万人、平均毎日5万人、毎年粥厰を運営・設立する費用は20万元を下らなかったことは、表4-8が示している通りである。これらの粥の施しを受けた貧苦人民は、これによってかろうじて余命を保つ(苟延残喘)ことができ、彼らは「家族ぐるみで(扶老携幼)、まさに熱々の粥を手に持って、しばしば手づかみでこれを食べた。帰る途中には、お互い笑って語らい、微笑ましい雰囲気にあふれていた。粥厰の門前には露店で漬物野菜が売られており、家が比較的遠い粥民は争って買い求め、夜明けの朝日(晨光熹微)の下でそれを食べていた」(張金陔「北平粥厰之研究」『社会学界』7巻、1933年)。
民国時期の北平千二百貧戸の調査が明らかにしているところでは、約67.42%の家庭が様々な救済を受けたことがあり、救済の状況はだいたい表の4-9のように示されている。しかし粥を受ける以外は、その多くはそのほかの救済を得ることはできず、これは救済形式が単一化している状況を表わすものである。
教育・訓練(教養)の手段については、貧民と流民に対して生計技能を伝授する新しいタイプの慈善機構が、教育・訓練の人員がきわめて限られていると言っても、こうした救助モデルはかえって長い目で見て意義のあるものとなっている。教育・訓練の救済方式をとる工芸局が若くて体力のある貧苦・無業の人々多く受け入れていることによって、社会の生産力と労働力を保存し、富の持続的な創造を可能にしている。たとえば京師習芸所は光緒32年の4月初1日から開設され、閏4月30日に閉鎖されているが、全部で軽犯罪者2750人、貧民646人、全部で3396人で、かつ収容・養成している貧民も次第に増えている。そのなかには、貧民の任連貴のように舅舅(母方のおじ)に身柄を引き取ってもらったのち、まだ習芸所にとどまることを望んで送還したといった例は少数ではなく、こうした小さなエピソードの戯劇性はこうした教育・訓練機構の実際の積極的な効果を反映したものである。また清末以来二十あまり創設されている龍泉寺の孤児院のように、「教養を図って18年、事業は既に成年になり、各種の技術・知識を備えさせて、自立して生を治めることができ、前後して孤児院を出て社会に奉仕する者は、既に三千余名に達している。
しかし多くが依然として初歩的な施しであり、単に収容効果を重視するだけの事前救済機関について言えば、それらは往々にして救助を実施すると同時に、実際上は不可避的に一群の社会救済機関に依存して生計を維持するような社会的に寄生した人々を生み出すことは避けられず、それによって実際の救助の効果が大きく引き下げられた。たとえば清末の、貧民の収容と流民の犯罪人の習芸所、一つは徳勝門外の習芸所、一つは広寧門外の教養局は、「両所であわせて600余名を数えるが、技能(芸事)は極めて乏しく、事実技能を身につけた者(習芸者)は百人に満たず、そのほかは飽食に安んじており、苦労して働く者もなく、毎年経費が不足している。いたずらに金銭を浪費(靡)し、享受してばかりであるが(价其享受)、これは乱を推奨して盗を勧めることと何が異なるだろうか。こうした消極的な施しの慈善事業に対して、梁啓超はかつて激しい攻撃を行っている。「慈善事業は、人を懶惰に導き、その依存心を生み出し、その廉恥の心を滅ぼすものである。このように言うのも、こうした事業が日に盛んになっているのに、貧民窟の現状はますますひどくなっているからである」(『新大陸游記』)。
2 焼け石に水(杯水車薪)と模範の機能
全体的に言えば、清末時期に設立された職業訓練所(工藝厰所)の救済の効果は焼け石に水であり、結局のところ北京社会の秩序悪化と貧困の深刻化の時代趨勢を阻止することは困難であった。これは一方では、慈善救済機関の資金の調達がずっと相当に逼迫(緊張)していて、投入された管理人員も不足かつ素質もより低く、屈辱を与えて虐待を行い、私服を肥やすなどの自ら克服できない現象が頻繁に見られたためであり、他方では、首都北京(京城)の数十万の旗漢貧困人口と数え切れないほど次々と流入してくる流民に比べると、これらの救済機構の教育・養成の対象は常に限られたものであり、多くて二三千、少なくて数十人であり、周辺の州・県の習芸救済機構にいたってはわずか数人で、薊州習芸所は部屋はたったの三間であり、習芸者は三人だけであった。光緒32年に拡充・修建された後も、習芸人員はやはり14名増えただけで、このように救助の力量は微々たるものであったと言うことができる。
しかし、慈善組織の評判と救済機構の社会的な効果は、決して一時一事の具体的な効果によるものではなく、さらにその潜在的な社会的影響を見なければならない。北京の慈善救済事業の積極的な影響は、その土地およびその土地に流れ着いた弱者集団におけるのみではなく、さらに「首善」の区である北京が全国に生み出している強大な規範性と・・
3 社会進歩の体現と社会的危機の暴露
時代の環境と制度的制約のために、伝統型でも教育型でも慈善組織と救済組織には、等しく多くの自ら克服できない古い弊害と新しい弊害が存在している。一方では、こうした弊害は慈善組織の救済機能の有効な発揮を妨げているだけではなく、事前救済組織が受ける社会制度的な制約の本質の所在を反映しており、近代社会の危機の深化および社会の弱体集団の増加によって、弊害にあふれている慈善組織は既に社会の需要を満たすことがまったくできなくなっている。他方では、人々の慈善組織と救済手段の弊害が、認識の上で次第に前面に深く入っており、不断に伝統的な慈善組織の立ち遅れと不合理を暴露・攻撃し、大きな力で慈善事業の転換を大きな力で呼びかけ、人々の主観的な意識の点から慈善組織の新陳代謝を加速させ、社会救済事業の進歩と時代の進歩を体現している。このような慈善組織の弊害に対して、弁証法的な程度で分析かつ扱わなければならない。
清末時期、官営の救済が当時の慈善救済事業の主要な特徴であったため、事前救済機構の弊害は主に管理と経費の両面に集中していた。
「新政以来、往々にして効果は著しくないのに弊はすでに深い。旧時と比べてみると、悪習でしかも理解されていないのは、一つには無駄な費用、二つには無駄な人員である。そもそも自分勝手に遣いすぎること(浮销)を無駄な費用と言うのであるが、収入に応じて支出を決めても、その全てが見た目を立派にすることに使われて全く効果を挙げないことも、無駄な費用という。凡庸で乱れた者を無駄な人員と言い、高い才能を持った時代の俊英で、肩書をあって給料を得ているが、責任がどこにあるのかを知らない者は、やは無駄な人員である。・・・・・」「各省は新政を実行し、その土地で資金集めを行っており、・・・その地方の財政に用いて、その土地の公益を運営している。・・・ただ一省の中にも、州県の貧富には差があり、富貴もまた異なる。・・・・・つまりうまく行っていない州県は、普段から上下の隔たりがあり、行政の資金調達などの仕事にも携わることなく、地方の紳士・董事に委ねている。紳士で賢い者は、面倒なことに関わることを避けようとしている。あるいは公益に熱心で、事業に力を尽くす者もいるが、官の力に頼って輿論の実情を理解できず、さらには籍端抑勒(?)、私服を肥やす者もいる。民衆(百姓)は己のことしか考えず、恨みや屈辱が沸き起こり、流言が至る所に広まり、事変を醸成している」。こうした総括と暴露は、慈善救済組織の中に対しても適用されると言うことができる。慈善的な性質をもった閲報社にも、管理が散漫になる現象が存在していた。
これらの弊害は深刻な消極的結果を導いている。一方では、政府が扶植かつ依拠すべき社会的な救助の力を大きく挫折させ、「紳士の賢者、あるいは身を清めて引き下がり、あえて関わろうとしない者もあれば、公益に熱心で、事業に力を出し、官の勢力に頼り、輿論を理解できなくなる者、さらには籍端抑勒(?)、私服を肥やす者もいる。民衆(百姓)は己のことしか考えず、恨みや屈辱が沸き起こり、流言が至る所に広まり、事変を醸成している」という厄介な(尴尬)局面を作り出していた(『宣統政紀』巻37、661頁)。他方では、援助を受ける者について言うと、遅れた慈善救済モデルと管理は容易に依存の心を形成するものであった。これは慈善事業の発展の歩みを維持困難にし、救済効果の発揮を非常に大きく制約するものであり、そして実際の救助の効果が、これによってさらに大きく削がれることになった。このように、「一杯の水、何ぞよく群生を普済せん」という、こうした感慨は珍しいものではなく、また非常に的を得た(所言極是)ものであった。結局のところその原因は、「(慈善行政は)名目は多くないということはなく、用意も周到でないということはないのだが、表面ばかりで内容がなく(徒有其表)、範囲は狭くて設置は広くなく、焼け石に水で効果をあげることが難しいだけではなく、弊害を生み出している」。(周成『地方慈善行政讲义』4頁)。
民国に入って以降は、慈善救済組織内部の弊害が克服されていないだけではなく、かえってますますひどくなっている。1923年、『益世報』は慈善組織内部の弊害に対する暴露を行っている。
慈善機関の内幕は様々である。最もはっきりしているのは、以下のものである。一つには、職員の採用は世襲制であり、父は子に伝え、子は孫に伝え、私人による運営になっている。二つには、警庁および各警区は乞食を収容し、表口から収容して、裏口から追い出しているが、これは慈善の本旨とは違うものである。この院の巡捕は乞食に対して勝手気ままに(任意)虐待して、実に残虐極まりない(惨無人道)ものである。四つには、少数の理事長が長期にわたって掌握し、誰も責任を負ったり立て直したりする人がいないことである。(「慈善機関黒幕重重」『益世報』1923年10月28日。)
ここで言われている、公の名のもとに私服を肥やす(因公肥己)、いい加減に対応する(敷衍塞責)、勝手気ままにでたらめに振舞う(任意妄為)などの弊害は、慈善救済の領域の中で普遍的に存在している。有識の士は慈善組織の弊害に対して深い憂慮を表わし、「近年、水害と旱魃による災害と飢饉が全国に遍く広がっており、中外の慈善家で救済を施す者は決して少なくなく、特に外国人の設けている救済機関は信用が明らかに高く、成績が最もよい。中国人(華人)の方面では、もとより熱心な従事者は多数を占めているが、救済に名を借りてそこから利益を得ようとする者も、やはり免れ難い。ゆえに救済の業務の前途に、影響がなくはない」。救済活動の中の弊害は、外来の救済の力量の信頼と賛助を失わせており、たとえば駐華美国賑済会は「何があろうとも、この資金は華人が行う災害救済の用には渡さない」と決定している(「美人処分賑余之計劃」『益世報』1921年10月25日)。
具体的な救済組織について言うと、管理の不備によって、育嬰堂の子供の死亡は非常に多く、そのため「社会では取りざたされていた(人言嘖嘖)」(「育嬰堂小孩死亡何多」『益世報』1923年5月19日)。粥配給所(粥厰)は救済対象を見分ける力がないため、「小康の家が粥配給所で粥を受け取って鶏や犬を飼育する」という現象が常に見られた(張金陔「北平粥厰之研究」『社会学界』第7巻、1933年)。各慈善救済機関の援助を受ける者に対する待遇も往々にして悪く、いい加減に放置されており、きわめて冷酷な待遇であった。たとえば北京の貧民教養院は、「80歳余りの老人に対して、冬の夜は地面に寝かせていた。さらに衣服の薄さや飲食の劣悪さは、状況がますますひどくなるばかりである(每况愈下)」(周震鱗「北平市社会局救済事業小史・北平特別市社会局第一習芸工厰」)。各地に設立された学校は、「過半は前代の旧制を踏襲し、民国十年以来、名目は変わっているものの、その精神の所在は、なお多くは従前のものと変わらない」(「天津急賑会開会紀」『益世報』1922年4月4日)。
民国時期には昆明市の救済機関に対して調査を行う人もおり、昆明市の男子感化院について、「受刑者(犯人)は豚小屋に住んでいるがごとくで、ベッドも布団もなく、集団で地面に臥し、窓や戸は開けっ放しで、暴風雨による痛みを味わっていた。疾病が流行し、医療・薬の設備はきわめて粗末なものであった。着てる服も全く洗濯されておらず、退院の時は入院の時と同じ服で、ひどいものだと数年あまりも服を着替えておらず、虱・蚤が集まって怪しげな臭いを発する人もいた」。「院長は一度も牢に入って見回ったことがなく、獄吏や巡警は日夜大声で叱り、受刑者は虎のように恐れていた」。40人余りが獄中で老いて死ぬよりも、連名で日本鬼子と前線で戦うことを要求したが、数十日たっても院長に会えなかったので、どうしようもなかった。受刑者は毎月死者が2、30人と自ら語っている。昆明市の救済事業の過半は消極の傾向があり、当然ながら経費が欠乏するところとなったが、しかし政府は真剣に運営せず、専門的な人材の訓練もなく、方法の多くは理に適ったものではなく、弊害は免れ難いものであった(許志致「昆明市救済事業調査」李文海・夏明方・黄興涛主編『民国時期社会調査叢編・社会保障巻』)。事実、これは決して昆明という一地域の救済の状況なのではなく、民国時期の全国的な範囲の救済組織に広く存在していた病弊の一つの典型的な代表例であった。北平市社会局局長が指摘していたように、北平の救済組織は、「職員が官僚化し、役人の地位を守ることが事業となっていて、救済を事業となっていない」「施設が粗末であるために、混乱して無秩序である(凌乱无章)。規約は不備で、初めは規約を具えていたが、きちんと成文化していたが、実際は依然として旧態依然であり、全体として放任されている」「要するに、形式があって精神がなく、名義があって実質がないのである」(周震鱗「北平市社会局救済事業小史・北平特別市社会局第一習芸工厰」)。さらに、「極めて苦しい生活(水深火热)に置かれた被災民たち」は、「老人も幼児も関係なく、誰もが黄色い顔色で瘠せており、表情は悲しげである」「戦争の前は400余りあった部屋が半分しかなくなってしまい、41頃あった田地は28頃に減ってしまった」が、「災害調査の人を歓迎するために、川を渡って十里あまりの隣の鎮に行って粗塩を買って焼飯を作った」というのも(善後救済総署『冀熱平津文署一年来的振務』4頁)、よくあることであった。
政府が主体となって運営する救済事業と民間の慈善事業の中に含まれている近代社会保障のシステムは、既に西洋の先進的な慈善思想と救済制度を参考にし、体系的な建設の道を歩み始めたものの、社会制度の制約によって依然として多くの弊害と不合理な要素を充満させていた。このように、清末の民国時期の北京地区の慈善組織と救済機関に対する考察は、一方ではこうした機関や組織の管理の点での弊害をはっきりと暴露し、当時の社会的な危機が深刻である歴史事実を表すものであったが、他方では慈善組織の具体的な運営やその発展・変化は、社会救済事業の進歩と希望を反映するものでもあった。こうした二重の考察の経路は、我々が近代の慈善組織が歴史発展の規律の正確な標準に合致していると評価すべきものである。
-------------------------------
前にも紹介した王娟の著作『近代北京慈善事業研究』の一部を抄訳した。
民国時期には社会主義ではなく、西欧あるいは日本に近い形での社会保障政策が展開される可能性があった。結果的にそれは抗日戦争以降の歴史的展開のなかで挫折することになったのだが、そうした大きな歴史的な要因の前に、既存の慈善団体との深刻な対立と矛盾を理解することが重要である。
民国時期の慈善団体に否定的な側面があったことは事実であろうが、それを単に否定的なものとしてのみ描き出すことには違和感がある。慈善団体の中に存在していたはずの、連帯の規範や組織のメカニズムを、それ自体として描き出すこともできるのではないかと考える。