【特集】日本と亜細亜~大東亜戦争【シリーズ】について、長く連載が停止していたことをお詫び致します。
【特集】日本と亜細亜~大東亜戦争【シリーズ】第三弾「一心一徳貫徹始終~同生共死和平反共建国」②
https://blog.goo.ne.jp/shishisamurai/e/d593c589b93577e56d933c9a3af5eb0bの続きです。

孫文先生の命日に行われる中国国民党の集会の様子。
遺言の「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なお未だ成功せず、同志よって須く努力すべし)」を謳っているが、台湾人を軽視して中国共産党に妥協する現在の国民党は本当に孫文の志を継承していると言えるのであろうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前回では中国の愛国者・アジア主義者としての孫文と容共主義者・諸民族を「中華」に同化しようとする帝国主義者としての孫文を考察した。
また、日本の「対華二十一カ条要求」という帝国主義的な過ちについても触れた。
聖戦未だ成らずhttps://blog.goo.ne.jp/shishisamurai/e/439bb41311a3cd6f3f06919086900857の記事でも書いたように、大日本帝国にはアジアに対する傲りが帝国主義として現れた一方、アジア解放の意志が民族主義として表現された。
私達は日本民族主義者として帝国主義を批判すると共に、先人たちの民族主義を継承し、現代に即した形で実践するための運動を展開しているのである。
大日本帝国に存在した矛盾の克服こそ新大日本帝国の課題である。
同じように孫文にも矛盾があった。
アジア主義であると同時に、同化主義に傾いた孫文の明と暗。
この明と暗は孫文の二人の後継者に受け継がれることになる。


【汪兆銘と蒋介石】
汪兆銘は日本留学中に孫文の思想に触れて革命党に参加し、清朝の醇親王載灃を狙ったテロ未遂事件を起こし、逮捕されたが、汪の人物を見込んだ粛親王善耆に助命された。
やがて孫文の信任を得て共に活動し、中華民国の建国宣言を起草した。
蒋介石は1907年7月に日本へ渡り、東京振武学校に留学した。2年間の教育課程を修めた後、蒋介石は日本の陸軍士官学校には入学せず、1910年より日本陸軍に勤務し、新潟県高田市(現在の上越市)の第13師団高田連隊の野戦砲兵隊の隊付将校として実習を受けた。このときに経験した日本軍の兵営生活について蒋介石は、中国にあっても軍事教育の根幹にならなければならないと手本として考えていた。
蒋介石は優れた軍事的才能を有し、対軍閥戦争で活躍、国民党軍の士官学校である黄埔軍官学校の校長に抜擢された。

(孫文による蒋介石任命の辞令)
6月10日に入学式を迎えた。蒋介石は新入生に対して三民主義に命をかける幹部の養成、軍の規律を説く講話を行った。黄埔軍官学校では、組織や訓練面ではソ連式が採用されたが、日常的な軍隊生活の規律は蒋介石の東京振武学校や新潟での日本陸軍第13師団での体験が基礎となっていた。また、清朝末期の改革派大官で蒋介石が尊敬する曽国藩が説いた儒学的人生訓・処世訓も教育に反映されていた。
黄埔軍官学校はソ連の支援の下につくられたため、共産党員も教官となった。後に西安事件で監禁された蒋介石を説得して第二次国共合作を成立させ、中華人民共和国の建国後に国務院総理(首相)となった周恩来が政治部副主任(後、主任に昇格)に、中華人民共和国元帥となった葉剣英が教授部副主任に任命された。

(周恩来)
黄埔軍官学校、正式名称を中国国民党陸軍軍官学校というこの士官学校では、国民党総理の孫文が唱える三民主義と同時にマルクス主義も教えられていたのである。この頃国民党内部では、共産党との合作を第一義に考える左派と共産党との対立姿勢を隠さない右派に分かれて対立が生じ始めていた。
左派の代表格は汪兆銘であったが、右派の領袖として蒋介石が擬せられるようになっていった。黄埔軍官学校の校長として蒋介石は共産党員の教官とともに軍人の養成に当たらねばならない立場にあったが、黄埔軍官学校内部でも国民党と共産党の対立が芽生えていく。
1924年8月から10月にかけて商団事件が勃発した。これは孫文の広東政府が「赤化」したとして危機感を覚えたイギリスなどが、広東にあるイギリス系銀行の代表者である陳廉伯に働きかけ、商人団に武装させて広東政府の転覆を図ったものである。陳炯明の残党と手を結んだ商人団が武装蜂起するや、孫文は蒋介石に鎮圧を命じた。蒋介石は黄埔軍官学校の学生を中核とする国民党軍を直接率いて事件を鎮圧した。
商団事件の最中の9月、北京では第二次奉直戦争が発生し、これを契機と捉えた孫文は「北伐宣言」を発した。ところが、商団事件により出陣準備に手間取っていたため、第二次奉直戦争は収束してしまった。しかし、北京政府の実権を握った馮玉祥や張作霖から善後策を協議したいとの招請を受け、孫文は北上することになった。
孫文はこの時、商人団の反乱など広東でのクーデターを危惧する側近に対し、「大丈夫だ。広東には腹心の蒋介石がいるから」と語ったという。
11月12日に広東を船で出発した孫文は、北京への途上黄埔軍官学校を訪れ、蒋介石と面会した。孫文は蒋介石が短期間に黄埔軍官学校を充実させ、軍の育成が進んでいることを高く評価した。その上で今回の北上では広東に戻れないことを覚悟しているとも語った。蒋介石が「何故そのように弱気になっているのですか」と訝り尋ねると、孫文は「私の説いた三民主義は、この学校の学生たちに実行してもらいたい。私は死に場所を得ればそれでいい。黄埔軍官学校の教育を見て、彼らにこそ私の命を継いでもらいたいと思った」と語ったという。孫文はこの後、香港・上海へと渡り、日本を経由して北京に入った。このときが蒋介石と孫文の今生の別れとなってしまった。
1925年に入ると、陳炯明軍が勢力を挽回して軍事行動を活発化させるようになり、蒋介石はこれに対峙することになった。2月、陳炯明軍が広東に侵攻すると、蒋介石は国民党軍に出動命令を出し、北路・中路・南路の三軍に分かれて陳炯明軍の本拠地である東江に攻撃を開始した。
東征軍は陳炯明軍を撃破していったが、中でも黄埔軍官学校の出身者が中核を占める南路軍の活躍は目覚しく、黄埔軍官学校総教官の何応欽率いる第一教導団、教授部主任の王柏齢率いる第二教導団は、陳炯明軍を追い詰めていった。3月7日には広東省の大部分を制圧することに成功、陳炯明は香港へ逃亡した。この第一次東征で黄埔軍官学校の学生部隊が活躍したことに感銘した蒋介石は、北京に滞在している孫文の体調悪化を知らせてきた胡漢民に対して、学生たちの精神力を評価し、自己の教育の成果に喜ぶ内容の電報を送っている。
しかし、その喜びも束の間、1925年3月12日、孫文は北京において病没した。蒋介石が孫文死去の知らせを受け取ったのは3月21日、軍を率いて駐屯していた広東省興寧においてであった。蒋介石はすぐさま学生部隊を招集し、涙ながらに「三民主義による中国統一という孫大元帥の遺志を達成するのが我々に課せられた使命である」と訓示した。
この孫文死去に際して、有名な「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なお未だ成功せず、同志よって須く努力すべし)」との一節がある孫文の遺言を起草したのが汪兆銘であった。
蒋介石、汪兆銘ともに孫文の精神を継承する後継者であったのだ。

孫文の死後、汪兆銘は広東で国民政府常務委員会主席・軍事委員会主席を兼任する。この政府には、毛沢東ら中国共産党メンバーも参加していた。
その頃、蒋介石は第二次東征を行って陳炯明の本拠地である恵州を陥落せしめ、広東省内に残る陳炯明軍の勢力を一掃し、広東の軍事的統一を実現した。この結果、軍事的功績を挙げた蒋介石の発言力は強まり、国民党・国民政府内に確固たる地位を確保することになった。
この時期、国民党・国民政府内では左派と右派の政治闘争が続いていたが、連ソ容共に積極的な汪兆銘と、軍事的功績を挙げ右派の領袖として台頭してきた蒋介石が二大巨頭として存在し、これをボロディンらソ連の顧問団が支えるという体制となった。
翌1926年1月、第2回党大会が開かれ、黄埔軍官学校での教育で左派にも人脈を広げていた蒋介石は、国民政府主席の汪兆銘に次ぐ得票数で党中央執行委員会常務委員に選出され、党内序列2位となった。2月1日には国民革命軍総監に就任した。
国民党内で確固たる地位を築きつつあった蒋介石は、孫文の遺志を継ぐべく早期に北伐を開始したいと考えていた。しかしながら、ソ連の軍事顧問団は時期尚早として反対した。
さらにソ連は広東国民政府だけでなく北京政府の馮玉祥への援助も並行して行うという背信行為に出ていた。
また、中国共産党も労働者や農民政策の実施の不充分を理由に北伐は時期尚早だと反対した。蒋介石はソ連の援助の必要性を痛感しており、ソ連との提携を排除したわけではなく(後の北伐も軍事顧問の一人ヴァシーリー・ブリュヘルが担当する)、ソ連や中国共産党の動きをみて、蒋介石は不信感を募らせていった。ことに国共合作による中国共産党の勢力拡大は蒋介石にとって看過できるものではなかった。
このような状況下で、1926年3月、中山艦事件が発生した。事件の概要は、共産党員が艦長を務める国民革命軍の砲艦「中山」が、軍総監の蒋介石の許可なく広州から軍官学校のある黄埔へ航行したため、蒋介石は「中山」の艦長を逮捕し、広州市内に戒厳令を布告して、ソ連の軍事顧問団の公邸や共産党が指導する広州の省港ストライキ委員会を包囲し、労働者糾察隊の武器を没収したというのものである。事件の真相は不明だが、蒋介石はこの事件を利用して共産党やソ連の軍事顧問団を牽制した。党内の支持基盤が弱くソ連の代表団や共産党に支えられて政権を維持してきた汪兆銘は、自己の権力基盤が揺らいだことに動揺し、3月21日、病気療養を名目にフランスに出国して事実上失脚となった。かくして蒋介石は国民党の権力を掌握することに成功したのである。
国民党・国民政府における主導権を掌握した蒋介石は、さらに最高権力者としての地位を固めていく。4月16日、中国国民党中央執行委員・国民政府委員連席会議において、蒋介石は国民政府軍事委員会主席に選出された。5月に開催された第2期中国国民党中央執行委員会第2回全体会議(第2期2中全会)では、蒋は党中央組織部長に就任した。蒋はこの会議で「党務整理案」を通過させ、中国共産党員を中国国民党の訓令に絶対服従させることとし、国民党中央部長職から共産党員を排除した。さらに7月6日の臨時党大会において、蒋介石は中国国民党の最高職である党中央執行委員会常務委員会主席に就任した。党と軍の最高職を得た蒋介石は、孫文の後継者としての地位を確実なものとしたのである。

(権力を掌握した頃の蒋介石(1926年))
【蒋介石による中国統一】
革命拠点である広東から北伐革命軍を組織して北上し、その過程で地方割拠の軍閥勢力を駆逐しながら最終的には北京政府を打倒して中国を統一し、南京に国民党政権を樹立する。これが孫文の追い求めた夢であった[70]。孫文の後継者を自負する蒋介石は、孫文の遺志を果たすべく北伐に乗り出す。
北京政府直隷派の呉佩孚が湖南省に進出を図ると、1926年5月、蒋介石は北伐先遣隊を湖南省に派遣し、呉佩孚と対峙していた省長代理の唐生智を支援した。唐生智軍と連携した北伐先遣隊は湖南省に橋頭堡を確保した。唐生智は国民政府に帰順し、その軍は国民革命軍に編入された。
6月5日、蒋介石は国民革命軍総司令に就任する。
そして7月1日、北伐宣言および国民革命軍動員令を発した。北伐に参加する国民革命軍は全8軍25師団で編制され、総兵力は約10万であった。国民革命軍の中核は黄埔軍官学校出身の将校・兵士であったが、黄埔軍官学校での教育で精鋭部隊を拡充するのは短期間では限界があり、蒋介石直系の第一軍以外の軍団は、政治工作によって国民政府に帰順した雲南や広西の李宗仁(第七軍)、湖南の唐生智(第八軍)などの西南軍閥諸軍を吸収・改編したものであった。国民革命軍は北伐開始にあたり、非国民党系の部隊を多く抱かざるを得ず、蒋介石は総司令として各軍の統率に手腕が問われることになる。
7月9日、北伐誓師の儀式を挙行し、北伐敢行を誓った。このとき蒋介石は居並ぶ将兵に対し、「今や北洋軍閥と帝国主義者が我々を包囲している。国民革命の精神を集中し、総理の遺志を完成せんときである」「我が将士よ!諸君は同徳同心、恥辱を忘れてはならぬ。辛苦を厭うな、死を惜しむな、生を偸むな、壮烈なる死は偸生よりもはるかに光栄である。この国家と人民を守るのは実に我が将士である」、と演説し鼓舞した。かくして蒋介石率いる国民革命軍は北伐に出陣した。
国民革命軍は湖南の呉佩孚、江西の孫伝芳の軍勢を各個撃破し、破竹の勢いを見せた。湖南・湖北戦線では、北伐軍は7月11日に湖南省の省都長沙を支配下に置き、8月には湖南省全域を制圧した。さらに湖北省に進出し、辛亥革命記念日である10月10日には革命の勃発地である武漢を占領した。これにより湖南・湖北における呉佩孚の勢力は壊滅し、呉は河南に退いた。かくして湖南・湖北の地は国民革命軍の支配するところとなった。続く主戦地となった江西では、蒋介石自ら作戦指揮を執った。蒋介石は、総司令としての威信と精鋭部隊を養成してきた自負にかけて、この戦いに敗れるわけにはいかなかった。省都南昌の攻防戦では孫伝芳軍に苦戦を強いられ、1万人以上の死傷者を出したものの、蒋介石直系の第一軍と李宗仁率いる第七軍の奮戦により11月7日には南昌を占領、江西省から孫伝芳の勢力は一掃され、かの地もまた国民革命軍の支配に置かれた。蒋介石は南昌に総司令部を置き、さらに攻勢に出る。12月には福建省も国民革命軍の支配下に入った。北方では馮玉祥が国民革命軍への帰順を表明し、11月下旬には陝西省を支配下に置いた。
北伐軍の快進撃は、国民革命軍を「我が軍」と呼ぶ民衆の支持なくしてはあり得なかった。一つの地域が解放されると、農民・労働者・学生たちが沿道で国民党の党旗である「青天白日旗」を打ち振った。
蒋介石は南昌に総司令部を構えると「各省人民に決起を促す」という声明を発表し、北伐軍への支持と協力を訴えたが、国民革命軍の支配下に入った湖南・湖北では、広東で養成されていた農民運動家を中心に農民協会が結成され、農民の武装化を進め、北伐の側面支援だけでなく、地主・土豪との激しい対立を繰り広げるようになった。農民協会の会員は国民革命軍の北上に呼応する形で激増し、1926年末には湖南省だけで約160万人に増加した。
これは国民革命軍にとって大きな援軍となった。他方、上海など都市部の自治運動も国民党の政治工作により反軍閥色を強めていき、北伐軍を支援した。
国民革命軍の快進撃によって蒋介石の威信は高まるばかりであった。

(北伐軍を率いる蒋介石)
【左派との対決・汪兆銘の転向】
武漢占領を受けて広州の国民党中央は国民政府と党中央の武漢移転を決定し、1927年1月1日、国民政府は武漢に遷都した(武漢国民政府)。国民党右派の要人は蒋介石とともに北伐に参加し、南昌の総司令部に滞在していたため、武漢国民政府の要職の多くは左派勢力で占められた。
蒋介石の権勢拡大に危機感を覚えた左派の陳友仁(国民政府外交部長)、徐謙(国民政府司法部長)、孫科(孫文の長男で国民政府交通部長)らは、ボロディンと結び、蒋介石から権力を剥奪しようとする。武漢遷都直前の前年12月、先んじて武漢に入った彼らは、国民党中央と国民政府の臨時連席会議を組織して今後この会議が最高職権を行使することを宣言した。そして、1月3日、臨時連席会議は3月に国民党第2期3中全会を武漢で開催することを決議した。この3中全会の決議で蒋介石の権限を縛ろうというのが左派の計画であった。さらに左派は領袖の汪兆銘をフランスから呼び戻して権力を強化しようとする。汪を国民政府主席に復職させて蒋介石を牽制しようというのである。
蒋介石は南昌の総司令部で軍事作戦を指揮し、武漢の国民政府に合流しようとはしなかった。蒋からすれば武漢国民政府は共産党に乗っ取られた政権に見えたのである。蒋介石は党の規約にない武漢の臨時連席会議の正統性は認められないとし、南昌に留まっていた党中央執行委員たちと党中央政治会議を招集、党中央と政府は暫時南昌に留め置くこと、第2期3中全会は南昌で開催することを決定した。
中国国民党中央委員会執行委員会主席・国民政府軍事委員会主席・国民革命軍総司令である蒋介石が総司令部を構える南昌には、国民政府主席代理の譚延闓、国民党中央執行委員会常務委員会主席代理の張静江がいて、南昌の党中央政治会議は組織的正統性を有していた。しかし、武漢側の工作により南昌の党中央執行委員の多くは武漢に赴いたため、南昌側の正統性は揺らぎ、武漢側が優位となった。北伐の軍事作戦中ということもあり、武漢側との決裂を避けたい蒋介石は、武漢訪問や汪兆銘の復職に賛同するなど妥協を図った。しかしながら蒋介石は軍権を握っており、江西や広東など共産党・左派の影響が強い地方の党部を自派へ転換していくなど、左派との対決に備えていった。
結局第2期3中全会は3月に武漢で開催され、党中央執行委員会常務委員会主席職の廃止と国民革命軍総司令の権限縮小、集団指導体制の確立などが決議された。これにより蒋介石の権限は掣肘を加えられることになった。さらに3中全会では党・政府の要職に国民党左派や共産党員が就くことが決議され、労工部長や農政部長など、労働問題や土地問題といった共産党が重視する問題を扱う閣僚には共産党員が就任することになった。共産党員の閣僚就任はこれが初めてのことであった。そして、汪兆銘の国民政府主席復職と、党中央執行委員会常務委員会の首席委員・党中央組織部長就任も決定された。
1927年4月1日、蒋介石の招電に応じ、再度帰国した汪兆銘は中央常務委員、組織部長に返り咲いた。同年に「中国国民党の多数の同志、およそ中国共産党の理論およびその中国国民党に対する真実の態度を了解する人々は、だれも孫総理の連共政策をうたがうことはできない。」と声明を発した。
こうしたなか、北伐軍は3月22日に上海、24日に南京に入城した。4月12日、蒋介石は何千に及ぶ共産主義者の容疑を持つ者たちへの迅速な攻撃を開始(上海クーデター)。彼は胡漢民を含む保守の同志の支持を受けて国民政府を南京に設立した。国民党から共産主義者は排除、ソビエトからの顧問は追放され、このことが国共内戦開始につながる。汪兆銘の国民政府(武漢政府)は大衆に支持されず、軍事的にも弱体であり、まもなく蒋介石と地元広西の軍閥・李宗仁に取って代わられ、結局汪兆銘と彼の左派グループは蒋介石に降伏し、南京政府に参加した。
汪は武漢政府に残ったが、やがて「共産党との分離」を決意し、容共から反共に転じて武漢政府内にて清党工作を進めることとなった。
【北伐の完遂・蒋介石と汪兆銘の合流】
蒋介石は国民革命軍を4つの集団軍に再編し、北伐を再開した。北伐軍は1928年6月8日、北京に入城し、北京政府打倒という孫文の遺志を果たした。北京に到達すると蒋介石は孫文の遺体に敬意を表し、首都南京に運ばせ、壮大な霊廟(中山陵)で祭った。そして12月には満州軍閥・張学良が蒋介石政府に忠誠を誓約し、中国の再統一は成った。
「反共産党」で一致したことから、武漢政府と南京政府の再統一がスケジュールにのぼり、蒋介石が下野して両政府は合体することとなった。
汪は新政府で、国民政府委員、軍事委員会主席団委員等の地位に着いている。しかし共産党の広東蜂起の混乱の責任をとって汪は政界引退を表明し、再びフランスへ外遊することとなる。

一方国内では、独裁の方向に動き出した蒋と、その動きに反発する反蒋派との対立が生じる。汪は反蒋派から出馬を請われて帰国し、民国19年 (1930年)9月、北京にて国民政府を樹立したが、北京国民政府主席は戦局の不利を見てすぐに下野を表明し、政権は1日で瓦解した。汪は国民党から除名処分を受ける。
汪はしばらく香港に蟄居していたが、民国20年(1931年)5月、反蒋派が結集した広東国民政府に参画した。満州事変を機に蒋政府との統一の機運が高まり、民国21年(1932年)1月1日、蒋と汪が中心となる南京国民政府が成立した。汪はこの政府で、行政院長、鉄道部長を務めた。
そして、日本に対する考え方の違いから蒋介石と汪兆銘は再び異なる道を歩むことになるのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は孫文の後継者としての蒋介石と汪兆銘について紹介した。
次回は日華事変における蒋介石と汪兆銘の訣別、汪兆銘率いる南京政府と大東亜戦争との関りを研究していきたいと思う。
【特集】日本と亜細亜~大東亜戦争【シリーズ】第三弾「一心一徳貫徹始終~同生共死和平反共建国」②
https://blog.goo.ne.jp/shishisamurai/e/d593c589b93577e56d933c9a3af5eb0bの続きです。

孫文先生の命日に行われる中国国民党の集会の様子。
遺言の「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なお未だ成功せず、同志よって須く努力すべし)」を謳っているが、台湾人を軽視して中国共産党に妥協する現在の国民党は本当に孫文の志を継承していると言えるのであろうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前回では中国の愛国者・アジア主義者としての孫文と容共主義者・諸民族を「中華」に同化しようとする帝国主義者としての孫文を考察した。
また、日本の「対華二十一カ条要求」という帝国主義的な過ちについても触れた。
聖戦未だ成らずhttps://blog.goo.ne.jp/shishisamurai/e/439bb41311a3cd6f3f06919086900857の記事でも書いたように、大日本帝国にはアジアに対する傲りが帝国主義として現れた一方、アジア解放の意志が民族主義として表現された。
私達は日本民族主義者として帝国主義を批判すると共に、先人たちの民族主義を継承し、現代に即した形で実践するための運動を展開しているのである。
大日本帝国に存在した矛盾の克服こそ新大日本帝国の課題である。
同じように孫文にも矛盾があった。
アジア主義であると同時に、同化主義に傾いた孫文の明と暗。
この明と暗は孫文の二人の後継者に受け継がれることになる。


【汪兆銘と蒋介石】
汪兆銘は日本留学中に孫文の思想に触れて革命党に参加し、清朝の醇親王載灃を狙ったテロ未遂事件を起こし、逮捕されたが、汪の人物を見込んだ粛親王善耆に助命された。
やがて孫文の信任を得て共に活動し、中華民国の建国宣言を起草した。
蒋介石は1907年7月に日本へ渡り、東京振武学校に留学した。2年間の教育課程を修めた後、蒋介石は日本の陸軍士官学校には入学せず、1910年より日本陸軍に勤務し、新潟県高田市(現在の上越市)の第13師団高田連隊の野戦砲兵隊の隊付将校として実習を受けた。このときに経験した日本軍の兵営生活について蒋介石は、中国にあっても軍事教育の根幹にならなければならないと手本として考えていた。
蒋介石は優れた軍事的才能を有し、対軍閥戦争で活躍、国民党軍の士官学校である黄埔軍官学校の校長に抜擢された。

(孫文による蒋介石任命の辞令)
6月10日に入学式を迎えた。蒋介石は新入生に対して三民主義に命をかける幹部の養成、軍の規律を説く講話を行った。黄埔軍官学校では、組織や訓練面ではソ連式が採用されたが、日常的な軍隊生活の規律は蒋介石の東京振武学校や新潟での日本陸軍第13師団での体験が基礎となっていた。また、清朝末期の改革派大官で蒋介石が尊敬する曽国藩が説いた儒学的人生訓・処世訓も教育に反映されていた。
黄埔軍官学校はソ連の支援の下につくられたため、共産党員も教官となった。後に西安事件で監禁された蒋介石を説得して第二次国共合作を成立させ、中華人民共和国の建国後に国務院総理(首相)となった周恩来が政治部副主任(後、主任に昇格)に、中華人民共和国元帥となった葉剣英が教授部副主任に任命された。

(周恩来)
黄埔軍官学校、正式名称を中国国民党陸軍軍官学校というこの士官学校では、国民党総理の孫文が唱える三民主義と同時にマルクス主義も教えられていたのである。この頃国民党内部では、共産党との合作を第一義に考える左派と共産党との対立姿勢を隠さない右派に分かれて対立が生じ始めていた。
左派の代表格は汪兆銘であったが、右派の領袖として蒋介石が擬せられるようになっていった。黄埔軍官学校の校長として蒋介石は共産党員の教官とともに軍人の養成に当たらねばならない立場にあったが、黄埔軍官学校内部でも国民党と共産党の対立が芽生えていく。
1924年8月から10月にかけて商団事件が勃発した。これは孫文の広東政府が「赤化」したとして危機感を覚えたイギリスなどが、広東にあるイギリス系銀行の代表者である陳廉伯に働きかけ、商人団に武装させて広東政府の転覆を図ったものである。陳炯明の残党と手を結んだ商人団が武装蜂起するや、孫文は蒋介石に鎮圧を命じた。蒋介石は黄埔軍官学校の学生を中核とする国民党軍を直接率いて事件を鎮圧した。
商団事件の最中の9月、北京では第二次奉直戦争が発生し、これを契機と捉えた孫文は「北伐宣言」を発した。ところが、商団事件により出陣準備に手間取っていたため、第二次奉直戦争は収束してしまった。しかし、北京政府の実権を握った馮玉祥や張作霖から善後策を協議したいとの招請を受け、孫文は北上することになった。
孫文はこの時、商人団の反乱など広東でのクーデターを危惧する側近に対し、「大丈夫だ。広東には腹心の蒋介石がいるから」と語ったという。
11月12日に広東を船で出発した孫文は、北京への途上黄埔軍官学校を訪れ、蒋介石と面会した。孫文は蒋介石が短期間に黄埔軍官学校を充実させ、軍の育成が進んでいることを高く評価した。その上で今回の北上では広東に戻れないことを覚悟しているとも語った。蒋介石が「何故そのように弱気になっているのですか」と訝り尋ねると、孫文は「私の説いた三民主義は、この学校の学生たちに実行してもらいたい。私は死に場所を得ればそれでいい。黄埔軍官学校の教育を見て、彼らにこそ私の命を継いでもらいたいと思った」と語ったという。孫文はこの後、香港・上海へと渡り、日本を経由して北京に入った。このときが蒋介石と孫文の今生の別れとなってしまった。
1925年に入ると、陳炯明軍が勢力を挽回して軍事行動を活発化させるようになり、蒋介石はこれに対峙することになった。2月、陳炯明軍が広東に侵攻すると、蒋介石は国民党軍に出動命令を出し、北路・中路・南路の三軍に分かれて陳炯明軍の本拠地である東江に攻撃を開始した。
東征軍は陳炯明軍を撃破していったが、中でも黄埔軍官学校の出身者が中核を占める南路軍の活躍は目覚しく、黄埔軍官学校総教官の何応欽率いる第一教導団、教授部主任の王柏齢率いる第二教導団は、陳炯明軍を追い詰めていった。3月7日には広東省の大部分を制圧することに成功、陳炯明は香港へ逃亡した。この第一次東征で黄埔軍官学校の学生部隊が活躍したことに感銘した蒋介石は、北京に滞在している孫文の体調悪化を知らせてきた胡漢民に対して、学生たちの精神力を評価し、自己の教育の成果に喜ぶ内容の電報を送っている。
しかし、その喜びも束の間、1925年3月12日、孫文は北京において病没した。蒋介石が孫文死去の知らせを受け取ったのは3月21日、軍を率いて駐屯していた広東省興寧においてであった。蒋介石はすぐさま学生部隊を招集し、涙ながらに「三民主義による中国統一という孫大元帥の遺志を達成するのが我々に課せられた使命である」と訓示した。
この孫文死去に際して、有名な「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なお未だ成功せず、同志よって須く努力すべし)」との一節がある孫文の遺言を起草したのが汪兆銘であった。
蒋介石、汪兆銘ともに孫文の精神を継承する後継者であったのだ。

孫文の死後、汪兆銘は広東で国民政府常務委員会主席・軍事委員会主席を兼任する。この政府には、毛沢東ら中国共産党メンバーも参加していた。
その頃、蒋介石は第二次東征を行って陳炯明の本拠地である恵州を陥落せしめ、広東省内に残る陳炯明軍の勢力を一掃し、広東の軍事的統一を実現した。この結果、軍事的功績を挙げた蒋介石の発言力は強まり、国民党・国民政府内に確固たる地位を確保することになった。
この時期、国民党・国民政府内では左派と右派の政治闘争が続いていたが、連ソ容共に積極的な汪兆銘と、軍事的功績を挙げ右派の領袖として台頭してきた蒋介石が二大巨頭として存在し、これをボロディンらソ連の顧問団が支えるという体制となった。
翌1926年1月、第2回党大会が開かれ、黄埔軍官学校での教育で左派にも人脈を広げていた蒋介石は、国民政府主席の汪兆銘に次ぐ得票数で党中央執行委員会常務委員に選出され、党内序列2位となった。2月1日には国民革命軍総監に就任した。
国民党内で確固たる地位を築きつつあった蒋介石は、孫文の遺志を継ぐべく早期に北伐を開始したいと考えていた。しかしながら、ソ連の軍事顧問団は時期尚早として反対した。
さらにソ連は広東国民政府だけでなく北京政府の馮玉祥への援助も並行して行うという背信行為に出ていた。
また、中国共産党も労働者や農民政策の実施の不充分を理由に北伐は時期尚早だと反対した。蒋介石はソ連の援助の必要性を痛感しており、ソ連との提携を排除したわけではなく(後の北伐も軍事顧問の一人ヴァシーリー・ブリュヘルが担当する)、ソ連や中国共産党の動きをみて、蒋介石は不信感を募らせていった。ことに国共合作による中国共産党の勢力拡大は蒋介石にとって看過できるものではなかった。
このような状況下で、1926年3月、中山艦事件が発生した。事件の概要は、共産党員が艦長を務める国民革命軍の砲艦「中山」が、軍総監の蒋介石の許可なく広州から軍官学校のある黄埔へ航行したため、蒋介石は「中山」の艦長を逮捕し、広州市内に戒厳令を布告して、ソ連の軍事顧問団の公邸や共産党が指導する広州の省港ストライキ委員会を包囲し、労働者糾察隊の武器を没収したというのものである。事件の真相は不明だが、蒋介石はこの事件を利用して共産党やソ連の軍事顧問団を牽制した。党内の支持基盤が弱くソ連の代表団や共産党に支えられて政権を維持してきた汪兆銘は、自己の権力基盤が揺らいだことに動揺し、3月21日、病気療養を名目にフランスに出国して事実上失脚となった。かくして蒋介石は国民党の権力を掌握することに成功したのである。
国民党・国民政府における主導権を掌握した蒋介石は、さらに最高権力者としての地位を固めていく。4月16日、中国国民党中央執行委員・国民政府委員連席会議において、蒋介石は国民政府軍事委員会主席に選出された。5月に開催された第2期中国国民党中央執行委員会第2回全体会議(第2期2中全会)では、蒋は党中央組織部長に就任した。蒋はこの会議で「党務整理案」を通過させ、中国共産党員を中国国民党の訓令に絶対服従させることとし、国民党中央部長職から共産党員を排除した。さらに7月6日の臨時党大会において、蒋介石は中国国民党の最高職である党中央執行委員会常務委員会主席に就任した。党と軍の最高職を得た蒋介石は、孫文の後継者としての地位を確実なものとしたのである。

(権力を掌握した頃の蒋介石(1926年))
【蒋介石による中国統一】
革命拠点である広東から北伐革命軍を組織して北上し、その過程で地方割拠の軍閥勢力を駆逐しながら最終的には北京政府を打倒して中国を統一し、南京に国民党政権を樹立する。これが孫文の追い求めた夢であった[70]。孫文の後継者を自負する蒋介石は、孫文の遺志を果たすべく北伐に乗り出す。
北京政府直隷派の呉佩孚が湖南省に進出を図ると、1926年5月、蒋介石は北伐先遣隊を湖南省に派遣し、呉佩孚と対峙していた省長代理の唐生智を支援した。唐生智軍と連携した北伐先遣隊は湖南省に橋頭堡を確保した。唐生智は国民政府に帰順し、その軍は国民革命軍に編入された。
6月5日、蒋介石は国民革命軍総司令に就任する。
そして7月1日、北伐宣言および国民革命軍動員令を発した。北伐に参加する国民革命軍は全8軍25師団で編制され、総兵力は約10万であった。国民革命軍の中核は黄埔軍官学校出身の将校・兵士であったが、黄埔軍官学校での教育で精鋭部隊を拡充するのは短期間では限界があり、蒋介石直系の第一軍以外の軍団は、政治工作によって国民政府に帰順した雲南や広西の李宗仁(第七軍)、湖南の唐生智(第八軍)などの西南軍閥諸軍を吸収・改編したものであった。国民革命軍は北伐開始にあたり、非国民党系の部隊を多く抱かざるを得ず、蒋介石は総司令として各軍の統率に手腕が問われることになる。
7月9日、北伐誓師の儀式を挙行し、北伐敢行を誓った。このとき蒋介石は居並ぶ将兵に対し、「今や北洋軍閥と帝国主義者が我々を包囲している。国民革命の精神を集中し、総理の遺志を完成せんときである」「我が将士よ!諸君は同徳同心、恥辱を忘れてはならぬ。辛苦を厭うな、死を惜しむな、生を偸むな、壮烈なる死は偸生よりもはるかに光栄である。この国家と人民を守るのは実に我が将士である」、と演説し鼓舞した。かくして蒋介石率いる国民革命軍は北伐に出陣した。
国民革命軍は湖南の呉佩孚、江西の孫伝芳の軍勢を各個撃破し、破竹の勢いを見せた。湖南・湖北戦線では、北伐軍は7月11日に湖南省の省都長沙を支配下に置き、8月には湖南省全域を制圧した。さらに湖北省に進出し、辛亥革命記念日である10月10日には革命の勃発地である武漢を占領した。これにより湖南・湖北における呉佩孚の勢力は壊滅し、呉は河南に退いた。かくして湖南・湖北の地は国民革命軍の支配するところとなった。続く主戦地となった江西では、蒋介石自ら作戦指揮を執った。蒋介石は、総司令としての威信と精鋭部隊を養成してきた自負にかけて、この戦いに敗れるわけにはいかなかった。省都南昌の攻防戦では孫伝芳軍に苦戦を強いられ、1万人以上の死傷者を出したものの、蒋介石直系の第一軍と李宗仁率いる第七軍の奮戦により11月7日には南昌を占領、江西省から孫伝芳の勢力は一掃され、かの地もまた国民革命軍の支配に置かれた。蒋介石は南昌に総司令部を置き、さらに攻勢に出る。12月には福建省も国民革命軍の支配下に入った。北方では馮玉祥が国民革命軍への帰順を表明し、11月下旬には陝西省を支配下に置いた。
北伐軍の快進撃は、国民革命軍を「我が軍」と呼ぶ民衆の支持なくしてはあり得なかった。一つの地域が解放されると、農民・労働者・学生たちが沿道で国民党の党旗である「青天白日旗」を打ち振った。
蒋介石は南昌に総司令部を構えると「各省人民に決起を促す」という声明を発表し、北伐軍への支持と協力を訴えたが、国民革命軍の支配下に入った湖南・湖北では、広東で養成されていた農民運動家を中心に農民協会が結成され、農民の武装化を進め、北伐の側面支援だけでなく、地主・土豪との激しい対立を繰り広げるようになった。農民協会の会員は国民革命軍の北上に呼応する形で激増し、1926年末には湖南省だけで約160万人に増加した。
これは国民革命軍にとって大きな援軍となった。他方、上海など都市部の自治運動も国民党の政治工作により反軍閥色を強めていき、北伐軍を支援した。
国民革命軍の快進撃によって蒋介石の威信は高まるばかりであった。

(北伐軍を率いる蒋介石)
【左派との対決・汪兆銘の転向】
武漢占領を受けて広州の国民党中央は国民政府と党中央の武漢移転を決定し、1927年1月1日、国民政府は武漢に遷都した(武漢国民政府)。国民党右派の要人は蒋介石とともに北伐に参加し、南昌の総司令部に滞在していたため、武漢国民政府の要職の多くは左派勢力で占められた。
蒋介石の権勢拡大に危機感を覚えた左派の陳友仁(国民政府外交部長)、徐謙(国民政府司法部長)、孫科(孫文の長男で国民政府交通部長)らは、ボロディンと結び、蒋介石から権力を剥奪しようとする。武漢遷都直前の前年12月、先んじて武漢に入った彼らは、国民党中央と国民政府の臨時連席会議を組織して今後この会議が最高職権を行使することを宣言した。そして、1月3日、臨時連席会議は3月に国民党第2期3中全会を武漢で開催することを決議した。この3中全会の決議で蒋介石の権限を縛ろうというのが左派の計画であった。さらに左派は領袖の汪兆銘をフランスから呼び戻して権力を強化しようとする。汪を国民政府主席に復職させて蒋介石を牽制しようというのである。
蒋介石は南昌の総司令部で軍事作戦を指揮し、武漢の国民政府に合流しようとはしなかった。蒋からすれば武漢国民政府は共産党に乗っ取られた政権に見えたのである。蒋介石は党の規約にない武漢の臨時連席会議の正統性は認められないとし、南昌に留まっていた党中央執行委員たちと党中央政治会議を招集、党中央と政府は暫時南昌に留め置くこと、第2期3中全会は南昌で開催することを決定した。
中国国民党中央委員会執行委員会主席・国民政府軍事委員会主席・国民革命軍総司令である蒋介石が総司令部を構える南昌には、国民政府主席代理の譚延闓、国民党中央執行委員会常務委員会主席代理の張静江がいて、南昌の党中央政治会議は組織的正統性を有していた。しかし、武漢側の工作により南昌の党中央執行委員の多くは武漢に赴いたため、南昌側の正統性は揺らぎ、武漢側が優位となった。北伐の軍事作戦中ということもあり、武漢側との決裂を避けたい蒋介石は、武漢訪問や汪兆銘の復職に賛同するなど妥協を図った。しかしながら蒋介石は軍権を握っており、江西や広東など共産党・左派の影響が強い地方の党部を自派へ転換していくなど、左派との対決に備えていった。
結局第2期3中全会は3月に武漢で開催され、党中央執行委員会常務委員会主席職の廃止と国民革命軍総司令の権限縮小、集団指導体制の確立などが決議された。これにより蒋介石の権限は掣肘を加えられることになった。さらに3中全会では党・政府の要職に国民党左派や共産党員が就くことが決議され、労工部長や農政部長など、労働問題や土地問題といった共産党が重視する問題を扱う閣僚には共産党員が就任することになった。共産党員の閣僚就任はこれが初めてのことであった。そして、汪兆銘の国民政府主席復職と、党中央執行委員会常務委員会の首席委員・党中央組織部長就任も決定された。
1927年4月1日、蒋介石の招電に応じ、再度帰国した汪兆銘は中央常務委員、組織部長に返り咲いた。同年に「中国国民党の多数の同志、およそ中国共産党の理論およびその中国国民党に対する真実の態度を了解する人々は、だれも孫総理の連共政策をうたがうことはできない。」と声明を発した。
こうしたなか、北伐軍は3月22日に上海、24日に南京に入城した。4月12日、蒋介石は何千に及ぶ共産主義者の容疑を持つ者たちへの迅速な攻撃を開始(上海クーデター)。彼は胡漢民を含む保守の同志の支持を受けて国民政府を南京に設立した。国民党から共産主義者は排除、ソビエトからの顧問は追放され、このことが国共内戦開始につながる。汪兆銘の国民政府(武漢政府)は大衆に支持されず、軍事的にも弱体であり、まもなく蒋介石と地元広西の軍閥・李宗仁に取って代わられ、結局汪兆銘と彼の左派グループは蒋介石に降伏し、南京政府に参加した。
汪は武漢政府に残ったが、やがて「共産党との分離」を決意し、容共から反共に転じて武漢政府内にて清党工作を進めることとなった。
【北伐の完遂・蒋介石と汪兆銘の合流】
蒋介石は国民革命軍を4つの集団軍に再編し、北伐を再開した。北伐軍は1928年6月8日、北京に入城し、北京政府打倒という孫文の遺志を果たした。北京に到達すると蒋介石は孫文の遺体に敬意を表し、首都南京に運ばせ、壮大な霊廟(中山陵)で祭った。そして12月には満州軍閥・張学良が蒋介石政府に忠誠を誓約し、中国の再統一は成った。
「反共産党」で一致したことから、武漢政府と南京政府の再統一がスケジュールにのぼり、蒋介石が下野して両政府は合体することとなった。
汪は新政府で、国民政府委員、軍事委員会主席団委員等の地位に着いている。しかし共産党の広東蜂起の混乱の責任をとって汪は政界引退を表明し、再びフランスへ外遊することとなる。

一方国内では、独裁の方向に動き出した蒋と、その動きに反発する反蒋派との対立が生じる。汪は反蒋派から出馬を請われて帰国し、民国19年 (1930年)9月、北京にて国民政府を樹立したが、北京国民政府主席は戦局の不利を見てすぐに下野を表明し、政権は1日で瓦解した。汪は国民党から除名処分を受ける。
汪はしばらく香港に蟄居していたが、民国20年(1931年)5月、反蒋派が結集した広東国民政府に参画した。満州事変を機に蒋政府との統一の機運が高まり、民国21年(1932年)1月1日、蒋と汪が中心となる南京国民政府が成立した。汪はこの政府で、行政院長、鉄道部長を務めた。
そして、日本に対する考え方の違いから蒋介石と汪兆銘は再び異なる道を歩むことになるのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は孫文の後継者としての蒋介石と汪兆銘について紹介した。
次回は日華事変における蒋介石と汪兆銘の訣別、汪兆銘率いる南京政府と大東亜戦争との関りを研究していきたいと思う。















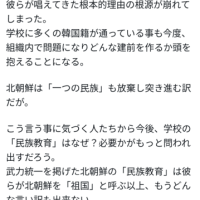
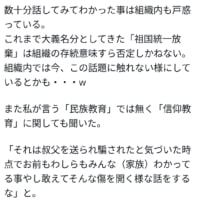



今回もとても興味深い内容で、大変勉強になりました。正直、汪兆銘は日本の協力者ということしか知りませんでしたが、かつて蒋介石と汪兆銘の間でこのような序幕があったのですね。
その後どのようにして汪兆銘と蒋介石が袂を別つことになったのか、について次回連載も楽しみにしています。