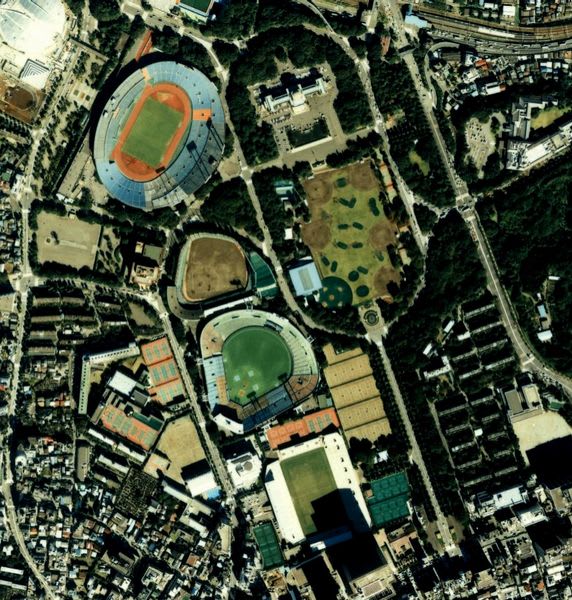今日は2限のテーマカレッジ(オープン教育センター設置のゼミ)に久しぶりに行って、日中関係に関する意見交換を行ったり、夜19時からの太田光のマニフェスト番組を見たり、新聞を読んだり、半藤一利さんの昭和史を読んだりして、歴史や政治について深く考える日だった。
たった一日なのに、多くの人の話を聞けたり読んだりできたから、すごく勉強になったかな。
印象に残ったのは二つ。
テーマカレッジの先生の言葉と、テレビの金美齢さんの話かな。
テーマカレッジでは日中の、特に今年は満州国に関して中心にやってるんだけど、実際に満州へ行って、思った感想やそれらを述べた後の先生の言葉っていうのが、ひどく的を射てたかな。
「満州国について、日本人のほとんどが知らない」
「中国人も満州国について調べようとしていない」
満州国って言う存在が歴史のかなたに置き去りにされてるような状態だったんですよ、今までの60年間って。日本でも、中国でも、「満州国ってのは悪だからいけない」、それだけで済まされてしまった。
しかし、詳しく調べると、満州国っていうのはひどく現実を見据えた政府であったことが見えてくる。岸信介や鮎川義介なんかが中心となって満州国をまともな政府にしようと努力していたことが伺える。
満州国では建国の理念として「五族協和」というのがあった。この五族というのは、満州人、日本人、漢人、朝鮮人、蒙古人のこと。五族が融和できるような政策を実際に努力していたという事実が実はある。それが治外法権の撤廃、という事実。満州国では当初、日本人に対する治外法権があったのだけど、それが1937年には廃止されている。これは満州国の自立性を確保するための政策であり、特筆されるべき事実である。なぜなら他の列強でこのような植民地政策をとった国はないのだから。
さらに、ユダヤ人の移民の推進やソ連から逃げてきたロシア人が多数住んでいた、という事実もあり、満州国を多民族国家として自立させていこうとしていた当時の日本人の努力があったのは事実だったのだ。(もちろん、政治的軍事的に、日本の傀儡政権であったというのは事実である。しかし、日本人が傀儡政権を使って、多民族国家を形成さていこうとしていた、という事実に俺はスポットを当てたい。)
俺も、上記のような事実を大学4年生になる今の今まで知らなかった。いや知らされなかったというのが正しいのかもしれない。日本において、満州国をはじめとした植民地政策は、すべて悪で済まされてしまっているのだから。
しかし、満州へ実際に行って、俺の認識は変わった。満州の土地にある日本が遺した建造物は、どれも日本に残る近代建築物をはるかに上回る、超A級の歴史的文化的価値のある建造物ばかりであった。長春(旧首都:新京)のあの建造物群を見せられて、日本の満州国経営はいい加減だった、と思う人はいないだろう。それくらい、現地に赴いたことは説得力のある歴史からの教えだった。
それらについて知った今だからこそ、今日の先生の言葉に重みを感じた。
歴史はさまざまな側面から切り込むことができる。そして、さまざまな側面を知らなければ語ることはできないものだと思う。教科書に書かれた歴史だけで知ったつもりになって語っているのは、実は、極めて危険な状態なのだ。右・左・自虐・自讃などと歴史はさまざまに語られるが、それぞれの立場を理解し、またそれ以外にもたくさんのことを学んだ上で、初めて歴史をおおっぴらに語る資格が得られるんじゃないだろうか?
俺は、その資格を持つに値する人間になるべく、これからも自分なりに歴史について学んでいきたいと思う。

そして、もう一つ、金美齢さんの言葉。
金さんの言葉が生まれたのは、憲法9条を変えるべきか残すべきか、という議論の過程でなんだけど(ちなみに金さんは憲法9条改正に賛成派)、日本の旧植民地であった台湾出身で、実際に米軍による空爆で、多くの死に直面し、自身も生死の境をさまよった経験のあるという、金さんの言葉はすごく重みのあるものだった。
戦争体験者で改正反対派のおばあさんが「戦争が終わったとき、9条とはなんてすばらしいものなんだ、と思った。戦後平和だったのは9条があったからじゃないんですか?」と言ったんですね、それに対する金さんの反論。
「戦後日本が平和だったのは日米安保があったからです。9条があれば平和?何もしてなくても、1996年の台湾総選挙のとき、中国は台湾海峡に向かってミサイルを撃ち込んできましたよ。これが止まったのは、アメリカが2隻の空母を台湾海峡に派遣してくれたからです。戦後、日本のまわりをアメリカの第7艦隊がずっと回ってくれていたという事実を忘れてはいけない。」
さらに原口一博衆議院議員は憲法9条を宗教に過ぎないと切り捨てた。「戦前の国家主義も憲法9条もいっしょです。それのせいで、現実を見ることのできなくなる、一種の宗教なんです。」と。
俺は、この流れを見て、あ~、確かにそうだなぁ、と思った。根拠のない理想論よりどれだけ効果のあることだろうかと思った。俺は憲法9条のおかげ、という側面もあると強く思っているけど、金さんや原口さんの反対する、「憲法9条のおかげだけで平和」、とは思っていない。
現実を正しく見据えること、そして、過去を正しく分析すること、これはきちんとやらなくちゃいけない。日本人はこの作業が苦手な人が多いんだけど、昨日の寺島さんが言っていたように「時代認識」をきちんと持っていなければならないんだと思う。
理想論は本当に美しい、だけど、理想論を妄信して時代を誤った教訓を日本人は忘れてはならない。ロマンも大切だけど、俺はリアリストとしての自分を常に忘れずに持ち続けたいね。
(写真上は、長春の溥儀の住んだ皇宮にある江沢民前国家主席による石碑。「勿忘九一八」とある。9・18とは満州事変の引き金となった柳条湖事件の日付。この日から受けた屈辱を忘れるな、という意味の石碑。日本では9・18という日時があまり重要視されずに教育されていることを考えると、日中で歴史の着目点が違うことに気づかされる。
写真下は長春の満州国国務院。国務院とは国会のこと。ここで、張恵景首相を頭とする内閣と多くの国会議員が政治を司っていた。傀儡政権とはいっても、カタチの上はきちんとした政府としての体裁は整っていた。ちなみに、現在ここは吉林大学の医学部として今だ現役バリバリで使われ続けている。60年たってもその威容は健在で、中国の文化財にも指定されている。)