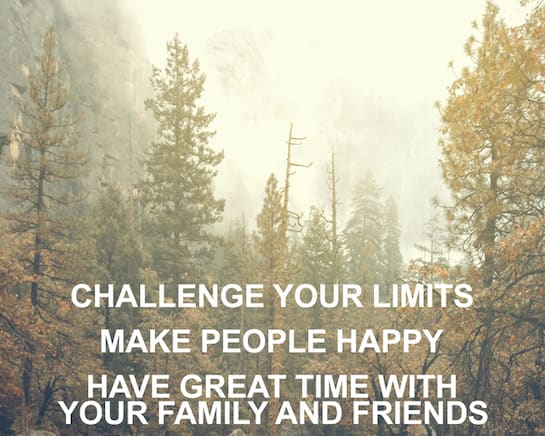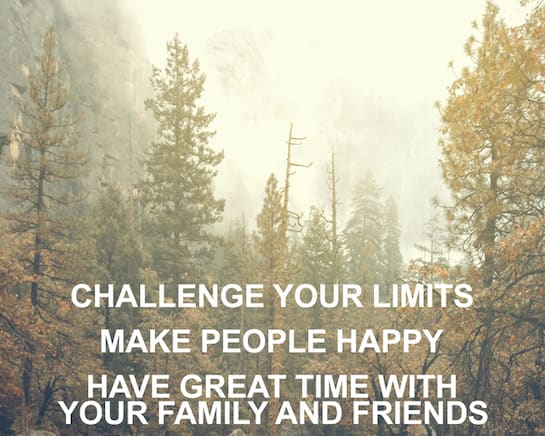2019年は大学院を卒業してから、社会人になってからの6年間の「まとめ」みたいな時期だった。
大きなまとめは3つある
1、選択のフレームワーク
以前の記事で書いた人生で何かを選択するときのフレームワークがうまく作用した。
特に、今の会社で働いてみてからこの3つが合っていたことが分かってきた。
A.興味より強みを重視
興味があって人より劣っていることを頑張るか、そこまで情熱はないけど強みがあることで簡単に成果を出すか。
僕の場合はマーケティングは以前に勉強していた建築より興味は劣るけど、周りから認められるから自然と仕事が頑張れる。
きっと一番いいのは自分の強みを利用して、情熱のあることを別の形で助ければいいのではないかと思う。
B.広さより深さを重視
これはビジネスやプロダクトを作るときの優先順位を決めるのと似ているのがあってそれが個人のスキルにも当てはまる。
例えばプロダクトが実際に世の中に受け入れられるか分からないまま、他の国に拡大するとうまく行かないことが多いのと似ていて、
一つのスキルがしっかりしていない中で他のスキルを幅広く身につけても、うまくいくのが難しい。
C.直感が怖いと思った方を重視
これは簡単で、このようなメリットがあった。
・怖い方が、危機に直面した方が人は速く走れる(=速く成長できる)
・多くの人は怖いと感じるとその選択をやめるので、他の人との差別化ができる
また今回の選択で誰かが作ったフレームワーク内で働くのではなくて、
自分がそれを考えれる立場だったので苦しい時もあったけど結果的には大きな成長につながった。
2、専門性
これは既に大学時代から始まっていた職種の「自分探し」がようやくひと段落落ち着いたと感じだ。
大学:建築デザイン
大学院:都市計画&国際開発
社会人(仕事1):ファウンダー(グラフィックデザイナー&セールス&バックオフィス)
社会人(仕事2):プロジェクトマネージャー
社会人(仕事3):ファウンダー(PM&エンジニア)
社会人(仕事4):カスタマーサクセス→プロダクト・マーケティング
社会人(仕事5):マーケティング(今ここ)
本当に色々な挑戦をしてみて、ほとんどの職種は自分の性格や能力の面でフィットしていなかった。
その中でも自分に合っているのではないかと思ったのは、都市計画&国際開発、マーケティングだった。
そして世の中の需要があったのはマーケティングだった。
今年は個別のマーケティング施策の実践から、採用、そしてマーケティング戦略まで幅広く担当させてもらえた。
まだまだ足りない知識や経験は多いけど、この1年で3年分ぐらいの経験を積ませてもらった気がする。
3、成功体験と自信
僕は大学院を卒業してからの過去の6年はうまく行かなくて、本当に普通の人のように生活できるのかと悩んだ時期もあった。
(個人でも、会社でも、国家でもこのような苦しい時期はあるから、今はもっと達観できているけどその時はずっと不安だった)
去年の転職の時も新しい挑戦という表向きの理由で上海の会社にある意味「逃げる」という選択肢もあったなかで、
あえて日本でもう一度頑張ってみたいと考え、リスクの高い選択をして、チームの高い目標の達成にも貢献できて”小さい成功体験”ができた。
この経験で過去大変だった6年間に対して、成果を出すために必要な訓練期間と考えることができるようになり、
そして諦めずに挑戦し続けたらいつかは成功するというも自信にもつながった。
本当に小さいことに聞こえるけど、この成功体験はこの後の仕事の中でも人生の中でもとても重要な”何か”だと思う。
もちろん成果を出す中でチームメンバーからのサポートをはじめ、以前に一緒に仕事をした先輩・同僚にもアドバイスをもらい、
さらには直接お仕事をしたことがなかった方々にも貴重な意見をもらったりなど、本当に多くの人たちに支えていただいた。
2019年の前半は日々が挑戦で毎日新しいことを学んでいたが、そのペースが後半は落ち着いてしまったのが反省点だ。
2020年とその10年も常にワクワクできるようにゴールを見据えながら、計算されたリスクをとって、一歩ずつ前進していきたい。

今年の1枚 - 大学院の200周年記念の時にシンシナティ時代の友達と