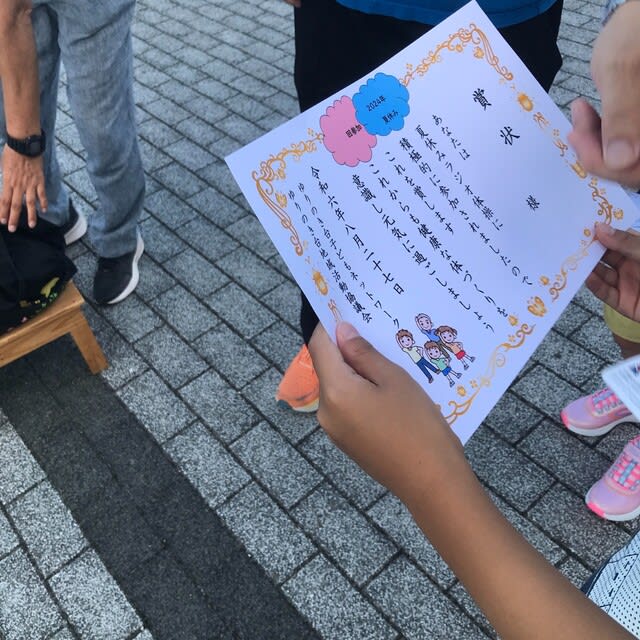6月議会に提案されていた、「三田市立学校の目的外使用条例の改正案」で地域が祭等を開催する際に飲酒の提供を禁止する条文が撤回され、19日の本会議で改めて飲酒条文が削除された目的外使用条例案が提出されました。
福祉教育常任委員会にこの議案が審議され、全会一致で賛成可決されました。
明日の本会議で委員会の採決で異議がないようなら、条例案は7月1日から施行されます。
改正内容は、校長先生が目的外使用許可できる施設の範囲の拡大とグランドの利用時間が7時から借りられるなど利便性が高まる内容となっています。
それにしても、今回の目的外使用の禁止に飲酒や酒類販売を入れ込むことは「子どもの保護の観点、教育の観点」から必要である。との教育委員会の論理は、子ども達を無菌状態で育て、汚いものから遠ざける行為にうつります。「教育現場である」ことは言うまでもありませんが、これを目的外使用許可を与えることで、地域がお借りする「地域の交流の場」となり、ここでは、大人も子供も、地域に住んでいる隣人として、例えばほろ酔いの大人たちを見ることも、子どもたちにとっての育ちになるのではないでしょうか。
数年後には地域社会も変わり、教育現場の学校からアルコールが完全に「無くなる日」が来るかも知れませんが、地域の学校のあり方を今回の条例案は、示してくれたのではないかと感じています。
これがきっかけとなり、地域と学校のコミュニケーションがますます、深まることを願っています。
福祉教育常任委員会にこの議案が審議され、全会一致で賛成可決されました。
明日の本会議で委員会の採決で異議がないようなら、条例案は7月1日から施行されます。
改正内容は、校長先生が目的外使用許可できる施設の範囲の拡大とグランドの利用時間が7時から借りられるなど利便性が高まる内容となっています。
それにしても、今回の目的外使用の禁止に飲酒や酒類販売を入れ込むことは「子どもの保護の観点、教育の観点」から必要である。との教育委員会の論理は、子ども達を無菌状態で育て、汚いものから遠ざける行為にうつります。「教育現場である」ことは言うまでもありませんが、これを目的外使用許可を与えることで、地域がお借りする「地域の交流の場」となり、ここでは、大人も子供も、地域に住んでいる隣人として、例えばほろ酔いの大人たちを見ることも、子どもたちにとっての育ちになるのではないでしょうか。
数年後には地域社会も変わり、教育現場の学校からアルコールが完全に「無くなる日」が来るかも知れませんが、地域の学校のあり方を今回の条例案は、示してくれたのではないかと感じています。
これがきっかけとなり、地域と学校のコミュニケーションがますます、深まることを願っています。