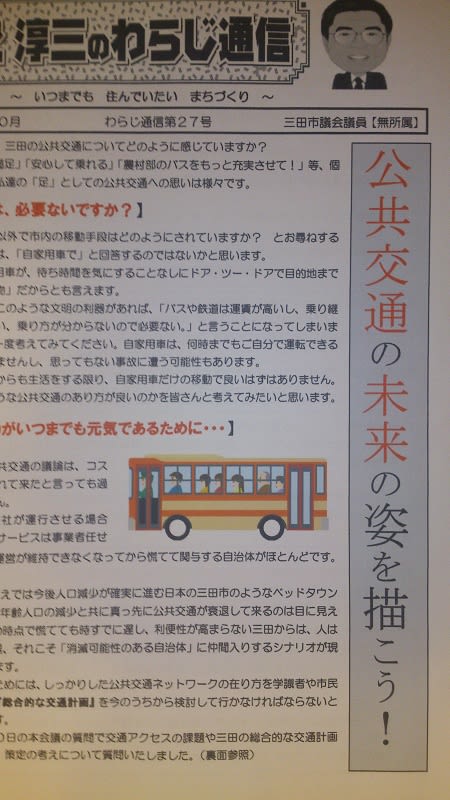昨日は、ウッディタウン市民センターで開催された「学校司書って、こんな仕事」と題した講演会に午前中出席、そして午後1時30分より約2時間タウン(わらじ)ミーティングを開催し、参加された皆様と意見交換させていただきました。
まず、午前中に開催された「学校司書の仕事」の講演会では、豊中市立第1中学校の学校司書今野千束さんの司書としての経験を中心に、法的な位置づけ、司書の仕事としての深さや意義を興味深く話され、良く理解できる内容だったと思います。
今野さんは、学校司書と司書教諭の違いにもふれ、多忙な教師が学校長から司書教諭を任命されている学校が多いが、子供に向き合う時間や本の紹介などは専門性の高い学校司書が必要。また、法的には学校司書は努力義務となっているが、アルバイトや学校数校を一人の司書が兼務する状態は学校図書館を運営する観点からすると好ましくない姿であり、三田市は是非一つひとつの学校に一人の司書を置いてほしい。と訴えかけました。
また、司書として日頃行っているブックトークを披露し、あらかじめテーマ「図書館」を決めての数冊の本を紹介した実演は、「本が読みたい!」と思わせる魅力あるトークでした。
また、参加者からは、学校司書がいる学校といない学校の違いは?との質問に対して今野さんは「その質問が一番回答しにくく、学校司書を配置しているから成績に直結する、子供の人生が変わった!など定量化できるものは見つからないが、社会人になったころに本に出会えて良かったと振り返ってくれれば・・・」と熱い思いを述べました。
さらに、学校司書のいた学校から転入してきたある女性からは、「今子供が中学生だが、子供から、学校司書と良く会話をし図書を紹介してもらったので、司書のいる学校は良かったと伝えてほしい。また、本を貸し出してもらえる時間が三田市は限定されており、子供の成長に与える影響は確実にあると思う」と学校司書配置の良さを発言していました。
三田市教育委員会が学校司書の配置を来年度予算で検討することになっていますが、どのレベルまで引き上げて来るのかその内容をしっかりと確認したいと思います。
さて、午後からは、恒例のタウンミーティングを同じ市民センターで開催させていただきました。
参加者は6名でした。その中で先日配付したわらじ通信第27号をお読みになり来て下さった方も来てくださいました。
今回のミーティングのテーマは、「環境」です。
先日視察した伊丹市学校給食センターの残渣高速発酵処理機の報告も交え私から学校給食の残渣の処理のあり方など「食育」「環境」に資する処理方法をコストだけにとらわれな検討を進めて行ければ・・。と説明させていただきました。
参加者からは、パスカル、福祉保健センターに行きたいが車を持っていない。行きの便はあるが、帰りの便がなく、便の増便の必要性を訴えておられました。
現在のバス便は、三田駅へ向かうバスルートが、3便ほど福祉保健センターに停車しますが、決して利便性が高いとは言えません。高齢者が増えて来る中、車を持たない、あるいは、免許を返納した市民の方をこのエリアに足を運んでいただくのは、バスなどの充実が必要です。事業者が出さないのであれば、市が負担をしてモビリティー・マネジメントを行い市民にバスに乗っていただくなど施策を展開してほしいと思います。
また、参加者からは、市内開発などで当初地域住民と約束していたことが守られていないことがあり、行政のその後の確認などは、どのようにしているのかや地域でグループ活動しているが、なかなか行政と連携できないことなどが意見として出されました。
このことに関して別の参加者からは、地域の似たようなグループ同士の連携や情報共有が市民グループには必要であり、点で動いても行政は動かない、点から面で動くことが大切ではないかとの意見が出されました。
さらに「政務活動費」に関しての質問もあり、三田市の現在の動きを知りたいことと政務活動費は、報告書をインターネットで開示すべきではないか?との意見が出されました。
現在の三田市議会での動きは、政務活動費の使途基準のルールなどを再点検する話が議会運営委員会で出てきており、今後検討が進むものと思われます。また、ネット公開についてもその中での議論となるのか、議会改革推進会議の話となるのかが定かではありませんが、私は、透明度を高めるためにも公開の必要性があるのではないかと考えています。
昨日、わざわざ参加していただいた市民の皆様に感謝いたします。
次回ミーティングは場所を変え、ゆりのき台コミュニティハウスで11月23日、午前10時~開催します。
皆様のお越しをお待ちしています。
まず、午前中に開催された「学校司書の仕事」の講演会では、豊中市立第1中学校の学校司書今野千束さんの司書としての経験を中心に、法的な位置づけ、司書の仕事としての深さや意義を興味深く話され、良く理解できる内容だったと思います。
今野さんは、学校司書と司書教諭の違いにもふれ、多忙な教師が学校長から司書教諭を任命されている学校が多いが、子供に向き合う時間や本の紹介などは専門性の高い学校司書が必要。また、法的には学校司書は努力義務となっているが、アルバイトや学校数校を一人の司書が兼務する状態は学校図書館を運営する観点からすると好ましくない姿であり、三田市は是非一つひとつの学校に一人の司書を置いてほしい。と訴えかけました。
また、司書として日頃行っているブックトークを披露し、あらかじめテーマ「図書館」を決めての数冊の本を紹介した実演は、「本が読みたい!」と思わせる魅力あるトークでした。
また、参加者からは、学校司書がいる学校といない学校の違いは?との質問に対して今野さんは「その質問が一番回答しにくく、学校司書を配置しているから成績に直結する、子供の人生が変わった!など定量化できるものは見つからないが、社会人になったころに本に出会えて良かったと振り返ってくれれば・・・」と熱い思いを述べました。
さらに、学校司書のいた学校から転入してきたある女性からは、「今子供が中学生だが、子供から、学校司書と良く会話をし図書を紹介してもらったので、司書のいる学校は良かったと伝えてほしい。また、本を貸し出してもらえる時間が三田市は限定されており、子供の成長に与える影響は確実にあると思う」と学校司書配置の良さを発言していました。
三田市教育委員会が学校司書の配置を来年度予算で検討することになっていますが、どのレベルまで引き上げて来るのかその内容をしっかりと確認したいと思います。
さて、午後からは、恒例のタウンミーティングを同じ市民センターで開催させていただきました。
参加者は6名でした。その中で先日配付したわらじ通信第27号をお読みになり来て下さった方も来てくださいました。
今回のミーティングのテーマは、「環境」です。
先日視察した伊丹市学校給食センターの残渣高速発酵処理機の報告も交え私から学校給食の残渣の処理のあり方など「食育」「環境」に資する処理方法をコストだけにとらわれな検討を進めて行ければ・・。と説明させていただきました。
参加者からは、パスカル、福祉保健センターに行きたいが車を持っていない。行きの便はあるが、帰りの便がなく、便の増便の必要性を訴えておられました。
現在のバス便は、三田駅へ向かうバスルートが、3便ほど福祉保健センターに停車しますが、決して利便性が高いとは言えません。高齢者が増えて来る中、車を持たない、あるいは、免許を返納した市民の方をこのエリアに足を運んでいただくのは、バスなどの充実が必要です。事業者が出さないのであれば、市が負担をしてモビリティー・マネジメントを行い市民にバスに乗っていただくなど施策を展開してほしいと思います。
また、参加者からは、市内開発などで当初地域住民と約束していたことが守られていないことがあり、行政のその後の確認などは、どのようにしているのかや地域でグループ活動しているが、なかなか行政と連携できないことなどが意見として出されました。
このことに関して別の参加者からは、地域の似たようなグループ同士の連携や情報共有が市民グループには必要であり、点で動いても行政は動かない、点から面で動くことが大切ではないかとの意見が出されました。
さらに「政務活動費」に関しての質問もあり、三田市の現在の動きを知りたいことと政務活動費は、報告書をインターネットで開示すべきではないか?との意見が出されました。
現在の三田市議会での動きは、政務活動費の使途基準のルールなどを再点検する話が議会運営委員会で出てきており、今後検討が進むものと思われます。また、ネット公開についてもその中での議論となるのか、議会改革推進会議の話となるのかが定かではありませんが、私は、透明度を高めるためにも公開の必要性があるのではないかと考えています。
昨日、わざわざ参加していただいた市民の皆様に感謝いたします。
次回ミーティングは場所を変え、ゆりのき台コミュニティハウスで11月23日、午前10時~開催します。
皆様のお越しをお待ちしています。