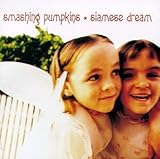|
Now I Got Worry 価格:¥ 1,341(税込) 発売日:1997-05-01 |
THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION「NOW I GOT WORRY」1996US
ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョン
「ナウ・アイ・ガット・ウォーリー」
1. Skunk
2. Identity
3. Wail
4. Fuck Shit Up
5. 2 Kindsa Love
6. Love All of Me
7. Chicken Dog
8. Rocketship
9. Dynamite Lover
10. Hot Shot
11. Can't Stop
12. Firefly Child
13. Eyeballin
14. B.L. Got Soul
15. Get over Here
16. Sticky
ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンは極めて今日的で意識的なバンドだ。ニルヴァーナ、ベック、に連なる現代的な意味性を抱えたバンドだと思う。そして恐ろしいことに極めて優秀なポップセンス、メロディーのバランスを持ったバンドでもある。
全世界が低成長時代に突入し、誰もが悩みを抱える90年代以降において、個々人がリアリティを感じる音は、大なり小なり、挫折や悩みや苦痛から出発したものが目立つようになってきた、といえるだろう。そしてそれは社会全体がまとめてハッピー、という訳にはいかなくなった以上、個々人での感情の発露であったり、方法論の模索であったり、より個人的で手作り感のあるものが多くのリアリティを獲得するようになってきたわけだ。
90年代前半までは、そんなパーソナルな感触の音楽なり映画はまだマイノリティだった。
ずっといつの時代もそういう音楽に対する需要はあり続けてきたし、ロックというもの自体が元来そういうものであったかもしれない。
しかし80年代の後半以降、じわじわとそういうタイプの映画や音楽が一般的な共感を得るようになってきた。
マイナーで、手作り感のある、じわじわっとした挫折感と回復や希望の物語、あるいは暗黒小説。
つまり70年代以前のように、生活者の根本的な生活や人権を脅かすような大きな脅威が希薄になった代わりに(当然たくさんの問題はありますが)ひとりひとりの幸福が、社会全体や国という大きな価値観のくくりでは保証されないことが明白になった世代、において、本来マイノリティの音楽であるはずのロック、というものが地下水脈のようにじわじわと、一般的な人たちに広く広くニーズとして広がっていた、それが90年代初頭までだったのでは、と思う。
そうした下地の上に、REMやソニックユースやビースティーボーイズなどがじわじわと共感を集め、一気にオセロをひっくり返すように、鬱屈したネガティブな個人的な感情を、”表”に引きずり出して圧倒的な共感を獲得してしまったのがニルヴァーナという器だった。ヘヴィメタとアメリカンロックとパンクといった音楽的には新しさはないが、これ以上ないほど圧倒的な感情の爆発と鬱積した魂の叫びを、これ以上ないほどポップで優れたソングライティングによって、地下に潜っていたはずの、社会を覆い尽くしていた時代の空気や感情を、一気に地上に引きずり上げ、目の前に暴き出してしまったのだ。
そして、その後を受けたベックは、暴き出された僕たちの日常を、あくまでも平熱でとらえ直し、そこをスタート地点として開き直ってしまった。猥雑で雑多な色々をそのまま飲み込んでゆけばいい、という感覚。精神性や時代性を伴ったミクスチュア。
ジョン・スペンサーが3rdアルバム「Orange」でブレイクしたのはそんな95年というタイミングだった。本作は翌96年の4thアルバムだ。
ジョン・スぺンサーは、ベックの立ち位置をさらに一歩おしすすめ、目一杯好きにやらせてもらうぜ、という我々にとって次に来るべきステップを、自ら先んじて、その圧倒的な実力とバランス感覚で、やってしまった。ということなんだろうと思う。ニルヴァーナによって、暴き出された焼け野原に一人一人が立ちすくんでいるような情景、それを日常と捉えなおしたベック、そして思う存分好きなようにやらせてもらうぜ、俺は!、と勝手にやりはじめた、それがジョンスぺであり、その姿が痛快で、まさしく象徴的であったがために、ジョンスぺはカリスマとなったのだ。その姿はまるで戦後の闇市にのしていこうとするチンピラの親分、仁義なき戦いの世界。あるいは最近のIT長者を彷彿とさせるのは僕だけでしょうか。あくまで褒め言葉の意味で。
さらにジョンスぺがキているのは、ブルースを持ち出したことだ。ブルースというのは元々が、極めてパーソナルな日常の喜びや悲しみや気持ちを歌うものだ。さらに言えば、奴隷としてつれてこられた新しい土地で、逃げることは出来ない、ここで生きていこうとしたときのある意味あきらめと覚悟を込めた歌でもある。そんな個人的な覚悟の宣誓歌を精神性のベースにして、もはや我々の日常となったガレージでパンクでHIPHOPなパーツを、自由自在なバランス感覚で”配置”してみせる。ガッツリと、魂の叫びをぶちまけながら、かゆいところに手が届くように音が叫びがくりだされてゆく。全ての音は、同じ負の感情を共有しているに違いない、という信頼感に変わっていく。同じように打ちのめされ、鬱積した感情を溜め込み、それでも圧倒的な感情を爆発させ、好きにやらせてもらうぜ、と叫ぶ。その叫びと狂気とブルースは、代弁者となり、先達となり、兄貴となり、カリスマとなる。
Orangeではブルースを絶妙のバランス感覚と狂気で豪快かつ大胆に再構築してみせたが、本作ではOrangeよりもソリッドでパンキッシュでロックにパワーアップしている。これだけチャレンジングな音楽に手をつけながら、同じ時代の空気をつかみ取り、今の僕らのストレスを振り払い、突き破り、突き進む音として機能する。そして徹頭徹尾退屈させず、注意を喚起し、釘付けにさせてしまうセンス、これはもうメロディーメイカー、ポップスターという因果な才能をもってしまったものの運命、とさえ言ってしまいたくなる。
ジョン・スペンサーのブルースの爆発、これはあくまで我々の先達としてのジョン・スペンサーのブルースの爆発であり、我々への意識的な問いかけでもあるのだ。我々は、どう爆発するのか。いずれにせよジョン・スぺは好きにやったのだ。