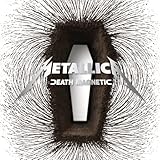|
Lateralus 価格:¥ 1,955(税込) 発売日:2001-04-18 |
Tool「Lateralus」2001年US
トゥール「ラタララス」
1.Grudge
2.Eon Blue Apocalypse
3.Patient
4.Mantra
5.Schism
6.Parabol
7.Parabola
8.Ticks & Leeches
9.Lateralis
10.Disposition
11.Reflection
12.Triad
13.Faaip De Oiad
Justin Chancellor(b)
Adam Jones(g)
Maynard James Keenan (vo)
Danny Carey(drs)
トゥールはいいですね。
ロス出身のへヴィロックなんだけど、普通のへヴィロックじゃない。
まず、現代のキング・クリムゾンって呼ばれるほどのバカテクがあること。
複雑怪奇で精巧な音が築き上げられる様は圧巻。
次にそのテクはあくまでも手段として、やはり暗黒な世界観、ブラックサバス的アリスインチェインズ的な呪術系ボーカル、しかしとてつもなく上手い叙情的ボーカルの生み出す独特の余韻。
この両者があいまって、Toolにしかない雰囲気、が生み出されます。
ちょっとクールで、ちょっと叙情的で、とてつもなく重く暗く、激しく、深く、闇のように静かで、無限にラウド。
陰影が生み出す深みが、クールな演奏と絶妙なバランスで、まさに「音をして語らしむ」といった感じです。そう、のたうつ音がグネグネと、まるで生き物のように、激しく語りかけてきます。楽器の演奏が主役、メイナードの乗り移ったようなボーカルが、それを煽り立てる、という感じです。ボーカルだけとっても超上手いんですが。
ブレイクした2nd「アニマ」よりも私はこの3rd「ラタララス」の方が好みです。
「アニマ」は叙情的な面が3rdよりも強くて、ちょっとDeftonesっぽい。
DeftonesのアルバムにもToolのメンバーは参加しているので似るのも不思議じゃないけど。
Toolには、あくまでもクールで、ハードで、インテレクチュアルで、ダークな、硬質なものをもとめたい。叙情性はほどほどにセーブしてもらいたい、なのでこの3rdがちょうどいいんです。
4th「10,000Days」もこの路線ですが、個人的には3rdに軍配を上げます。
これらのアルバムの発表周期はほとんど5年に一度。
超寡作ですね。
それなのに計2000万枚売ってると。
それだけ固定ファンをつかんでるって事ですね。
2ndは全米2位登場、3rdと4thは初登場1位です。
KornやRATMと並ぶかしのぐほど向こうではメジャーってことですか。
彼らの人気の要因はいくつもあると思いますが、ひとつは複雑な音世界の中にも、なにか立体的な構成空間が感じられ、マニアックなのにどこか聴き続けさせてしまうものがあります。ひとつにはGuitarのアダム氏が映画関係の製作にかかわっていたあたりの映像感覚が影響しているということがありそうです。
また演奏技術の高さ、がオリジナリティのある多彩なフレーズを生み出すことにつながり、次から次に繰り出される暗いフレーズの数々が、知性と深みと叙情性を感じさせます。
それが、たぶんグランジ世代、へヴィロックを求める世代に指示され続ける理由じゃないでしょうか。NINとか今聴くとちょっと単純というか、人生のある特定の時期に限定して響く音というか、時代性を感じてしますところもありますが、Toolのちょっとわかりにくい複雑で難解な感じも、時代の波を乗り越える上で、功を奏しているという気がします。
言い方を変えると、大人も聞けるへヴィロック。その点、ファンのあり方が、キング・クリムゾンっぽい気もします。クリムゾンも1stの叙情性から徐々に離れていきましたし。
両者は一緒にツアーもしてますね。
21世紀の名盤のひとつ、プログレとかDeftonesとかサウンドガーデンとかアリス・イン・チェインズとかへヴィロック全般好きな方にもおすすめです。
1stの1993年、すでに神がかったパフォーマンスが観客をのみこんでます。
Schism