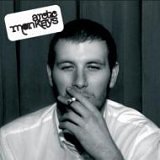銀座のラール・エ・ラ・マニエールに夜、行きました。
まあ1万円であのボリュームと工夫、なによりそのやる気と気概が気持ちいい、気分の良くなるお店でした。
まずはじめのアペリティブにビーツとオレンジのジュース。
そしてオードブルがほどよくしんなりさせてある辺りから気が利いています。
次の前菜の野菜盛り合わせから結構なバラエティ感を堪能でき、実量以上のボリュームを感じます。
おくらって生で食べれるんだ、って思いましたが。
パンは新丸ビルのポワン・エ・リーニュから取り寄せ、すべて温めてあって、トマトやメイプル、コーンなど甘めのものからバラエティに富む非常においしいもので、おかわりも持ってきてくれます。
次にムール貝のスープが大きな皿にきました。メレンゲを焦がした表面がアクセント。
次の来たのが、ハモと燻製ハム、ゆり根、とソースを絡めて、一口でほおばると、チーズのこげとスモーキーなハムと全体があいまってやはり非常にうまい。
さらにオマール海老、蕪に後からトマトコンソメのスープを注ぎ足す一皿。添えてあるなすのピューレと混ぜていただくと、非常にうまい。
グラスワインの値段がわからないので、こわくて白ワイン一杯でここまで粘ったが、まだ魚介の皿とお肉の皿が一皿ずつあることを確認し、赤ワインを一杯追加。
スモーキーでさっぱりとした赤ワインと合う。
全体通して、素材の味わいと絶妙なこげ感、火のいれ具合のバランスのとり方、が料理の大きな特徴になっていることに気づきます。
食事ラストは、わらに鶏肉を丸ごと包み込んで焚き染めた焼き物。
なべに入った状態で、同時間帯のお客にテーブルを回ってお披露目。
手羽部分と胸肉、もも肉の3部位がそれぞれ出て、濃厚なわらの香りと肉汁ソース、甘めのマッシュポテトのピューレといただく。ぎりぎりの香りの濃厚さでした。
これでおなか一杯、というところで小さなデザート、にんじんジュースにパッションフルーツ、ジンジャー入り、で口直し。
次に来たのが、なんと今組み上げたばかりの巨大なミルフィーユ、大きさと豪快さにびっくり。鳥もそうですが、その場の4組くらいのお客に切り分ける前に店に来る配慮がにくいです。
どのくらい来るかと思えば、結構な大きさで来ましたが、いただくとサックサクで軽いので、超すっぱいベリーのアイスクリームとぺロッといただけました。
かなり濃いコーヒーと合うこと。
で、さらに、ここで、試食ぐらいのサイズのクリームブリュレと温かいマドレーヌに焼き菓子2品。まあ、量を少なめにして、品数を増やし、サプライズ的にこちらの予想を超えてくる演出が、いいですね。そのあたりの気持ちというか気概に拍手というか。
これで、ワインの値段もグラス一杯2000円前後、で、こういう店ならまあそうでしょう、という範囲内。どれだけそこで持っていかれるかと思いましたが、全然普通。
というよりも、1万円でこの満足感はちょっとした驚きでした。
料理の内容、という以上に、何かシェフの気持ちに価格以上のものを感じた気がします。
焼き加減などの香りの濃さが、もしかすると人によってはギリギリのライン、かもしれませんが。
帰り際にご挨拶に顔をのぞかれたシェフはパリ帰りでまだ34歳とのことで、精悍でまじめな印象で20代後半にも見えましたが、これからもっと有名になられるかもしれませんね。
ウェイターさんが皆さん若いんですが、中にちょっとまあつたないというか、全体的にこなれた感が未だないのが、玉にキズでしょうが、お料理がそれを補って余りある、非常に満足な時間でした。
あ、あと時間でいえば、19時から食べ終わりが23時、トータル4時間で、皿が出てくるに応じて順調に食べてそれなので、ちょっと時間かかりすぎ、というのもフランス感覚でしょう、あやうく終電ギリギリでした。
以上。
<<まんぞく度ランキング>>
一位:てんぷら近藤(和、銀座)
二位:ラ・ベットラ・ダ・オチアイ(イタリアン、東銀座)
三位:シェ・ヤマライ(広島)
四位:ジョエル・ロブション(フレンチ、恵比寿)、ラール・エ・ラ・マニエール(フレンチ、銀座)
五位:ラトリエ・ドゥ・グー(フレンチ、吉祥寺)、シェ・パルメ(フレンチ、渋谷)
六位:トリスケル(イタリアン、広島)
七位:ロス・レイエス・マーゴス(スペイン、代々木上原)、カサ・デ・フジモリ(スペイン、広島)
八位:サヴォイ(イタリアン、目黒)、ナプレ(イタリアン、青山)
九位:アルポルト(イタリアン、六本木)
十位:
サルヴァトーレ・クオモ(イタリアン、表参道、赤坂)
リストランテ・ヒロ(イタリアン、代官山)
メイハネ・トプカプ(トルコ、青山)
瀬里奈(新宿)
スーパーダイニングジパング(赤坂)
高瀬(代々木)
<番外編>
カリブ(広島・坂)
利久(牛タン、仙台)、旨味太助(牛タン、仙台)
<ハンバーガー満足度ランキング>
1.East Village(池袋東口)
2.Oatman Diner(池袋西口)
3.632(原宿)
4.ウエストパーク・カフェ(赤坂)
5.サニー・ダイナー(北千住)
6.ベーカー・バウンス(東京ミッドタウン)
6.クアアイナ(青山)
7.バーガー・キング
他