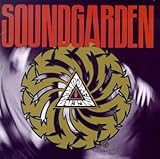|
I Can Hear the Heart Beating as One 価格:¥ 1,211(税込) 発売日:1997-04-22 |
Yo La Tengo「I Can Hear the Heart Beating as One」1997年US
ヨ・ラ・テンゴ「アイ・キャン・ヒア・ザ・ハート・ビーティング・アズ・ワン」
1. Return to Hot Chicken
2. Moby Octopad
3. Sugercube
4. Damage
5. Deeper into Movies
6. Shadows
7. Stockholm Syndrom
8. Autumn Sweater
9. Little Honda
10.Green Arrow
11.One PM Again
12.The Lie and How We Told it
13.Center of Gravity
14.Spec Bebop
15.We're an American Band
16.My Little Corner of the World
17.Bush with My Together
Georgia Hubley(Vocal,Drums), Ira Kaplan(Vocal,Guiter), James Mcnew(Vocal,Bass)
奇妙な名前の3人組。アイラさんとジョージさんは夫婦。名前の由来は、スペイン語で”I got it."の意。
マイ・ブラッディ・バレンタインとかシューゲイザー系の轟音とささやきヴォーカル、ヴェルベット・アンダーグラウンドのフォロワー的な面、繊細で優しいメロディはレモンヘッズやティーンエイジファンクラブ、マシュースウィートを彷彿とさせたり、まあとらえ所のない独特の世界があります。ソフィア・コッポラの映画ヴァージン・スーサイズとかベル&セバスチャンとか好きな方にもおすすめします。
本作は8枚目。米インディ界のベテランがようやく?出した傑作です。
全体通して、メロディが優しくて美しい。
しかし、そこは長年インディでやってきた強者。そう簡単にはいきません。
印象に残るのは、曲ごとの対比、コントラスト、落差。
ふわふわした曲の後には轟音ギター系、疾走感のある曲の後にはゆっーーくりまっーーたりした曲、交互にきます。
またこの対比は1曲の中でも見られます。
ふわふわした浮遊感のあるヴォーカルやメロディーラインには、正対するようにグイングインのベースや轟音ギター、疾走感のある曲だって、簡単には歌ってきません。膜の向こう側からまるで夢の中で声を聴いているような感じです。
この対比性が、それ自体で批評性を帯びているようです。
夢の中なのに覚醒している、疾走しているはずなのに、水の中で走っているような感じ。
しかしこの感じ、クセになります。
イントロのゆったりした入りからの2.Moby Octopadの冒頭のベースラインは非常に印象的です。
一転して3は疾走感のあるナンバーです。米ギターポップ系のメロディーのよさとハーモニーが懐かしい。しかしそこはヨラテンゴ、後半ギターが歪みながら、あくまでもメロディーは美しい。
4.Damageなんかはもろヴェルヴェッツ・ミーツ・ヨラテンゴです。浮遊感満点のサイケなナンバーです。
5はフレーズのリピートが夢に出そうなノイズギターナンバー。
一転して6は静謐なボーカルナンバー。
7は、これまた一転して、ジェームスのボーカルがどこか切なく印象的なアコースティックナンバー。これだけ曲ごとに印象を変える事自体が、不思議です。夢のような曲でトリップさせたと思ったら、次にはその世界をぷっつり変えてくるわけですから。これは批評性、覚醒を帯びていると感じるでしょう。それにしても不思議です。
8はアイラのオルガンと加工処理されたボーカルが不思議な世界を紡ぎ出す印象的なポップナンバー。
9はまたヴェルヴェッツを感じさせる疾走感あるビーチボーイズのロックンロールナンバー。轟音ギターと共に。ヴォーカルは決してシャウトしません。
またまた一転して10は夜の虫の声からはじまる静謐なインスト。
11、12は穏やかで柔らかなポップナンバー。
14はいかにもなインスト。
15は轟音ギターがゆったりしたテンポのダイナソーJrっぽいナンバー。
16はカバー曲で60年代ポップスのような雰囲気。
ラストはボーナストラックでちょっと浮いてるけど16の延長。
捨て曲なし、と言われる傑作の条件をそなえた本作、曲ごとのメリハリが、曲の個性を際だたせています。ジョギングをしながら聴くと合うんです、これ。
アメリカン・オルタナティヴが生んだサイケ・ギターロックの金字塔、傑作です。




■この記事を評価して、関連の人気記事もチェック!
★★★★(素晴らしい)
★★★☆(すごい)
★★☆☆(とても良い)
★☆☆☆(良い)
by TREview