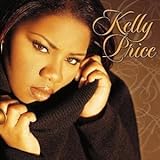|
Funky Divas 価格:¥ 1,127(税込) 発売日:1992-03-23 |
En Vogue「Funky Divas」1992年US
アン・ヴォーグ「ファンキー・ディーバス」
1 This Is Your Life (05:05)
2 My Lovin' (You're Never Gonna Get It) (04:42)
3 Hip Hop Lover (05:13)
4 Free Your Mind (04:52)
5 Desire (04:01)
6 Giving Him Something He Can Feel (03:56)
7 It Ain't over Till the Fat Lady Sings (04:13)
8 Give It up, Turn It Loose (05:13)
9 Yesterday (02:30)
10 Hooked on Your Love (03:35)
11 Love Don't Love You (03:56)
12 What Is Love (04:19)
13 Thanks/Prayer
Dawn Robinson(Vo)
Terry Ellis(Vo)
Maxine Jones(Vo)
Cindy Herron(Vo)
70年代のシュープリームスらが第一次ガールズ・グループブームだったとすると、SWV、TLC、デスティニーズチャイルドに繋がる第二次ガールズ・グループの流れは1990年アン・ヴォーグの1st「Born to sing」から始まりました。
80年代後半を席巻したGuyのテディ・ライリーによる”ニュー・ジャック・スウィング”の切れが良くてバウンシーで刺激的なダンスビートは、90年代に入ってもまだまだシーンを一色に染めていました。
しかし徐々に、NJS(New Jack Swing)の中心だったニューエディションの内の3人が結成したベル・ビブ・デヴォーの「Poison」(90年)などを契機に、イギリスから流入してきた”グラインド・ビート”のゆったりとした重心の低いダンス・ナンバーへと、シーン全体はシフトし始めてゆきました。いわゆる”Low beat化”現象です。
一方HIPHOPサイドでも洗練されたニュー・スクール勢の登場が一般のファン層を拡大し、ゆったりとしたR&Bのダンスビートは、HIPHOPとの相性がよい、ということが徐々に明らかになってゆきます。
やがてそれはヒップホップ+ソウルの融合、ということでメアリー・J・ブライジの登場に繋がってゆくことになります。
そんな過渡期に西海岸から登場したのが、ルックスと実力を兼ね備えたスーパーグループ、アン・ヴォーグでした。
初めは雑誌から取った「ヴォーグ」という名前で活動していたくらいの迫力の容姿でいながら、実力は十分でした。
なかなか腰の据わった、というかドスのきいた節回し、スローなナンバーからアップビートな曲まで歌いこなす歌唱力を備えていました。
本作では、かなり1曲1曲が粒だっており、クオリティとバラエティはかなり充実しています。分厚いコーラスと洗練されたビートの2曲目はR&B1位、真逆のアレサ・フランクリンのスローナンバー6曲目もR&B1位を獲得しました。
圧巻のブラック・ロックの4曲めも最高です。
一転して5曲目はシルキーなヴォーカルが最高なレゲエ調ナンバー、7曲目などの流れるようなラップの挿入は、NJSとは異なる角度でHIPHOP感の導入にとりくんだ仕掛け人フォスター&マッケルロイの成果でしょう。
ハイライトのミディアムナンバー8曲目、ピアノとギターがジャジーな再びアレサのカバー10曲目、アン・ヴォーグ流どポップナンバーの11曲目、12曲目と最後まで全くだれない捨て曲なしの充実ぶりです。大ヒットしないわけがありません。
しかし、すこしずつ時代は移り変わってゆきます。
タイトなNJSに対し、ルースな(ゆるい)ロウ・ビートの流れは、HIPHOPのストリートでダークなテイストとも共振するところで、次代の気分だったのだと思います。その辺りは、90年代に入るところで、ロックの精神性の流れとも一致するところでしょう。
アン・ヴァーグは、その真ん中で、その実力ゆえに、時代を超えた、特に70年代的なテイストを引っ張ってこれるほどの歌唱力をもって、あたらしい次代の音のヴァリエーションを歌いこなしてくれました。
しかし、美しくて洗練された非日常的な歌唱の実力を持つ彼女らに対し、よりストリート的で、生まれつきのHIPHOP感覚をもった次の世代、への移行は一気に進みました。
ある意味では80年代的な気分の最後の花、だったのかもしれません。
しかし、彼女らに続いたガールズ・グループがその後のシーンを引っ張ったこと、脱退したドーン・ロビンソンが、やはりNJSからスタートし、そのセンスで超然としたポジションを獲得したトニ・トニ・トニのラファエル・サディーク、やはり芸術的なセンスでHIPHOP界を牽引したATCQのアリ・シャヒードという豪華な3人でつるんだLucy Pearlで、2000年に最高の傑作を出し、存在感をしめしたこと、などやはり、その功績は大きいものがありました。
90年代初めの忘れられないスーパーグループ、アン・ヴォーグの傑作です。
"Free your mind"
"My Lovin' (You're Never Gonna Get It) "