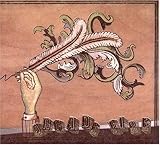 |
Funeral 価格:¥ 1,437(税込) 発売日:2004-09-14 |
Arcade Fire「Funeral」2004年US
アーケイド・ファイヤ「フューネラル」
1 Neighbourhood (Part 1/Tunnels)
2 Neighbourhood (Part 2/Laika)
3 Une Annee Sans Lumiere
4 Neighbourhood (part 3/Power Out)
5 Neighbourhood (part 4/7 Kettles)
6 Crown Of Love
7 Wake Up
8 Haiti
9 Rebellion (Lies)
10 In The Backseat
ウィン・バトラー (Win Butler) ボーカル、ギター、ベース、キーボード他
レジーヌ・シャサーニュ (Régine Chassagne) ボーカル、アコーディオン、ハーディ・ガーディ他
ウィル・バトラー (William Butler) シンセサイザー、ギター、ベース、パーカッション他
リチャード・パリー (Richard Reed Parry) アップライト・ベース、ギター、アコーディオン他
ティム・キングズベリー (Tim Kingsbury) ギター、ベース、キーボード他
サラ・ニューフェルド (Sarah Neufeld) ヴァイオリン他
ハワード・ビラーマン (Haward Bilerman) ドラム他
2作目である本作と3作目の「ネオン・バイブル」だけで全世界が注目するバンドになったアーケイドファイヤ。
2004年に出された本作は、当時の大統領であったブッシュのお膝元であるテキサス出身であるバンドの主人物ウィンが、大学進学を契機にカナダへ移住し、弟以外はカナダ人と作ったバンド。
故に懐かしさを感じさせる強烈な個性、アメリカの古い時代を連想させる衣装、コミュニティへの憧憬、ここではない世界への渇望を歌うその個性は、違和感を感じさせるアメリカ、世界への反発がこめられています。
その意味では、ほかの多くのグランジ以降のバンド同様、負の時代のアメリカ、社会への違和感や反発を歌う世代のバンドと同じメンタリティを抱えているといえるでしょう。
しかし、どこかほかのバンドと違うのは、直情的に自分の感情をぶちまけるのではなく、いったん物語的なアプローチをとること、フォークロアな多種多彩な古い楽器を使いまくることによって現代的な分厚い音を出してしまおうという取り組みの意思性があります。
かつ、どこかパンク以降のエキセントリックなニューウェーブの香りを醸し出す音。
オーケストレーションを効かせた壮大な曲、お葬式というタイトルやコンセプトアルバムという形式。
それらすべてが、時代全体と向き合おうとする視点の高さ、スケールの大きさをかんじさせます。
そしてなにより6-70年代のロックを思い起こさせるボーカルスタイル。
声質はどこかデヴィッド・ボウイを彷彿とさせるところがあります。
ちょっと頼りなさげに、しかし切々と謳い上げる情感的な歌いまわし、これはこのバンドの肝ともいえる要素でしょう。
1曲目は幻想的な音の中で、ピアノがパンチを効かせた立ち上がり。
徐々にボーカルの熱が上がるに沿って、楽器隊の音も熱くなってゆきます。
2曲目、まさにこのバンドの真骨頂。
今度はドラムでオープニングと思ったらすぐに、ギターが絡んできて、そこへ懐かしいフォークロアな感じのアコーディオンが昔感を醸し出したと思ったら、ニューウェーブっぽいエキセントリックなボーカルがかぶさってくるという。そしてそれらの音の層がそろったところでキャッチーなサビへ突入。
3曲目は女性ボーカルと絡む静かで幻想的な一曲。と思いきや最後に転調しアップテンポに。
4曲目は、圧巻。強烈かつ切実感を伴った音とボーカルが胸に迫ってくる。鉄琴の音が効いてる。古いアメリカを感じさせるフォークロアな音で、とても厚い音を作り上げている。とても勢いのあるアップテンポな曲でもあるのでライブでハイライトのひとつになりそう。
5曲目は主にバイオリンとボーカルのアコースティックな一曲。メロディとボーカルのよさが際立つ曲だが、曲の隅々までピリッとパンチが効いてる。ぼやっとならない所がすばらしい。
6曲目は低音から始まる叙情的なバラード。ここでもバイオリンがボーカルに寄り添う。
パンクな精神とオーケストラが出会った、という感じ。
7曲目はアンセムソング。
こういう曲が書けてしまうことから感じるのは、その人(達)には始めから世界観とか出したい音の像がしっかりとあるんだろうな、ということ。
その確固たるイメージ像の要素やパーツは、80年代ロックや80年代ニューウェーブ、パンク、90年代インディーロックを経由し、かつ社会に対する人とてのポリシーみたいなものがしっかり存在することを感じさせます。
それらを音にする時のこの人たちの武器、個性が、ウィンの声であり、フォークロア的な楽器隊であり、厚いメロディーだということです。
8曲目も怪しげでレトロなメロディが軽くてポップでいい感じです。
サイケに音を揺らめかせながらノンストップで9曲目へ展開。
分厚い王道のパワーポップという感じです。
ラストはウィンの奥さんレジーヌの絶唱が聴ける名曲。
そんな訳で非常にすばらしいアルバムが突然変異のように登場したわけです。
次のアルバム「Neon Bible」もいいんですが、ポップになった分ボーカルの個性がかき消されるつくりになってしまった気がします。かつ謳い上げる系の曲はどこか大仰で、かのミートローフを思い出したりするくらいでした。悪くは無いですが。
この「Funeral」は叙情的であるぶん、コンセプトがしっかりと音の輪郭、メリハリを際立たせていて、曲やバンドの個性が明確に打ち出せていると思います。
今後も楽しみな集団が2004年に残した名盤です。
”Neighborhood #3 (Power Out) ”
”Neighbourhood (Part 2/Laika) ”













