1920年代のモダニズム文学 「浅草を“捕獲”すること」
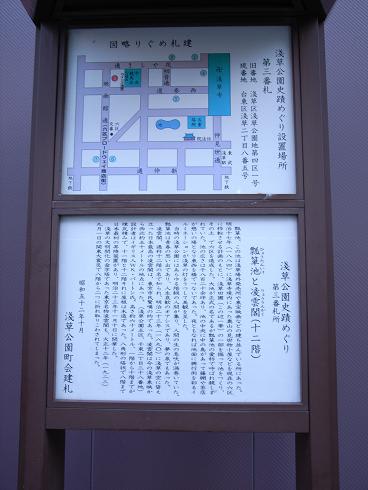
1920年代当時、十二階がそびえ立つ浅草は有数の繁華街、映画館では『メトロポリス』が鳴り物入りで封切られていた…。
浅草は文化の中心であり、十二階は時代のランドマークであった。浅草寺を中心とする門前町には、祝祭的な気分、ハレとケを無化する空気があふれていた。
浅草の賑わいを、高村光太郎は「米久の晩餐」という詩で描いている。「米久」は、大衆的な牛鍋屋で、高村もよく通ったという。
「 まるで魂の銭湯のやうに
自分の心を平気でまる裸にする群集、
かくしてゐたへんな隅隅の暗さまですつかりさらけ出して
のみ、むさぼり、わめき、笑ひ、そしてたまには起こる群集、 」
この詩は、近代都市の成立とともに生まれた「群衆」という概念が、東京にも息づいていることを告げる。「八月の夜は今米久にもうもうと煮え立つ。」。煮え立つのは牛鍋ばかりではない。大正モダニズムの大衆文化は群集のエネルギーによって加速し、成熟に向かう。
群集によって突き動かされ、めまぐるしく変貌する都市の姿をいかに捉えるか。都市の感受性を持った作家は、そんな命題に挑んだ。
川端康成は、『浅草紅団』でルポタージュの手法を用いて、浅草の雰囲気を小説空間に再現しようと試みた。
また、谷崎潤一郎は、様々なスタイルで浅草を舞台にした小説を明治・大正期に残している。主な作品を挙げると、「秘密」は、浅草に一人暮らしする主人公が映画館で偶然女性と再会する都市小説であるし、「魔術師」「人魚の嘆き」は、見世物小屋の“白昼に見る夢”的イメージを結晶化した散文詩風小品である。
未完だが「鮫人」は、浅草を小説中に構造化しようとした野心作だった。
「鮫人」で、谷崎は、主要登場人物の容姿を10数ページにわたって(!)描写し尽すことによって、浅草の混沌としたエネルギーを象徴的にミニチュア化する荒技を見せている。
「……或る皮肉屋は彼の容貌を評して「剥製の大蝙蝠」と云った。また口の悪い女優は彼を罵って「河馬」と云った。これらの警句は幾分か実物を髣髴せしめるには足りるけれども、要するに一面の観察たるに過ぎない。で、読者が若し此の不思議な面魂に就いてもっと委しく知りたいと思うならば、……」 「鮫人」より
このような描写が延々と続く。作品としての破綻を辞さないこの“怪物”的な描写は、谷崎が浅草を“捕獲”した成果であると思われる。
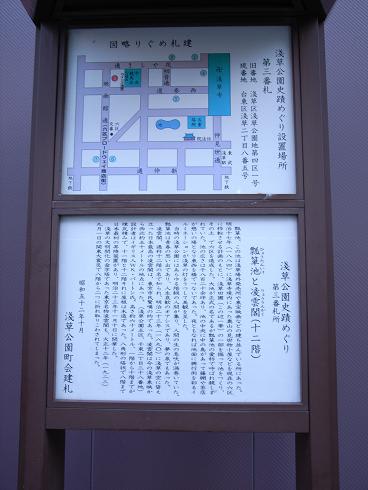
1920年代当時、十二階がそびえ立つ浅草は有数の繁華街、映画館では『メトロポリス』が鳴り物入りで封切られていた…。
浅草は文化の中心であり、十二階は時代のランドマークであった。浅草寺を中心とする門前町には、祝祭的な気分、ハレとケを無化する空気があふれていた。
浅草の賑わいを、高村光太郎は「米久の晩餐」という詩で描いている。「米久」は、大衆的な牛鍋屋で、高村もよく通ったという。
「 まるで魂の銭湯のやうに
自分の心を平気でまる裸にする群集、
かくしてゐたへんな隅隅の暗さまですつかりさらけ出して
のみ、むさぼり、わめき、笑ひ、そしてたまには起こる群集、 」
この詩は、近代都市の成立とともに生まれた「群衆」という概念が、東京にも息づいていることを告げる。「八月の夜は今米久にもうもうと煮え立つ。」。煮え立つのは牛鍋ばかりではない。大正モダニズムの大衆文化は群集のエネルギーによって加速し、成熟に向かう。
群集によって突き動かされ、めまぐるしく変貌する都市の姿をいかに捉えるか。都市の感受性を持った作家は、そんな命題に挑んだ。
川端康成は、『浅草紅団』でルポタージュの手法を用いて、浅草の雰囲気を小説空間に再現しようと試みた。
また、谷崎潤一郎は、様々なスタイルで浅草を舞台にした小説を明治・大正期に残している。主な作品を挙げると、「秘密」は、浅草に一人暮らしする主人公が映画館で偶然女性と再会する都市小説であるし、「魔術師」「人魚の嘆き」は、見世物小屋の“白昼に見る夢”的イメージを結晶化した散文詩風小品である。
未完だが「鮫人」は、浅草を小説中に構造化しようとした野心作だった。
「鮫人」で、谷崎は、主要登場人物の容姿を10数ページにわたって(!)描写し尽すことによって、浅草の混沌としたエネルギーを象徴的にミニチュア化する荒技を見せている。
「……或る皮肉屋は彼の容貌を評して「剥製の大蝙蝠」と云った。また口の悪い女優は彼を罵って「河馬」と云った。これらの警句は幾分か実物を髣髴せしめるには足りるけれども、要するに一面の観察たるに過ぎない。で、読者が若し此の不思議な面魂に就いてもっと委しく知りたいと思うならば、……」 「鮫人」より
このような描写が延々と続く。作品としての破綻を辞さないこの“怪物”的な描写は、谷崎が浅草を“捕獲”した成果であると思われる。









