招魂社から靖国神社・護国神社への考察 川村一彦
童謡に蹴鞠、お手玉など共に数え歌が伝わって、時代やその地域を象徴する伝承文化となって残っている中で「一番初めは一ノ宮」と言う数え歌がある。
一番初めは、一ノ宮
二は、日光東照宮
三は、讃岐の金比羅さん
四は、信州の善光寺
五は、出雲の大社(おおやしろ)
六つ、村には鎮守様
七つ、成田の不動様
八つ、やはたの八幡宮
九つ、高野の弘法さん
十は、東京招魂社
これだけ真願かけたなら、浪子の病も治るだろ、ごうごうと鳴る汽車は、
武男と浪子の別列車、二度と逢えない汽車の窓、鳴いて血を吐くほととぎす。
ここに出てくる数え歌の十に出てくる「招魂社」は何かと訪ねて直ぐに答えられる人は少ない。実際は数え歌に出てくる、十は、東京招魂社は「靖国神社」「護国神社」の前身の名称である。
明治に入って戌辰戦争後の大総督有栖川宮熾仁親王が戦没の官軍の将校の招魂祭を江戸城に斎行に始るという。
その後、戦没者を慰霊、顕彰する動きが活発になり、お国の為に殉死した、「忠霊」「忠魂」を祀るために「招魂社」が創建された。
靖国神社
東京招魂社は軍が管轄するものとされた、一般の神社と異なるために問題が生じ正規な神社とするために軍当局は明治天皇の裁可を経て、社名を明治十二年に「靖国神社」と改め直され、別格官幣大社に列せられるようになった。
祭神は幕末から明治維新にかけて功のあった志士に始まりペルー来航以降の日本の国内外の事変、戦争等、国事に殉じた軍事、軍属の戦没者を「英霊」として祀る。
戦後は政教分離の推進により国家管理を離れ、宗教法人になり、公職に就く者の参拝については問題になった。
一時はGHQは靖国神社を焼き払い、ドックレース場計画が持ち上がったが、賛否両論で混乱し「靖国神社を焼却する事は、連合軍の占領政策と相容れない犯罪行為ある」と言って残されて、日本国のために殉死した英霊を祀る神社として平成16年度現在246万6532柱が祀られている。
戦後日本では国家の為に殉死した英霊の合祀の是非をめぐり神社本庁との包括関係にない、また管理の処遇を巡り政治色の強い神社となって、未解決の問題が多く残っている。
では明治時代に各地に祀られた招魂社はどうなったのか、概ね各府県に一社が設立された招魂社は昭和十四年に内務省令によって改称し「護国神社」と改められた。
各護国神社の祭神は靖国神社に一部重なるものの、靖国神社から分祀されたものではなく、府県に国の為に殉死した人の英霊を祀るための神社である。
終戦後、軍国主義の施設と見なされ、維持存続をするために社名をかえた。
独立後は元の社名に戻された。
府県に五十二社あって、昭和三十五年より天皇、皇后陛下から幣帛が終戦から数えて十年ごとに賜与されている。
社格は府社、県社と相当する内務大臣指定護国神社と村社に相当する指定外護国神社に分けられた。
指定護国神社には北海道に三社、兵庫県、広島県、島根県、岐阜県に二社の護国神社が祀られている。
北海道護国神社 指定、 北海道旭川市
北海道,樺太関係の戦没者を英霊として祀る。戌辰戦争から大東亜戦争までの63141柱の英霊が祀られている。明治35年大迫陸軍大将を祭主として招魂祭を執り行なったのが始まりと言う。昭和14年には招魂社から内務省護国神社となった。昭和19年に樺太護国神社が合祀された。戦後はGHQからの追及を逃れるため北海道神社と社名を変えたが独立後、北海道護国神社に戻された。
幌護国神社 指定、 北海度札幌市中央区
明治10年の西南の役に戦病没した屯田兵の霊を祀る。 有栖川熾仁親王により屯田兵招魂碑と題し、明治12年8月2日屯田兵司令部に於て祭祀を斎行する。日露戦争の戦病没者の合祀のため忠魂碑を建て、乃木将軍之を題す。昭和8年札幌招魂社を造営し官幣大社札幌神社に、昭和14年4月1日内務省指定の護国神社となる。
松前護国神社、 北海道松前郡松前町
明治元年10月榎本武揚らの率いる旧幕府軍函館を戦いに、同2年5月平定に至る迄官軍に従って戦死した遺骸を神止山に埋葬し招魂場と称して祀ったことに始まる。昭和14年3月全國の招魂社を護國神社と改称せられた。松前郡下の英霊を奉斎している
桧山護国神社 北海道桧山郡江差町桧山護国神社 日本海をはるかに眺める小高い丘の上にあります。境内には1、407柱の殉死者の英霊をまつった戦没者墓所があります。
十勝護国神社 北海道帯広市
日露戦争が終わって明治39年、矢後喜一郎之命を始め9柱の戦没者招魂祭を執行したのが十勝護國神社の起こりであった。大正2年4月、現在地に帯廣神社の旧仮殿を譲り受け、帯廣招魂社と称した。昭和11年には招魂社祭典協賛会を組織し、昭和21年に帯廣護國神社と改称、翌22年4月帯廣平和神社と改称し、7月15日を例祭日とした。昭和33年に現社殿を造営、同39年4月には帯広出身者のみでなく十勝管内の町村出身者も合祀の為、十勝護國神社と改称した。1208柱の殉死者を祀る。
函館護国神社 指定 北海道函館市
函館護国神社は、日本国に殉じた戦没者の英霊を祀り、その始まりは、箱館戦争終結後に明治政府が政府側の戦没者をまつるために建てた「招魂場」です。
この「招魂場」時代以来、函館護国神社には箱館戦争・西南戦争・日清戦争・太平洋戦争までの戦没者が英霊としてまつられています。13000余柱の御霊だ祀られてる。
青森懸護国神社、 指定 青森県弘前市
戊辰戦争で死亡した津軽藩士67人を明治二年に慰霊したのが始り、昭和14年に内務省指定護国神社となった。敗戦後青森県を本籍とする軍人、軍属計2万9171柱を祀る。
岩手護国神社、 指定 岩手県盛岡市
日清戦争後の明治三十一年に組織され昭忠社が母体となって日露戦争の明治37年に現在の地に招魂社が建設され昭和14年に内務大臣指定の護国神社となった。戦死、殉死者五万6千人で靖国神社と同様に戊辰戦争より朝廷、天皇側に立った戦死者を祀っている。
宮城懸護国神社、 指定 宮城県仙台市青葉区
宮城県護国神社は青葉山の仙台城址にあって明治維新後、事変戦没者殉死者5万6千余りの英霊の御柱を祀る。日清戦争の昭忠社を母体として日露戦争後現在野地に招魂社を建立、昭和14年に内務大臣指定の宮城懸護国神社となった。
福島懸護国神社、 指定 福島県福島市
明治十二年、相馬、三春、若松の三箇所にあった招魂場に祀られていた戊辰戦争の従軍者とこれら祀られていなかった従軍国者及び西南戦争で戦死した管内の殉死者の御霊を合祀し招魂社を創設したことに始まる。昭和14年に内務大臣の指定護国神社となった。祭神は69512柱の英霊を祀っている。
秋田県護国神社、 指定 秋田県秋田市
明治2年秋田藩主佐竹義堯が戊辰戦争に殉じた官軍戦没者を祀ったのが始まりという。明治32年秋田出身の軍人軍属を合祀して秋田招魂社と称した。昭和十四年に秋田懸護国神社となり、戦後は県に軍人、軍属の英霊を3800余柱を祀っている。
山形懸護国神社 指定 山形県山形市
明治維新から第二次世界大戦まで殉国者4万余柱の英霊を祀る。明治2年戊辰戦争で戦死した薩摩藩士10柱を祀ったのが始まり、その後山形県関係の殉職者を合祀したが社殿が焼失,大正3年に再建され、昭和9年に現在の地に遷座され、昭和十四年内務大臣の指定により山形懸護国神社と称した。
鶴岡護国神社 山形県鶴岡市
鶴岡護国神社の創建は明治二十八年で旧庄内藩主酒井忠胤が発起人となり、戊辰戦争、西南戦争の戦死者を祀ったのが始まりである。鶴ケ岡城本丸の西南の隅に鎮座し庄内神社と隣接してる。
茨城懸護国神社 指定 茨城市水戸市
明治11年(1878年)、明治維新に殉死した、水戸藩士約1800柱を祀るため、常盤神社の境内の現在の東湖神社の場所に立てられた鎮霊社を起源とする。茨城県出身の殉国者を逐次合祀していった。1939年4月に鎮霊社護国神社に改称した。昭和16年(1941年)10月、内務大臣指定護国神社となって茨城県護国神社に改称し、同年11月に現在地の偕楽園内の桜山に遷座した。戦後は県に関係した軍人、軍属の英霊を合祀、祭神の数は63、494柱が祀られている。
栃木懸護国神社 指定 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市にある護国神社は、境内には護国会館がある。 明治維新、日清戦争、日露戦争、大東亜戦争などの戦没者や警察、消防、自衛隊の殉職者などの旧 宇都宮藩、栃木県関係の英霊55,361柱を祀る。 天皇・皇后が日本全国で唯一公式に親拝している護国神社で、世界平和と人類共存を祈る神社とされている。 大東亜戦争後、海外各戦地の慰霊巡拝を国籍や当時の敵味方の区別なく永年に亘って継続しており、皇族や神社本庁とも所縁が深く、天皇・皇后が親拝した時の写真が本殿正面左右上方に掲げられている。
大田原護国神社 栃木県太田原市
群馬懸護国神社 指定 群馬県高崎市
群馬県高崎市にある護国神社は明治維新から第二次世界大戦までの群馬県出身関係の殉国の英霊4万7千余柱を祀る。明治42年に群馬県招魂会が結成され、高崎公園内の英霊殿で毎年招魂祭を行っていた。昭和16年に内務大臣指定護国神社に指定され、同年に鎮座祭が行われた。
渋川護国神社 群馬県渋川市
千葉懸護国神社 指定 千葉県千葉市中央区
戊辰戦争から太平洋戦争に至るまで、国事に殉じた千葉県出身・由縁ある英霊を祀る神社。合祀祭神は現在五万七千余柱。
明治11年(1878年)1月27日に柴原和初代県令の発起により、「千葉縣招魂社」として創建され、明治維新で亡くなった佐倉藩の安達直次郎盛篤ら16人の霊が祀られた。昭和14年(1939年)、招魂社の制度が護国神社に改められるのに伴い「千葉縣護國神社」と改称した。昭和18年(1943年)4月には主務大臣により1県1社の「護國神社」として指定される。
四街道護国神社 千葉県四街道市
新潟懸護国神社 指定 新潟県新潟市中央区
戊辰戦争から第二次世界大戦までの新潟県出身の戦死者を英霊として祀り、現在の祭神の数は75,000余柱となっている。
鳥羽・伏見の戦いから始まり、やがて全国各地に広がった戊辰戦争は、新潟市も例外なく激しい戦場と化した。西軍(薩摩、長州ら新政府軍)と東軍(米沢、会津、庄内)の両軍に多数の戦死者が出て尊い命が失われた。明治元年に新政府軍(西軍)側戦死者の墓碑を常磐ケ岡(旧新潟大学本部の跡地)に設置され、戊辰戦争の戦没者415柱を祀って社殿を造立し新潟招魂社として祭られた。 昭和16年新潟招魂社から護國神社と改称し、昭和20年に西船見町に移転された。
富山懸護国神社 指定 富山県富山市
富山県富山市にある護国神社は富山県出身の明治維新から大東亜戦争(太平洋戦争)までの戰歿英霊を祭神とする。祭神は28,678柱である。明治45年(大正元年・1912年)3月に富山縣招魂社として設立が認められ、昭和14年、富山縣護國神社に改称した。大東亜戦争でを焼失した。社殿は昭和29年に再建された。
石川県護国神社 指定 石川県金沢市
石川県金沢市にある護国神社は市街地中心部の兼六園の隣にある。戊辰戦争で戦死した水野徳三郎寛友ほか加賀藩の107人の霊を祀るため、明治3年に加賀藩14代藩主前田慶寧が創建した招魂社にはじまる。当時は卯辰山にあったが、境内が狭く式典を行うのが困難であったため、昭和10年、現在地である旧陸軍小立野練兵場の一角に遷座した。昭和14年、石川護国神社に改称した。
福井懸護国神社 指定 福井県福井市
明治維新前後から第二次世界大戦までの国難に殉じた福井県関係者約3万2千柱を祀る。この中には、明治維新の志士・橋本左内も含まれている。別殿・公安霊社には、警察等の殉職者、満州開拓団の戦災死亡者、自衛隊殉職者が祀られている。昭和14年の護国神社制度の成立を受けて福井県知事らを中心としてに護国神社創建のための奉賛会が結成された。昭和16年(1941年)3月に社殿が竣工し、鎮座祭が行われ、内務大臣指定護国神社となった。
山梨懸護国神社 指定 山梨県甲府市
山梨県甲府市にある護国神社は西南戦争以来の山梨県関係の戦没軍人・軍属の英霊25039柱を祀る。明治12年、招魂社として市内太田町に建立されたのに始まる。昭和17年(1942年)に現在地に遷座し、昭和19年(1944年)、山梨縣護國神社に改称した。
長野懸護国神社 指定 長野県松本市
長野県松本市美須々にある護国神社は明治維新から第二次世界大戦までの国難に殉じた長野県出身者を祀る。昭和13年に長野県招魂社として仮社殿で創建された。昭和14年(1939年)3月に長野縣護國神社に改称した。昭和32年、神社本庁の別表神社に指定された。
諏訪護国神社 長野県諏訪市
岐阜懸護国神社 指定 岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市にある護国神社は岐阜城の築かれた金華山の麓に鎮座する。春は桜の名所として境内の早咲きの鵜飼桜(江戸彼岸桜)が有名である。明治維新以来の岐阜県関係の護国の英霊3万7千余柱を祀る
濃飛護国神社 指定 岐阜県大垣市
岐阜県大垣市にある護国神社は大垣城址に鎮座する。岐阜県(主として西濃・飛騨地方)出身の護国の英霊1万9千余柱を祀る。明治4年(1871年)、元大垣藩主・戸田氏共が戊辰戦争の戦死者54名を祀るため招魂祠を創建したのに始まる。明治8年に官祭招魂社となって大垣招魂社に改称し、昭和14年、招魂社の制度が護国神社に改められたのに伴い濃飛護國神社と改称した。
飛騨護国神社 岐阜県高山市
静岡懸護国神社 指定 静岡県静岡市葵区
靜岡縣護國神社は静岡県静岡市葵区にある神社である。明治維新から大東亜戦争(太平洋戦争)に至る静岡県出身の英霊7万6千余柱を祀る。社務所の二階は遺品館になっており、戦没者の遺品約4千点が展示されている。
愛知懸護国神社 指定 愛知県名古屋中区
愛知県名古屋市中区にある護国神社は戊辰戦争から第二次世界大戦までの愛知県関係の戦没者9万3千余柱を祀る。明治元年、尾張藩主徳川慶勝が、戊辰戦争で戦死した藩士ら25人の霊を、現在の名古屋市昭和区川名山に祀り、翌明治2年5月、「旌忠社」として祠を建てたのに始まる。明治8年に招魂社となり、明治34年には官祭招魂社となった。大正7年、城北練兵場(現在の名城公園内)に、更に昭和10年には現在地に遷座、昭和14年に愛知縣護國神社に改称した。
三重懸護国神社 指定 三重県津市
三重県津市にある護国神社は禁門の変・戊辰戦争から第二次世界大戦までの三重県関係の戦歿者6万3百余柱を祀る。明治2年、津藩主藤堂高猷が、戊辰戦争で戦死した藩士の霊を祀る小祠を津八幡宮の境内に建て、「表忠社」と称したのに始まる。明治8年に官祭の招魂社となり、明治42年に現在地に遷座、昭和14年に三重縣護國神社に改称した。昭和20年の空襲で本殿・神饌所以外の建物を焼失した。昭和32年に本殿も含めて新たに社殿を造営した。
滋賀懸護国神社 指定 滋賀県彦根市
滋賀県彦根市の彦根城址には護国神社である。戊辰戦争から第二次世界大戦までの滋賀県関係の戦歿者3万4千余柱を祀る。明治2年、彦根の大洞竜潭寺に戊辰戦争で戦死した彦根藩士26人の霊を祀る招魂碑が建てられた。明治8年元彦根藩主井伊直憲の主唱により招魂碑を神社に改造する旨の政府の通達が出され、招魂碑を現在地に移し、翌明治9年、同地に社殿を造営・鎮座した。昭和14年に内務大臣指定護国神社として「滋賀県護國神社」に改称した。
京都霊山護国神社 指定 京都府京都市東山区
京都府京都市東山区にある神社である。慶応4年、明治天皇から維新を目前にして倒れた志士たち(天誅組など)の御霊を奉祀するために、京都・東山の霊山の佳域社を創建せよとの詔・御沙汰が発せられた。それに感激した京都の公家や山口・高知・福井・鳥取・熊本などの諸藩が相計らい京都の霊山の山頂にそれぞれの祠宇を建立したのが神社創建のはじまりであり、招魂社である。靖国神社より古い歴史を持つ。当初の社号を霊山官祭招魂社と称し、社格にはとくに「官祭社」に列し国費で営繕されてきた。1936年(昭和11年)、支那事変(日中戦争)をきっかけとして国難に殉じた京都府出身者の英霊を手厚く祀ろうという運動がおき、霊山官祭招魂社造営委員会が組織され、境内を拡大して新たに社殿を造営した。
大阪府護国神社 指定 大阪府大阪市住之江区
大阪府大阪市住之江区にある護国神社は、明治33年より毎年、城東練兵場で弔魂祭を行っていた。昭和13年、知事・市長らが護国神社造営奉賛会を結成し、昭和15年(1940年)5月4日に鎮座祭が行われた。ただし、人材・資材の不足のため正式な社殿の建築をする事が出来ず仮社殿での鎮座であった。昭和38年社殿が竣工し、5月29日に遷座祭が行われた。
兵庫縣神戸護國神社 指定 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市灘区にある護国神社は、兵庫県東部地区出身の護国の英霊約5万3千柱を祀る。明治以降、兵庫会下山(現 兵庫区会下山町)に祭庭を設けて英霊の招魂祭が行われていたが、昭和16年灘区王子町に社殿を造営し、内務大臣指定護国神社となった
兵庫懸姫路護国神社 指定 兵庫県姫路市
兵庫県姫路市の姫路城の近くにある護国神社である。兵庫県西部地区出身の護国の英霊56988柱を祀る。明治26年より毎年、現鎮座地の近くに祭庭を設けて英霊の招魂祭が行われていたが、正式な社殿を造営して招魂社とすることとなり、昭和14年、制度改革により兵庫縣姫路護國神社となり、内務大臣指定護国神社となった。
奈良懸護国神社 指定 奈良県奈良市
奈良県奈良市にある護国神社は明治維新から大東亜戦争までの国難に殉じた奈良県出身者29,110柱の英霊を祀る。昭和14年、奈良県知事を会長として護国神社建設奉賛会が組織され、昭和15年10月に創立を許可されて造営を開始、昭和17年(1942年)に竣工・鎮座し、内務大臣指定護国神社となった。
和歌山県護国神社 指定 和歌山県和歌山市
明治戊辰の役以降、大東亜戦争に至る迄の国難に殉じられた本県出身の神霊36,669柱命。明治戊辰の役以来、国家のため散華され、靖国神社に合祀された本県出身の戦没者を祭祀するため、招魂祭が執り行われていた。
昭和3年に入り和歌山県招魂社建設期成会が発足、和歌山市より敷地の譲渡をうけて現在地に招魂社が創建された。昭和14年4月1日、内務省令により和歌山県護国神社と改稱、内務大臣指定神社となる。昭和同37年5月24日、昭和天皇、皇后両陛下御親拝。
鳥取県護国神社 指定 鳥取県鳥取市
松江護国神社 指定 島根県松江市
島根県松江市の松江城址にある護国神社は明治維新後の国難に殉じた旧出雲国・隠岐国出身の英霊2万2千余柱を祀る。昭和10年に島根県招魂社建設奉賛会が組織された。昭和14年に松江招魂社として創建・鎮座したが、同年4月、招魂社の制度改革により松江護國神社となった。
濱田護国神社 指定 島根県浜田市
島根県浜田市の浜田城(亀山城)址にある護国神社は明治維新後の国難に殉じた旧石見国出身の英霊約2万3千柱を祀る。島根県内には他に松江護國神社がある。浜田では、明治39年より年2回の浜田招魂祭が行われていた。昭和10年に島根県招魂社建設奉賛会が組織され、昭和13年に濱田招魂社として創建・鎮座した。翌昭和14年、招魂社の制度改革により濱田護國神社となった。
岡山懸護国神社 指定 岡山県岡山市中区
岡山県岡山市中区奥市にある護国神社である。旧社格は内務大臣指定護国神社で、戦後別表神社となった。境内には戦死者の慰霊碑が数多く建立されており、明治7年)3月17日に官祭となり、岡山招魂社となった。大正4年に現在地に移転、4月26日に社殿が竣工した。昭和14年に内務大臣指定と共に「岡山縣護國神社」と改称した。
備後護国神社 指定 広島県福山市
広島県福山市丸之内の福山城北側に護国神社がある。祭神は備後国出身の護国の英霊、大彦命・武沼河別命・豊幹別命および阿部正弘をはじめとする歴代備後福山藩主である。明治元年、福山藩主・阿部正桓が、石見益田の役と箱館戦争での戦死者の霊を祀るために、旧深津郡吉津村に招魂社を創立したのに始まる。明治34年に官祭福山招魂社に改称した。昭和14年に内務大臣の指定を受けて福山護國神社と改称した。戦後昭和32年に備後護国神社に改称した。
鞆護国神社 広島県福山市鞆町
広島護国神社 指定 広島県広島市中区
広島県広島市中区にある護国神社は広島城址公園内にある。祭神は第二次世界大戦までの広島県西部(旧安芸国)出身の英霊のほか、広島市への原子爆弾投下によって犠牲になった勤労奉仕中の動員学徒および女子挺身隊等など含め約9万2千柱である。
可部護国神社 広島県広島市安佐北区
五日市護国神社 広島県広島市佐伯市
山口懸護国神社 指定 山口県山口市
山口県山口市にある護国神社は山口県関係の明治維新以降の国難に殉じた護国の英霊を祀る。この中には、吉田松陰、久坂玄瑞、来島又兵衛、大村益次郎、高杉晋作、月性も含まれている。昭和14年山口県にも護国神社を創建することとなり、昭和16年、現在地に社殿が竣工した。内務大臣から指定護国神社の指定を受け創建された。山口県出身の英霊7159柱を合祀されている。
宇部護国神社 山口県宇部市
岩国護国神社 山口県岩国市
防府護国神社 山口県防府市
朝日山護国神社 山口県山口市
徳島懸護国神社 指定 徳島県徳島市
徳島県徳島市にある護国神社は戊辰戦争から第二次大戦に至る事変・戦争等の国難に準じた徳島県出身の英霊三万四千三百余柱を祀り、相殿に徳島県出身の殉職自衛官二十余柱を祀る。1879年、眉山公園に招魂社として創建された。明治39年、徳島中央公園の徳島城跡に遷座。昭和14年、徳島縣護國神社と改称する。
香川懸護国神社 指定 香川県善通寺市
香川県善通寺市に鎮座する護国神社は讃岐宮(さぬきのみや)とも称する。境内面積は.604m²。香川県出身の護国の英霊35700余柱を祀る。 明治31年(1898年)、善通寺に陸軍第11師団が設けられた際、招魂社を設置したのに始まる。昭和13年(1938年)、内務大臣の指定により護国神社となった。
愛媛懸護国神社 指定 愛媛県松山市
愛媛県松山市にある護国神社は戊辰の役以来の愛媛県出身の戦没者のほか、軍属、女子学徒、看護婦、電話交換手、報国隊、義勇隊、富山丸・東予丸犠牲者、警察官・消防団・自衛隊等の公務殉職者、交響に尽くして県民に恩恵をもたらせた先賢諸士として加藤嘉明・藤堂高虎・久松定行・伊達秀宗をはじめとする各藩の藩主、足立重信、建武の新政から明治維新に至るまでに国事に殉じて贈位を受けた方々、産業功労者として義農作兵衛、下見吉二郎、鍵谷カナ、文化人として尾藤二洲、近藤篤山、矢野玄道、正岡子規などを合祀し、49722柱を祀る。
南媛懸護国神社 愛媛県宇和島市
高知懸護国神社 指定 高知県高知市
高知県高知市にある護国神社は、国難に殉じた高知県関係の護国の英霊4万1千余柱を祀る。 知県護国神社奉賛会がある。東征の陣で没した土佐藩士105柱。 明治維新志士四天王とされる武市半平太命・坂本龍馬命・中岡慎太郎命・吉村寅太郎命。堺事件(慶応4年)で没した11名の土佐藩士。幕末以来日清・日露、大東亜戦争にあたって国家公共の為に殉じた高知県にゆかりのある英霊。高知県出身並びに、縁故ある護国の英霊、4万1千余柱。
福岡懸護国神社 指定 福岡県福岡市中央区
福岡県福岡市中央区にある護国神社は明治維新から大東亜戦争/太平洋戦争までの国難に殉じた福岡県関係の護国の英霊約13万柱を祀る。明治元年、福岡藩主・黒田長知が、戊辰戦争に殉じた藩士を祀るため那珂郡堅粕村(妙見招魂社)と馬出村(馬出招魂社)に招魂社を創建したのに始まる。明治39年、馬出招魂社に妙見招魂社を合祀して妙見馬出招魂社とした。昭和13年に福岡招魂社と改称し、昭和14年、招魂社の制度改正により福岡護國神社に改称した。これとは別に、県内には他に4つの護国神社があった。
柳川護国神社 福岡県柳川市
八景山護国神社 福岡県京都郡
佐賀懸護国神社 指定 佐賀県佐賀市
佐賀県佐賀市にある護国神社は明治維新以降の国難に殉じた佐賀県関係の護国の英霊および第二次世界大戦後の殉職自衛官、あわせて約3万5千柱を祀る。明治3年、旧佐賀藩主・鍋島直大が、戊辰戦争で戦死した藩士78柱を祀ったことに始まる。明治7年以降、佐賀の乱などの戦死者を合祀した。当初は「招魂場」と称していたが、明治8年に官祭招魂社となり、昭和14年、招魂社の制度改正により内務大臣指定の佐賀縣護國神社に改称した。
長崎縣護國神社 指定 長崎県長崎市
長崎県長崎市にある護国神社は明治維新から太平洋戦争(大東亜戦争)までの国難に殉じた長崎県関係の護国の英霊約6万柱を祀る。明治2年、長崎市梅ヶ崎に、戊辰戦争で戦死した藩士43柱を祀る梅ヶ崎招魂社が創建された。明治7年、長崎市西小島に台湾の役の戦死者536柱を祀る佐古招魂社が創建され、以降、国難に殉じた英霊を合祀してきた。昭和14年、招魂社の制度改正により両招魂社は護国神社となった。昭和17年両護国神社を合併して内務大臣指定の長崎縣護國神社とした。
壱岐護国神社 長崎県壱岐市
祭神の亀山天皇、後宇多天皇は元寇の役に日本国の危き時に国家安泰を祈願した。 壱岐島民は、壱岐神社御創建の事業を進め、昭和19年御本殿の建設を実現した。昭和23年に御祭神三柱の鎭座祭を執行し、同27年には壱岐護国神社の鎭座祭を執行した。壱岐で一番新しい神社である。
長崎懸護国神社 指定 長崎県長崎市
長崎県長崎市にある護国神社は明治維新から太平洋戦争(大東亜戦争)までの国難に殉じた長崎県関係の護国の英霊約6万柱を祀る。明治2年(1869年)、長崎市梅ヶ崎に、戊辰戦争で戦死した藩士43柱を祀る梅ヶ崎招魂社が創建された。明治7年(1874年)、長崎市西小島に台湾の役の戦死者536柱を祀る佐古招魂社が創建され、以降、国難に殉じた英霊を合祀してきた。昭和14年、招魂社の制度改正により両招魂社は護国神社となった。
熊本懸護国神社 指定 熊本県熊本市
明治維新から大東亜戦争(太平洋戦争)までの国難に殉じた熊本県出身または縁故のある護国の英霊約6万5千柱を祀る。明治2年、熊本藩主細川韶邦と細川護久が、明治維新に殉じた藩士150柱を祀るために市内花岡山に招魂社を建立したのに始まる。明治7年に官祭の招魂社となり、昭和14年、招魂社の制度改正により内務大臣指定の熊本県護国神社となった。
相良護国神社 熊本懸人吉市
大分懸護国神社 指定 大分県大分市
大分県縁故の英霊約4万4千柱を主祭神とし、殉職警察官・自衛官を相殿に祀る。明治7年佐賀の乱の戦死者15柱、台湾出兵での病死者3柱、明治維新の勤皇の志士など5柱の英霊を合わせて祀り、翌明治8年、霊顕彰のために招魂社を創建したのに始まる。昭和14年昭招魂社の制度改正により大分縣護國神社に改称し、内務大臣指定護国神社となった。
宮崎懸護国神社 指定 宮崎県宮崎市
しかし宮崎県は、明治維新の当時、小藩分立の状態で招魂社は創立されていなかった。 昭和16年県民の要望に応えるため、当時の知事をはじめ各界の代表者数十名が設立者となって宮崎県護国神社建設奉賛会を組織し、昭和18年4月23日内務大臣の許可を得て宮崎市下北方の高台に尾国神社を創建した。
鹿児島懸護国寺 指定 鹿児島県鹿児島市
明治維新以降の国事に殉じた鹿児島県出身の英霊や、殉職した自衛官、警察官、消防士等77,000余柱を祀る。明治元年、明治天皇から与えられた鳥羽・伏見の戦いの戦死者を祀るための金500両により創建された靖献霊社(いさたまれいしゃ)に始まる。当初は照国神社の右手横(現在の戊辰駐車場)に鎮座していた。明治8年に鹿児島招魂社に改称、昭和14年に鹿児島県護国神社に改称した。
沖縄懸護国神社 指定 沖縄県那覇市
沖縄県関係の護国の英霊だけでなく、第二次世界大戦の沖縄戦に殉じた本土出身者や犠牲となった一般市民も祭神として祀っており、平成17年現在の祭神の数は17万8689柱である。昭和11年の日清・日露戦争以降の国難に殉じた英霊を祀るために創建された招魂社に始まる[1]。昭和15年の内務省令により内務大臣指定護国神社となり沖縄県護国神社に改称した。
戦前日本各地に護国神社が創建されたが、敗戦後軍国主義の影響を恐れ排除され各地の護国神社は名称を変えて偲び、独立後もとの護国神社に社名を戻した。
戦後も靖国神社と同様日本の国に為に殉死者の英霊を祀っているが、靖国神社ほどに関心、注目は去れず、むしろひっそりと各地の護国神社は鎮座している。維持管理され参拝される縁故者も年々減少し、祀られる殉死者も自衛隊員と公職での住職者に限られて、その参拝も減少傾向にある。機会がなければ訪れることのない護国神社は近代日本の礎となった人々の英霊を祀られていることを後世の人々にも受け継ぎ伝えなければ、日本の伝統歴史の軽視に繫がるのではないだろうか。たまたま大阪の護国神社の前を通りかかって知った次第である。

童謡に蹴鞠、お手玉など共に数え歌が伝わって、時代やその地域を象徴する伝承文化となって残っている中で「一番初めは一ノ宮」と言う数え歌がある。
一番初めは、一ノ宮
二は、日光東照宮
三は、讃岐の金比羅さん
四は、信州の善光寺
五は、出雲の大社(おおやしろ)
六つ、村には鎮守様
七つ、成田の不動様
八つ、やはたの八幡宮
九つ、高野の弘法さん
十は、東京招魂社
これだけ真願かけたなら、浪子の病も治るだろ、ごうごうと鳴る汽車は、
武男と浪子の別列車、二度と逢えない汽車の窓、鳴いて血を吐くほととぎす。
ここに出てくる数え歌の十に出てくる「招魂社」は何かと訪ねて直ぐに答えられる人は少ない。実際は数え歌に出てくる、十は、東京招魂社は「靖国神社」「護国神社」の前身の名称である。
明治に入って戌辰戦争後の大総督有栖川宮熾仁親王が戦没の官軍の将校の招魂祭を江戸城に斎行に始るという。
その後、戦没者を慰霊、顕彰する動きが活発になり、お国の為に殉死した、「忠霊」「忠魂」を祀るために「招魂社」が創建された。
靖国神社
東京招魂社は軍が管轄するものとされた、一般の神社と異なるために問題が生じ正規な神社とするために軍当局は明治天皇の裁可を経て、社名を明治十二年に「靖国神社」と改め直され、別格官幣大社に列せられるようになった。
祭神は幕末から明治維新にかけて功のあった志士に始まりペルー来航以降の日本の国内外の事変、戦争等、国事に殉じた軍事、軍属の戦没者を「英霊」として祀る。
戦後は政教分離の推進により国家管理を離れ、宗教法人になり、公職に就く者の参拝については問題になった。
一時はGHQは靖国神社を焼き払い、ドックレース場計画が持ち上がったが、賛否両論で混乱し「靖国神社を焼却する事は、連合軍の占領政策と相容れない犯罪行為ある」と言って残されて、日本国のために殉死した英霊を祀る神社として平成16年度現在246万6532柱が祀られている。
戦後日本では国家の為に殉死した英霊の合祀の是非をめぐり神社本庁との包括関係にない、また管理の処遇を巡り政治色の強い神社となって、未解決の問題が多く残っている。
では明治時代に各地に祀られた招魂社はどうなったのか、概ね各府県に一社が設立された招魂社は昭和十四年に内務省令によって改称し「護国神社」と改められた。
各護国神社の祭神は靖国神社に一部重なるものの、靖国神社から分祀されたものではなく、府県に国の為に殉死した人の英霊を祀るための神社である。
終戦後、軍国主義の施設と見なされ、維持存続をするために社名をかえた。
独立後は元の社名に戻された。
府県に五十二社あって、昭和三十五年より天皇、皇后陛下から幣帛が終戦から数えて十年ごとに賜与されている。
社格は府社、県社と相当する内務大臣指定護国神社と村社に相当する指定外護国神社に分けられた。
指定護国神社には北海道に三社、兵庫県、広島県、島根県、岐阜県に二社の護国神社が祀られている。
北海道護国神社 指定、 北海道旭川市
北海道,樺太関係の戦没者を英霊として祀る。戌辰戦争から大東亜戦争までの63141柱の英霊が祀られている。明治35年大迫陸軍大将を祭主として招魂祭を執り行なったのが始まりと言う。昭和14年には招魂社から内務省護国神社となった。昭和19年に樺太護国神社が合祀された。戦後はGHQからの追及を逃れるため北海道神社と社名を変えたが独立後、北海道護国神社に戻された。
幌護国神社 指定、 北海度札幌市中央区
明治10年の西南の役に戦病没した屯田兵の霊を祀る。 有栖川熾仁親王により屯田兵招魂碑と題し、明治12年8月2日屯田兵司令部に於て祭祀を斎行する。日露戦争の戦病没者の合祀のため忠魂碑を建て、乃木将軍之を題す。昭和8年札幌招魂社を造営し官幣大社札幌神社に、昭和14年4月1日内務省指定の護国神社となる。
松前護国神社、 北海道松前郡松前町
明治元年10月榎本武揚らの率いる旧幕府軍函館を戦いに、同2年5月平定に至る迄官軍に従って戦死した遺骸を神止山に埋葬し招魂場と称して祀ったことに始まる。昭和14年3月全國の招魂社を護國神社と改称せられた。松前郡下の英霊を奉斎している
桧山護国神社 北海道桧山郡江差町桧山護国神社 日本海をはるかに眺める小高い丘の上にあります。境内には1、407柱の殉死者の英霊をまつった戦没者墓所があります。
十勝護国神社 北海道帯広市
日露戦争が終わって明治39年、矢後喜一郎之命を始め9柱の戦没者招魂祭を執行したのが十勝護國神社の起こりであった。大正2年4月、現在地に帯廣神社の旧仮殿を譲り受け、帯廣招魂社と称した。昭和11年には招魂社祭典協賛会を組織し、昭和21年に帯廣護國神社と改称、翌22年4月帯廣平和神社と改称し、7月15日を例祭日とした。昭和33年に現社殿を造営、同39年4月には帯広出身者のみでなく十勝管内の町村出身者も合祀の為、十勝護國神社と改称した。1208柱の殉死者を祀る。
函館護国神社 指定 北海道函館市
函館護国神社は、日本国に殉じた戦没者の英霊を祀り、その始まりは、箱館戦争終結後に明治政府が政府側の戦没者をまつるために建てた「招魂場」です。
この「招魂場」時代以来、函館護国神社には箱館戦争・西南戦争・日清戦争・太平洋戦争までの戦没者が英霊としてまつられています。13000余柱の御霊だ祀られてる。
青森懸護国神社、 指定 青森県弘前市
戊辰戦争で死亡した津軽藩士67人を明治二年に慰霊したのが始り、昭和14年に内務省指定護国神社となった。敗戦後青森県を本籍とする軍人、軍属計2万9171柱を祀る。
岩手護国神社、 指定 岩手県盛岡市
日清戦争後の明治三十一年に組織され昭忠社が母体となって日露戦争の明治37年に現在の地に招魂社が建設され昭和14年に内務大臣指定の護国神社となった。戦死、殉死者五万6千人で靖国神社と同様に戊辰戦争より朝廷、天皇側に立った戦死者を祀っている。
宮城懸護国神社、 指定 宮城県仙台市青葉区
宮城県護国神社は青葉山の仙台城址にあって明治維新後、事変戦没者殉死者5万6千余りの英霊の御柱を祀る。日清戦争の昭忠社を母体として日露戦争後現在野地に招魂社を建立、昭和14年に内務大臣指定の宮城懸護国神社となった。
福島懸護国神社、 指定 福島県福島市
明治十二年、相馬、三春、若松の三箇所にあった招魂場に祀られていた戊辰戦争の従軍者とこれら祀られていなかった従軍国者及び西南戦争で戦死した管内の殉死者の御霊を合祀し招魂社を創設したことに始まる。昭和14年に内務大臣の指定護国神社となった。祭神は69512柱の英霊を祀っている。
秋田県護国神社、 指定 秋田県秋田市
明治2年秋田藩主佐竹義堯が戊辰戦争に殉じた官軍戦没者を祀ったのが始まりという。明治32年秋田出身の軍人軍属を合祀して秋田招魂社と称した。昭和十四年に秋田懸護国神社となり、戦後は県に軍人、軍属の英霊を3800余柱を祀っている。
山形懸護国神社 指定 山形県山形市
明治維新から第二次世界大戦まで殉国者4万余柱の英霊を祀る。明治2年戊辰戦争で戦死した薩摩藩士10柱を祀ったのが始まり、その後山形県関係の殉職者を合祀したが社殿が焼失,大正3年に再建され、昭和9年に現在の地に遷座され、昭和十四年内務大臣の指定により山形懸護国神社と称した。
鶴岡護国神社 山形県鶴岡市
鶴岡護国神社の創建は明治二十八年で旧庄内藩主酒井忠胤が発起人となり、戊辰戦争、西南戦争の戦死者を祀ったのが始まりである。鶴ケ岡城本丸の西南の隅に鎮座し庄内神社と隣接してる。
茨城懸護国神社 指定 茨城市水戸市
明治11年(1878年)、明治維新に殉死した、水戸藩士約1800柱を祀るため、常盤神社の境内の現在の東湖神社の場所に立てられた鎮霊社を起源とする。茨城県出身の殉国者を逐次合祀していった。1939年4月に鎮霊社護国神社に改称した。昭和16年(1941年)10月、内務大臣指定護国神社となって茨城県護国神社に改称し、同年11月に現在地の偕楽園内の桜山に遷座した。戦後は県に関係した軍人、軍属の英霊を合祀、祭神の数は63、494柱が祀られている。
栃木懸護国神社 指定 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市にある護国神社は、境内には護国会館がある。 明治維新、日清戦争、日露戦争、大東亜戦争などの戦没者や警察、消防、自衛隊の殉職者などの旧 宇都宮藩、栃木県関係の英霊55,361柱を祀る。 天皇・皇后が日本全国で唯一公式に親拝している護国神社で、世界平和と人類共存を祈る神社とされている。 大東亜戦争後、海外各戦地の慰霊巡拝を国籍や当時の敵味方の区別なく永年に亘って継続しており、皇族や神社本庁とも所縁が深く、天皇・皇后が親拝した時の写真が本殿正面左右上方に掲げられている。
大田原護国神社 栃木県太田原市
群馬懸護国神社 指定 群馬県高崎市
群馬県高崎市にある護国神社は明治維新から第二次世界大戦までの群馬県出身関係の殉国の英霊4万7千余柱を祀る。明治42年に群馬県招魂会が結成され、高崎公園内の英霊殿で毎年招魂祭を行っていた。昭和16年に内務大臣指定護国神社に指定され、同年に鎮座祭が行われた。
渋川護国神社 群馬県渋川市
千葉懸護国神社 指定 千葉県千葉市中央区
戊辰戦争から太平洋戦争に至るまで、国事に殉じた千葉県出身・由縁ある英霊を祀る神社。合祀祭神は現在五万七千余柱。
明治11年(1878年)1月27日に柴原和初代県令の発起により、「千葉縣招魂社」として創建され、明治維新で亡くなった佐倉藩の安達直次郎盛篤ら16人の霊が祀られた。昭和14年(1939年)、招魂社の制度が護国神社に改められるのに伴い「千葉縣護國神社」と改称した。昭和18年(1943年)4月には主務大臣により1県1社の「護國神社」として指定される。
四街道護国神社 千葉県四街道市
新潟懸護国神社 指定 新潟県新潟市中央区
戊辰戦争から第二次世界大戦までの新潟県出身の戦死者を英霊として祀り、現在の祭神の数は75,000余柱となっている。
鳥羽・伏見の戦いから始まり、やがて全国各地に広がった戊辰戦争は、新潟市も例外なく激しい戦場と化した。西軍(薩摩、長州ら新政府軍)と東軍(米沢、会津、庄内)の両軍に多数の戦死者が出て尊い命が失われた。明治元年に新政府軍(西軍)側戦死者の墓碑を常磐ケ岡(旧新潟大学本部の跡地)に設置され、戊辰戦争の戦没者415柱を祀って社殿を造立し新潟招魂社として祭られた。 昭和16年新潟招魂社から護國神社と改称し、昭和20年に西船見町に移転された。
富山懸護国神社 指定 富山県富山市
富山県富山市にある護国神社は富山県出身の明治維新から大東亜戦争(太平洋戦争)までの戰歿英霊を祭神とする。祭神は28,678柱である。明治45年(大正元年・1912年)3月に富山縣招魂社として設立が認められ、昭和14年、富山縣護國神社に改称した。大東亜戦争でを焼失した。社殿は昭和29年に再建された。
石川県護国神社 指定 石川県金沢市
石川県金沢市にある護国神社は市街地中心部の兼六園の隣にある。戊辰戦争で戦死した水野徳三郎寛友ほか加賀藩の107人の霊を祀るため、明治3年に加賀藩14代藩主前田慶寧が創建した招魂社にはじまる。当時は卯辰山にあったが、境内が狭く式典を行うのが困難であったため、昭和10年、現在地である旧陸軍小立野練兵場の一角に遷座した。昭和14年、石川護国神社に改称した。
福井懸護国神社 指定 福井県福井市
明治維新前後から第二次世界大戦までの国難に殉じた福井県関係者約3万2千柱を祀る。この中には、明治維新の志士・橋本左内も含まれている。別殿・公安霊社には、警察等の殉職者、満州開拓団の戦災死亡者、自衛隊殉職者が祀られている。昭和14年の護国神社制度の成立を受けて福井県知事らを中心としてに護国神社創建のための奉賛会が結成された。昭和16年(1941年)3月に社殿が竣工し、鎮座祭が行われ、内務大臣指定護国神社となった。
山梨懸護国神社 指定 山梨県甲府市
山梨県甲府市にある護国神社は西南戦争以来の山梨県関係の戦没軍人・軍属の英霊25039柱を祀る。明治12年、招魂社として市内太田町に建立されたのに始まる。昭和17年(1942年)に現在地に遷座し、昭和19年(1944年)、山梨縣護國神社に改称した。
長野懸護国神社 指定 長野県松本市
長野県松本市美須々にある護国神社は明治維新から第二次世界大戦までの国難に殉じた長野県出身者を祀る。昭和13年に長野県招魂社として仮社殿で創建された。昭和14年(1939年)3月に長野縣護國神社に改称した。昭和32年、神社本庁の別表神社に指定された。
諏訪護国神社 長野県諏訪市
岐阜懸護国神社 指定 岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市にある護国神社は岐阜城の築かれた金華山の麓に鎮座する。春は桜の名所として境内の早咲きの鵜飼桜(江戸彼岸桜)が有名である。明治維新以来の岐阜県関係の護国の英霊3万7千余柱を祀る
濃飛護国神社 指定 岐阜県大垣市
岐阜県大垣市にある護国神社は大垣城址に鎮座する。岐阜県(主として西濃・飛騨地方)出身の護国の英霊1万9千余柱を祀る。明治4年(1871年)、元大垣藩主・戸田氏共が戊辰戦争の戦死者54名を祀るため招魂祠を創建したのに始まる。明治8年に官祭招魂社となって大垣招魂社に改称し、昭和14年、招魂社の制度が護国神社に改められたのに伴い濃飛護國神社と改称した。
飛騨護国神社 岐阜県高山市
静岡懸護国神社 指定 静岡県静岡市葵区
靜岡縣護國神社は静岡県静岡市葵区にある神社である。明治維新から大東亜戦争(太平洋戦争)に至る静岡県出身の英霊7万6千余柱を祀る。社務所の二階は遺品館になっており、戦没者の遺品約4千点が展示されている。
愛知懸護国神社 指定 愛知県名古屋中区
愛知県名古屋市中区にある護国神社は戊辰戦争から第二次世界大戦までの愛知県関係の戦没者9万3千余柱を祀る。明治元年、尾張藩主徳川慶勝が、戊辰戦争で戦死した藩士ら25人の霊を、現在の名古屋市昭和区川名山に祀り、翌明治2年5月、「旌忠社」として祠を建てたのに始まる。明治8年に招魂社となり、明治34年には官祭招魂社となった。大正7年、城北練兵場(現在の名城公園内)に、更に昭和10年には現在地に遷座、昭和14年に愛知縣護國神社に改称した。
三重懸護国神社 指定 三重県津市
三重県津市にある護国神社は禁門の変・戊辰戦争から第二次世界大戦までの三重県関係の戦歿者6万3百余柱を祀る。明治2年、津藩主藤堂高猷が、戊辰戦争で戦死した藩士の霊を祀る小祠を津八幡宮の境内に建て、「表忠社」と称したのに始まる。明治8年に官祭の招魂社となり、明治42年に現在地に遷座、昭和14年に三重縣護國神社に改称した。昭和20年の空襲で本殿・神饌所以外の建物を焼失した。昭和32年に本殿も含めて新たに社殿を造営した。
滋賀懸護国神社 指定 滋賀県彦根市
滋賀県彦根市の彦根城址には護国神社である。戊辰戦争から第二次世界大戦までの滋賀県関係の戦歿者3万4千余柱を祀る。明治2年、彦根の大洞竜潭寺に戊辰戦争で戦死した彦根藩士26人の霊を祀る招魂碑が建てられた。明治8年元彦根藩主井伊直憲の主唱により招魂碑を神社に改造する旨の政府の通達が出され、招魂碑を現在地に移し、翌明治9年、同地に社殿を造営・鎮座した。昭和14年に内務大臣指定護国神社として「滋賀県護國神社」に改称した。
京都霊山護国神社 指定 京都府京都市東山区
京都府京都市東山区にある神社である。慶応4年、明治天皇から維新を目前にして倒れた志士たち(天誅組など)の御霊を奉祀するために、京都・東山の霊山の佳域社を創建せよとの詔・御沙汰が発せられた。それに感激した京都の公家や山口・高知・福井・鳥取・熊本などの諸藩が相計らい京都の霊山の山頂にそれぞれの祠宇を建立したのが神社創建のはじまりであり、招魂社である。靖国神社より古い歴史を持つ。当初の社号を霊山官祭招魂社と称し、社格にはとくに「官祭社」に列し国費で営繕されてきた。1936年(昭和11年)、支那事変(日中戦争)をきっかけとして国難に殉じた京都府出身者の英霊を手厚く祀ろうという運動がおき、霊山官祭招魂社造営委員会が組織され、境内を拡大して新たに社殿を造営した。
大阪府護国神社 指定 大阪府大阪市住之江区
大阪府大阪市住之江区にある護国神社は、明治33年より毎年、城東練兵場で弔魂祭を行っていた。昭和13年、知事・市長らが護国神社造営奉賛会を結成し、昭和15年(1940年)5月4日に鎮座祭が行われた。ただし、人材・資材の不足のため正式な社殿の建築をする事が出来ず仮社殿での鎮座であった。昭和38年社殿が竣工し、5月29日に遷座祭が行われた。
兵庫縣神戸護國神社 指定 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市灘区にある護国神社は、兵庫県東部地区出身の護国の英霊約5万3千柱を祀る。明治以降、兵庫会下山(現 兵庫区会下山町)に祭庭を設けて英霊の招魂祭が行われていたが、昭和16年灘区王子町に社殿を造営し、内務大臣指定護国神社となった
兵庫懸姫路護国神社 指定 兵庫県姫路市
兵庫県姫路市の姫路城の近くにある護国神社である。兵庫県西部地区出身の護国の英霊56988柱を祀る。明治26年より毎年、現鎮座地の近くに祭庭を設けて英霊の招魂祭が行われていたが、正式な社殿を造営して招魂社とすることとなり、昭和14年、制度改革により兵庫縣姫路護國神社となり、内務大臣指定護国神社となった。
奈良懸護国神社 指定 奈良県奈良市
奈良県奈良市にある護国神社は明治維新から大東亜戦争までの国難に殉じた奈良県出身者29,110柱の英霊を祀る。昭和14年、奈良県知事を会長として護国神社建設奉賛会が組織され、昭和15年10月に創立を許可されて造営を開始、昭和17年(1942年)に竣工・鎮座し、内務大臣指定護国神社となった。
和歌山県護国神社 指定 和歌山県和歌山市
明治戊辰の役以降、大東亜戦争に至る迄の国難に殉じられた本県出身の神霊36,669柱命。明治戊辰の役以来、国家のため散華され、靖国神社に合祀された本県出身の戦没者を祭祀するため、招魂祭が執り行われていた。
昭和3年に入り和歌山県招魂社建設期成会が発足、和歌山市より敷地の譲渡をうけて現在地に招魂社が創建された。昭和14年4月1日、内務省令により和歌山県護国神社と改稱、内務大臣指定神社となる。昭和同37年5月24日、昭和天皇、皇后両陛下御親拝。
鳥取県護国神社 指定 鳥取県鳥取市
松江護国神社 指定 島根県松江市
島根県松江市の松江城址にある護国神社は明治維新後の国難に殉じた旧出雲国・隠岐国出身の英霊2万2千余柱を祀る。昭和10年に島根県招魂社建設奉賛会が組織された。昭和14年に松江招魂社として創建・鎮座したが、同年4月、招魂社の制度改革により松江護國神社となった。
濱田護国神社 指定 島根県浜田市
島根県浜田市の浜田城(亀山城)址にある護国神社は明治維新後の国難に殉じた旧石見国出身の英霊約2万3千柱を祀る。島根県内には他に松江護國神社がある。浜田では、明治39年より年2回の浜田招魂祭が行われていた。昭和10年に島根県招魂社建設奉賛会が組織され、昭和13年に濱田招魂社として創建・鎮座した。翌昭和14年、招魂社の制度改革により濱田護國神社となった。
岡山懸護国神社 指定 岡山県岡山市中区
岡山県岡山市中区奥市にある護国神社である。旧社格は内務大臣指定護国神社で、戦後別表神社となった。境内には戦死者の慰霊碑が数多く建立されており、明治7年)3月17日に官祭となり、岡山招魂社となった。大正4年に現在地に移転、4月26日に社殿が竣工した。昭和14年に内務大臣指定と共に「岡山縣護國神社」と改称した。
備後護国神社 指定 広島県福山市
広島県福山市丸之内の福山城北側に護国神社がある。祭神は備後国出身の護国の英霊、大彦命・武沼河別命・豊幹別命および阿部正弘をはじめとする歴代備後福山藩主である。明治元年、福山藩主・阿部正桓が、石見益田の役と箱館戦争での戦死者の霊を祀るために、旧深津郡吉津村に招魂社を創立したのに始まる。明治34年に官祭福山招魂社に改称した。昭和14年に内務大臣の指定を受けて福山護國神社と改称した。戦後昭和32年に備後護国神社に改称した。
鞆護国神社 広島県福山市鞆町
広島護国神社 指定 広島県広島市中区
広島県広島市中区にある護国神社は広島城址公園内にある。祭神は第二次世界大戦までの広島県西部(旧安芸国)出身の英霊のほか、広島市への原子爆弾投下によって犠牲になった勤労奉仕中の動員学徒および女子挺身隊等など含め約9万2千柱である。
可部護国神社 広島県広島市安佐北区
五日市護国神社 広島県広島市佐伯市
山口懸護国神社 指定 山口県山口市
山口県山口市にある護国神社は山口県関係の明治維新以降の国難に殉じた護国の英霊を祀る。この中には、吉田松陰、久坂玄瑞、来島又兵衛、大村益次郎、高杉晋作、月性も含まれている。昭和14年山口県にも護国神社を創建することとなり、昭和16年、現在地に社殿が竣工した。内務大臣から指定護国神社の指定を受け創建された。山口県出身の英霊7159柱を合祀されている。
宇部護国神社 山口県宇部市
岩国護国神社 山口県岩国市
防府護国神社 山口県防府市
朝日山護国神社 山口県山口市
徳島懸護国神社 指定 徳島県徳島市
徳島県徳島市にある護国神社は戊辰戦争から第二次大戦に至る事変・戦争等の国難に準じた徳島県出身の英霊三万四千三百余柱を祀り、相殿に徳島県出身の殉職自衛官二十余柱を祀る。1879年、眉山公園に招魂社として創建された。明治39年、徳島中央公園の徳島城跡に遷座。昭和14年、徳島縣護國神社と改称する。
香川懸護国神社 指定 香川県善通寺市
香川県善通寺市に鎮座する護国神社は讃岐宮(さぬきのみや)とも称する。境内面積は.604m²。香川県出身の護国の英霊35700余柱を祀る。 明治31年(1898年)、善通寺に陸軍第11師団が設けられた際、招魂社を設置したのに始まる。昭和13年(1938年)、内務大臣の指定により護国神社となった。
愛媛懸護国神社 指定 愛媛県松山市
愛媛県松山市にある護国神社は戊辰の役以来の愛媛県出身の戦没者のほか、軍属、女子学徒、看護婦、電話交換手、報国隊、義勇隊、富山丸・東予丸犠牲者、警察官・消防団・自衛隊等の公務殉職者、交響に尽くして県民に恩恵をもたらせた先賢諸士として加藤嘉明・藤堂高虎・久松定行・伊達秀宗をはじめとする各藩の藩主、足立重信、建武の新政から明治維新に至るまでに国事に殉じて贈位を受けた方々、産業功労者として義農作兵衛、下見吉二郎、鍵谷カナ、文化人として尾藤二洲、近藤篤山、矢野玄道、正岡子規などを合祀し、49722柱を祀る。
南媛懸護国神社 愛媛県宇和島市
高知懸護国神社 指定 高知県高知市
高知県高知市にある護国神社は、国難に殉じた高知県関係の護国の英霊4万1千余柱を祀る。 知県護国神社奉賛会がある。東征の陣で没した土佐藩士105柱。 明治維新志士四天王とされる武市半平太命・坂本龍馬命・中岡慎太郎命・吉村寅太郎命。堺事件(慶応4年)で没した11名の土佐藩士。幕末以来日清・日露、大東亜戦争にあたって国家公共の為に殉じた高知県にゆかりのある英霊。高知県出身並びに、縁故ある護国の英霊、4万1千余柱。
福岡懸護国神社 指定 福岡県福岡市中央区
福岡県福岡市中央区にある護国神社は明治維新から大東亜戦争/太平洋戦争までの国難に殉じた福岡県関係の護国の英霊約13万柱を祀る。明治元年、福岡藩主・黒田長知が、戊辰戦争に殉じた藩士を祀るため那珂郡堅粕村(妙見招魂社)と馬出村(馬出招魂社)に招魂社を創建したのに始まる。明治39年、馬出招魂社に妙見招魂社を合祀して妙見馬出招魂社とした。昭和13年に福岡招魂社と改称し、昭和14年、招魂社の制度改正により福岡護國神社に改称した。これとは別に、県内には他に4つの護国神社があった。
柳川護国神社 福岡県柳川市
八景山護国神社 福岡県京都郡
佐賀懸護国神社 指定 佐賀県佐賀市
佐賀県佐賀市にある護国神社は明治維新以降の国難に殉じた佐賀県関係の護国の英霊および第二次世界大戦後の殉職自衛官、あわせて約3万5千柱を祀る。明治3年、旧佐賀藩主・鍋島直大が、戊辰戦争で戦死した藩士78柱を祀ったことに始まる。明治7年以降、佐賀の乱などの戦死者を合祀した。当初は「招魂場」と称していたが、明治8年に官祭招魂社となり、昭和14年、招魂社の制度改正により内務大臣指定の佐賀縣護國神社に改称した。
長崎縣護國神社 指定 長崎県長崎市
長崎県長崎市にある護国神社は明治維新から太平洋戦争(大東亜戦争)までの国難に殉じた長崎県関係の護国の英霊約6万柱を祀る。明治2年、長崎市梅ヶ崎に、戊辰戦争で戦死した藩士43柱を祀る梅ヶ崎招魂社が創建された。明治7年、長崎市西小島に台湾の役の戦死者536柱を祀る佐古招魂社が創建され、以降、国難に殉じた英霊を合祀してきた。昭和14年、招魂社の制度改正により両招魂社は護国神社となった。昭和17年両護国神社を合併して内務大臣指定の長崎縣護國神社とした。
壱岐護国神社 長崎県壱岐市
祭神の亀山天皇、後宇多天皇は元寇の役に日本国の危き時に国家安泰を祈願した。 壱岐島民は、壱岐神社御創建の事業を進め、昭和19年御本殿の建設を実現した。昭和23年に御祭神三柱の鎭座祭を執行し、同27年には壱岐護国神社の鎭座祭を執行した。壱岐で一番新しい神社である。
長崎懸護国神社 指定 長崎県長崎市
長崎県長崎市にある護国神社は明治維新から太平洋戦争(大東亜戦争)までの国難に殉じた長崎県関係の護国の英霊約6万柱を祀る。明治2年(1869年)、長崎市梅ヶ崎に、戊辰戦争で戦死した藩士43柱を祀る梅ヶ崎招魂社が創建された。明治7年(1874年)、長崎市西小島に台湾の役の戦死者536柱を祀る佐古招魂社が創建され、以降、国難に殉じた英霊を合祀してきた。昭和14年、招魂社の制度改正により両招魂社は護国神社となった。
熊本懸護国神社 指定 熊本県熊本市
明治維新から大東亜戦争(太平洋戦争)までの国難に殉じた熊本県出身または縁故のある護国の英霊約6万5千柱を祀る。明治2年、熊本藩主細川韶邦と細川護久が、明治維新に殉じた藩士150柱を祀るために市内花岡山に招魂社を建立したのに始まる。明治7年に官祭の招魂社となり、昭和14年、招魂社の制度改正により内務大臣指定の熊本県護国神社となった。
相良護国神社 熊本懸人吉市
大分懸護国神社 指定 大分県大分市
大分県縁故の英霊約4万4千柱を主祭神とし、殉職警察官・自衛官を相殿に祀る。明治7年佐賀の乱の戦死者15柱、台湾出兵での病死者3柱、明治維新の勤皇の志士など5柱の英霊を合わせて祀り、翌明治8年、霊顕彰のために招魂社を創建したのに始まる。昭和14年昭招魂社の制度改正により大分縣護國神社に改称し、内務大臣指定護国神社となった。
宮崎懸護国神社 指定 宮崎県宮崎市
しかし宮崎県は、明治維新の当時、小藩分立の状態で招魂社は創立されていなかった。 昭和16年県民の要望に応えるため、当時の知事をはじめ各界の代表者数十名が設立者となって宮崎県護国神社建設奉賛会を組織し、昭和18年4月23日内務大臣の許可を得て宮崎市下北方の高台に尾国神社を創建した。
鹿児島懸護国寺 指定 鹿児島県鹿児島市
明治維新以降の国事に殉じた鹿児島県出身の英霊や、殉職した自衛官、警察官、消防士等77,000余柱を祀る。明治元年、明治天皇から与えられた鳥羽・伏見の戦いの戦死者を祀るための金500両により創建された靖献霊社(いさたまれいしゃ)に始まる。当初は照国神社の右手横(現在の戊辰駐車場)に鎮座していた。明治8年に鹿児島招魂社に改称、昭和14年に鹿児島県護国神社に改称した。
沖縄懸護国神社 指定 沖縄県那覇市
沖縄県関係の護国の英霊だけでなく、第二次世界大戦の沖縄戦に殉じた本土出身者や犠牲となった一般市民も祭神として祀っており、平成17年現在の祭神の数は17万8689柱である。昭和11年の日清・日露戦争以降の国難に殉じた英霊を祀るために創建された招魂社に始まる[1]。昭和15年の内務省令により内務大臣指定護国神社となり沖縄県護国神社に改称した。
戦前日本各地に護国神社が創建されたが、敗戦後軍国主義の影響を恐れ排除され各地の護国神社は名称を変えて偲び、独立後もとの護国神社に社名を戻した。
戦後も靖国神社と同様日本の国に為に殉死者の英霊を祀っているが、靖国神社ほどに関心、注目は去れず、むしろひっそりと各地の護国神社は鎮座している。維持管理され参拝される縁故者も年々減少し、祀られる殉死者も自衛隊員と公職での住職者に限られて、その参拝も減少傾向にある。機会がなければ訪れることのない護国神社は近代日本の礎となった人々の英霊を祀られていることを後世の人々にも受け継ぎ伝えなければ、日本の伝統歴史の軽視に繫がるのではないだろうか。たまたま大阪の護国神社の前を通りかかって知った次第である。













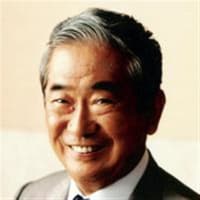






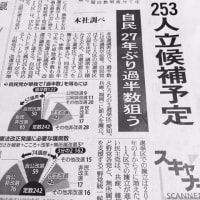
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます