二十一、長屋王から藤原四兄弟
“長屋(ながや)王(おう)の頭角(とうかく)”
時代は不比等から長屋王へと変わって行った。元正が没した。
養老五年(721)政権は不比等に変わり、長屋王が就いた。本来なら皇族の重要な地位でもあったが、あえて皇籍を降り、臣籍と成っての政権だった。
天平元年(729)栄光から悲劇の失脚までの、謎の多い八年間を平城京の政権を担った。本来なら天武の長子高市皇子の王子として後継の有力候補として、皇族の中枢でいるはずが、高市皇子の母方の血筋が九州豪族の娘と言うことで身分の低さから父と同様皇権から外されていた。
だが高市皇子は壬申の乱の折には若干十九歳にして、勝利に導く働きの功績は大きかった。その後持統五年(690)持統在位中では八年間太政大臣として、朝廷を支えた。
妃には天智の皇女御名部皇女が向けられた、元明天皇の上の姉に当たる。
草壁皇子に継ぐ存在だったが享年四十三歳で没した。御名部皇女の間に三人の皇子と三人の皇女が生まれた・父高市皇子と違い長屋王は母が天智女である以上最も王権に近い存在だった。
だがもし長屋王が王権に意欲を見せていたならば、政争に巻き込まれて、排除されて、抹殺されていた可能性は、否定できない。
父はそんな事を察知しいち早く、臣籍の道を歩むことを、選択したに違いない。
まして首皇子が誕生した以上は全ての皇族は、皇権に意欲のないことを示さなければ、身の安全は無ことは熟知していたかも知れない。
運命の選択は父の生き方を、知った上の官人として登り詰めて行った。
“北宮(きたみや)王家(おうけ)と木管(もっかん)“
長屋王自身その生き方に臣籍に活路を求めた。
長屋王については、謎が多かったが、奈良市の大型建築物の基礎工事で元長屋王の住居跡から長屋王の関係する、多くの木管が出土し、その権力と、その暮し振りや様子が解明されつつある。
長屋王 天武五年(676)飛鳥で高市皇子の長子として生まれた、母は御名部皇女である。
☆妃に吉備内親王、草壁皇子と元明天皇の内親王で三人の王子が生まれている。*膳夫王、葛木王、鍵取王。
☆石川夫人には王子が一人。*桑田王。
☆安倍大刀自夫人に一人の女王。*加茂女王。
☆藤原不比等の娘の長我子の間に四人の王子。*安宿王、黄文王、山背王、教勝?
☆他に分かっているだけで六人の女王。三人の王子。*円方女王、紀女王、忍海部女王、珎努女王、日下女王、栗田女王、林王、小冶田王、太若?
なかでも吉備内親王の血縁は深く微妙である。
それが北宮王家(高市皇子、長屋王)という特別な存在だった。あたもかも、聖徳太子の上宮王家を彷彿とさせるものがある。
首皇子の誕生以降は皇位継承からも外されてからは、その代償として、特別な処遇であった。
政治家の道を選択した長屋王は、父同様にその才覚を発揮したのではないだろうか、平城京遷都から失脚する十九年間、長屋王邸宅は正殿と脇殿と建つ、床面積三百六十平方メートルという、天皇の次に観られる大きな邸宅である。
上記の家族構成に充分住居としても、特別扱いだった。
その機能やシステム構造は宮殿を少し小さくしたもので、政所、務所、(事務所)主殿司、(殿舎管理)大炊司、(食料庫)膳司、(調理)菜司、(野菜所)、酒司、主水司、(水酒の管理)染め司、(染色工)工司、(職人所)鋳物司、銅造司(金物の製造)嶋造司、(庭園所)仏造司、斎会司、(仏事)薬師処、馬司、犬司、鶴司、など多岐に渡りあって、あって一国の王宮のまかないのに相当するものである。
これらの長屋王の関係する人々の従事する人数は数百人に及んだだろうと思われる。
邸宅は北門の二条大路に面し、大路には本来門を開いてはいけないのに、表通りに開く北門があって、広大な邸には、妃、夫人と、それぞれの家族に王子、女王が、区割りされた処に住み長屋王の一族を成していた。
そんな大勢の人々の暮しを守るだけの、物資、資金を考えた場合、奈良の大型デパートの建設の折り、たまたま長屋王の邸跡だった。
出土された、多くの木簡は、奈良時代と長屋王の謎を解く鍵として、大量に出てきたのである。
木管は長屋王のその暮し振りと、当時の情景や、情報が膨大に出てきたのである。
しかも途方もない作業であった、木管は長さ二十センチ位で、幅三センチ位、厚さ四ミリ、紙の代行で諸国を流通する、貴重な木札であった。役割は書簡、命令書、明細書、荷札,連絡書など多彩である。
木といっても貴重である、決して使いすではない。削って再利用するのである。その削りカスを、一つ一つ広げて、判読するのである。
三万五千点に及ぶ木管を解明しつつある。
実に気の遠くなるような話である。そんな中から当時の長屋王の日々暮らしを見ることができる。
領地から送られてくる数々の品は、その豊かな食卓を物語るものであるが、荷札の木管からは、父の領地、遠くは高市皇子の母方の宗像(宗形)から送られた物があり九州からの結びつきを物語る、封戸四千五百戸分に相当する。
諸国父高市皇子から受け継いだものを入れ三十七カ国にも及ぶ、摂津国の塩漬け鯵、伊豆国の荒鰹、上総国のゴマ油、越後国の栗、阿波国の猪なで、近郊から野菜など、夏には奈良の山手の氷室から氷まで、その豊かな美食が窺い知れる。
長屋王の取り巻く家族はそれぞれの夫人の王子や女王に加え、妃や夫人の背景をも巻き込み、北宮王家として存在していた。
北宮王家についての呼称の由縁は、藤原京時代に父高市皇子が京の北側に住居したのが始まりという。
そういえば藤原四家も北家、南家も藤原京の方角に住んでいたからだと言われている。
“長屋王政権”
不比等から長屋王へ、やがて藤原四兄弟の台頭、不比等が長屋王に全権を委ねる見返りに、わが子の抜擢を促すが如く、長子武智麻呂の妻に長屋王の妹竹郎女王を嫁がせ関係を深める。
養老四年(721)十二月元明太上天皇が没し、十二月に右大臣長屋王が誕生し、打ち出した政策は、農業振興政策で、良田百万町の開墾政策で、遷都十年平城京の米などの消費に生産が追いつかず、増産するために開墾を奨励する政策である。
次に出した政策に「三世一身法」で開墾と道、水路を整備したものには、三世代に渡りその土地の占有を認めるということである。
聖武天皇(首皇子)父文武天皇・母藤原宮子・皇后藤原光明子・五六歳没・在位二六年間・
養老八年(724)天武、持統、草壁の、直系の期待の首皇子が万を辞して、大極殿に於いて即位した。
平城京の申しの皇子、聖武天皇の誕生である。
元明、元正と仲継ぎの天皇十七年にも及ぶ女帝を経ての天皇誕生には皇族内に安堵があっただろう。
異例と云えば皇位継承に、皇族を母に持たない天皇は初例であった。
“長屋王の変“
それが、その後の長屋王の問題に成っていったのであるが、大夫称号事件が起きた。
皇族でない藤原宮子は、天皇の母のその処遇に当初は大夫人と呼ぶ勅をだしが。そこで長屋王は、勅に従っていれば問題が無かった。
所が長屋王は聖武に大夫人とは「令」に照らし合わせても呼ぶことが出来ないと発言した、
皇を上に加えれば可能と進言、「令」を出して宮子の名を聖武に云ったことには悪意は無かったが、宮子に「皇」の一字を付けることで威光を持たせたかったのが本心だったろうが、律儀と言えば律儀、返って聖武天皇、光明皇后の威信を傷つける結果となった。
結局、長屋王の意見が通り「皇大夫人」となったが、口頭では「大御祖」と呼ぶことで落ち着いた。
天皇の発言に異を唱えたことの重大さに長屋王は気がついていなかった。
神亀三年(726)この頃より元正は体調を崩し、災害が起こり、信心深い聖武は写経や仏に寺院建立に励む日々であった。
翌年には待望の皇子の誕生に、宮廷の官人までが、明るく一変し祝賀に庶民まで恩恵を受け、税や免除が、物が振舞われた。
処が翌年、生後一年で皇子は世を去り、聖武、光明の落胆は計り知れないものだった。
この頃より益々、聖武、光明は仏への信心は深まり、大きく仏教へ傾いていくのである。
仏教への深まりは光明の影響から、余々に光明の発言力の強さへと変化していった。
鎮護国家への道は聖武と光明に取り最早、長屋王は邪魔な存在でしかなかった。
それもなんの予告も無く、突如神亀六年(729)二月十日の夜、六衛府の兵が長屋王の邸を取り囲んだ。
兵を指揮していたのは、藤原四兄弟の三男の宇合と次官であった。
手順として逃亡の恐れありと、地方の兵の混乱を避けるために、固関(こげん)が実施された、三関(鹿関、不破関(ふわせき)、愛発関(あらちぜき))これからの起こる政変に備えてである。
皇族からは、舎人親王、新田部親王、他、大納言、中納言、藤原武智麻呂などが長屋王の罪状を問うために門を叩いた。
その嫌疑は国家(こっか)転覆(てんぷく)罪(ざい)、左道を持って天皇を呪詛したという疑いで取調べを受けた。
密告者は下級役人三人で、明らかに冤罪であるが、抗弁、弁明しても、覆るものではない。
長屋王は翌日には自決享年五十四歳のことだった。
自決の前に、妻子、吉備内親王と三人の子、膳夫王、葛木王、鉤取王と、石川夫人の子桑田王に毒を飲ませて絞殺、こうして長屋王家、北王家は悲劇の結末で滅亡した。
一族は生駒山の麓の平群に葬られ、吉備内親王には罪がないと理由でその葬を賎しくしてはならないと長屋王の他の夫人、王子、女王には一切罪は問わない勅が下された。
★長屋王(684~7299奈良時代の左大臣。高市皇子の子で天武天皇の孫。母は天智天皇の女。妻は元明天皇の子の吉備内親王。天平元年(729)左道を学び国家を傾けようとしているとして訴えられ、吉備内親王や膳夫(かしわで)・葛木王らと共に自殺し滅亡した。
長屋王邸が宮城の北側にあったことから「北宮王家」と言われている。
◆左(さ)道(どう)*①不正な道、邪道、転じて、不都合、不謹慎の意。②粗末の意。
※長王の変で解るように皇権に近い長王は臣籍に降下して政権を担ったが、聖武帝を取り巻く皇族や重臣にとって目障りな存在でしかなかった。
新興勢力の藤原四兄弟の台頭が相まって長屋王の突き落としに一役買ったかもしれない。とりもなおさず藤原宮子、光明子の立場や存在を否定するものではないが、皇位継承保持者の存在は除外に他ならない。
“長屋(ながや)王(おう)の頭角(とうかく)”
時代は不比等から長屋王へと変わって行った。元正が没した。
養老五年(721)政権は不比等に変わり、長屋王が就いた。本来なら皇族の重要な地位でもあったが、あえて皇籍を降り、臣籍と成っての政権だった。
天平元年(729)栄光から悲劇の失脚までの、謎の多い八年間を平城京の政権を担った。本来なら天武の長子高市皇子の王子として後継の有力候補として、皇族の中枢でいるはずが、高市皇子の母方の血筋が九州豪族の娘と言うことで身分の低さから父と同様皇権から外されていた。
だが高市皇子は壬申の乱の折には若干十九歳にして、勝利に導く働きの功績は大きかった。その後持統五年(690)持統在位中では八年間太政大臣として、朝廷を支えた。
妃には天智の皇女御名部皇女が向けられた、元明天皇の上の姉に当たる。
草壁皇子に継ぐ存在だったが享年四十三歳で没した。御名部皇女の間に三人の皇子と三人の皇女が生まれた・父高市皇子と違い長屋王は母が天智女である以上最も王権に近い存在だった。
だがもし長屋王が王権に意欲を見せていたならば、政争に巻き込まれて、排除されて、抹殺されていた可能性は、否定できない。
父はそんな事を察知しいち早く、臣籍の道を歩むことを、選択したに違いない。
まして首皇子が誕生した以上は全ての皇族は、皇権に意欲のないことを示さなければ、身の安全は無ことは熟知していたかも知れない。
運命の選択は父の生き方を、知った上の官人として登り詰めて行った。
“北宮(きたみや)王家(おうけ)と木管(もっかん)“
長屋王自身その生き方に臣籍に活路を求めた。
長屋王については、謎が多かったが、奈良市の大型建築物の基礎工事で元長屋王の住居跡から長屋王の関係する、多くの木管が出土し、その権力と、その暮し振りや様子が解明されつつある。
長屋王 天武五年(676)飛鳥で高市皇子の長子として生まれた、母は御名部皇女である。
☆妃に吉備内親王、草壁皇子と元明天皇の内親王で三人の王子が生まれている。*膳夫王、葛木王、鍵取王。
☆石川夫人には王子が一人。*桑田王。
☆安倍大刀自夫人に一人の女王。*加茂女王。
☆藤原不比等の娘の長我子の間に四人の王子。*安宿王、黄文王、山背王、教勝?
☆他に分かっているだけで六人の女王。三人の王子。*円方女王、紀女王、忍海部女王、珎努女王、日下女王、栗田女王、林王、小冶田王、太若?
なかでも吉備内親王の血縁は深く微妙である。
それが北宮王家(高市皇子、長屋王)という特別な存在だった。あたもかも、聖徳太子の上宮王家を彷彿とさせるものがある。
首皇子の誕生以降は皇位継承からも外されてからは、その代償として、特別な処遇であった。
政治家の道を選択した長屋王は、父同様にその才覚を発揮したのではないだろうか、平城京遷都から失脚する十九年間、長屋王邸宅は正殿と脇殿と建つ、床面積三百六十平方メートルという、天皇の次に観られる大きな邸宅である。
上記の家族構成に充分住居としても、特別扱いだった。
その機能やシステム構造は宮殿を少し小さくしたもので、政所、務所、(事務所)主殿司、(殿舎管理)大炊司、(食料庫)膳司、(調理)菜司、(野菜所)、酒司、主水司、(水酒の管理)染め司、(染色工)工司、(職人所)鋳物司、銅造司(金物の製造)嶋造司、(庭園所)仏造司、斎会司、(仏事)薬師処、馬司、犬司、鶴司、など多岐に渡りあって、あって一国の王宮のまかないのに相当するものである。
これらの長屋王の関係する人々の従事する人数は数百人に及んだだろうと思われる。
邸宅は北門の二条大路に面し、大路には本来門を開いてはいけないのに、表通りに開く北門があって、広大な邸には、妃、夫人と、それぞれの家族に王子、女王が、区割りされた処に住み長屋王の一族を成していた。
そんな大勢の人々の暮しを守るだけの、物資、資金を考えた場合、奈良の大型デパートの建設の折り、たまたま長屋王の邸跡だった。
出土された、多くの木簡は、奈良時代と長屋王の謎を解く鍵として、大量に出てきたのである。
木管は長屋王のその暮し振りと、当時の情景や、情報が膨大に出てきたのである。
しかも途方もない作業であった、木管は長さ二十センチ位で、幅三センチ位、厚さ四ミリ、紙の代行で諸国を流通する、貴重な木札であった。役割は書簡、命令書、明細書、荷札,連絡書など多彩である。
木といっても貴重である、決して使いすではない。削って再利用するのである。その削りカスを、一つ一つ広げて、判読するのである。
三万五千点に及ぶ木管を解明しつつある。
実に気の遠くなるような話である。そんな中から当時の長屋王の日々暮らしを見ることができる。
領地から送られてくる数々の品は、その豊かな食卓を物語るものであるが、荷札の木管からは、父の領地、遠くは高市皇子の母方の宗像(宗形)から送られた物があり九州からの結びつきを物語る、封戸四千五百戸分に相当する。
諸国父高市皇子から受け継いだものを入れ三十七カ国にも及ぶ、摂津国の塩漬け鯵、伊豆国の荒鰹、上総国のゴマ油、越後国の栗、阿波国の猪なで、近郊から野菜など、夏には奈良の山手の氷室から氷まで、その豊かな美食が窺い知れる。
長屋王の取り巻く家族はそれぞれの夫人の王子や女王に加え、妃や夫人の背景をも巻き込み、北宮王家として存在していた。
北宮王家についての呼称の由縁は、藤原京時代に父高市皇子が京の北側に住居したのが始まりという。
そういえば藤原四家も北家、南家も藤原京の方角に住んでいたからだと言われている。
“長屋王政権”
不比等から長屋王へ、やがて藤原四兄弟の台頭、不比等が長屋王に全権を委ねる見返りに、わが子の抜擢を促すが如く、長子武智麻呂の妻に長屋王の妹竹郎女王を嫁がせ関係を深める。
養老四年(721)十二月元明太上天皇が没し、十二月に右大臣長屋王が誕生し、打ち出した政策は、農業振興政策で、良田百万町の開墾政策で、遷都十年平城京の米などの消費に生産が追いつかず、増産するために開墾を奨励する政策である。
次に出した政策に「三世一身法」で開墾と道、水路を整備したものには、三世代に渡りその土地の占有を認めるということである。
聖武天皇(首皇子)父文武天皇・母藤原宮子・皇后藤原光明子・五六歳没・在位二六年間・
養老八年(724)天武、持統、草壁の、直系の期待の首皇子が万を辞して、大極殿に於いて即位した。
平城京の申しの皇子、聖武天皇の誕生である。
元明、元正と仲継ぎの天皇十七年にも及ぶ女帝を経ての天皇誕生には皇族内に安堵があっただろう。
異例と云えば皇位継承に、皇族を母に持たない天皇は初例であった。
“長屋王の変“
それが、その後の長屋王の問題に成っていったのであるが、大夫称号事件が起きた。
皇族でない藤原宮子は、天皇の母のその処遇に当初は大夫人と呼ぶ勅をだしが。そこで長屋王は、勅に従っていれば問題が無かった。
所が長屋王は聖武に大夫人とは「令」に照らし合わせても呼ぶことが出来ないと発言した、
皇を上に加えれば可能と進言、「令」を出して宮子の名を聖武に云ったことには悪意は無かったが、宮子に「皇」の一字を付けることで威光を持たせたかったのが本心だったろうが、律儀と言えば律儀、返って聖武天皇、光明皇后の威信を傷つける結果となった。
結局、長屋王の意見が通り「皇大夫人」となったが、口頭では「大御祖」と呼ぶことで落ち着いた。
天皇の発言に異を唱えたことの重大さに長屋王は気がついていなかった。
神亀三年(726)この頃より元正は体調を崩し、災害が起こり、信心深い聖武は写経や仏に寺院建立に励む日々であった。
翌年には待望の皇子の誕生に、宮廷の官人までが、明るく一変し祝賀に庶民まで恩恵を受け、税や免除が、物が振舞われた。
処が翌年、生後一年で皇子は世を去り、聖武、光明の落胆は計り知れないものだった。
この頃より益々、聖武、光明は仏への信心は深まり、大きく仏教へ傾いていくのである。
仏教への深まりは光明の影響から、余々に光明の発言力の強さへと変化していった。
鎮護国家への道は聖武と光明に取り最早、長屋王は邪魔な存在でしかなかった。
それもなんの予告も無く、突如神亀六年(729)二月十日の夜、六衛府の兵が長屋王の邸を取り囲んだ。
兵を指揮していたのは、藤原四兄弟の三男の宇合と次官であった。
手順として逃亡の恐れありと、地方の兵の混乱を避けるために、固関(こげん)が実施された、三関(鹿関、不破関(ふわせき)、愛発関(あらちぜき))これからの起こる政変に備えてである。
皇族からは、舎人親王、新田部親王、他、大納言、中納言、藤原武智麻呂などが長屋王の罪状を問うために門を叩いた。
その嫌疑は国家(こっか)転覆(てんぷく)罪(ざい)、左道を持って天皇を呪詛したという疑いで取調べを受けた。
密告者は下級役人三人で、明らかに冤罪であるが、抗弁、弁明しても、覆るものではない。
長屋王は翌日には自決享年五十四歳のことだった。
自決の前に、妻子、吉備内親王と三人の子、膳夫王、葛木王、鉤取王と、石川夫人の子桑田王に毒を飲ませて絞殺、こうして長屋王家、北王家は悲劇の結末で滅亡した。
一族は生駒山の麓の平群に葬られ、吉備内親王には罪がないと理由でその葬を賎しくしてはならないと長屋王の他の夫人、王子、女王には一切罪は問わない勅が下された。
★長屋王(684~7299奈良時代の左大臣。高市皇子の子で天武天皇の孫。母は天智天皇の女。妻は元明天皇の子の吉備内親王。天平元年(729)左道を学び国家を傾けようとしているとして訴えられ、吉備内親王や膳夫(かしわで)・葛木王らと共に自殺し滅亡した。
長屋王邸が宮城の北側にあったことから「北宮王家」と言われている。
◆左(さ)道(どう)*①不正な道、邪道、転じて、不都合、不謹慎の意。②粗末の意。
※長王の変で解るように皇権に近い長王は臣籍に降下して政権を担ったが、聖武帝を取り巻く皇族や重臣にとって目障りな存在でしかなかった。
新興勢力の藤原四兄弟の台頭が相まって長屋王の突き落としに一役買ったかもしれない。とりもなおさず藤原宮子、光明子の立場や存在を否定するものではないが、皇位継承保持者の存在は除外に他ならない。












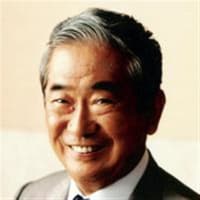






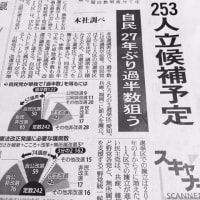
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます