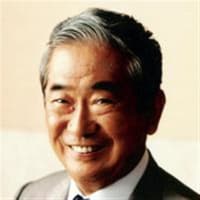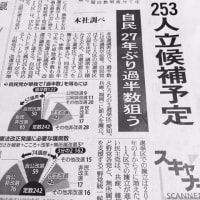十八、持統天皇と藤原京
天武天皇の皇位継承については、波瀾が有った。年齢的に長子の壬申の乱でも活躍した高市皇子(長王の父)は血筋で母親が北九州の豪族で胸形君徳善の娘の尼子娘であったので皇位継承は無理であった。
これは壬申の乱で悲運の大友皇子もそうであったように、母方の血脈がもの言う。次に最も有力な草壁皇子と大津皇子の二人は一つ違いで大津皇子が上で、母方が姉妹であった。
皇位継承の筆頭の二人には鸕(うの)野(の)賛(さら)良(ら)皇女(こうじょ)(持統)の皇子は草壁皇子で影が薄く、評判も芳しくなく体も脆弱であったらしい。
それに対して一歳年下の大津皇子は文武両道に長けていて、資質も文句なし評され、天武帝生存中は両者同対等な立場で登場するが、天武帝の没後から大津皇子の身辺が急変する。
天智帝の殯宮(もがりのみや)葬儀が執り行われている最中、大津皇子の謀反が発覚する。四日間取り調べの後に、捕えられて自邸で死を賜った。
この事件で連座して三十人が逮捕されたが結局、大津皇子に謀反を進めた新羅からの渡来僧行心が謀反を進めたと言う配流されたが、これは明らかに冤罪で持統らの仕組んだ策略と思われる。
こう言った王族内の粛清に似た、抹殺を危惧して天武帝が吉野の会盟が死後何の意味も持たないことと、天武帝の予測が的中した形だった。
持統天皇の在位中に夫天武帝がかねがね意としてた、「飛鳥浄御原令」を編纂するに至り、二十二巻、作成には難航を極め、中国唐律に大きく依存し影響されたものになった。
主として中央集権の構築するために、八色の姓等など豪族統制策が盛り込まれた。
次に「庚寅年籍」戸籍について。次に課役について「賦役令(ふえきれい)」「調・田令・課戸・計帳」「」などが大宝律令まで効力を発した。
★持統天皇(645~702)称制四年、在位十二年長きに渡り天皇不在の中継ぎの女帝、父は天智天皇、母は蘇我石川麻呂の女遠智娘。天武天皇の皇后なり草壁皇子を生んだ。壬申の乱後夫大海人皇子と行動を共に支え続けた。
★草壁皇子(662~689)天武天皇の第一皇子、大津皇子と同様に筑紫に娜(な)の大津で誕生、母は鸕野皇女、吉野で盟約を行い、翌々年に立太子した。天武が病の中、皇后と共に天下事を委ねられたが即位しないままに没した。
★大津皇子(663~686)天武天皇の皇子、母は天智天皇の皇女で大田皇女。大津皇子は百済救援戦争に筑紫に向かう途中に誕生した。壬申の乱の時も最後まで祖父の天地天皇ところに留まっていた。これは天智帝が有能な後継者として期待してた結果だろうと思われている。
※七年前のことで、天武と持統は天武の皇子四人と天智系の御子二人を集め、互いに裏切ることなく千年の誓いを地祇天神に盟約をした。持統の目した寵愛の皇子は皇位を継ぐことなく、若くして亡くなった。
こうして次期皇位継承者の出現までの中継ぎとして、持統即位し藤原京に着手、これは亡き夫の天武帝の願いでもあった。
最近の発掘で藤原京の造営計画は天武帝の病気祈願の頃から定めら、我が国初の本格的都城の藤原京が造営されることになった。
勿論都城は中国の都城に刺激されてのことだったろう。この藤原京造営と天武帝没後の四年後に正式皇位を継承、即位をしたのが六九〇年で二年後に地鎮祭が執り行われた。
大藤原京の規模は諸説があって、東西五・二キロメートル、南北五・二キロメートと考えており、南北十条、東西十坊と想定され、その中央に藤原京が周囲一キロメートルと思われている。
現在地としては奈良県橿原市(かしはらし)付近で北に耳成山、西に畝傍山(うねびさん)、南東に香久山の大和三山に囲まれていて、藤原京の周囲には掘立柱を塀の大垣で囲まれている。
外堀(外濠)の幅五メートル、東西南北面に三カ所の門が開き、中央に朝堂院と正殿として大極殿のある堂々たる藤原京であった。
天武天皇の皇位継承については、波瀾が有った。年齢的に長子の壬申の乱でも活躍した高市皇子(長王の父)は血筋で母親が北九州の豪族で胸形君徳善の娘の尼子娘であったので皇位継承は無理であった。
これは壬申の乱で悲運の大友皇子もそうであったように、母方の血脈がもの言う。次に最も有力な草壁皇子と大津皇子の二人は一つ違いで大津皇子が上で、母方が姉妹であった。
皇位継承の筆頭の二人には鸕(うの)野(の)賛(さら)良(ら)皇女(こうじょ)(持統)の皇子は草壁皇子で影が薄く、評判も芳しくなく体も脆弱であったらしい。
それに対して一歳年下の大津皇子は文武両道に長けていて、資質も文句なし評され、天武帝生存中は両者同対等な立場で登場するが、天武帝の没後から大津皇子の身辺が急変する。
天智帝の殯宮(もがりのみや)葬儀が執り行われている最中、大津皇子の謀反が発覚する。四日間取り調べの後に、捕えられて自邸で死を賜った。
この事件で連座して三十人が逮捕されたが結局、大津皇子に謀反を進めた新羅からの渡来僧行心が謀反を進めたと言う配流されたが、これは明らかに冤罪で持統らの仕組んだ策略と思われる。
こう言った王族内の粛清に似た、抹殺を危惧して天武帝が吉野の会盟が死後何の意味も持たないことと、天武帝の予測が的中した形だった。
持統天皇の在位中に夫天武帝がかねがね意としてた、「飛鳥浄御原令」を編纂するに至り、二十二巻、作成には難航を極め、中国唐律に大きく依存し影響されたものになった。
主として中央集権の構築するために、八色の姓等など豪族統制策が盛り込まれた。
次に「庚寅年籍」戸籍について。次に課役について「賦役令(ふえきれい)」「調・田令・課戸・計帳」「」などが大宝律令まで効力を発した。
★持統天皇(645~702)称制四年、在位十二年長きに渡り天皇不在の中継ぎの女帝、父は天智天皇、母は蘇我石川麻呂の女遠智娘。天武天皇の皇后なり草壁皇子を生んだ。壬申の乱後夫大海人皇子と行動を共に支え続けた。
★草壁皇子(662~689)天武天皇の第一皇子、大津皇子と同様に筑紫に娜(な)の大津で誕生、母は鸕野皇女、吉野で盟約を行い、翌々年に立太子した。天武が病の中、皇后と共に天下事を委ねられたが即位しないままに没した。
★大津皇子(663~686)天武天皇の皇子、母は天智天皇の皇女で大田皇女。大津皇子は百済救援戦争に筑紫に向かう途中に誕生した。壬申の乱の時も最後まで祖父の天地天皇ところに留まっていた。これは天智帝が有能な後継者として期待してた結果だろうと思われている。
※七年前のことで、天武と持統は天武の皇子四人と天智系の御子二人を集め、互いに裏切ることなく千年の誓いを地祇天神に盟約をした。持統の目した寵愛の皇子は皇位を継ぐことなく、若くして亡くなった。
こうして次期皇位継承者の出現までの中継ぎとして、持統即位し藤原京に着手、これは亡き夫の天武帝の願いでもあった。
最近の発掘で藤原京の造営計画は天武帝の病気祈願の頃から定めら、我が国初の本格的都城の藤原京が造営されることになった。
勿論都城は中国の都城に刺激されてのことだったろう。この藤原京造営と天武帝没後の四年後に正式皇位を継承、即位をしたのが六九〇年で二年後に地鎮祭が執り行われた。
大藤原京の規模は諸説があって、東西五・二キロメートル、南北五・二キロメートと考えており、南北十条、東西十坊と想定され、その中央に藤原京が周囲一キロメートルと思われている。
現在地としては奈良県橿原市(かしはらし)付近で北に耳成山、西に畝傍山(うねびさん)、南東に香久山の大和三山に囲まれていて、藤原京の周囲には掘立柱を塀の大垣で囲まれている。
外堀(外濠)の幅五メートル、東西南北面に三カ所の門が開き、中央に朝堂院と正殿として大極殿のある堂々たる藤原京であった。