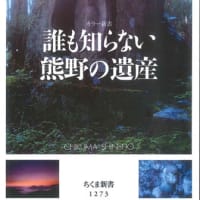2011年9月に紀伊半島を襲った台風12号による災害について、当時現地を歩いて見たこと/知ったことをシリーズで書いています。
前半は土砂災害(土石流)について1)~5)に書いたので、後半は水害(河川氾濫)について書いています。
8)洪水は下流から来る - 高田川の場合 -
高田川は、熊野川の河口から10kmくらい上流の所に注ぐ、(前回紹介の相野谷川に次いで2番目に河口に近い)比較的大きな支流です。
この高田川の洪水も、下から上がってきました。というか、本流熊野川への合流点にまるでダムがあるかのようなイメージで、本流へ注げないどころか、本流から逆に流入してきたので、ダムのように増水したのでした。
地図を見ていただくとわかるのですが、高田川流域は、下流3kmくらいの相賀という急斜面が両側に迫った渓谷地域と、そこからさらに1.5kmくらい上流に広く開けた高田盆地でできてきます。高田集落が"ろうと"の広い口、相賀集落が"ろうと"の狭い管の部分にあると思っていただければわかりやすいかと。
この"ろうと"みたいな地形も、被害を悪化させたかと思います。
相賀から高田へ上がるのに1km近くも高田トンネルを掘っていることからわかるように、"ろうと"の管部分の相賀一帯は険しい地形になっています。
そして、高田川流域で一番被害が酷かったのは、その水の逃げ場のない下流の相賀地域でした。
高田集落へは災害の5日後の9/9にボランティアで入ったので、写真はその時の様子です。
上の写真は、相賀バス停付近ですが、あの長さの植林木が橋に引っ掛かって立つほどの水量があったことを示しています。左に見えている民家は完全に水没しました。
そして橋の高さに道路があるわけですが、↓

道路脇の木についた傷からも、水位の高さが伺えます。

相当の厚さに泥が堆積しています。
(泥をかいたので車が入れるようになった)

避難所ではなく自宅待機している方のお宅に、役場の方が飲料水を運び、保健婦さんと一緒に伺います。
道から坂道をどんどん上がっていくんですが、それでもご自宅の屋根瓦まで水が来たことがわかります(写真右側の民家) 住民の方は、母屋からさらに斜面の上の納屋に逃げて助かりました。
住民の方が仮生活している納屋まで行きましたが、こんな高さまで!?と驚くような、川を見晴らす斜面の上だったです。なのに納屋でさえ足もとまで水が来たそうです。
川の合流部は氾濫する、
そして、合流部に近い支流下部では、本流に遮られた水&本流からの逆流のダブルパンチでダムのように増水する、
ということを、実感した一日でした。
ちなみに、高田川上流の高田集落では、皆さんが避難していた雲取温泉の直下まで水没したものの、そこでかろうじて増水は止まりました。

それでも、雲取温泉のすぐ下の橋はこんな感じ。
増水だけでもイヤなのに、こんな木が流れてくるなんて凶器!!危険すぎる(;;)
PS
川の合流部は氾濫するというのに付け加えですが、熊野川本流への赤木川の合流部(2011年7月の台風でも冠水していた)の能城~日足地区では、台風12号時には熊野川町旧役場庁舎(4階建て)の3階まで水没しました。(2階にあった防災無線は全滅でした)