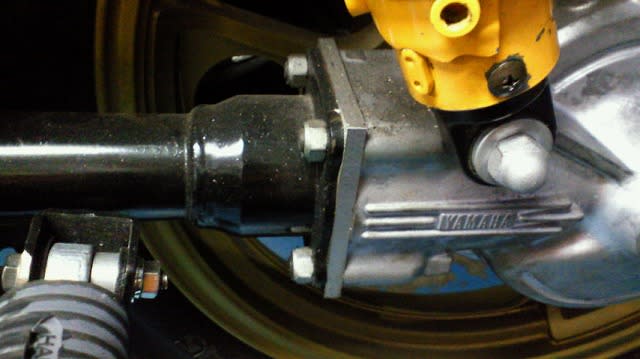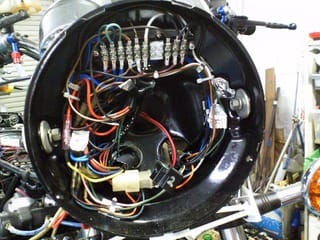ユーザー車検に成功しました。
成功というほどの事ではありませんが、それでもひとつの区切りが付きました。
車検場へ行く前に、近くの予備検査工場で光軸調整をお願いしました。
手際のいいお姉ちゃんが、チャチャっと調整してくれて、1000円!
おまけに冷たいコーヒーまでサービス。
車検場でまずは書類の作成と提出です。
書類を作って、代書屋さんで自賠責に入ろうとお願いした時です。
「この廃車証は原本じゃないねえ。おそらくこのままでは通らないよ」
・・・・
そんなの知らないよ~
「じゃあ、とりあえず窓口で聞いてみますね」
そう言って、窓口で確認すると・・・
「古い書類だからねえ。大丈夫ですよ」
な~んだ、大丈夫じゃん!
こんな感じで、自賠責に入るため、再度代書屋さんい行こうとしたときに
念のため、窓口に尋ねておきました。
「ホントに大丈夫なんですね! 自賠責入ってきますから」
窓口→「わかりました。揃ったら受付しますから持ってきてくださいね」
ここまで言われれば、その通りにするのは当然ですよね。
で、自賠責に入って、印紙などの支払いを済ませて窓口へ行くと
ポンポン!ってハンコを押して、「それじゃ、検査の受付窓口行ってください」
こう言うわけで、検査窓口に行って、書類を提出しました。
そしたら、検査窓口の年配の係員が
「あれ? これって写しだなあ。原本ないですか?」
こう言ってきたのです。
こっちはそんなの知らないし、買った時にもらった書類をそのまま出しただけです。
「さっき、あちらの受付で確認したら、大丈夫って言われて、ハンコも押してあるでしょ」
検査窓口→「でもねえ、これだと受けられないですよ」
ちょっと待ってよ!。おたくらの仲間が大丈夫って言ってるんだけどなあ~
その旨を、最初の窓口でもう1回確認します。
「さっきおたくが大丈夫って言った書類を、検査窓口はダメだって言ってるよ」
「どういうこと?」
受付→「・・・・」
「ちょっと待ってくださいね」
奥の方で、何やら話し合ってます。
上司のような人が出てきて
「あのですねえ、これ写しみたいなんですよ」
「写しだろうとなんだろうと、こっちはわからないけど、それをさっき確認してお金払ってきたんだけど」
「今更、そんなこと言われても、こっちもそうですか!ってわけにいかないでしょ」
「そっちでなんとかしてよ」
こう言い放って、待ちます。
しばらくすると
「あのですねえ、書類は本物みたいですが、ちょっと手続きに数日掛かるんですよ」
「どちらにしても今日の検査は無理ですねえ」
ムカッ!
「あのねえ、そっちの受付印があるじゃん」
「念押ししてお金払ったんだけど」
すると
「じゃあ、今日なんとか手続きするので、明日来てもらえますか?」
バカかこいつら
「あのねえ、それが出来ないから、さっきさんざん確認したんだよ」
「自賠責だって1ヶ月余分に払ってるけど、次はいつ来れるかわからないわけ」
「勝手なこと言ってないで、そっちのミスなんだから今やってよ!」
待つこと30分
今、品川陸自に照会して、大丈夫なことがわかりましたので、今日検査してください」
やりゃ出来るじゃん。最初からやれよ!
ホントにお役所仕事丸出しですね。
書類ですったもんだして、予約した検査時間はとっくに過ぎてます。
いざ検査ラインに入ると、もう他の受検者は終わってしまって
検査官もひまそうです。
「じゃあ、こっちに入ってください。」
そう言われてラインに入ると、あれこれ2人の検査官に念入りなチェックを受けます。
「そんなに見なくていいのになあ~」
「はい!OKです。じゃあ騒音測定しますので、3750回転まで上げてください」
何だよ、そのハンパな数字
レッドゾーンの半分の回転まで上げるらしいのですが、おれのは7000回転だぜ。
計算まちがってねえ・・・
後ろでタコメーターを凝視してます。見なくていいのになあ~
で、指定の回転まで上げると
「あれ、115デシベルもあるなあ~ そんなにあるかなあ」
こう言ってます。
規定値上限は99デシベルです。
軽くオーバーしてるじゃん(笑)
「もう1回上げてくれる?」
アクセル捻って回転を上げます。
今度は102デシベル
「はい!いいですよ」
OKじゃないよねえ・・・
結果を聞くと
「えっと、音が規定値超えてるのと、ライトスイッチにオンオフの文字がないんですよ」
「あと1時間あるけど直せます?」
もちろんやりますよ。
「すぐに対策してきますから。」
そう言って、気は焦るばかり
とりあえずライトスイッチは、白い修正ペンで書いちゃいました。

明らかに書きすぎww
音をどうしよう・・・
もう、こうなったら何でもありです。
マフラーの出口につけていた、ディフューザーの裏側に、空き缶を裂いて作った
板を巻きつけて、細いドライバーで穴を開けました。

こんなんでいいのかなあ~
音も明らかに小さくなりました。
再度、検査ラインへ
両方とも合格!
「よく対策出来ましたねえ。これでOKですよ」
すげーいい加減。こんなもんなんですね。
晴れて公道復帰となりました。


まだまだ、改善点が多いのですが、これで堂々と乗ることが出来ます。
いや~ なんとも低速の気持ちいい車体です。
あとでわかったのですが、タコメーターの動作不良で回転指示の上がりが不十分でした。
もしかしたら5000回転くらい上がってたんかなあ~
明らかに、これより大きな音のバイクがちゃんと検査合格でしたから
検査官がおかしいなあ~って言っていたのも、うなづけます。