
室生犀星 『蜜のあわれ』
講談社文芸文庫(1993年)、小学館(2007年)、小学館・昭和文学全集(2007年)、国書刊行会・日本幻想文学集成(1995年) など
金魚と少女の間を自在に往還するコケティッシュな「あたい」と、老作家「おじさま」の奇妙な交流。そして、そこにひそやかに訪れる「ゆうれい」の女性の影。室生犀星が晩年に発表したこの小説は、男女の情の切なさ、性欲や愛情のかなしさを、シュールな設定で耽美的に描いた作品です。なかやまあきこ撮影による金魚・花・少女の写真との美しきコラボレーションで、犀星の傑作がいっそう鮮やかに蘇ります。
小学館
<例会レポート>
早いが取り柄のワタクシ。
室生犀星は教科書にも名前が出てたし、その名はつとに有名だけど、
小説は一度も読んだことがなかった、ってか、詩人だと思ってたから
小説を書いてたなんて知らなかった。
という会員が圧倒的多数を誇る今回の課題本。
かくいう推薦人のワタクシも、NHKドラマ「火の魚」を観て
原作に触れたのが、犀星を初めて読むきっかけとなったのでした。
ではワタクシ以外の24人の参加者の雑感を、記憶のかぎり書きます。
・以前『杏っ子』を読んでいた。
今回は魚を取り上げた短編集の『日本幻想文学集成 32 室生犀星 』を読了。
旧仮名使いだったけれど、読みやすかった。室生犀星は素直な人だという
気がする。記念館のサイトに見るように、「いいおじいちゃん」そのままの印象。
・室生犀星というと、堀辰雄や立原道造との交流があり、詩人の印象が強い。
『かげろうの 日記遺文』をこれまで読んだが、今作品は別の一面を見た思いで新鮮だった。
年寄りと若い女というと川端康成が思い浮かぶが、あちらは気持ち悪さが先に立ったが、
これは楽しく読めた。「あたいは死なない」と言う金魚がいじらしい。
『火の魚』も良く、作家はいい人なのだろうと思う。
・正直でピュアな印象。憎めない人だと思う。江戸の時代の名残もあり、
全体的に好き。身近な感じがある。『杏っ子』は厚みに驚いたが、最後まで読めた。
・金沢の犀川がペンネームの由来と聞き、川のイメージを持った。
西村賢太で私小説になじみを持ち、面白さを知った。
課題本はお爺さんと可愛い女の子の関係がエロく?、びくびくしつつ読んでしまったが、表現力が素敵。
特に赤い色の表現が。芥川龍之介が「超えられない」と嘆いた犀星の感性に納得する。
全ての作品に死生観が漂い、死と対比する生が浮かび上がる。
・金魚がコケティッシュで可愛らしいが、「おじさま」に一抹の寂しさを覚える。
『火の魚』で死と隣り合わせにある人が魚拓をとることに向かう姿がよかった。
『陶古の女人』も、これはこれでよい。
・文庫と旧仮名遣いの全集を読了。
説明のつかないファンタジーだが、すごく面白かった。
最初は金魚と女性の姿を区別して読もうとしたが、
やがて渾然一体としていることが、それで良いのだという気になった。
『火の魚』を読んで、モデルとなった装幀家・栃折久美子の『モロッコ革の本』も読了。
犀星は、まさか読むとは思わなかった作家だったが読めてよかった。
・「あたい」という一人称に引っかかったが、慣れるとするする読めた。
ラストはあっけない。もう少し長くてもいいと思った。
・読んで「老人の戯言」という感を拭えなかった。
「赤い風船」は大好きな映画なので、一緒に語らないでほしいとネガティブに受け止めたが、
同世代として何か共通するものがあるはずと再読し、たとえば若い美少年が、
ただ生き物として美しいと感じる最近の自分の気持ちに通ずるものがあるかもと思った。
そっと観るだけで関われない老いの孤独、かけがえのない美を感じる。
・妄想話だが、案外いやらしくはない。
文が女々しく子供っぽいが、老人なので許せるか。金魚が可愛い。
女性ではなく金魚として読めば、犬を可愛がる親父と同じかも。
写真付きの単行本を読んだが、あるとかえっていやらしく、妨げになる。
・作品もスタイルも、どれも面白かった。『蜜のあわれ』は好きな世界。
年をとると「本物だけになって生きかえっているところがある」という言葉が
すとんと落ちて納得出来た。
会話体の小説は難しいと思うが面白く、赤のイメージが染み込む。
・課題本のみ急いで読んでしまったが、作家をもっと知って読めばもっとよかったかも。
皆の意見を聞くと、自分の感性が鈍っていると感じる。
「なんでにっかつロマンポルノで映画化されてないのか」とか思うばかりで、
「良かった」という思いが味わえなくて悔しい。
・初めて読んだが、文章表現に引き込まれた。
「のめのめ」とかぬめり感がよく出ていて面白い。想像力が掻き立てられる。金魚が可愛く、お臀の話も面白い。
あちこちの文に深い意味を持つことが書かれている。
70歳で「本物だけ・・」という言葉も考えさせられた。
・写真付きの本を読んだが、画像に邪魔され読みづらかった。
金魚が人間になったのか、人間が金魚になったのか。
人間では生々しいので金魚にしたのか。
70歳の室生犀星は若い子にこう言ってもらいたいのか。エロティック。
・金魚の本と思って写真集を手にした。
皆の話を聞いて、女の子の話だったのかとやっとわかった。写真付きは読まない方がいいと思う。
・『蜜のあわれ』はなかなか読めなかったが、『われはうたえどもやぶれかぶれ』は身につまされた。
死ぬ間際にありながら、この明るさ、饒舌ぶりは、
私小説作家として書く事への気持ちの強さの表れであり、大したものだと思う。
・読めなかった。見ただけでダメ。
・課題本は全て読了を目指していたが、40ページで諦めた。
・会話体が読みにくく難航した。魚と女性に思い入れのある作家だと思う。
金魚のお節介ぶりは好きになれないが、『火の魚』は面白かった。
ドラマは途中までしか見てないのでちゃんと見たい。
魚はやさしく女のひとのどこかに似ていて、というくだりの意味を知りたい。
・室生犀星は名の響きがいいが詩人だと思っていた。
『蜜のあわれ』は良さがわからなかった。女性でも子供でもない短い少女の時期を描いたのか。
出目金など華やかな金魚がモデルだろうが、個人的には金魚といえば、地味な金魚すくいのイメージしかない。
ただ『炎の魚』のあと再読すると、けっこう楽しめた。『やぶれかぶれ』の方がじんとくる。
・数年前に金沢に行ったが、室生犀星の記念館にはいかなかった。
軽井沢の家は見たことがある。ちんまりした昭和の家だった。
課題本は特にイヤでもなく、それなりに面白くは読んだ。エロくて可愛い。
金魚は一昔前のレベッカのNOKKOのイメージ。
若くてぴちぴちの金魚より、ゆうれいの方が大きな存在だったのでは。
『火の魚』では、現役イメージの強い栃折久美子との交流が意外だった。
・ファンタジーはあまり好きではなく、作品に入れなかった。
会話体にも小説らしさを感じない。写真があるより活字だけの方が良い。
谷崎潤一郎は理解できるが、これには無理がある。
マンガならばうまく作品化できるのでは。詩人としての擬態語の使い方などは上手い。
・教科書に出てる人という印象。ざっと読んだらよくわからなかったが、
再読したら会話が楽しめた。意外性があって面白い。
金魚娘はコケティッシュ。二人の関係は、ベタベタしているが
性的なものではなく、父と娘に似ているかも。
・通勤中に読んだが感想がまとまらない。
自分のそばにずっといてくれる女性が理想なのだろうか。
・ようやく読んだ。一言で言うと、すごくいやらしくて、そこがいいと思う。
「のめのめ」「ぬらぬら」などの擬態語に、絵的というより触覚的なイメージが湧く。
・・・
いろんな本に収録されていた課題本ですが、写真付きの単行本が意外や不評。
文字の方が奥行のある想像力が得られるようです。
そんな「読むの初めて~」とか言ってる会員を前に、高校時代に川端、谷崎に加え、
室生犀星の『幼年時代』『或る少女の死まで』『性に目覚める頃』を、
愛読というか熱読され、国語教師が作成したテストの設問にまで抗議されたという
菊池先生の講評を。
●私生児として養父母に育てられ、逆境に生きた室生犀星は体系的な学問をしておらず、
川端康成と通じるものがある。
叙情に包まれた作品の中に冷徹な視線をもち、それは絶えず自分にも向けられている。
●谷崎を含めた3人の作品は、女の人を描くために生まれたものだ。
室生犀星は課題本にしたかったが、今では忘れられた作家となっていた。
しかし『火の魚』というドラマで人々の目が向いたと思う。
●犀星の作品は、
①初期 『幼年時代』『或る少女の死まで』『性に目覚める頃』
②中期 『あにいもうと』
戦争中の中断期を経て
③後期 『杏っ子』『蜜のあわれ』・・・
という3期に分かれているが、老年期の作品が、いちばん質が高い。
浴衣の裾からのぞく白いふくらはぎ、二の腕など、女性の美しさを追い求める描写は見事なまでにエロティック。
彼の小説には、哲学も思想もない。そこがいい。だから強い。
『蜜のあわれ』は男の妄想が生んだものだが、それは普通の人間の妄想とは違い、
文章に書かれ、世に出るものとして描かれている。エロティック。奥野健男は三島、
川端、谷崎を超えると評しているが、このシュルレアリスムは、カフカの『変身』以上のものと思う。
・・・講師の熱き思いとはうらはらに、意外と女性に好評、男性陣にはイマイチ
という結果でしたが、
「キミらも60~70歳になればわかってくる」とのこと。そして本日の〆のお言葉は
「男は皆、“少女”を求めるんです」
推薦人のワタクシも熱く前説を語りましたが、
出席者のみなさんに聞いていただいたのでヨシってことで。
いくつかの作品については、「よりみち」の方にも、これまでにUPしております♪
(文責:ままりん)










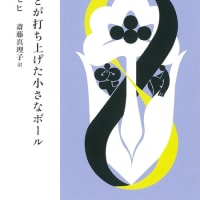
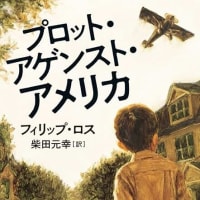













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます