"お役所仕事"と揶揄される我々の世界でも人材育成が重要と言われて久しい。
出来が悪いので周りに支えられて何とか、というか騙し騙しというか、30年来の県庁勤めをしてきた私がどうこう言うのはおこがましいし、私が中核となって仕事をしてきた30歳代から40歳代において長く配属された財政課などは実質的にスタッフ制をとっていたので、仕事のスタイルが、"分担してチームで取り組む型"というよりも"個人商店のように自己完結的な型"として出来上がってきたということもあって、若手職員に組織人としての仕事の進め方などを上手く教えられるような素養を身に着ける機会が十分ではなかったのだ。
それでも、本庁の課長になどなってしまうと、好む好まざるにかかわらず、課長補佐から主事まで幅広い職位の構成メンバーを抱えて、それぞれの事務分担と業務の難易度に応じて課題の解決に寄与して頂き、それが組織としてのより良い成果へと結びつくようにマネジメントする役割を担わざるを得ない。そのために人材育成の取り組みは必須なのだ。
人材育成というと何か大仰で体系的なものを考えてしまいがちだが、私にはそれほどの知見は無い。日々の個別具体の仕事で担当課員とやりとりをする中で、少し気になるところについて対処や修正を「お願いする」形をとりながら、その奥で意図する仕事の進め方や品質を確保する仕組みづくりについて、課員自身が気づき、自身にとって最適な形で自ら構築していくようになって欲しいと願うのだ。
何か問題が発生した後に再発防止策を議論していくと「要は関係者の意識次第」と結論付けられることが多い。「意識啓発」と記して幕引きするのは最も間抜けな結論だと私は思っているのだが、再発防止を構造的に担保するための仕組みづくりである「ISO9000シリーズ」とか「経営品質賞」というのも、そのスキームを導入するだけではまた「仏作って魂いれず」のごとし。
何かのシステムを運用する人間は、機械ではなく生き物として多様なのだから、一人ひとりが自身の資質や素養に即したメカニズムを、他の誰にも作りえない中で、自身で自らの内心に規範化して、組織のシステムに連動させる能動性が必要なのだと思う。
それでも、本庁の課長になどなってしまうと、好む好まざるにかかわらず、課長補佐から主事まで幅広い職位の構成メンバーを抱えて、それぞれの事務分担と業務の難易度に応じて課題の解決に寄与して頂き、それが組織としてのより良い成果へと結びつくようにマネジメントする役割を担わざるを得ない。そのために人材育成の取り組みは必須なのだ。
人材育成というと何か大仰で体系的なものを考えてしまいがちだが、私にはそれほどの知見は無い。日々の個別具体の仕事で担当課員とやりとりをする中で、少し気になるところについて対処や修正を「お願いする」形をとりながら、その奥で意図する仕事の進め方や品質を確保する仕組みづくりについて、課員自身が気づき、自身にとって最適な形で自ら構築していくようになって欲しいと願うのだ。
何か問題が発生した後に再発防止策を議論していくと「要は関係者の意識次第」と結論付けられることが多い。「意識啓発」と記して幕引きするのは最も間抜けな結論だと私は思っているのだが、再発防止を構造的に担保するための仕組みづくりである「ISO9000シリーズ」とか「経営品質賞」というのも、そのスキームを導入するだけではまた「仏作って魂いれず」のごとし。
何かのシステムを運用する人間は、機械ではなく生き物として多様なのだから、一人ひとりが自身の資質や素養に即したメカニズムを、他の誰にも作りえない中で、自身で自らの内心に規範化して、組織のシステムに連動させる能動性が必要なのだと思う。
松浦静山「些末なこともかき残さねば後世に伝わらず。」
◇◇◇今日この頃の人材育成あれこれエピソード◇◇◇
☆自分の頭で考える
予算や事業報告など、内外に示す資料の説明を受ける際、その書式の作成目的を担当に問うと「例年同様なので」と答える場合がある。事案に関して何を訊かれてどう答えるのに役立つか、異常値の有無やその理由を浮き彫りにするためか。慣例が持つ目的や意図を"自分の頭で考え"て作業してみてねと優しく促す。
予算や事業報告など、内外に示す資料の説明を受ける際、その書式の作成目的を担当に問うと「例年同様なので」と答える場合がある。事案に関して何を訊かれてどう答えるのに役立つか、異常値の有無やその理由を浮き彫りにするためか。慣例が持つ目的や意図を"自分の頭で考え"て作業してみてねと優しく促す。
☆検討過程を見える化する
意思決定に向け説明を受けながら見る資料は、課題から対応案が淀みなく論述されていて、今時の若手職員の優秀さを感じるが、論理が一直線iに過ぎることも度々。多くの行政課題は答えが一つでない中で判断を迫られる。代替案と各々の長短など検討過程を"見える化"して凡人上司の私に教えて欲しいのだ。
意思決定に向け説明を受けながら見る資料は、課題から対応案が淀みなく論述されていて、今時の若手職員の優秀さを感じるが、論理が一直線iに過ぎることも度々。多くの行政課題は答えが一つでない中で判断を迫られる。代替案と各々の長短など検討過程を"見える化"して凡人上司の私に教えて欲しいのだ。
☆網羅性と一覧性
社会経済と同様に行政課題も複雑化していて、何かの判断には余波とか影響を多面多角的に考えなくてはならない。事案にもよるが、事業推進等の検討に関しては"網羅性と一覧性"をキーワードに部下に資料作成をお願いしている。取組作用の関係性全体を俯瞰して見るとコストとリスクが遍く浮き彫りとなる。
社会経済と同様に行政課題も複雑化していて、何かの判断には余波とか影響を多面多角的に考えなくてはならない。事案にもよるが、事業推進等の検討に関しては"網羅性と一覧性"をキーワードに部下に資料作成をお願いしている。取組作用の関係性全体を俯瞰して見るとコストとリスクが遍く浮き彫りとなる。
☆資料説明は初見者の立場で
部局長や知事へと伺いを上げていくほど、相手は事案との馴染みが薄い上に、説明に使える時間は短くなるので、資料の調製と説明は究極のエキス絞り込みが求められる。記載事項は最小にして、資料はなぞるのでなく端折って視線で追わせ、混乱させないよう記載のない言葉を極力使わない等のスキルが必要。
部局長や知事へと伺いを上げていくほど、相手は事案との馴染みが薄い上に、説明に使える時間は短くなるので、資料の調製と説明は究極のエキス絞り込みが求められる。記載事項は最小にして、資料はなぞるのでなく端折って視線で追わせ、混乱させないよう記載のない言葉を極力使わない等のスキルが必要。
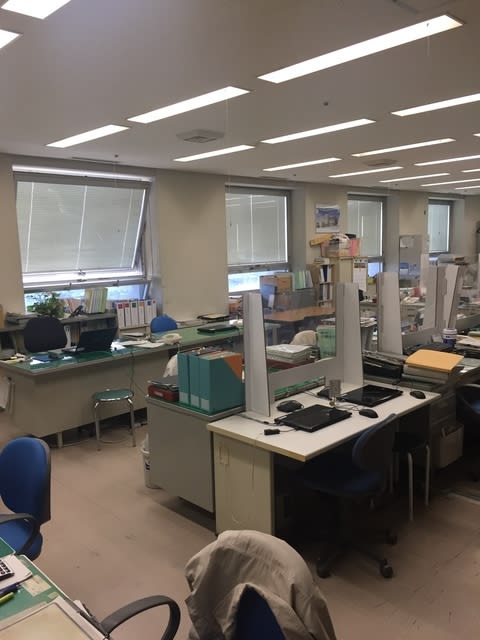

☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea

















