京都駅のバスターミナルを経由し、七条通りを東へ。
堀川通りを右折して堀川七条のバス停で下車。
北の方に西本願寺が見えています。
西本願寺の堀川通りを隔てた向かい側に龍谷ミュージアム。
いつもなら京都駅の一つ手前のバス停 烏丸七条で下車して徒歩で向かうのですが、
バスが満員で降りることができなかったんですよね。
京都駅で数人を残して乗客は降り、また大勢の人が乗り込んできました。
慌てて最前列に移動です。
龍谷ミュージアムのチケット売り場は地下で、
会場は3階、2階、ちょっと変わっています。
ミュージアムの入り口。


地下に降りたところに

入場券。

ちらし


あらゆる生命の根源“水”。地域や時代を超えて、人々は水を敬い、畏れ、そして様々な願いを捧げてきました。とりわけ、四方が海に囲まれ、かつ水源が豊かな日本では、仏教や神道の思想・儀礼が深く関わり合い、水にまつわる多くのほとけや神が信仰されました。たとえば竹生島(滋賀県)や江島(神奈川県)など「水の聖地」の女神とされる『弁才天』や海運の神『住吉明神』、雨乞い祈祷の本尊となった『龍王』などはその好例といえるでしょう。また近世においては、国内各地の水辺の名所を描いた華麗な屛風絵が人々の目を楽しませました。
本特別展では、水に込められた願いや祈りを表した絵画・彫刻・典籍などの名品を通して、日本人が育んできた豊かな水の精神性を紹介します。浄らかな水が生んだ神秘のかたち―その造形美を心ゆくまでお楽しみください。 (ちらしより)
きっと弁財天なんかがメインとなるんだろう、とおもっていたら、もちろんそれもそうなのですが、様々な水がかかわるものが展示されています。
長谷寺の十一面観音も水にかかわりが深いんだ。
例のごとく図録は購入せず、絵葉書を。
MIHO MUSEUM所蔵の弁財天座像。
MIHO MUSEUMはたくさんええもんを所蔵していますねぇ。

大阪本山寺所蔵の宇賀神像。顔が人、体が蛇という異形の神像。5/5までの展示です。

一方、顔が蛇で体が人間という、石山寺所蔵の天川弁財天曼荼羅。


奈良国立博物館所蔵の春日龍玉箱。


サントリー美術館所蔵の丸山応挙筆青楓瀑布図。

大阪金剛寺所蔵の月日山水図屏風。
前期展示ということでたのしみにしていたら、4/27までの展示でした・・・


これらの絵葉書を入れてくれた封筒のロゴ。

さて、多くの展示を観て、小腹が空きました。
朝食、食パン1枚にコーヒー、目玉焼き卵1個、野菜ジュースを朝6時に食べたきり。
たしかこの辺にたぬきうどんを出している店があったはず・・・
大阪でたぬき、といえば、油揚げの乗ったきつねそば。(なのでたぬきうどんはありません。)
関東でたぬき、といえば、天かすの乗ったおうどん。
で、京都にはたぬきうどんがあって、きつねにあんがかかったのがたぬきうどん。
堀川七条を東に入ったところにある「大阪屋」さんでたぬきうどんを昼食にいただきました。
細めのおうどんに細切りの油揚げと九条ネギ、そしてあんがかかっていて、
おろししょうががトッピング。



さて、この後東寺(教王護国寺)にでも行ってみよう。
そう思って店内に貼られていたバス路線図を眺めていると、
店の女性店員さんが
「どこに行きはるん?東寺やったら歩いて10分ほどやから、歩いた方が早いですよ」
と言って、行き方をおしえていただけました。
では歩いて東寺へ向かいます。













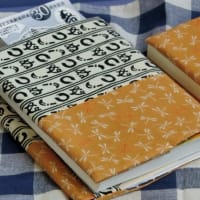






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます