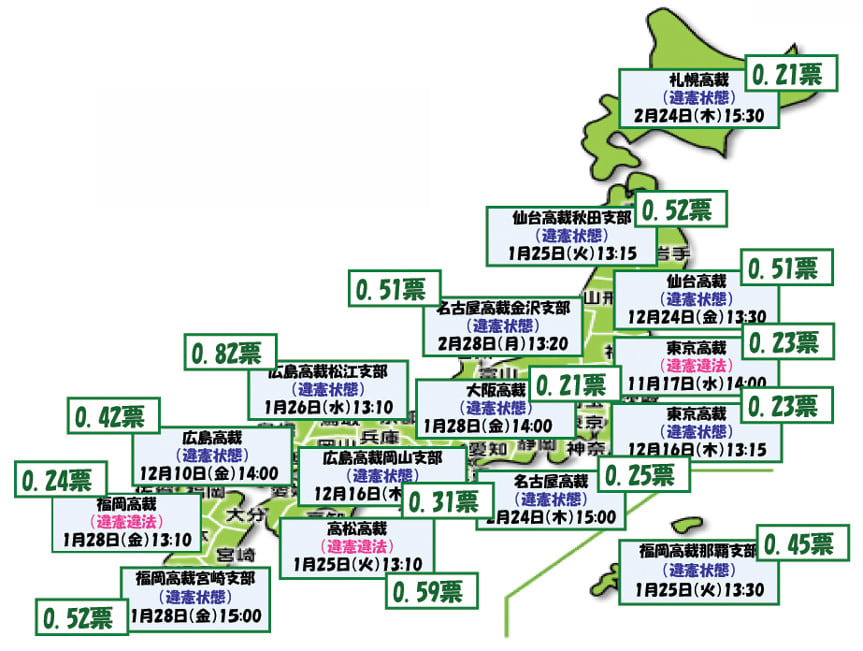
去る7月28日、最高裁の判決で「違憲状態」とされた参議院議員選挙における1票の格差を是正することを目的に、衆議院本会議において選挙区の定数を「10増10減」する改正公職選挙法案が(自民党、維新の党、次世代の党などの賛成多数により)可決、成立しました。
改正案は自民、維新、元気、次世代、新党改革の5党により共同提出されたものですが、今回「合区」となる選挙区は自民党議員の地盤であることもあって、党内には当初から根強い反対意見があったようです。また、民主党や公明党、生活の党は、改正後も約3倍の格差が残る今回の自民党案に強く反発、独自に「12増12減」案を提出していたこともあって、「1票の格差」の問題を巡ってはこれからも国会を中心に様々な議論が続いていくことでしょう。
さて、こうした選挙制度に係る「公平感」については、見る視点によって人それぞれに意外なほど感覚の違いというものがあるようです。7月31日の総合経済サイト「ダイヤモンド・オンライン」では、経営コンサルタントで情報誌その他に政治係コラムなどの連載を持つ松井雅博(まつい・まさひろ)氏が、一票の価値の「格差」を議論する前に私達にはまだ考えるべきことがあるのではないかとする興味深い論評(「民意なんてそっちのけ?参議院10増10減に隠された政治家の思惑」)を掲載しています。
松井氏はこの論評で、「一票の格差」という単純な数字に翻弄される前に、現状ではその「格差」とされる数字にどれほどの意味があるかについて考えてみる必要があるのではないかと、読者に向けて問いかけています。
国政選挙でさえもはや半数の有権者が選挙に行かないような状況を、まずはどう認識すべきなのか。しかも「10増10減」とは、すなわち議員定数はそのままにしておくということ。冷静に考えてみれば、本会議中に居眠りしている議員や不祥事を起こしたりしている議員、政党名だけで当選している一部の議員をどのように評価し選別するかという問題のほうが、有権者にとってよほど重要なのではないかという指摘です。
実際、国政選挙のような大型の選挙では、有権者が候補者個人を評価することは極めて難しくなります。氏は、そうした選挙では有権者の多くが「政党名」を頼りに候補者を選んでいるのが現実であり、議員個人を(自分達の代表としてふさわしいかどうか)評価し判断する手段として「選挙」は既に機能しなくなっているのではないかとの懸念を示しています。
このような状況の中で政治(家)の質を保つためには、まず優秀な候補者をいかに発掘しいかにして育て評価するかが最も重要になる。実態として機能していない議員を選別し、新陳代謝により国政を活性化させることが(選挙という仕組みには)求められているという指摘です。
松井氏は、それを困難にしている原因のひとつとして、現在行われている政党による候補者の選定過程の不透明さを挙げています。
政党はそれぞれの公認補者の適性や能力について、一定の評価基準の下に有権者に示していく責任を負っている。しかし少なくとも現在、候補者が政党の中で評価され公認されていくプロセスの多くはブラックボックス化されており、能力以外の要素が大きく影響するアンフェアなものとなっていると松井氏はこの論評で述べています。
分立する「三権」の中で、行政府の職員は公務員試験、司法府の職員は司法試験によりそれぞれ必要とされる基礎的な知識や思考力を確認され、その上で任についていることは言うまでもありません。それでは、憲法上国権の最高機関として位置づけられている立法府を担う国会議員の能力は、何をもってどのように確認されるべきなのか。
松井氏は、選挙に当たって(第三者機関を設けてでも)彼らの仕事ぶりを厳しく評価する仕組みを作ることが、政治の活性化に最も求められていると考えています。具体的にどのような政治活動を行ったのか、公約が守られたのかどうか、政治資金をどのように調達したのかといった様々な情報が、一定の公平性の下で詳らかにされる必要があるということです。
間接民主主義の下では、有権者は議員を「選ぶ」ことしかできない。それが唯一にして最大の国民の権利であるとすれば、「一票の格差」という法律論議だけでは不十分だと松井氏はこの論評を結んでいます。
ガバナンスの在り方の議論や区割りも含めた選挙制度の検討は確かに大切なものだと思います。しかし、具体的な数字を持ち出す前に、より本質的な議論として、私達の持つ「一票」をより価値のあるものにしていくためにはまず候補者の質を上げるための仕組みが必要ではないかとする松井氏の主張を、選挙制度改革に当たっての基本的な論点の一つとして、今回私も興味深く読んだとことです。
.





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます