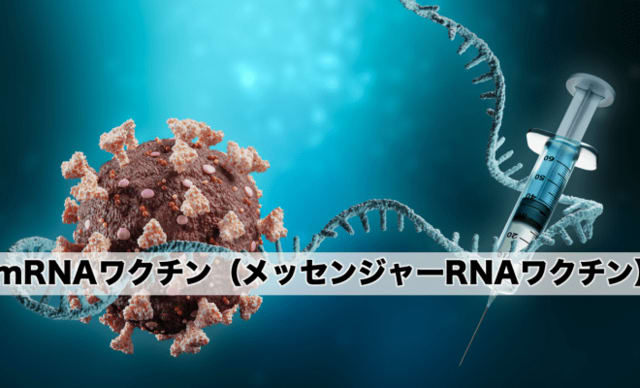8月後半の実施が取りざたされている福島第一原発にかかる処理水の海洋放出を前に、東アジアの周辺諸国を巻き込んだ様々な議論が広がっています。
中国・香港では、税関当局が日本から輸入した水産物に対する放射線の検査を全面的に始め日本からの鮮魚などの輸出が実質的に滞っているほか、韓国においても各メディアでは依然強い反対の声が上がり続けています。
一方、松野博一官房長官は「政府としては引き続きIAEAの包括報告書の結論を踏まえ、高い透明性を持って国際社会に丁寧に説明していく考えだ。日本産食品の安全性は科学的に証明されており、輸入規制を早期に撤廃するよう今後もあらゆる機会を通じて中国側に強く働きかけていく」と話しており、日本政府としてはIAEAの報告書を一種の「お墨付き」として一気に放出開始に踏み切る構えと見受けられます。
貯められた処理水に関しては、量の面でも放射線の面でも(まさに)大海の一滴に過ぎない。この極めて低レベルの放射性同位体が健康に悪影響を及ぼす可能性は限りなく低いという指摘は、(日本政府にとっては)たしかに科学的なエビデンスに基づくものなのかもしれません。
しかし、だからといって、長期にわたる海洋放出が海底や海洋生物にどんな影響が及ぶのかについてはわからないことも多いのが実態であり、ましてや当事者である東電が2011年の事故を(「想定外の事態」として)防げなかったことを考えれば、「俺を信じろ」と言われても「はい、そうですか」とはいかない気持ちも理解できます。
そんな折、7月28日の総合情報サイト「BUSINESS INSIDER JAPAN」にジャーナリストの岡田充(おかだ・たかし)氏が、『IAEA報告書は「処理水の海洋放出」を承認していない。中国を「非科学的」と切り捨てる日本の傲慢』と題する論考を寄せていたので、参考までにその概要を小欄に残しておきたいと思います。
処理水の海洋放出に対しては、全国漁業協同組合連合会や地元・福島の漁業協同組合をはじめ多くの市民団体が強く反対してきた。さらに、IAEAの調査報告書公表を受け、中国や太平洋島しょ国からも反対の声が上がり、外交問題に発展していると岡田氏はこの論考に記しています。
中国の主張は、簡単に言ってしまえば
① これまで事故で溶けた炉心に接触した汚染水が放出された例はない
② 溶け落ちた炉心と直接接触した汚染水には60種類以上の放射性核種が含まれる可能性がある
③ 日本はただちに海洋放出計画を中止し、国際社会と真剣に協議し、科学的、安全、透明で、各国に認められる処理方式を共同で検討すべき
(↑ 呉江浩・駐日大使と駐日大使館報道官による7月4日の記者会見)というもの。こうした主張を踏まえ、中国税関当局が日本の水産物に対する放射性物質の検査を7月から厳格化したことで、放出問題は日中間の外交問題へと発展したということです。
このような中国政府の対応について、日本のメディアは「中国政府は処理水問題を(政治的に)利用している」といった社説を掲載し、「処理水問題が科学的議論を離れ外交カードと化している」といった政府関係者の見解を紹介し対中非難を煽っている。しかし、(改めて周囲を見渡せば)放出に反対しているのは中国だけではないというのがこの論考で岡田氏の見解です。
オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニアなどの太平洋島しょ国が加盟する「太平洋諸島フォーラム(PIF)」は、IAEAが報告書を公表する直前の6月26日、プナ事務局長が海洋放出に反対する態度を明らかにしていると氏は言います。
その主張は、「海洋投棄は太平洋島しょ国にとって、大きな影響と長期的な憂慮をもたらす」というもの。そのうえで、「代替案を含む新たなアプローチが必要であり、責任ある前進の道である」と話しているということです。
こうした状況を踏まえ、岡田氏はこの論考で「そもそも、今回のIAEAによる調査報告書を、海洋放出の安全性や正当性を保証するものとみなしていいのか?」との疑問を呈しています。
最も注意しなければならないのは、報告書では「処理水の放出は日本政府が決定することであり、その方針を推奨するものでも承認するものでもない」と明記されていること。政治的判断として海洋放出を行うべきかどうかについて、報告書は一切判断していないというのが氏の認識です。
来日したIAEAのグロッシ事務局長はNHKとのインタビュー(7月7日)に答え、日本政府の要請はあくまで海洋放出に当たっての「基本方針の評価」だと話している。従って報告書は、「政治的にいいか悪いかを決めたわけではなく、(あくまで)放出に対する日本の取り組みそのものを調査したもの」だということです。
一方、政府与党自民党の茂木敏充幹事長は7月25日の記者会見で、海洋放出を批判する中国について、「科学的根拠に基づいた議論を行うよう強く求めたい。中国で放出されている処理水の濃度はさらに高い」と反論した。しかしこの茂木氏の態度は、溶け落ちた原発の炉心に直接接触した汚染水を処理した水を史上初めて海洋に放出するという事実を無視し、(単純に)放射性物質の含まれる「濃度」の問題にすり替えているようにも見えると、岡田氏はここで指摘しています。
市民団体からは、「タンク貯蔵されている水の7割近くには、トリチウム以外の放射性核種が全体としての排出濃度基準を上回って残存している」との指摘もある。放水前に処理するにせよ、指摘に対する確認や追加の調査もないまま中国の主張を「非科学的」と決めつける姿は、傲慢で非科学的との誹りを免れないというのが氏の見解です。
実際、日本原子力文化財団が発行した「原子力総合パンフレット2022年度版」には、「事故から2年後頃までは、ALPSの設備導入を検討している段階であったため、セシウム以外の放射性物質が除去できていない高濃度汚染水があり、その時期はタンクに貯蔵する際の放射性物質の濃度の基準を下回ることを優先していたため、環境へ処分するための基準を満たしていない処理途上水もタンクに貯蔵されています」と記されていると氏は言います。そして「これらは、処分するための基準が満たされるまで浄化処理されますが、その間タンクに貯蔵されています(保管中の水の約7割)」と説明されているということです。
(改めて言うが)IAEAの報告書には、海洋放出以外の選択肢については一切触れられていないし、(中国も指摘するように)東京電力と日本政府が海洋放出以外の選択肢を考慮した形跡も見当たらないと、氏はこの論考の最後に記しています。
一方で、専門家からは「大型堅牢タンクでの保管」や「モルタル固化」などの代替案も提示されている。指摘によれば、もしも海洋放出を選択した場合、放出を開始してからも増え続ける汚染水と放射性物質の総量がどこまで膨れ上がるのか、環境への負荷が未知数であることも大きな問題として残されているということです。
蓄蔵されていく処理水が廃炉作業の大きな障害となっていること、なにより10年前の原発事故の象徴となっている処理水タンクをなんとかしたいという関係者の思いは理解できますが、海洋放出という思い切った対応に丁寧な説明が必要なのは当然のこと。
いわゆる「戦狼外交」をくりかえす昨今の中国の動きを腹立たしく感じる向きも多いでしょうが、こちらの事情ばかりを強引に主張し続けても問題が解決するようには思えません。そうした折、8月にも開始されるという海洋放出はいったん中止し、代替案を含め再検討すべきだろうと提案するこの論考における岡田氏の指摘を、私も興味深く読んだところです。