<第2章> 4学年1学期の<90日闘争>
〔第10回〕 何を求め何と闘ったのか
都立日比谷高校は、1960年代に関西の私立灘高校と並んで東大への進学率トップを争うエリート校として知られていました。灘高校は早期に高校過程を終えて受験に備え校則も厳しいものがありましたが、それに比べ日比谷高校では教養主義的な教育が行われ、大学受験は生徒に任せる風潮がありました。
しかし、高校入試で学校間の格差をなくすため1967年に「学校群制度」が導入されたことで日比谷高校をはじめ戸山や新宿、小石川、両国、上野高校などの名門都立高校の東京大学を始めとする難関大学への進学実績が低下し、とりわけ日比谷では極端な落ち込みがみられています。一方で名門都立高校と同じ学校群を構成した青山や富士、国立(くにたち)高校などの進学実績は急速に上昇しているのですが、制度導入以降、都立高校全体の難関大学進学実績は長期低落に向かっていました。
■学校群制度導入による功罪
「学校群制度」とは入試実施方法のひとつで、高校入試で学校群内各校の「学力格差を無くし均質化を実現」したことでは成果をあげました。しかし、学区内の学校群間で入試難易度の格差が新たに発生し、受験生の選択の自由は大きく制約され否定的な評価が多くなったことで、同制度は2004年までにすべて廃止されています。
制度導入の背景として受験戦争の過熱があって、制度内容からして「日比谷潰し」ではないかといわれていました。60年代に入り高度経済成長を反映して高度な知識を求めて大学進学熱は一気に加速したのですが、一方で企業就職に有利とされる「大卒」肩書を乱発する大学のマスプロ化も進行しています。すると、高校における「大学受験予備校化」といった現象が現れてきます。それだけに「学力格差を無くし均質化を実現」が諮られ進学率トップをいく日比谷高校が標的になったというべきでしょうか。
しかし制度導入は、受験生の意思による単独での学校選択が出来なくなり学区外からの越境入学が難しくなりました。また受験出来る者が限られたこともあって志願者層に変化が起こります。そのことで国立や私立高校、さらに私立中学へと受験生が流出し都立高校の進学実績が全般的に低下することになったのです。難関学校群を受験した高学力の不合格者は、いわゆる「滑り止め」などの私立高校へ流出することとなりました。
高校入試における学校群制度が全国的に広がり、制度導入から20余年を経た1990年代に入ると都市部の公立進学校の一部で大学進学実績面での凋落が顕著となっています。それは小学区制度導入で伝統的な公立高校への入学者層が狭い地域に限定され、成績優秀な生徒が集まらなくなったわけです。一方で、公立高校は「自由放任で受験向けの教育に力を入れなくなった」との評価が定着し、「公立高校の人気が下落した」との見方があります。結果的に、その背景として60年代後半から70年にかけての<高校紛争>を理由とする学校関係者は少なくありません。<紛争>では「受験制度反対」を訴えていたのですからね――。
■高校生<叛乱>の背景
1969年春の段階で全国的に広がった「卒業式闘争」に伴う混乱は、マスメディアで大きく報道されました。この闘いは本格的に始まる<高校紛争>の序章に過ぎませんでした。
新書版『高校紛争』(小林哲夫著)によると、「全国の高校で紛争が最も盛んだったのは1969年9月から70年3月までの約半年間」と指摘しています。この期間、新聞が「バリケード封鎖」をはじめ「校内集会やデモ」「授業や試験のボイコット」や、「始業式・終業式妨害、卒業式妨害」などの見出しで報道されたのが、全国35都道府県で計176校208件だったとか。

●<高校紛争>で生徒が求めた「要求項目」をテーマ別にみると次のようになります。
【1】生活指導、校則=生徒心得改訂・撤廃▽制服・制帽自由化▽登下校時の外出禁止反対▽集会・結社の自由▽表現の自由、刊行物の検閲廃止▽男女交際の自由など 【2】教育制度=エリート教育反対▽定期試験廃止▽受験教育につながる学力試験・模擬試験廃止▽通知表廃止、通知表の成績評価廃止▽コース別編成廃止▽教科書粉砕▽授業批判の自由を認めよ▽自主講座の設定▽生徒会解体▽産業のための教育反対など
【3】学校運営・政策=学校運営への参加▽職員会議の公開、生徒出席▽生徒指導部解体▽クラブ顧問制の廃止▽運動会や文化祭の自主管理▽PTA解体▽学校の経理公開▽学費値上げ反対▽各種式典反対など 【4】政治課題=ベトナム戦争反対▽沖縄奪還▽米軍基地撤去▽自衛隊反対▽三里塚(成田)空港建設反対▽紀元節復活反対▽文部省手引書、教育委員会通達による「高校生の政治活動禁止」粉砕など
高校生が学内をはじめ街頭へ向けて闘争を主体的に担っていった背景には、受験戦争へ追いやられる教育体制もさることながら、60年代半ばからのベトナム戦争に対する反戦運動が大きいといえましょう。1967年に学生・労働者が佐藤首相の南ベトナム訪問を実力で阻止しようとした<10・8羽田闘争>を皮切りに、翌68年1月には米海軍原子力空母エンタープライズが長崎県佐世保に寄港することを阻止する<佐世保闘争>、また3月には東京都北区の米陸軍王子キャンプに野戦病院が設置されたことに対する反対運動<王子闘争>が果敢に闘われています。
この羽田、佐世保、王子と<3つの大闘争>には高校生も積極的に多数参加し数名が逮捕者されていますが、この段階では高校生独自の組織はあったもののデモ隊列は学生や労働者と一緒に行動するか、デモの最後尾にくっついて行動していました。やがて新左翼党派(セクト)系の高校生組織が独自の集会やデモを行うようになっていきます。例えば革共同中核派系「反戦高協」、社学同(ブント)系「社学同高委」、ML派(日本マルクス・レーニン主義者同盟)系「高校生解放戦線」、フロント(構造改革派)系「高反協」など新左翼各セクトの存在、影響に大きいものがありました。
■エリート校の闘争
「学校群制度」が導入されて2年が経過した段階で、日比谷高校での<叛乱>が本格化しています。同校では全学闘争連合(全闘連)を結成。69年3月の卒業式の警官導入の自己批判、文部省手引書の拒否などを訴えて同年10月8日に校内の同窓会館(如蘭会館)を封鎖しています。一時、教師によって封鎖を解除しましたが、再封鎖。同月28日に機動隊を導入し立て籠もっていた全闘連を排除、抵抗した生徒2名を逮捕しました。
これを契機に学校側は校門周辺を鉄板で囲み、無許可の集会や掲示、ビラ配布等を一切禁止するなど生徒に対する管理を強化しています。これに対し生徒側は11月に入って400名規模の集会を2度にわたって開催し学校に抗議集会とデモを行っていますが、学校側は管理を強化するだけで全闘連が突きつけた問題提起に何ら答えようとしていません。
熊本県には県立熊本高校(熊高)と同熊本工業高校(熊工)があるのですが、両校ともに略称を「くまこう」と呼ぶことを避けるため「熊高」を、あえて「くまたか」と呼び、「熊工」(くまこう)と区別しています。熊本高校(熊高)は県内でもトップ校として知られており、「くまたか」はエリート校の呼称ともいえます。
そのエリート校・県立熊本高校(熊高=くまたか)では、高校が政治活動を禁止した「生徒の政治活動に関する指導方針」に対し生徒側が70年1月に配ったビラには次のような内容が書かれていました。「我々は県高校教育界のシンボル的存在である熊本高校において、この指導方針が出されたことに注目しなければならない。…熊本のすべての闘う高校生諸君! 熊高における指導粉砕の闘いを再結集せよ!」と。
ここで熊本高校を「(熊本)県高校教育界のシンボル的存在」とみなしていることが面白いですね。「…熊本高校において、この指導方針が出されたことに注目しなければならない」と続くのですが、ここには熊本高校が県下のトップ校としての認識があるからです。つまり、トップ校が政治活動禁止となれば「県下の高校に大きな影響を与えるから、ここで食い止めよう」という考えで、この発想に「エリート意識」がみえるわけです。
全国的に拡大した<高校紛争>ですが、その中心となったのは一般的に「進学校」といわれた一流高校で紛争が活発でした。県立多摩高校(神奈川)では「定期試験、制服廃止」を訴えて校舎を封鎖する闘争が行われたのですが、後年、同校教師が当時を振り返って「当時、生徒のなかには紛争をやらぬ高校は一流じゃないという考え方があった。多摩高も一流になろうとしたんだ」と同校の記念誌に記述しています。なんとなく自己顕示のための<闘争>を構えた感じもするのですが。
■「大学受験予備校化」への疑問
高校で紛争が激化するなかで「受験特化型」の教育の在り方が問われています。大阪府立東淀橋高校では「能力別クラス編成が、生徒への差別を助長する教育だ」ということで学校を封鎖、「能力別クラス編成撤廃」を求めていたのですが、同校では撤廃を認めています。
東淀橋高校は当時としては新しく創設された学校で、府内の伝統校に追いつくために進学実績を高めることを目標に「能力別クラス」が設けられたようですが、国は「理数系クラス」を人材養成の方策として奨励したところがあります。68年に全国16都道府県の進学校29校で理数系コースが設置されていますが、府立東淀橋高校のように「理数系コース」はエリート養成として批判されています。
また、高校の教育体制を批判していくなかで「大学受験予備校化」が追及されています。学期中に行われる定期試験は、本来、授業で教えられた中身を生徒がどの程度、修得したかを図ることが試験の目的です。でも試験結果が全人格的な評価につながっているとの批判が行われていました。「授業の中身、試験の問題はそのまま大学入試の出題内容につながってくる」ことが問題視されていました。そこには「高校は大学受験予備校ではない。受験対策的な試験、そして授業は改めるべき」との主張があります。
「大学受験予備校化」については、高校で紛争が起きる以前から「暗記型の授業」と生徒から疑問が出ており、自分たちが関心をもつテーマを学ぶ機会をもちたいとの要望は多かったようです。
■<高校紛争>の根源的な問いかけ
それぞれの高校が抱える事情や地域性が<紛争>の背景に大きく関わっているわけで、この<高校紛争>を通じて「高校とは何のためにあるのか」といった根源的な問いかけが生徒をはじめ教師、保護者、文部省(当時)、教育委員会など多方面から論議されたのですが、このような課題を真正面から取組むことは、これまで皆無であったことを考えると教育行政そのものを問いただす最良の機会だったと思います。
しかし、現実には学校はバリケード封鎖した生徒や、街頭で機動隊と衝突して逮捕された生徒に対して退学や停学など厳しい処分を行っています。また、<高校紛争>を担っていた生徒に対して学校および警察は彼らが未成年であることから、単に「非行少年」扱いしていたことです。政治的課題をもって活動しても「非行少年」の枠組みで少年鑑別所へ送致されるケースが多かったようです。
都立小石川高校の元教師は後年、次のように語っています。「…教師は活動家を非行少年と同じように扱い、生徒指導として接していました。しかし、思想をもって行動している活動家は非行と思っておらず、何の効き目もなかった」と(『高校紛争』260頁)。
高校生による運動(紛争)は、大学生における学生運動とは根本的なところで異なっているわけで、高校生運動は校則や教育制度に対する「改革運動」の側面が強いといえましょう。学生運動は1967~68年にかけての初期段階では教養教育やエリート教育、マスプロ教育、産学協同路線に対する批判や大学教育の在り方を課題としていましたが、60年代末の69年から70年以降は「安保と沖縄」をテーマとした政治闘争が中心課題となっています。また、そこには大学生の「闘争に対する自己の内面性」、つまり「自分の存在」(例えば「自己否定」)などを問いかける<闘い>でもあったのです。
高校紛争の過程で停学や退学処分を受けた生徒も数多く現れていますが、高校生は「学校を辞めたら中卒扱い」となり社会的に厳しい現実が待っています。この「高校中退者」というのは、代々木高校を中退していった学友が後年、「高校中退というのは大学中退と違って、実際には中卒扱いだよ」と語っていたことが思い出されます。
■定時制高校生は何と闘っていたのか。
さてさて。ここまで本書『高校紛争』をびら~んと読み込んでみますと、我が代々木高校には学校群制度はないしぃ~男女交際は自由だしぃ~別にエリート教育なんて行われていなかったしぃ~ましてや「受験教育につながる学力試験・模擬試験」なんてなかったよなぁ…え?実際には色々あったの? わたしゃ知らんかったわぁ~!
――と、まぁ<ズル休モード>で定時制高校に通っていた身にとって、この世の一般的な高校生の生活とは隔世の感がありますねぇ。そうなんだ。キミ達、全日制の高校生諸君は勉強漬けのうえ学校から強制的な管理に絡めとられ大変だったよねぇ~。 むふ。同情しちゃう。
でもね。本書を読み進むうちに代々木高校に在籍し少なからず定時制高校の様々な課題、とりわけ「労働と学業」を両立せざるを得ない生徒<若年労働者>の現実を追及していた経験からしますと、本書を手にした当初から感じていた<違和感>の実態が、おぼろげながら具体性を帯びた輪郭となって現れてきたということでしょうか。
ひとつは、私が1学年2学期末に手にした冊子の付録『高校生日記』に掲載されていた同世代高校生の写真を見て、「同じ高校生なのに、この格差は何だ」といった単純な疑問ですね。本書を読むと私が当時考えていた「同じ高校生なのに」というのは明らかに私の思い違いで、必ずしも「同じ高校生ではなかった」ということです。
それは、「もてる者と、もたざる者」の違いということです。「同じ高校生」と思っていた彼らと私たち定時制高校生の間で誰が「もっていた」のか、何を「もっていなかった」のか。それは経済的側面(お金)なのかも知れませんが、本質的には<時間所有の有無>なのです。
本書『高校紛争』に登場する高校生は全日制の生徒たちです。彼らは学校運営や教育制度、政治課題(安保・反戦)等に対し異議を唱え<叛乱>を起こしたのですが、68年から70年にかけて彼らと皮膚感覚で「激動期に同じ<時代>を共有」した私(若しくは私たち)にとって、当時の情況において<叛乱>に「連帯」はするけれど、「共闘」までにはいかなかったと思います。
彼ら高校生と、私のなかの<高校生>とは異次元のものだったということですね。それは、彼ら<叛乱>高校生たちは「時間をもっていた」たっぷりと。「24時間」これすべて<闘争>を日常化できたわけです。バリスト封鎖の学内で、また近くの喫茶店や生徒の自宅などで自由な「時間」を費やして論争を闘わすことができたのです。なんら制約されることなく。
それに対し私たち定時制高校生は、日常管理されている<労働>の合間をぬって学校に通い「学ぶ」という両面性をもつ<勤労学生>の立場にあったわけです。一日7~8時間働いた後、高校へ通い授業の合間に学内問題(生徒心得・PTA問題)や政治課題(安保・反戦)に関する討議を行い、行動を起こしました。
すなわち私たち定時制高校生が社会に対し異議を唱え<闘争>を構えるとなると、その<闘争>の対象は学校であり社会であるとともに「最大の敵」は、他ならぬ『高校紛争』に登場する高校生たちがたっぷり持っていた時間。その<時間>だったわけですね。 (⇒この項つづく)
〔第10回〕 何を求め何と闘ったのか
都立日比谷高校は、1960年代に関西の私立灘高校と並んで東大への進学率トップを争うエリート校として知られていました。灘高校は早期に高校過程を終えて受験に備え校則も厳しいものがありましたが、それに比べ日比谷高校では教養主義的な教育が行われ、大学受験は生徒に任せる風潮がありました。
しかし、高校入試で学校間の格差をなくすため1967年に「学校群制度」が導入されたことで日比谷高校をはじめ戸山や新宿、小石川、両国、上野高校などの名門都立高校の東京大学を始めとする難関大学への進学実績が低下し、とりわけ日比谷では極端な落ち込みがみられています。一方で名門都立高校と同じ学校群を構成した青山や富士、国立(くにたち)高校などの進学実績は急速に上昇しているのですが、制度導入以降、都立高校全体の難関大学進学実績は長期低落に向かっていました。
■学校群制度導入による功罪
「学校群制度」とは入試実施方法のひとつで、高校入試で学校群内各校の「学力格差を無くし均質化を実現」したことでは成果をあげました。しかし、学区内の学校群間で入試難易度の格差が新たに発生し、受験生の選択の自由は大きく制約され否定的な評価が多くなったことで、同制度は2004年までにすべて廃止されています。
制度導入の背景として受験戦争の過熱があって、制度内容からして「日比谷潰し」ではないかといわれていました。60年代に入り高度経済成長を反映して高度な知識を求めて大学進学熱は一気に加速したのですが、一方で企業就職に有利とされる「大卒」肩書を乱発する大学のマスプロ化も進行しています。すると、高校における「大学受験予備校化」といった現象が現れてきます。それだけに「学力格差を無くし均質化を実現」が諮られ進学率トップをいく日比谷高校が標的になったというべきでしょうか。
しかし制度導入は、受験生の意思による単独での学校選択が出来なくなり学区外からの越境入学が難しくなりました。また受験出来る者が限られたこともあって志願者層に変化が起こります。そのことで国立や私立高校、さらに私立中学へと受験生が流出し都立高校の進学実績が全般的に低下することになったのです。難関学校群を受験した高学力の不合格者は、いわゆる「滑り止め」などの私立高校へ流出することとなりました。
高校入試における学校群制度が全国的に広がり、制度導入から20余年を経た1990年代に入ると都市部の公立進学校の一部で大学進学実績面での凋落が顕著となっています。それは小学区制度導入で伝統的な公立高校への入学者層が狭い地域に限定され、成績優秀な生徒が集まらなくなったわけです。一方で、公立高校は「自由放任で受験向けの教育に力を入れなくなった」との評価が定着し、「公立高校の人気が下落した」との見方があります。結果的に、その背景として60年代後半から70年にかけての<高校紛争>を理由とする学校関係者は少なくありません。<紛争>では「受験制度反対」を訴えていたのですからね――。
■高校生<叛乱>の背景
1969年春の段階で全国的に広がった「卒業式闘争」に伴う混乱は、マスメディアで大きく報道されました。この闘いは本格的に始まる<高校紛争>の序章に過ぎませんでした。
新書版『高校紛争』(小林哲夫著)によると、「全国の高校で紛争が最も盛んだったのは1969年9月から70年3月までの約半年間」と指摘しています。この期間、新聞が「バリケード封鎖」をはじめ「校内集会やデモ」「授業や試験のボイコット」や、「始業式・終業式妨害、卒業式妨害」などの見出しで報道されたのが、全国35都道府県で計176校208件だったとか。

●<高校紛争>で生徒が求めた「要求項目」をテーマ別にみると次のようになります。
【1】生活指導、校則=生徒心得改訂・撤廃▽制服・制帽自由化▽登下校時の外出禁止反対▽集会・結社の自由▽表現の自由、刊行物の検閲廃止▽男女交際の自由など 【2】教育制度=エリート教育反対▽定期試験廃止▽受験教育につながる学力試験・模擬試験廃止▽通知表廃止、通知表の成績評価廃止▽コース別編成廃止▽教科書粉砕▽授業批判の自由を認めよ▽自主講座の設定▽生徒会解体▽産業のための教育反対など
【3】学校運営・政策=学校運営への参加▽職員会議の公開、生徒出席▽生徒指導部解体▽クラブ顧問制の廃止▽運動会や文化祭の自主管理▽PTA解体▽学校の経理公開▽学費値上げ反対▽各種式典反対など 【4】政治課題=ベトナム戦争反対▽沖縄奪還▽米軍基地撤去▽自衛隊反対▽三里塚(成田)空港建設反対▽紀元節復活反対▽文部省手引書、教育委員会通達による「高校生の政治活動禁止」粉砕など
高校生が学内をはじめ街頭へ向けて闘争を主体的に担っていった背景には、受験戦争へ追いやられる教育体制もさることながら、60年代半ばからのベトナム戦争に対する反戦運動が大きいといえましょう。1967年に学生・労働者が佐藤首相の南ベトナム訪問を実力で阻止しようとした<10・8羽田闘争>を皮切りに、翌68年1月には米海軍原子力空母エンタープライズが長崎県佐世保に寄港することを阻止する<佐世保闘争>、また3月には東京都北区の米陸軍王子キャンプに野戦病院が設置されたことに対する反対運動<王子闘争>が果敢に闘われています。
この羽田、佐世保、王子と<3つの大闘争>には高校生も積極的に多数参加し数名が逮捕者されていますが、この段階では高校生独自の組織はあったもののデモ隊列は学生や労働者と一緒に行動するか、デモの最後尾にくっついて行動していました。やがて新左翼党派(セクト)系の高校生組織が独自の集会やデモを行うようになっていきます。例えば革共同中核派系「反戦高協」、社学同(ブント)系「社学同高委」、ML派(日本マルクス・レーニン主義者同盟)系「高校生解放戦線」、フロント(構造改革派)系「高反協」など新左翼各セクトの存在、影響に大きいものがありました。
■エリート校の闘争
「学校群制度」が導入されて2年が経過した段階で、日比谷高校での<叛乱>が本格化しています。同校では全学闘争連合(全闘連)を結成。69年3月の卒業式の警官導入の自己批判、文部省手引書の拒否などを訴えて同年10月8日に校内の同窓会館(如蘭会館)を封鎖しています。一時、教師によって封鎖を解除しましたが、再封鎖。同月28日に機動隊を導入し立て籠もっていた全闘連を排除、抵抗した生徒2名を逮捕しました。
これを契機に学校側は校門周辺を鉄板で囲み、無許可の集会や掲示、ビラ配布等を一切禁止するなど生徒に対する管理を強化しています。これに対し生徒側は11月に入って400名規模の集会を2度にわたって開催し学校に抗議集会とデモを行っていますが、学校側は管理を強化するだけで全闘連が突きつけた問題提起に何ら答えようとしていません。
熊本県には県立熊本高校(熊高)と同熊本工業高校(熊工)があるのですが、両校ともに略称を「くまこう」と呼ぶことを避けるため「熊高」を、あえて「くまたか」と呼び、「熊工」(くまこう)と区別しています。熊本高校(熊高)は県内でもトップ校として知られており、「くまたか」はエリート校の呼称ともいえます。
そのエリート校・県立熊本高校(熊高=くまたか)では、高校が政治活動を禁止した「生徒の政治活動に関する指導方針」に対し生徒側が70年1月に配ったビラには次のような内容が書かれていました。「我々は県高校教育界のシンボル的存在である熊本高校において、この指導方針が出されたことに注目しなければならない。…熊本のすべての闘う高校生諸君! 熊高における指導粉砕の闘いを再結集せよ!」と。
ここで熊本高校を「(熊本)県高校教育界のシンボル的存在」とみなしていることが面白いですね。「…熊本高校において、この指導方針が出されたことに注目しなければならない」と続くのですが、ここには熊本高校が県下のトップ校としての認識があるからです。つまり、トップ校が政治活動禁止となれば「県下の高校に大きな影響を与えるから、ここで食い止めよう」という考えで、この発想に「エリート意識」がみえるわけです。
全国的に拡大した<高校紛争>ですが、その中心となったのは一般的に「進学校」といわれた一流高校で紛争が活発でした。県立多摩高校(神奈川)では「定期試験、制服廃止」を訴えて校舎を封鎖する闘争が行われたのですが、後年、同校教師が当時を振り返って「当時、生徒のなかには紛争をやらぬ高校は一流じゃないという考え方があった。多摩高も一流になろうとしたんだ」と同校の記念誌に記述しています。なんとなく自己顕示のための<闘争>を構えた感じもするのですが。
■「大学受験予備校化」への疑問
高校で紛争が激化するなかで「受験特化型」の教育の在り方が問われています。大阪府立東淀橋高校では「能力別クラス編成が、生徒への差別を助長する教育だ」ということで学校を封鎖、「能力別クラス編成撤廃」を求めていたのですが、同校では撤廃を認めています。
東淀橋高校は当時としては新しく創設された学校で、府内の伝統校に追いつくために進学実績を高めることを目標に「能力別クラス」が設けられたようですが、国は「理数系クラス」を人材養成の方策として奨励したところがあります。68年に全国16都道府県の進学校29校で理数系コースが設置されていますが、府立東淀橋高校のように「理数系コース」はエリート養成として批判されています。
また、高校の教育体制を批判していくなかで「大学受験予備校化」が追及されています。学期中に行われる定期試験は、本来、授業で教えられた中身を生徒がどの程度、修得したかを図ることが試験の目的です。でも試験結果が全人格的な評価につながっているとの批判が行われていました。「授業の中身、試験の問題はそのまま大学入試の出題内容につながってくる」ことが問題視されていました。そこには「高校は大学受験予備校ではない。受験対策的な試験、そして授業は改めるべき」との主張があります。
「大学受験予備校化」については、高校で紛争が起きる以前から「暗記型の授業」と生徒から疑問が出ており、自分たちが関心をもつテーマを学ぶ機会をもちたいとの要望は多かったようです。
■<高校紛争>の根源的な問いかけ
それぞれの高校が抱える事情や地域性が<紛争>の背景に大きく関わっているわけで、この<高校紛争>を通じて「高校とは何のためにあるのか」といった根源的な問いかけが生徒をはじめ教師、保護者、文部省(当時)、教育委員会など多方面から論議されたのですが、このような課題を真正面から取組むことは、これまで皆無であったことを考えると教育行政そのものを問いただす最良の機会だったと思います。
しかし、現実には学校はバリケード封鎖した生徒や、街頭で機動隊と衝突して逮捕された生徒に対して退学や停学など厳しい処分を行っています。また、<高校紛争>を担っていた生徒に対して学校および警察は彼らが未成年であることから、単に「非行少年」扱いしていたことです。政治的課題をもって活動しても「非行少年」の枠組みで少年鑑別所へ送致されるケースが多かったようです。
都立小石川高校の元教師は後年、次のように語っています。「…教師は活動家を非行少年と同じように扱い、生徒指導として接していました。しかし、思想をもって行動している活動家は非行と思っておらず、何の効き目もなかった」と(『高校紛争』260頁)。
高校生による運動(紛争)は、大学生における学生運動とは根本的なところで異なっているわけで、高校生運動は校則や教育制度に対する「改革運動」の側面が強いといえましょう。学生運動は1967~68年にかけての初期段階では教養教育やエリート教育、マスプロ教育、産学協同路線に対する批判や大学教育の在り方を課題としていましたが、60年代末の69年から70年以降は「安保と沖縄」をテーマとした政治闘争が中心課題となっています。また、そこには大学生の「闘争に対する自己の内面性」、つまり「自分の存在」(例えば「自己否定」)などを問いかける<闘い>でもあったのです。
高校紛争の過程で停学や退学処分を受けた生徒も数多く現れていますが、高校生は「学校を辞めたら中卒扱い」となり社会的に厳しい現実が待っています。この「高校中退者」というのは、代々木高校を中退していった学友が後年、「高校中退というのは大学中退と違って、実際には中卒扱いだよ」と語っていたことが思い出されます。
■定時制高校生は何と闘っていたのか。
さてさて。ここまで本書『高校紛争』をびら~んと読み込んでみますと、我が代々木高校には学校群制度はないしぃ~男女交際は自由だしぃ~別にエリート教育なんて行われていなかったしぃ~ましてや「受験教育につながる学力試験・模擬試験」なんてなかったよなぁ…え?実際には色々あったの? わたしゃ知らんかったわぁ~!
――と、まぁ<ズル休モード>で定時制高校に通っていた身にとって、この世の一般的な高校生の生活とは隔世の感がありますねぇ。そうなんだ。キミ達、全日制の高校生諸君は勉強漬けのうえ学校から強制的な管理に絡めとられ大変だったよねぇ~。 むふ。同情しちゃう。
でもね。本書を読み進むうちに代々木高校に在籍し少なからず定時制高校の様々な課題、とりわけ「労働と学業」を両立せざるを得ない生徒<若年労働者>の現実を追及していた経験からしますと、本書を手にした当初から感じていた<違和感>の実態が、おぼろげながら具体性を帯びた輪郭となって現れてきたということでしょうか。
ひとつは、私が1学年2学期末に手にした冊子の付録『高校生日記』に掲載されていた同世代高校生の写真を見て、「同じ高校生なのに、この格差は何だ」といった単純な疑問ですね。本書を読むと私が当時考えていた「同じ高校生なのに」というのは明らかに私の思い違いで、必ずしも「同じ高校生ではなかった」ということです。
それは、「もてる者と、もたざる者」の違いということです。「同じ高校生」と思っていた彼らと私たち定時制高校生の間で誰が「もっていた」のか、何を「もっていなかった」のか。それは経済的側面(お金)なのかも知れませんが、本質的には<時間所有の有無>なのです。
本書『高校紛争』に登場する高校生は全日制の生徒たちです。彼らは学校運営や教育制度、政治課題(安保・反戦)等に対し異議を唱え<叛乱>を起こしたのですが、68年から70年にかけて彼らと皮膚感覚で「激動期に同じ<時代>を共有」した私(若しくは私たち)にとって、当時の情況において<叛乱>に「連帯」はするけれど、「共闘」までにはいかなかったと思います。
彼ら高校生と、私のなかの<高校生>とは異次元のものだったということですね。それは、彼ら<叛乱>高校生たちは「時間をもっていた」たっぷりと。「24時間」これすべて<闘争>を日常化できたわけです。バリスト封鎖の学内で、また近くの喫茶店や生徒の自宅などで自由な「時間」を費やして論争を闘わすことができたのです。なんら制約されることなく。
それに対し私たち定時制高校生は、日常管理されている<労働>の合間をぬって学校に通い「学ぶ」という両面性をもつ<勤労学生>の立場にあったわけです。一日7~8時間働いた後、高校へ通い授業の合間に学内問題(生徒心得・PTA問題)や政治課題(安保・反戦)に関する討議を行い、行動を起こしました。
すなわち私たち定時制高校生が社会に対し異議を唱え<闘争>を構えるとなると、その<闘争>の対象は学校であり社会であるとともに「最大の敵」は、他ならぬ『高校紛争』に登場する高校生たちがたっぷり持っていた時間。その<時間>だったわけですね。 (⇒この項つづく)



















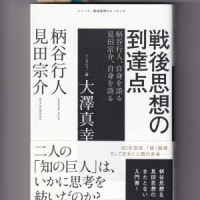






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます