<第1章> 『下北沢通信』 闘争の構図
〔第3回〕 奥浩平『青春の墓標』(1)
[1]真に前進的な人間の発達の鍛錬の場としよう。
1969年の春。一冊の本を手にしました。奥浩平『青春の墓標』です。
――3月のある日。新聞のコラムに「学生活動家の遺稿集」として、21歳で自死した奥浩平が自ら綴った手記や恋人に送った手紙を編纂した本の紹介を目にしました。
67年秋の<10・8羽田闘争>を契機に、大学生を先頭とした全国的な「若者の反乱」が続き、翌68年からは各大学を拠点とした紛争がテレビや新聞などで毎日のように報じられていました。代々木高校のなかでは学友たちと日頃から、「私たちと同じ世代の大学生が、どのような考えで何を目的に反乱を起こしているのか」と様々な意見や議論が活発に行われていても、いまひとつ実感がわかない。
その頃――69年の春の段階で、私自身は社研部に所属しながら少しずつ社会の情勢に関心をもっていましたが自ら何かに取組むとまでは至っておらず、生徒会の代議員として正月明け以来、役員選挙の準備に奔走していました。一方で、その年に卒業する先輩たちの「卒業式闘争」の議論に加わるなど徐々にではありますが、表舞台へ登場していました。
そのような状況のなかで新聞コラム「学生活動家の遺稿集」紹介を目にして、「遺稿集というからには、学生活動家の考えや内面が伺い知れるかもしれない」と思い、さっそく近くの本屋へ行きました。すると、そこに奥浩平『青春の墓標』を一冊だけ見つけたのです。副題に「ある学生活動家の愛と死」とあります。

新聞販売店の自室に戻って一読すると、何というか…衝撃の一言。いや、羨望すら感じました。それだけの内容が、奥浩平の『青春の墓標』にはあったのです。
■「今度の日曜デイトしないか。今のうちならまだあるから昼飯ぐらいおごります。(中略)…君のこれからのことを話そう。実は大変だと思う。女性解放の課題はより全般的、より広範、より深刻な問題を投げかけているし、絶対に急速には進展し得ないものだと思う――」このような書き出しで始まる奥浩平の手紙は1962年3月29日付けで、高校時代から付き合いのあった恋人・N子へ宛てたものです。
この手紙を出した頃の奥浩平は浪人中でしたが、翌63年、横浜市立大学へ入学してからは学生組織、マルクス主義学生同盟・中核派(マル学同)へ加盟。その後、上部組織の革命的共産主義者同盟全国委員会(革共同)へ加盟しています。以後、学生活動家として常に学生運動の先頭に立ち果敢に闘争をリードしていたのですが、1965年3月6日に自宅の勉強部屋で服毒、午後4時頃絶命しています。
検死の際に所見された彼の四肢(手足)に残る無数の紫斑は、60年安保闘争以来5年にわたる学生デモにおいて機動隊の警棒の乱打や軍靴まがいの靴先で蹴りつけられた傷痕でした。自死した半月前の2月17日、日韓闘争過程の「椎名訪韓羽田闘争」において機動隊の装甲車を乗り越えたところで殴りつけられた警棒の一撃で、鼻硬骨を数個に砕かれて入院しています。
――彼の死は、退院後10日目のことでした。21歳と6ヵ月-熾烈な短い一生といえます。
この奥浩平の遺稿集『青春の墓標』は、彼が大学へ入ってマル学同加盟(63年4月)から断片的に記していた手記(日記)をベースに、恋人・N子をはじめ友人や兄姉らに宛てた手紙、また学生運動に伴う政治論文などで構成されています。
本書「まえがきにかえて」のなかで兄・奥紳平氏は、「遺稿集と呼ばれるものが一般にそうであるように、本来、不特定な多数の読者を予定せずに書かれた文章」と記されていますが、浩平自身、「…日記というのは、人間が成長するのに吐き出す汚物のカメだ。汚水タンクの蓋をとって中をのぞいて、どんな功徳があろうか!」(64年8月16日)と記述している。そのような「日記」を彼は何故、書いたのか――。
――1963年4月12日付。奥浩平は「ノート」を新たに記すにあたって、次のように記述しています。
〔 手記をつくるまいと何度思ったか知れない。手記をつくることによって犯される過ちのほとんどを、高校時代にしてしまったと言っていいと思う。
過ちとは次のようなものである。▽手記を休息の場としたこと。作文することによって休み、愉しみ、嘆き、泣いた。即ち、頽廃的にしたのである。▽考えが凝縮されなかった。ぼくの思惟の順序は、動→反動→凝縮(止揚)の型をいつでもとっていたが、でたらめに書きつけた手記に於いては、一時の思いつきがそのまま述べられた。
だが、いま手記をつくることの必要性をひしひしと感じる。一時の思いつきが一つの形を整えられるまでに煮つめられたのちには、書き留められねばならぬ。書くことは<考えた>ことである。そしてまた<考える>ことであり、書かれた時以上に<考えねばならない>ことを要求するものである。
この手帳を反省の場としよう。あの恥辱に満ちた、ガソリンをぶっかけて焼かなければならなかった十数冊のノートの過ちを克服して、真に前進的な人間の発達の鍛錬の場としよう。
重ねて決心するが、恋心的な、ぐち的な、自慰的な文章を書かぬようにしよう。考えたのちに書こう。書いて考え、考えて書こう。同じ誤りは二度繰り返されてはならぬ。言葉の遊びに堕することを警戒しよう。(⇒以下略) 〕
この記述を読む限り、奥浩平は高校時代から日記を書き綴っていたようですが、「手記をつくることによって犯される過ち」の反省のもと、新たに「真に前進的な人間の発達の鍛錬の場」とすることの決意を述べています。ここに、この「遺稿集」の核心があると思うのです。
■私は、奥浩平『青春の墓標』を初めて手にした69年の春の段階で、「彼は、何とよく学び思索し、しっかりした論調で記述しているのだろう」という思いがありました。さらに彼独特のユーモアと明るくて人に好かれるタイプであって、学生運動の活動家としての決断力や活動的な行動力には、羨望すら感じたものです。
高校入学以来、一貫して「何故、学ぶのか。何を学ぶのか」と自ら課題を抱え、どこか茫漠とした思いで3年間を過ごしてきたのですが、奥浩平は大学入学とともに「貪欲な読書を始めた」(兄・奥紳平「あとがき」)ことで、彼がノートに示した「真に前進的な人間の発達の鍛錬の場」を自らに課したのではないかと思うと、その生きざまに私自身が恥ずかしくなりました。
それは、まず「何故、学ぶのか。何を学ぶのか」と自ら問いかけはしながら、これといった勉強をするではなく本一冊を真剣に読んだこともなく、例えていえばシッポを噛もうとしてクルクル回っている犬のような生き方をしていたものだ、と感じました。確かに本は数冊読んでいました。それは、「ただ読んでいた」というだけで、「本に対する真摯な姿勢に欠けていた」思いをうけました。
しかし、当時の私は新聞配達で生計を支え、午前中に高校へ登校するだけで辟易しており、そこに社研部や生徒会へ首を突っ込んだものだから本を手にしたとしても、ズルっと寝入ってしまうばかり。それじゃ社研部や生徒会活動を行う前に何をやっていたのか…映画を観たり喫茶店でベチャくってばかりしていたじゃないか――それはそれでよいとして、『青春の墓標』が私のなかに突きつけてくるものは、何だろう…。
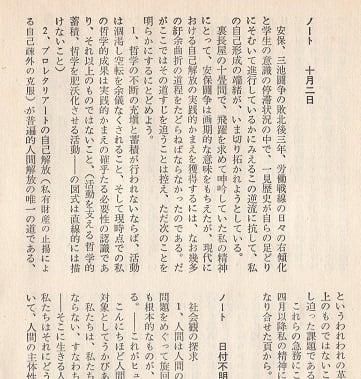
だが、時間が経過し『青春の墓標』を初めて手にしたときの衝撃が過ぎて、じっくり読み進んでいくと、幾つかの課題を見つけることができました。それは、奥浩平が大学入学とともに始めた学生運動の本質とは何か、恋人・N子との関係性。さらに21歳で自死した理由とは?――69年春、私はまさに<21歳>になろうとしていました。 (⇒この項つづく)
〔第3回〕 奥浩平『青春の墓標』(1)
[1]真に前進的な人間の発達の鍛錬の場としよう。
1969年の春。一冊の本を手にしました。奥浩平『青春の墓標』です。
――3月のある日。新聞のコラムに「学生活動家の遺稿集」として、21歳で自死した奥浩平が自ら綴った手記や恋人に送った手紙を編纂した本の紹介を目にしました。
67年秋の<10・8羽田闘争>を契機に、大学生を先頭とした全国的な「若者の反乱」が続き、翌68年からは各大学を拠点とした紛争がテレビや新聞などで毎日のように報じられていました。代々木高校のなかでは学友たちと日頃から、「私たちと同じ世代の大学生が、どのような考えで何を目的に反乱を起こしているのか」と様々な意見や議論が活発に行われていても、いまひとつ実感がわかない。
その頃――69年の春の段階で、私自身は社研部に所属しながら少しずつ社会の情勢に関心をもっていましたが自ら何かに取組むとまでは至っておらず、生徒会の代議員として正月明け以来、役員選挙の準備に奔走していました。一方で、その年に卒業する先輩たちの「卒業式闘争」の議論に加わるなど徐々にではありますが、表舞台へ登場していました。
そのような状況のなかで新聞コラム「学生活動家の遺稿集」紹介を目にして、「遺稿集というからには、学生活動家の考えや内面が伺い知れるかもしれない」と思い、さっそく近くの本屋へ行きました。すると、そこに奥浩平『青春の墓標』を一冊だけ見つけたのです。副題に「ある学生活動家の愛と死」とあります。

新聞販売店の自室に戻って一読すると、何というか…衝撃の一言。いや、羨望すら感じました。それだけの内容が、奥浩平の『青春の墓標』にはあったのです。
■「今度の日曜デイトしないか。今のうちならまだあるから昼飯ぐらいおごります。(中略)…君のこれからのことを話そう。実は大変だと思う。女性解放の課題はより全般的、より広範、より深刻な問題を投げかけているし、絶対に急速には進展し得ないものだと思う――」このような書き出しで始まる奥浩平の手紙は1962年3月29日付けで、高校時代から付き合いのあった恋人・N子へ宛てたものです。
この手紙を出した頃の奥浩平は浪人中でしたが、翌63年、横浜市立大学へ入学してからは学生組織、マルクス主義学生同盟・中核派(マル学同)へ加盟。その後、上部組織の革命的共産主義者同盟全国委員会(革共同)へ加盟しています。以後、学生活動家として常に学生運動の先頭に立ち果敢に闘争をリードしていたのですが、1965年3月6日に自宅の勉強部屋で服毒、午後4時頃絶命しています。
検死の際に所見された彼の四肢(手足)に残る無数の紫斑は、60年安保闘争以来5年にわたる学生デモにおいて機動隊の警棒の乱打や軍靴まがいの靴先で蹴りつけられた傷痕でした。自死した半月前の2月17日、日韓闘争過程の「椎名訪韓羽田闘争」において機動隊の装甲車を乗り越えたところで殴りつけられた警棒の一撃で、鼻硬骨を数個に砕かれて入院しています。
――彼の死は、退院後10日目のことでした。21歳と6ヵ月-熾烈な短い一生といえます。
この奥浩平の遺稿集『青春の墓標』は、彼が大学へ入ってマル学同加盟(63年4月)から断片的に記していた手記(日記)をベースに、恋人・N子をはじめ友人や兄姉らに宛てた手紙、また学生運動に伴う政治論文などで構成されています。
本書「まえがきにかえて」のなかで兄・奥紳平氏は、「遺稿集と呼ばれるものが一般にそうであるように、本来、不特定な多数の読者を予定せずに書かれた文章」と記されていますが、浩平自身、「…日記というのは、人間が成長するのに吐き出す汚物のカメだ。汚水タンクの蓋をとって中をのぞいて、どんな功徳があろうか!」(64年8月16日)と記述している。そのような「日記」を彼は何故、書いたのか――。
――1963年4月12日付。奥浩平は「ノート」を新たに記すにあたって、次のように記述しています。
〔 手記をつくるまいと何度思ったか知れない。手記をつくることによって犯される過ちのほとんどを、高校時代にしてしまったと言っていいと思う。
過ちとは次のようなものである。▽手記を休息の場としたこと。作文することによって休み、愉しみ、嘆き、泣いた。即ち、頽廃的にしたのである。▽考えが凝縮されなかった。ぼくの思惟の順序は、動→反動→凝縮(止揚)の型をいつでもとっていたが、でたらめに書きつけた手記に於いては、一時の思いつきがそのまま述べられた。
だが、いま手記をつくることの必要性をひしひしと感じる。一時の思いつきが一つの形を整えられるまでに煮つめられたのちには、書き留められねばならぬ。書くことは<考えた>ことである。そしてまた<考える>ことであり、書かれた時以上に<考えねばならない>ことを要求するものである。
この手帳を反省の場としよう。あの恥辱に満ちた、ガソリンをぶっかけて焼かなければならなかった十数冊のノートの過ちを克服して、真に前進的な人間の発達の鍛錬の場としよう。
重ねて決心するが、恋心的な、ぐち的な、自慰的な文章を書かぬようにしよう。考えたのちに書こう。書いて考え、考えて書こう。同じ誤りは二度繰り返されてはならぬ。言葉の遊びに堕することを警戒しよう。(⇒以下略) 〕
この記述を読む限り、奥浩平は高校時代から日記を書き綴っていたようですが、「手記をつくることによって犯される過ち」の反省のもと、新たに「真に前進的な人間の発達の鍛錬の場」とすることの決意を述べています。ここに、この「遺稿集」の核心があると思うのです。
■私は、奥浩平『青春の墓標』を初めて手にした69年の春の段階で、「彼は、何とよく学び思索し、しっかりした論調で記述しているのだろう」という思いがありました。さらに彼独特のユーモアと明るくて人に好かれるタイプであって、学生運動の活動家としての決断力や活動的な行動力には、羨望すら感じたものです。
高校入学以来、一貫して「何故、学ぶのか。何を学ぶのか」と自ら課題を抱え、どこか茫漠とした思いで3年間を過ごしてきたのですが、奥浩平は大学入学とともに「貪欲な読書を始めた」(兄・奥紳平「あとがき」)ことで、彼がノートに示した「真に前進的な人間の発達の鍛錬の場」を自らに課したのではないかと思うと、その生きざまに私自身が恥ずかしくなりました。
それは、まず「何故、学ぶのか。何を学ぶのか」と自ら問いかけはしながら、これといった勉強をするではなく本一冊を真剣に読んだこともなく、例えていえばシッポを噛もうとしてクルクル回っている犬のような生き方をしていたものだ、と感じました。確かに本は数冊読んでいました。それは、「ただ読んでいた」というだけで、「本に対する真摯な姿勢に欠けていた」思いをうけました。
しかし、当時の私は新聞配達で生計を支え、午前中に高校へ登校するだけで辟易しており、そこに社研部や生徒会へ首を突っ込んだものだから本を手にしたとしても、ズルっと寝入ってしまうばかり。それじゃ社研部や生徒会活動を行う前に何をやっていたのか…映画を観たり喫茶店でベチャくってばかりしていたじゃないか――それはそれでよいとして、『青春の墓標』が私のなかに突きつけてくるものは、何だろう…。
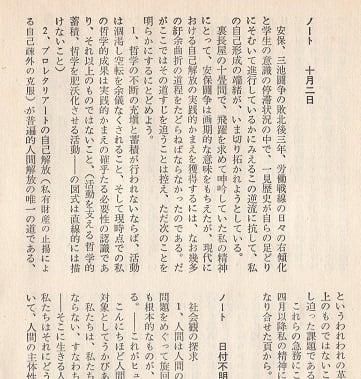
だが、時間が経過し『青春の墓標』を初めて手にしたときの衝撃が過ぎて、じっくり読み進んでいくと、幾つかの課題を見つけることができました。それは、奥浩平が大学入学とともに始めた学生運動の本質とは何か、恋人・N子との関係性。さらに21歳で自死した理由とは?――69年春、私はまさに<21歳>になろうとしていました。 (⇒この項つづく)















