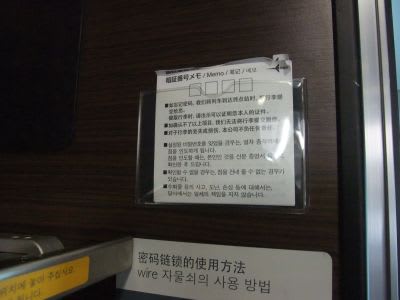この週末、Champagne地方のリリ・ラ・モンターニュ (Rilly-la-Montagne) と
ランス (Reims) を訪れる日帰り旅行に出かけてきました。
今回は団体のバス旅行でしたが、本ログの最後にTGVで行かれる方への情報も。
パリからわずか45分で着きますので、お試しあれ。
朝8時にパリを出発し、10時半ごろ、ランス市の南側に小高く控える
ランス山地方公園 (Parc régional de la Montagne de Reims)の北端にある、
Rilly-la-Montagneという村に到着。
Reims と Epernay を結ぶ路線上にあり、列車でも行けます。
シャンパーニュ地方といったらこれですね!

シャンパーニュ生産者、Henri Chauvet さんのカーブです。
こちらでブドウ畑も持ち、生産・販売を行っています。



フクロウがおでむかえ。

アペリティフだけでなく、食事中に飲んでも料理に負けないシャンパーニュで、
コストパフォーマンスも抜群。

白・ロゼと、合計5種類の試飲をしました。
昼食はランスへの途中、レストラン Lys du Roy でこの地方の料理を。

メインは当地の名物料理「ポテ」(Potée)。

牛肉を野菜と一緒に煮込んだ「ポトフ」は日本でも有名ですが、
その豚肉版となります。
ヌーベル・キュイジーヌが現れる前の、これぞ元祖フランス料理!
2時半ごろ、ランスに到着です。
まずは画家 藤田嗣治が建てた Chapelle Foujita です。
藤田が描いたフレスコ画がすばらしいのですが、内部は撮影禁止なので、
外から。

実は2000年と2012年にそれぞれ正面の門まで来ているのですが、
2回とも閉まっていて、中に入れたのは今回が初めて。
まさに3度目の正直!

バスぎりぎりに木がこすってますよ。紅葉の季節です。

世界遺産、ランスのノートルダム大聖堂 (Cathédrale Notre-Dame de Reims)。
1211年に礎石され、それより建築、増築を重ね、15世紀には現在の形に。
歴代フランス王が戴冠式を行った場所です。
日本では天皇のご即位の時は後ろ向きとなりますが、
フランスでは戴冠式は横向きまたは前向きになっていたそうです。


シャガールのステンドグラス。
フランス王シャルル7世 (Charles VII) の戴冠に貢献したジャンヌダルク (Jeanne d'Arc) も、
ここのシンボル的存在です。



虹が出ました!
帰りのシャンパーニュ・アルデンヌ地方からイル・ド・フランス地方に入るあたり。
さて、バス旅行も楽しかったですが、
昨年、個人で行った際はTGVで行きました。
パリ東駅 (Gare de l'Est) からわずかに45分。
あっという間にランスです。



東ヨーロッパ線に投入された平屋タイプはすべてリニューアルを受けており、
ラクロワ (Lacroix)によってデザインされた内装となっています。
機関車すぐ後ろの個室のようになっている部分は売れていることも少なく、
静かに過ごしたい人にはもってこいです。
ランス (Reims) を訪れる日帰り旅行に出かけてきました。
今回は団体のバス旅行でしたが、本ログの最後にTGVで行かれる方への情報も。
パリからわずか45分で着きますので、お試しあれ。
朝8時にパリを出発し、10時半ごろ、ランス市の南側に小高く控える
ランス山地方公園 (Parc régional de la Montagne de Reims)の北端にある、
Rilly-la-Montagneという村に到着。
Reims と Epernay を結ぶ路線上にあり、列車でも行けます。
シャンパーニュ地方といったらこれですね!

シャンパーニュ生産者、Henri Chauvet さんのカーブです。
こちらでブドウ畑も持ち、生産・販売を行っています。



フクロウがおでむかえ。

アペリティフだけでなく、食事中に飲んでも料理に負けないシャンパーニュで、
コストパフォーマンスも抜群。

白・ロゼと、合計5種類の試飲をしました。
昼食はランスへの途中、レストラン Lys du Roy でこの地方の料理を。

メインは当地の名物料理「ポテ」(Potée)。

牛肉を野菜と一緒に煮込んだ「ポトフ」は日本でも有名ですが、
その豚肉版となります。
ヌーベル・キュイジーヌが現れる前の、これぞ元祖フランス料理!
2時半ごろ、ランスに到着です。
まずは画家 藤田嗣治が建てた Chapelle Foujita です。
藤田が描いたフレスコ画がすばらしいのですが、内部は撮影禁止なので、
外から。

実は2000年と2012年にそれぞれ正面の門まで来ているのですが、
2回とも閉まっていて、中に入れたのは今回が初めて。
まさに3度目の正直!

バスぎりぎりに木がこすってますよ。紅葉の季節です。

世界遺産、ランスのノートルダム大聖堂 (Cathédrale Notre-Dame de Reims)。
1211年に礎石され、それより建築、増築を重ね、15世紀には現在の形に。
歴代フランス王が戴冠式を行った場所です。
日本では天皇のご即位の時は後ろ向きとなりますが、
フランスでは戴冠式は横向きまたは前向きになっていたそうです。


シャガールのステンドグラス。
フランス王シャルル7世 (Charles VII) の戴冠に貢献したジャンヌダルク (Jeanne d'Arc) も、
ここのシンボル的存在です。



虹が出ました!
帰りのシャンパーニュ・アルデンヌ地方からイル・ド・フランス地方に入るあたり。
さて、バス旅行も楽しかったですが、
昨年、個人で行った際はTGVで行きました。
パリ東駅 (Gare de l'Est) からわずかに45分。
あっという間にランスです。



東ヨーロッパ線に投入された平屋タイプはすべてリニューアルを受けており、
ラクロワ (Lacroix)によってデザインされた内装となっています。
機関車すぐ後ろの個室のようになっている部分は売れていることも少なく、
静かに過ごしたい人にはもってこいです。