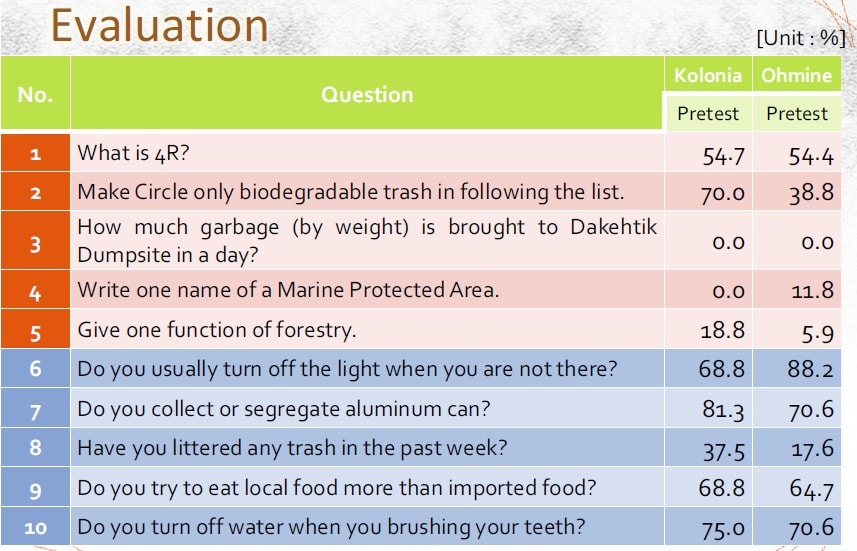ポンペイ島にある唯一の公共のごみ処分場、タケチックダンプサイト。ここには一日約14tのゴミが運ばれてくる。(ポンペイ島の人口:35,000人)ポンペイにはアルミ缶以外リサイクルがされないため、ありとあらゆるごみ全てがここには運ばれてくる。オープンから16年以上が経っており、もうすでに受け入れ限界に達しているといわれ、数年が経過している。
このダンプサイトとしては初の大規模なリハビリテーション(改善工事)が6月17日(月)~27日(木)のおよそ2週間で実施された。これはJICAが大洋州12か国に対して、5年間に渡り実施している廃棄物対策プロジェクト(通称J-PRISM)の一貫として行われた。このプロジェクトの特徴は「技術援助」を目的としていることだ。工事をドナー国が一方的に進めるのではなく、現地の関係者に実際に工事に参加してもらい、ダンプサイトの改善技術を学んでもらう。そのため、今回はコスラエ州、ヤップ州、チューク州、マーシャル共和国、ポンペイの各村から公共工事、廃棄物関係の人材が集まり、一緒に学び、工事をした。
初日に盛大なオープニングセレモニーがあった。州知事、州議会議員、環境庁大臣などリーダーも列席し、この工事の期待度の高さを感じさせた。というのも、2年前に新規処分場の建設計画があった。アメリカのコンサルタントに依頼をし、はじき出された見積もりは16億円(アクセスロード工事費は別途)。。。途方もない額にみんな思考停止していた。そこにこのプロジェクトがあったため、その期待が高いのも良くわかる。
現場での説明。

初めの一週間はひたすらエクスカベータ2台、ブルドーザー1台でゴミの山を掘り、堤防を作っていく。30m×70mの谷が掘られた。


谷の下流側には浸出液をためる池が掘られた。

翌週からはマンパワーで建設を進めていく。この改善工事は福岡方式(福岡大学より発信)と呼ばれており、途上国の状況に応じた技術が売りだ。
通常、ごみを堆積していくと、下層部は圧密され、空気が循環しなくなる(嫌気性の状態)。そうなると嫌気性発酵進み、メタンガスなどが発生する。これがダンプサイトの悪臭の元だ。これらのガスに着火すると煙が立ち上る。フィリピンのスモーキーマウンテンがその代表的な様子だ。下層部に浸出液(汚染水)を集めるパイプを通し、それらに垂直に穴を開いたパイプ(ベンチレーションパイプ)を接続する。こうすることで内部に空気が送り込まれるようになり、好気性発酵が行われるようになる。分解も早く、悪臭もない。ポンプなどで強制的に空気を送り込む方法もあるが、この方法は自然に空気が循環する仕組みのため準好気性の方式と呼ばれる。
途上国ではお金もなく、資材も揃いにくい。福岡方式は現地にあるもので建設が可能だ。ドラム缶、古タイヤ、現地調達できる岩、パイプも竹で代用可能。廃材利用もすることができ、コストを圧縮することができる。そして、構造がきわめてシンプルなため、知識、技術が特になくともマンパワーで十分に工事ができる。
浸出液を通すパイプの設置。ゴミの荷重に耐えられるように岩で覆う。ここではサンゴの岩を使用した。

ベンチレーションパイプの設置。


3日間炎天下の中、地道に作業を続け完成!


この研修で感動したことがある。EPAの同僚であり現地の責任者であったチャールスの働きぶりである。セレモニーではMCを堂々と務め、現場でも率先して働き、スタッフに対するリーダーシップもすごかった。彼がいなければ、これほど上手く進まなかったのではないかと思う。
正直なところ今までJICAの人材育成という方針に懐疑的な目を持っていた。研修で日本に行っても帰国後なかなかそれが本国で生かされることがないと感じていた。しかし、彼は違った。2年前に日本に研修に行っている。そして、今年二月にはヤップ州で行われた同様のダンプサイトに関する研修にも参加している。そこで学んだことを彼は今回存分に発揮していた。
研修最終日の夕方に彼が言っていたこと。
「これでやることが二つできた。一つはダンプサイトにおけるごみの分別の開始。もう一つは美化活動。小学生をここに連れてきて花を植えるんだ。そして学校の名前を古いタイヤにペイントして入り口に並べていく。そうすれば、もっとみんなダンプサイトに感心が湧くだろう!」
この言葉に本当に感動した。ワクワクした!
彼はこの国の自律的な未来を描いている。
数は少ないかもしれないが、確実に人材は育ってきている。
この貴重で素晴らしい時間を提供して頂いたJ-PRISMの面々に感謝したい。
プロジェクトリーダーの長谷山さん。プロジェクトの立ち上げから長期に渡り、本当にご苦労様でした。
J-PRISMチーフアドバイザー天野さんの言葉。
「物は作ったところから古くなっていくが、人はそうじゃない。成長するし進化する。」
24年度2次隊 ポンペイEPA 浜川