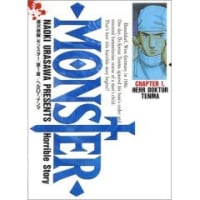17
このノートは、誰も見ないで欲しい。このノートは、単純な文字で誤魔化して、自分の気持ちを封じ込めるためのすべてだ。
僕はいつまでも僕でありたかった。だから僕は恋をした。
生きる意味が欲しかった。ありふれた幸せを手に入れたかった。人と波長を合わせながら、同じ道を歩いて行きたかった。幸せは、理想を形にしていったら、いつの間にか完成するものだと信じていた。
公園のベンチに座って、じっと景色を眺めてみる。すうっと通り過ぎる爽やかな風があって、木の葉がざわざわと音を立てて揺れる。当たり前に小鳥が空を飛び、当たり前に時間が流れる。平和な風景である。誰の目にも、きっとそんな風景が映るはずだ。
だが、僕の目にはいつもそんな風景に寄り添って、一人の女の子が映った。その子はどこにいても、じっと僕を見つめて、ふいに視界から姿を消す。その子から目を離すと同時に僕は罪悪感に蝕まれる。じっとその子を見つめると、深い悲しみが胸を痛めつける。しだいに僕の呼吸は乱れ、その場に立っていられなくなる。考えれば考えるほど苦しくなり、考えることをやめると、不安で頭の中が真っ白になる。
日々を重なるうちに、僕はどんどん現実から離れていくような錯覚に陥った。無意識のうちに僕の頭は、真実を押し隠していった。怖かった。自分が自分でなくなっていくのが怖くて仕方なかった。
だから僕は、平常心を保つためノートを綴った。
そのノートには、その女の子のことを書き記した。僕と彼女は恋人同士で、僕らは愛し合っていた。ただ、断片的な僕らの話を淡々と書き記した。それが真実か、真実でないかは不確かだった。でも、それを書くことで僕の心は落ち着いた。でたらめでいいから、僕はノートを綴った。
ストーリーを途切れさすわけにはいかなかった。そのストーリーが途切れるということは、僕の人生が終わるということだったから。僕は死に物狂いでノートを綴った。
本当に少しずつ、僕の記憶は蘇っていた。それは、ドミノ崩しのようにゴールに向かって一個一個が倒れていくような感覚だった。
「あの日もお前は、真実を知りたいと俺に言った。」
健司は、俯いた顔を上げ、呟いた。同時に僕も顔を上げる。
「あの日、お前は俺に言った。」
じっと僕を見つめながら、健司はしゃべり始めた。その日の様子が、少しずつ思い出された。
「美鈴は、なぜ死んだのか。」
僕は遠い記憶に身を委ねるようにぽつりと呟いた。
「あまりにも・・・。」
表情を曇らせながら、健司は応える。
「あまりにも、タイミングが悪かったんだ。」
すぅっと息を吸い込んで、健司は僕を見つめる。
「あれは、事故だ。」
訴えかけるように健司は言った。それは、僕を説得させるために放たれた、重苦しい言葉であった。
「事故だ。」
事故だ、その言葉に聞き覚えがある。
その言葉は、何かに追い込まれ、身動きが取れなくなったあの日の僕に健司が言った言葉だ。あの日、とはサキが死んで一ヶ月の月日が流れたある日のことだった。僕は混乱していた。
サキがいなくなって、僕はすべてを失った。そんな気持ちは僕をどん底に陥れた。
そんな僕を勇気付けてくれたのは、美鈴だった。放課後、僕はずっと教室で美鈴がやってくるのを待っていた。僕らだけの秘密の時間。
「リョウスケくん・・・?」
気が付くと、そこには美鈴がいた。暗闇の教室の中、月明かりに照らされて。
不思議な感覚と共に、僕らが付き合っていた頃に時間が戻った気がした。繋がっている気がした。美鈴も、この放課後の教室で僕が来るのを待ってくれていた。そんな一方的な気持ちが湧き出してきた。
僕はギリギリだったのかも知れない。サキが死んでぽっかり空いた隙間を、埋めるために、必死だったのかも知れない。
不安は募って、すべてを駄目にしてしまう。美鈴は確かにそこにいた。僕の目には映っていた。それはあたかも僕に会うためにそこに来たように見えたし、美鈴が来て、僕はどれだけほっとしたことだろう。
「もう一度、やり直そう。」
と僕は言った。サキへの罪悪感は確かにあった。でも、僕は少しでも早く立ち直りたかったんだ。
「うん。」
と美鈴は笑って返す。
頭の中で、僕のストーリーは繋がっていた。そこにあったのは、束の間の幸せ。矛盾とか、ずれを修正するために僕が作り出した幻だ。
そうだ、それは幻だった。
美鈴はもうこの世にいない。僕の目の前にいたのは、僕が頭の中で作り上げた幻だ。
だけど、僕は気付かなかった。気付く余裕なんて無かった。きっと、幻でも良かったのだ。ギリギリだったから、そんな幻にしがみ付いてでも平気な顔をしていたかったんだ。
放課後の教室が好きだった。僕は毎日のように美鈴と会った。美鈴が死んだことを受け入れられなかった僕は、美鈴の幻を頭の中で作り上げて、幻想の世界で彼女としゃべっていた。偽者の幸せで心を落ち着かせて、何もなくなった心を埋めようとしていた。
夜が過ぎると、その魔法は解けた。でも、夜になると美鈴に会える。夜の学校で、僕らはずっとくだらない話を続けた。
取り返しのつかないことになっていた。もう、僕は現実の世界で生きていけなくなっていた。壊れそうな心を、必死に隠そうとしていた。それは、ふとしたことで崩壊しそうで怖かった。
気付いていたのか、本当に気付いていなかったのか。今となっては分からない。あの頃の僕は、ただただ不安定で危なっかしい、そんな道の上を歩いていた。
美鈴と会ってない時間は、生きている心地がしなかった。苦しかった。誰の言葉も耳に入らない、僕に意味を与えるのは美鈴だけだった。
それが幻だと、知ってしまったら、すべてが終わってしまう。すべてが。
「何やってんだよ。」
ある日、暗闇の教室に健司が立っていた。
「健司・・・。」
僕は焦った声を上げた。美鈴と二人でいるところを見られてしまった、と僕は焦った。だが、健司の目は僕をじっと睨み付けたまま、美鈴の方に目を向けることは無かった。その時ようやく僕は現実の世界に引き戻された。気がつくと、その教室に美鈴の姿はなかった。
「美鈴はもう・・・。」
健司は泣き出しそうな顔で、僕に言った。その瞬間、僕の中の世界が壊れ始めた。終わり、が近付いてきている。これは夢の世界じゃない。現実の世界の中で、僕だけが夢を見ているのだ。
言葉が出てこなかった。うすうす僕は感じていたのだ。美鈴がこの世にいないことも、それでも僕は自分を誤魔化し続けていたことを。
いつか分かる日が来る、それに気付いていた。きっかけが必要だった。それは間違っている、と僕を一喝してくれる何かが必要だった。健司に本当の事を言われた時、僕は現実の世界に立っていた。
美鈴がいない、夜の教室に立っていた。
「美鈴は、もう死んだ。」
搾り出すような台詞が、健司からこぼれる。
「もう、やめよう。こんなこと。」
健司は優しく僕に言った。その言葉は、少しだけ僕を落ち着けた。
「もう、やめにしよう。」
落ち着いた声が僕の耳に届く。湧き出す思いはあったものの、妙にその言葉に癒された自分がいた。見失っていた自分が、ちょっとだけ姿を現した。ここは夢の世界じゃない。
「美鈴は、死んだ。」
自分に言い聞かせるように、健司に確認するように僕はぼんやりと言った。
僕は冷静に考えた。
思い返していた。美鈴に好きだと告げたこと。二人のことは秘密にしようって言われたこと。美鈴は死んだと聞いても、信じようとしなかった自分のこと。サキと付き合ってやってほしい、とサキの母親に言われたこと。サキと付き合い始めたときのこと。サキの最後の誕生日のこと。いつかやってくると分かっていたサキの死さえも、信じようとしなかった自分のこと。
そして、思い出した。美鈴から死ぬ前に告げられたこと。
「全部、知ってたのか。」
沈黙のあと、僕は健司に尋ねた。幾分、冷静な声を取り戻していた。
「ああ、知ってた。」
健司は答える。
「美鈴から聞いていた。」
夜の静けさのせいで、その声は教室に響き渡っていた。妙な緊迫感が張り詰める。
「真実を知りたい。」
僕は突発的に健司に突きつけていた。その言葉は、どんな刃物よりも鋭かったかも知れない。知ってはいけないこと、知らないほうがいいこと。そんなことの向こう側を覗き込むような、非常識な言葉だった。
健司は黙り込んでしまった。
「美鈴が死んだと聞かされた前日、僕は美鈴と会った。」
僕は静かにしゃべり始めた。健司はじっと聞いていた。
「いつも通り、この教室で。」
僕は美鈴の幻が立っていた教室の隅に目を向けながら続けた。
「何の変哲もない日だった。」
思い起こすと自然と涙が溢れた。あの日から、少しずつ何かが狂い始めていた。
「別れよう、と美鈴は言った。」
美鈴の弱々しい声が思い出される。泣きそうで居て、それでもって強がった、切ない声。
別れよう、と告げられてもそんなに僕は驚かなかった。むしろ、自分に対する失望感に包まれていた。もっと努力すべきだった。美鈴にもっと好かれるために、伝えなければならないことがたくさんあったのに。別れは、必然的に訪れたんだと僕は思ってしまった。
「うん、分かった。」
と僕は答えた。すぐにでも消えてしまいそうな秘密の関係だったから、別れても何も変わらないことは分かっていた。美鈴も僕も、これまでの生活を続けるだけだ。辛いけれど、仕方のないことだった。
「その次の日、美鈴が死んだと聞かされた。」
涙が止まらなかった。
思い出してはいけない、そんな記憶が蘇って溢れて押さえ切れなかった。
「違う。」
健司の叫び声が聞こえる。しかし、僕には届かなかった。感情が洪水のように襲い掛かってきた。苦しくて、息が出来なくなった。
健司が思いっきり僕の肩を掴む。感覚のなくなった肩は、何の痛みも感じなかった。
「あれは事故だったんだ。あれは・・・。」
叫び声が響く。届かなかった。
僕は教室を飛び出していた。後ろを振り向くこともせずに、一目散に飛び出していた。全部、思い出してしまった。美鈴が死んだ時のこと、サキが死んだ時のこと。思い出してしまった。
僕はきっと、いつまでもこんなことを続けるのだ。頭の中でぐるぐると思いが巡る。走っていた。どこまでも必死で走って、僕は自分の家に駆け込んだ。封印していたものが全部、溢れ出していた。
健司はどこまで追いかけてきただろう。辛いのは、きっと健司だって同じはずだ。
ノートを綴った。死に物狂いで、感情にまかせてノートを綴った。
このノートは、誰も見ないで欲しい。このノートは、単純な文字で誤魔化して、自分の気持ちを封じ込めるためのすべてだ。
僕はいつまでも僕でありたかった。だから、僕は恋をしたんだ。その恋は、理想的で、永遠で、美しいものであって欲しかった。でも、現実は違った。美鈴が死んで、サキが死んで、結局すべてを失ってしまった。
思い出してしまった記憶を封じ込めるのだ。もし、もう一度このノートを開くことがあったとしても、僕が思い出してしまわないために。
ノートの中の僕と彼女は、雨の日に出会い、そして付き合って、永遠を誓った。天真爛漫な彼女は時に僕を困らせ、時に僕を勇気付けた。そして死んでしまった。それは現実と理想が混ざり合った、物語だった。
夜が明けて朝が来るまで、必死に書き記した。
『教室に差し込む光は、彼女の頬を照らす。その光が反射して、午後の静まり返った教室は明るく、爽やかな空気に包まれる。僕の中で生まれる世界が、頭の中で弾けた。道なき道を素足で歩く感覚。歩き心地の悪い、ふわふわした廊下に立っている錯覚。それは恋だった。僕の目に映る世界を、一気に変えてしまう魔力を持つ。それは、事件でもあり、小さな奇跡でもあった。夢の世界と手を握ることができる権利をつかむ、この手。今まで何も掴めなかったこの両手で、不確かで曖昧な現実にふれることができたならば、僕の世界は真っ白な愛のあるものに変わるだろう。ただ、その世界の彼女はあまりにも美しすぎた。』
純粋なストーリーだった。
そのノートの中の彼女はどこまでも透明で美しい。幸せなストーリーだった。
でも読み進め、最後の一行で絶望はやってくる。
『彼女は死んだ。』
そこでストーリーは終わる。ぷつっと途切れたその一行は、僕を再び絶望のふちへと誘う。
ぴかっと外で雷が鳴った。
数時間後、健司が僕の部屋に入ってきた時見えたのは、一冊のノートと倒れ込んだ僕と、僕を発見した誰かに宛てた一枚のメモ書きだったはずだ。
そのメモ書きにはこう記した。
『僕は死神だ。これ以上、誰かを殺したくない。だから、僕は死ぬ。』
生まれた瞬間に両親が死に、初めて好きになった人も死に、本当に愛した子も死んだ。
僕は死神だ。
その言葉は冷たくて、残酷だ。
僕が死んだら、誰も死なないで済む。なぜ、それに早く気付かなかったのか。そんな思いでいっぱいになった。
雨がざあざあと降りしきっていた。
雨は時に奇跡を生み、時に悲劇を生む。
誰も悲しまない、それだけが僕の救いだった。
このノートは、誰も見ないで欲しい。このノートは、単純な文字で誤魔化して、自分の気持ちを封じ込めるためのすべてだ。
僕はいつまでも僕でありたかった。だから僕は恋をした。
生きる意味が欲しかった。ありふれた幸せを手に入れたかった。人と波長を合わせながら、同じ道を歩いて行きたかった。幸せは、理想を形にしていったら、いつの間にか完成するものだと信じていた。
公園のベンチに座って、じっと景色を眺めてみる。すうっと通り過ぎる爽やかな風があって、木の葉がざわざわと音を立てて揺れる。当たり前に小鳥が空を飛び、当たり前に時間が流れる。平和な風景である。誰の目にも、きっとそんな風景が映るはずだ。
だが、僕の目にはいつもそんな風景に寄り添って、一人の女の子が映った。その子はどこにいても、じっと僕を見つめて、ふいに視界から姿を消す。その子から目を離すと同時に僕は罪悪感に蝕まれる。じっとその子を見つめると、深い悲しみが胸を痛めつける。しだいに僕の呼吸は乱れ、その場に立っていられなくなる。考えれば考えるほど苦しくなり、考えることをやめると、不安で頭の中が真っ白になる。
日々を重なるうちに、僕はどんどん現実から離れていくような錯覚に陥った。無意識のうちに僕の頭は、真実を押し隠していった。怖かった。自分が自分でなくなっていくのが怖くて仕方なかった。
だから僕は、平常心を保つためノートを綴った。
そのノートには、その女の子のことを書き記した。僕と彼女は恋人同士で、僕らは愛し合っていた。ただ、断片的な僕らの話を淡々と書き記した。それが真実か、真実でないかは不確かだった。でも、それを書くことで僕の心は落ち着いた。でたらめでいいから、僕はノートを綴った。
ストーリーを途切れさすわけにはいかなかった。そのストーリーが途切れるということは、僕の人生が終わるということだったから。僕は死に物狂いでノートを綴った。
本当に少しずつ、僕の記憶は蘇っていた。それは、ドミノ崩しのようにゴールに向かって一個一個が倒れていくような感覚だった。
「あの日もお前は、真実を知りたいと俺に言った。」
健司は、俯いた顔を上げ、呟いた。同時に僕も顔を上げる。
「あの日、お前は俺に言った。」
じっと僕を見つめながら、健司はしゃべり始めた。その日の様子が、少しずつ思い出された。
「美鈴は、なぜ死んだのか。」
僕は遠い記憶に身を委ねるようにぽつりと呟いた。
「あまりにも・・・。」
表情を曇らせながら、健司は応える。
「あまりにも、タイミングが悪かったんだ。」
すぅっと息を吸い込んで、健司は僕を見つめる。
「あれは、事故だ。」
訴えかけるように健司は言った。それは、僕を説得させるために放たれた、重苦しい言葉であった。
「事故だ。」
事故だ、その言葉に聞き覚えがある。
その言葉は、何かに追い込まれ、身動きが取れなくなったあの日の僕に健司が言った言葉だ。あの日、とはサキが死んで一ヶ月の月日が流れたある日のことだった。僕は混乱していた。
サキがいなくなって、僕はすべてを失った。そんな気持ちは僕をどん底に陥れた。
そんな僕を勇気付けてくれたのは、美鈴だった。放課後、僕はずっと教室で美鈴がやってくるのを待っていた。僕らだけの秘密の時間。
「リョウスケくん・・・?」
気が付くと、そこには美鈴がいた。暗闇の教室の中、月明かりに照らされて。
不思議な感覚と共に、僕らが付き合っていた頃に時間が戻った気がした。繋がっている気がした。美鈴も、この放課後の教室で僕が来るのを待ってくれていた。そんな一方的な気持ちが湧き出してきた。
僕はギリギリだったのかも知れない。サキが死んでぽっかり空いた隙間を、埋めるために、必死だったのかも知れない。
不安は募って、すべてを駄目にしてしまう。美鈴は確かにそこにいた。僕の目には映っていた。それはあたかも僕に会うためにそこに来たように見えたし、美鈴が来て、僕はどれだけほっとしたことだろう。
「もう一度、やり直そう。」
と僕は言った。サキへの罪悪感は確かにあった。でも、僕は少しでも早く立ち直りたかったんだ。
「うん。」
と美鈴は笑って返す。
頭の中で、僕のストーリーは繋がっていた。そこにあったのは、束の間の幸せ。矛盾とか、ずれを修正するために僕が作り出した幻だ。
そうだ、それは幻だった。
美鈴はもうこの世にいない。僕の目の前にいたのは、僕が頭の中で作り上げた幻だ。
だけど、僕は気付かなかった。気付く余裕なんて無かった。きっと、幻でも良かったのだ。ギリギリだったから、そんな幻にしがみ付いてでも平気な顔をしていたかったんだ。
放課後の教室が好きだった。僕は毎日のように美鈴と会った。美鈴が死んだことを受け入れられなかった僕は、美鈴の幻を頭の中で作り上げて、幻想の世界で彼女としゃべっていた。偽者の幸せで心を落ち着かせて、何もなくなった心を埋めようとしていた。
夜が過ぎると、その魔法は解けた。でも、夜になると美鈴に会える。夜の学校で、僕らはずっとくだらない話を続けた。
取り返しのつかないことになっていた。もう、僕は現実の世界で生きていけなくなっていた。壊れそうな心を、必死に隠そうとしていた。それは、ふとしたことで崩壊しそうで怖かった。
気付いていたのか、本当に気付いていなかったのか。今となっては分からない。あの頃の僕は、ただただ不安定で危なっかしい、そんな道の上を歩いていた。
美鈴と会ってない時間は、生きている心地がしなかった。苦しかった。誰の言葉も耳に入らない、僕に意味を与えるのは美鈴だけだった。
それが幻だと、知ってしまったら、すべてが終わってしまう。すべてが。
「何やってんだよ。」
ある日、暗闇の教室に健司が立っていた。
「健司・・・。」
僕は焦った声を上げた。美鈴と二人でいるところを見られてしまった、と僕は焦った。だが、健司の目は僕をじっと睨み付けたまま、美鈴の方に目を向けることは無かった。その時ようやく僕は現実の世界に引き戻された。気がつくと、その教室に美鈴の姿はなかった。
「美鈴はもう・・・。」
健司は泣き出しそうな顔で、僕に言った。その瞬間、僕の中の世界が壊れ始めた。終わり、が近付いてきている。これは夢の世界じゃない。現実の世界の中で、僕だけが夢を見ているのだ。
言葉が出てこなかった。うすうす僕は感じていたのだ。美鈴がこの世にいないことも、それでも僕は自分を誤魔化し続けていたことを。
いつか分かる日が来る、それに気付いていた。きっかけが必要だった。それは間違っている、と僕を一喝してくれる何かが必要だった。健司に本当の事を言われた時、僕は現実の世界に立っていた。
美鈴がいない、夜の教室に立っていた。
「美鈴は、もう死んだ。」
搾り出すような台詞が、健司からこぼれる。
「もう、やめよう。こんなこと。」
健司は優しく僕に言った。その言葉は、少しだけ僕を落ち着けた。
「もう、やめにしよう。」
落ち着いた声が僕の耳に届く。湧き出す思いはあったものの、妙にその言葉に癒された自分がいた。見失っていた自分が、ちょっとだけ姿を現した。ここは夢の世界じゃない。
「美鈴は、死んだ。」
自分に言い聞かせるように、健司に確認するように僕はぼんやりと言った。
僕は冷静に考えた。
思い返していた。美鈴に好きだと告げたこと。二人のことは秘密にしようって言われたこと。美鈴は死んだと聞いても、信じようとしなかった自分のこと。サキと付き合ってやってほしい、とサキの母親に言われたこと。サキと付き合い始めたときのこと。サキの最後の誕生日のこと。いつかやってくると分かっていたサキの死さえも、信じようとしなかった自分のこと。
そして、思い出した。美鈴から死ぬ前に告げられたこと。
「全部、知ってたのか。」
沈黙のあと、僕は健司に尋ねた。幾分、冷静な声を取り戻していた。
「ああ、知ってた。」
健司は答える。
「美鈴から聞いていた。」
夜の静けさのせいで、その声は教室に響き渡っていた。妙な緊迫感が張り詰める。
「真実を知りたい。」
僕は突発的に健司に突きつけていた。その言葉は、どんな刃物よりも鋭かったかも知れない。知ってはいけないこと、知らないほうがいいこと。そんなことの向こう側を覗き込むような、非常識な言葉だった。
健司は黙り込んでしまった。
「美鈴が死んだと聞かされた前日、僕は美鈴と会った。」
僕は静かにしゃべり始めた。健司はじっと聞いていた。
「いつも通り、この教室で。」
僕は美鈴の幻が立っていた教室の隅に目を向けながら続けた。
「何の変哲もない日だった。」
思い起こすと自然と涙が溢れた。あの日から、少しずつ何かが狂い始めていた。
「別れよう、と美鈴は言った。」
美鈴の弱々しい声が思い出される。泣きそうで居て、それでもって強がった、切ない声。
別れよう、と告げられてもそんなに僕は驚かなかった。むしろ、自分に対する失望感に包まれていた。もっと努力すべきだった。美鈴にもっと好かれるために、伝えなければならないことがたくさんあったのに。別れは、必然的に訪れたんだと僕は思ってしまった。
「うん、分かった。」
と僕は答えた。すぐにでも消えてしまいそうな秘密の関係だったから、別れても何も変わらないことは分かっていた。美鈴も僕も、これまでの生活を続けるだけだ。辛いけれど、仕方のないことだった。
「その次の日、美鈴が死んだと聞かされた。」
涙が止まらなかった。
思い出してはいけない、そんな記憶が蘇って溢れて押さえ切れなかった。
「違う。」
健司の叫び声が聞こえる。しかし、僕には届かなかった。感情が洪水のように襲い掛かってきた。苦しくて、息が出来なくなった。
健司が思いっきり僕の肩を掴む。感覚のなくなった肩は、何の痛みも感じなかった。
「あれは事故だったんだ。あれは・・・。」
叫び声が響く。届かなかった。
僕は教室を飛び出していた。後ろを振り向くこともせずに、一目散に飛び出していた。全部、思い出してしまった。美鈴が死んだ時のこと、サキが死んだ時のこと。思い出してしまった。
僕はきっと、いつまでもこんなことを続けるのだ。頭の中でぐるぐると思いが巡る。走っていた。どこまでも必死で走って、僕は自分の家に駆け込んだ。封印していたものが全部、溢れ出していた。
健司はどこまで追いかけてきただろう。辛いのは、きっと健司だって同じはずだ。
ノートを綴った。死に物狂いで、感情にまかせてノートを綴った。
このノートは、誰も見ないで欲しい。このノートは、単純な文字で誤魔化して、自分の気持ちを封じ込めるためのすべてだ。
僕はいつまでも僕でありたかった。だから、僕は恋をしたんだ。その恋は、理想的で、永遠で、美しいものであって欲しかった。でも、現実は違った。美鈴が死んで、サキが死んで、結局すべてを失ってしまった。
思い出してしまった記憶を封じ込めるのだ。もし、もう一度このノートを開くことがあったとしても、僕が思い出してしまわないために。
ノートの中の僕と彼女は、雨の日に出会い、そして付き合って、永遠を誓った。天真爛漫な彼女は時に僕を困らせ、時に僕を勇気付けた。そして死んでしまった。それは現実と理想が混ざり合った、物語だった。
夜が明けて朝が来るまで、必死に書き記した。
『教室に差し込む光は、彼女の頬を照らす。その光が反射して、午後の静まり返った教室は明るく、爽やかな空気に包まれる。僕の中で生まれる世界が、頭の中で弾けた。道なき道を素足で歩く感覚。歩き心地の悪い、ふわふわした廊下に立っている錯覚。それは恋だった。僕の目に映る世界を、一気に変えてしまう魔力を持つ。それは、事件でもあり、小さな奇跡でもあった。夢の世界と手を握ることができる権利をつかむ、この手。今まで何も掴めなかったこの両手で、不確かで曖昧な現実にふれることができたならば、僕の世界は真っ白な愛のあるものに変わるだろう。ただ、その世界の彼女はあまりにも美しすぎた。』
純粋なストーリーだった。
そのノートの中の彼女はどこまでも透明で美しい。幸せなストーリーだった。
でも読み進め、最後の一行で絶望はやってくる。
『彼女は死んだ。』
そこでストーリーは終わる。ぷつっと途切れたその一行は、僕を再び絶望のふちへと誘う。
ぴかっと外で雷が鳴った。
数時間後、健司が僕の部屋に入ってきた時見えたのは、一冊のノートと倒れ込んだ僕と、僕を発見した誰かに宛てた一枚のメモ書きだったはずだ。
そのメモ書きにはこう記した。
『僕は死神だ。これ以上、誰かを殺したくない。だから、僕は死ぬ。』
生まれた瞬間に両親が死に、初めて好きになった人も死に、本当に愛した子も死んだ。
僕は死神だ。
その言葉は冷たくて、残酷だ。
僕が死んだら、誰も死なないで済む。なぜ、それに早く気付かなかったのか。そんな思いでいっぱいになった。
雨がざあざあと降りしきっていた。
雨は時に奇跡を生み、時に悲劇を生む。
誰も悲しまない、それだけが僕の救いだった。