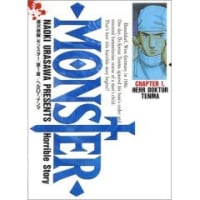12
夕日が落ちる前に、タイムカプセルを彫ろう。
サキは思いついたように笑って、そして言った。
「何十年か後に、またここに来よう。」
僕は心臓をぎゅっと掴まれたように苦しくなった。
またここに来よう、と言う無邪気な言葉が心に刺さった。
僕の不安が、彼女に伝わったのだろうか。
「ずっと、一緒だよね?」
そう不安そうにサキは僕に尋ねた。
「ずっと、一緒だ。」
サキの不安を取り除くように、僕は強く言った。彼女の笑顔が蘇る。
「じゃあ、これを入れよう。」
僕は財布の中から、下手に編み込まれたミサンガを取り出した。
「なに、それ?」
とサキが聞いた。
「誕生日プレゼントに編もうとしてたミサンガ。いくらやってもうまくできなかったから諦めた。」
そう言って、僕は頭を掻いた。
「リョウスケらしいね。」
くすくすと笑って、サキが言う。
「じゃぁ、私は・・・。」
鞄に手を入れながら、サキが言う。
「これを・・・。」
サキが鞄から取り出したのは、表紙に大きく日記帳と書かれた一冊のノートだった。
「なに、それ?」
僕もサキと同じ言葉で尋ねる。
「内緒。」
でも、反応は違った。
「また掘り出した時の、お楽しみってコト。」
サキはそう言って、ふふ、と笑った。
「えぇ~、気になるな。」
僕はノートを見つめながら言った。
「そうだ。」
急にサキは叫んだ。僕の言葉を遮るようなタイミングだった。
「これも入れよう。」
サキは僕があげた一輪のひまわりを手に取った。
「これを最後の一ページに。」
サキはノートの最後の白いページにひまわりを挟んだ。そして、それを押さえつける。
「押し花か。」
僕はそれを見て言う。
「リョウスケも手伝って。」
とサキが言ったので、僕も一緒になって押さえた。
小さなタイムカプセルが完成した。何重にもノートとミサンガを包んで、分かりやすい場所に埋めた。
誰にも掘り返されないような場所に、二人だけの秘密を作った。そんな秘密があるってだけで、どこか特別でそれだけで十分だった気がする。
「楽しみが増えたね。」
サキは無垢な笑顔を浮かべる。
複雑な気持ちながら、僕も思いっきり笑った。
そして、山道を降りていく。二人の秘密を置いて、綺麗な絶景に別れを告げて・・・。
遠くなっていく二人の思い出が夕日に照らされていた。
夜が来る前に、僕らは旅館に辿りついた。
頂上から一時間ほど離れた場所にその旅館はあった。
気品漂う入り口を通って、僕は受付を済ませ、足を進める。
「すごい、かっこいい。」
その雰囲気にひるむことなく、手続きをしていく僕を見て、サキは言った。でも、予約してくれたのも女将に伝えといてくれたのも、斉藤なのであんまり威張れなかった。
でも、思いっきり自分がすべてやったかのように、僕はサキの手を引きながら、部屋へと向かった。計画通りだった。サキの手を引いて、僕は歩く。
「惚れ直しちゃった。」
と言って、サキは僕を見た。
「まあね。」
と頬を掻きながら、僕は笑う。
斉藤に心の中でまた感謝した。
部屋は窓から綺麗な景色が見える立派な和室だった。サキはキラキラした目で、その景色を見つめていた。
僕はサキに近付き、そして後ろからギュッと彼女を抱きしめた。
どこにも行かないでくれ、サキ・・・。
必死に笑って、心で泣いた。
涙を堪えるために、彼女をぎゅっと抱きしめる。
もう、何十年も寄り添って生きてきた妻を抱く、夫のような気持ちだった。
サキ・・・。
時間が止まったのを感じましたか?
僕らのために、世界が少しだけ回るのを止めたことに気付きましたか?
世界は僕らを祝福してくれてる、そう信じている。
遠くまで来たね。
不条理で残酷な現実から離れ、二人だけの特別な時間の中に潜り込んだね。
傍にいれることが、奇跡のように感じる。
ずっと、こんな時間が続けばいいのに。
何度思ったことだろう。
サキは今、どんな気持ちなんだろう。
僕と同じ気持ちでいてくれているだろうか。
どれくらい、君の気持ちに近づけただろうか。僕はどれくらい理解してやれるだろうか。
「もしも、私がいなくなったらどうする?」
ぼそっとサキが呟いた。ドキッとした。心を見透かされているかのようだった。その不安は、ずっと僕の胸の中にあった筈だから。
「探しに行くよ。」
心から、僕は叫ぶ。
「すぐに、探しに行く。」
僕のその言葉に、サキはぱっと笑顔になる。抱きしめた僕の腕を掴んで、サキは振り返った。僕の両腕をぎゅっと握って、サキは僕を見上げる。
目が潤んでいた。今日はあまりにも特別だったから、感情をうまく整理できてなかった。
ようやく、僕は肩の荷を降ろしてサキを見つめる。
もしかしたら、僕の目も潤んでいたかも知れない。
感情が高鳴って、僕らは無意識に泣いていた。嬉しくて、切なくて、僕は泣いた。
始めてサキは自分から僕に唇を寄せた。言葉のない会話は、そして繋がる。
僕が祝える、サキの最初で最後の誕生日が終わる。夜の空に星が散って、ファンタジックな世界が生まれる。サキと二人で見る星は、いつもより輝いていた。
不思議だった。
何もかもが新鮮な二人の時間は、熟年夫婦のように濃厚で、それでいて初恋のようにドキドキした。
一緒に空を見上げて、そして思う。
奇跡はきっと、いつまでも続く。サキは僕の隣にいて、僕はサキを抱きしめている。ずっと、永遠に・・・。
・・・探しに行くよ。
いつかの言葉が僕の頭の中で響いた。はっきりとしてて、力強い言葉。
僕の足は腐ってしまったのだろうか。
何をやってるんだ、自分は。
今すぐ、サキを探しに行くべきだろう。それが、サキとの約束だから。
振り返ってみたら、何もかもが幸せだった。
サキとの時間、埋まっていくピース、目の前の景色。全部、好きだった。
僕は間違ってなんかいなかった。サキと一緒にいれて、僕は本当に幸せだったから。
「もしも、私がいなくなったらどうする?」
未だにサキは、僕に尋ねる。遠くから、僕を呼んでる。
愛している、も今なら嘘っぽく聞こえてしまうかも知れないね。サキ・・・。
あの日、僕が泣いたのは、こんな日がやってくるって分かってたからなんだよ。
何もかも受け入れて、そしてすべてを信じようと決心したけど。僕はまだ大人になりきれない馬鹿な子供だから・・・。うまくいかないことを、受け止められない子供だから。だから、息ができなくなるくらい悲しくなってしまう。
あの日の言葉は、嘘じゃなかった。あの時、サキが消えたら、すぐに僕はサキを探しに走ってただろう。
でも、時間は残酷で、僕の気持ちを変えてしまった。僕の足は完全に止まってしまって、君を追いかけることができなくなってしまった。
おかしいくらい、僕の頭は何も考えられなくなっていたし、体は金縛りにあったみたいに動かなかった。
言い訳ばかりを繰り返す僕は、情けない小さな男だ。サキに嫌われても仕方がない。
僕の隣はぽっかり空いた。ついに来てしまった。覚悟はしていた。でも、やっぱり無理だった。
強くはなれない。正義のヒーローにもなれない。残るのは後悔と、楽しかった思い出だけ。
ただ、それだけだった。
あれから、一年の月日が流れていた。
騒がしい教室の中で、ぽっかりと空いた空席をぼんやり眺めていた。
サキが急に学校に来なくなって、一週間が過ぎようとしていた。
昼休みが終わって、僕は教官室に行った。でも、教師に何を聞いても、生徒のどんな噂を聞いても、本当の事は分かっていた。
覚悟はしていた。ただ、こんな終わりが来るなんて思ってもいなかった。
サキは自分の家から、近くの病院から、いや・・・この街から姿を消した。何も言わずに、サキは消えた。
一緒に歩いた通学路を一人で歩いていると、サキの姿をつい探してしまう。サキの後姿を追いかける日々が、もう来ない。
あんなに夢中だった日々を失って、僕はこれからどう生きていけばいいんだろう。
肩を落として歩いた。サキを最後まで追いかけられなかった自分に、僕は絶望した。サキとの約束を、こんなにも簡単に破ってしまう自分を責めた。
でも、僕には追いかけられなかった。
サキはいつも笑っていた。そんなサキと対等な笑顔を見せられない自分が情けなかった。くるりと振り返って見せる、サキの笑顔。
いつも話のきっかけはサキだった。サキが夢中になってしゃべって、僕がそれに相槌を打つ。
「ねぇ、聞いてる?」
「えっ、あぁ、聞いてるよ。」
「ホント?」
「うん、ホント。」
終着駅の見えない会話。噛み合っているようで、噛み合っていない微妙な会話。
どうでもいい話ばかりだった。
それでも最後は寂しくて、バイバイを言うのが嫌で、僕が話を切ろうとすると、慌ててサキは僕の声を遮った。
「それでね、それでね。」
二度言う、それが時間を延長するおまじない。
結局日は暮れて、真っ暗になって・・・。
サキの言葉を思い出していた。きっとずっと魔法の言葉。
「実はね、私、透明人間になれるんだよ。」
僕も思わず口に出す、
「透明人間になれるんだよ。」
一人暮らしの部屋は、よりいっそう寂しく狭かった。
サキを探しに行きたかった。だけど、それが無駄なことだってことくらい分かっていた。それに、探す当てが全く無かった。
僕は、ネジが外れてぐらぐらになった椅子に力なく腰掛ける。きいっという怪しい音が鳴って、椅子は揺れた。
机の上は綺麗に片付いていて、隅っこに小さな紙が置いてあった。僕はゆっくりとその紙を手に取り、開いた。
「話したいことがあります。」
それはサキの字だった。僕とサキが付き合うことになった日にサキからもらった、呼び出しの手紙。
想いが巡って、同じところをぐるぐると回った。好きだといってくれたサキ、ありがとうと言って泣いたサキ、透明人間になれるんだよ、と笑って言ったサキ・・・。
紙に書かれた文字が、みるみるうちに涙で滲んでいった。
まだまだ、思い出が足りないと思っていた。僕は、単純にサキといることしかできなかったから。でも、悲しくなるには十分だった。悲しみに暮れて、涙を流すには十分すぎた。
僕は、泣いた。
まだ死んだわけじゃないだろ、と自分を叱って、涙は流さずにいたのに。だけど、止まらなかった。
不意打ちだった。
こんなに悲しくなって、息が詰まって、全部消したくなるくらい苦しいなんて、僕には耐えられなかった。
サキにもう一度会いたい。
このまま、さよならだなんて辛すぎる。
サキが僕にかけた魔法が解け始めていた。僕を惑わしたのは、あの言葉だった。
「実はね、私、透明人間になれるんだよ。」
サキはいなくなったんじゃない、どこかに行ったんじゃない。透明人間になっただけだ。ずっと、傍にいる。隣にいる。そんな幻想にすがっていた自分に気付いた。
僕は精一杯、弱々しい手で涙を拭った。
僕は心を落ち着けて、そして深呼吸した。
サキが透明人間になってしまって、本当に消え去ってしまう前に、僕は走り出す。
「探しに行くよ。」
僕は大声で言った。
「すぐに、探しに行く。」
夕日が落ちる前に、タイムカプセルを彫ろう。
サキは思いついたように笑って、そして言った。
「何十年か後に、またここに来よう。」
僕は心臓をぎゅっと掴まれたように苦しくなった。
またここに来よう、と言う無邪気な言葉が心に刺さった。
僕の不安が、彼女に伝わったのだろうか。
「ずっと、一緒だよね?」
そう不安そうにサキは僕に尋ねた。
「ずっと、一緒だ。」
サキの不安を取り除くように、僕は強く言った。彼女の笑顔が蘇る。
「じゃあ、これを入れよう。」
僕は財布の中から、下手に編み込まれたミサンガを取り出した。
「なに、それ?」
とサキが聞いた。
「誕生日プレゼントに編もうとしてたミサンガ。いくらやってもうまくできなかったから諦めた。」
そう言って、僕は頭を掻いた。
「リョウスケらしいね。」
くすくすと笑って、サキが言う。
「じゃぁ、私は・・・。」
鞄に手を入れながら、サキが言う。
「これを・・・。」
サキが鞄から取り出したのは、表紙に大きく日記帳と書かれた一冊のノートだった。
「なに、それ?」
僕もサキと同じ言葉で尋ねる。
「内緒。」
でも、反応は違った。
「また掘り出した時の、お楽しみってコト。」
サキはそう言って、ふふ、と笑った。
「えぇ~、気になるな。」
僕はノートを見つめながら言った。
「そうだ。」
急にサキは叫んだ。僕の言葉を遮るようなタイミングだった。
「これも入れよう。」
サキは僕があげた一輪のひまわりを手に取った。
「これを最後の一ページに。」
サキはノートの最後の白いページにひまわりを挟んだ。そして、それを押さえつける。
「押し花か。」
僕はそれを見て言う。
「リョウスケも手伝って。」
とサキが言ったので、僕も一緒になって押さえた。
小さなタイムカプセルが完成した。何重にもノートとミサンガを包んで、分かりやすい場所に埋めた。
誰にも掘り返されないような場所に、二人だけの秘密を作った。そんな秘密があるってだけで、どこか特別でそれだけで十分だった気がする。
「楽しみが増えたね。」
サキは無垢な笑顔を浮かべる。
複雑な気持ちながら、僕も思いっきり笑った。
そして、山道を降りていく。二人の秘密を置いて、綺麗な絶景に別れを告げて・・・。
遠くなっていく二人の思い出が夕日に照らされていた。
夜が来る前に、僕らは旅館に辿りついた。
頂上から一時間ほど離れた場所にその旅館はあった。
気品漂う入り口を通って、僕は受付を済ませ、足を進める。
「すごい、かっこいい。」
その雰囲気にひるむことなく、手続きをしていく僕を見て、サキは言った。でも、予約してくれたのも女将に伝えといてくれたのも、斉藤なのであんまり威張れなかった。
でも、思いっきり自分がすべてやったかのように、僕はサキの手を引きながら、部屋へと向かった。計画通りだった。サキの手を引いて、僕は歩く。
「惚れ直しちゃった。」
と言って、サキは僕を見た。
「まあね。」
と頬を掻きながら、僕は笑う。
斉藤に心の中でまた感謝した。
部屋は窓から綺麗な景色が見える立派な和室だった。サキはキラキラした目で、その景色を見つめていた。
僕はサキに近付き、そして後ろからギュッと彼女を抱きしめた。
どこにも行かないでくれ、サキ・・・。
必死に笑って、心で泣いた。
涙を堪えるために、彼女をぎゅっと抱きしめる。
もう、何十年も寄り添って生きてきた妻を抱く、夫のような気持ちだった。
サキ・・・。
時間が止まったのを感じましたか?
僕らのために、世界が少しだけ回るのを止めたことに気付きましたか?
世界は僕らを祝福してくれてる、そう信じている。
遠くまで来たね。
不条理で残酷な現実から離れ、二人だけの特別な時間の中に潜り込んだね。
傍にいれることが、奇跡のように感じる。
ずっと、こんな時間が続けばいいのに。
何度思ったことだろう。
サキは今、どんな気持ちなんだろう。
僕と同じ気持ちでいてくれているだろうか。
どれくらい、君の気持ちに近づけただろうか。僕はどれくらい理解してやれるだろうか。
「もしも、私がいなくなったらどうする?」
ぼそっとサキが呟いた。ドキッとした。心を見透かされているかのようだった。その不安は、ずっと僕の胸の中にあった筈だから。
「探しに行くよ。」
心から、僕は叫ぶ。
「すぐに、探しに行く。」
僕のその言葉に、サキはぱっと笑顔になる。抱きしめた僕の腕を掴んで、サキは振り返った。僕の両腕をぎゅっと握って、サキは僕を見上げる。
目が潤んでいた。今日はあまりにも特別だったから、感情をうまく整理できてなかった。
ようやく、僕は肩の荷を降ろしてサキを見つめる。
もしかしたら、僕の目も潤んでいたかも知れない。
感情が高鳴って、僕らは無意識に泣いていた。嬉しくて、切なくて、僕は泣いた。
始めてサキは自分から僕に唇を寄せた。言葉のない会話は、そして繋がる。
僕が祝える、サキの最初で最後の誕生日が終わる。夜の空に星が散って、ファンタジックな世界が生まれる。サキと二人で見る星は、いつもより輝いていた。
不思議だった。
何もかもが新鮮な二人の時間は、熟年夫婦のように濃厚で、それでいて初恋のようにドキドキした。
一緒に空を見上げて、そして思う。
奇跡はきっと、いつまでも続く。サキは僕の隣にいて、僕はサキを抱きしめている。ずっと、永遠に・・・。
・・・探しに行くよ。
いつかの言葉が僕の頭の中で響いた。はっきりとしてて、力強い言葉。
僕の足は腐ってしまったのだろうか。
何をやってるんだ、自分は。
今すぐ、サキを探しに行くべきだろう。それが、サキとの約束だから。
振り返ってみたら、何もかもが幸せだった。
サキとの時間、埋まっていくピース、目の前の景色。全部、好きだった。
僕は間違ってなんかいなかった。サキと一緒にいれて、僕は本当に幸せだったから。
「もしも、私がいなくなったらどうする?」
未だにサキは、僕に尋ねる。遠くから、僕を呼んでる。
愛している、も今なら嘘っぽく聞こえてしまうかも知れないね。サキ・・・。
あの日、僕が泣いたのは、こんな日がやってくるって分かってたからなんだよ。
何もかも受け入れて、そしてすべてを信じようと決心したけど。僕はまだ大人になりきれない馬鹿な子供だから・・・。うまくいかないことを、受け止められない子供だから。だから、息ができなくなるくらい悲しくなってしまう。
あの日の言葉は、嘘じゃなかった。あの時、サキが消えたら、すぐに僕はサキを探しに走ってただろう。
でも、時間は残酷で、僕の気持ちを変えてしまった。僕の足は完全に止まってしまって、君を追いかけることができなくなってしまった。
おかしいくらい、僕の頭は何も考えられなくなっていたし、体は金縛りにあったみたいに動かなかった。
言い訳ばかりを繰り返す僕は、情けない小さな男だ。サキに嫌われても仕方がない。
僕の隣はぽっかり空いた。ついに来てしまった。覚悟はしていた。でも、やっぱり無理だった。
強くはなれない。正義のヒーローにもなれない。残るのは後悔と、楽しかった思い出だけ。
ただ、それだけだった。
あれから、一年の月日が流れていた。
騒がしい教室の中で、ぽっかりと空いた空席をぼんやり眺めていた。
サキが急に学校に来なくなって、一週間が過ぎようとしていた。
昼休みが終わって、僕は教官室に行った。でも、教師に何を聞いても、生徒のどんな噂を聞いても、本当の事は分かっていた。
覚悟はしていた。ただ、こんな終わりが来るなんて思ってもいなかった。
サキは自分の家から、近くの病院から、いや・・・この街から姿を消した。何も言わずに、サキは消えた。
一緒に歩いた通学路を一人で歩いていると、サキの姿をつい探してしまう。サキの後姿を追いかける日々が、もう来ない。
あんなに夢中だった日々を失って、僕はこれからどう生きていけばいいんだろう。
肩を落として歩いた。サキを最後まで追いかけられなかった自分に、僕は絶望した。サキとの約束を、こんなにも簡単に破ってしまう自分を責めた。
でも、僕には追いかけられなかった。
サキはいつも笑っていた。そんなサキと対等な笑顔を見せられない自分が情けなかった。くるりと振り返って見せる、サキの笑顔。
いつも話のきっかけはサキだった。サキが夢中になってしゃべって、僕がそれに相槌を打つ。
「ねぇ、聞いてる?」
「えっ、あぁ、聞いてるよ。」
「ホント?」
「うん、ホント。」
終着駅の見えない会話。噛み合っているようで、噛み合っていない微妙な会話。
どうでもいい話ばかりだった。
それでも最後は寂しくて、バイバイを言うのが嫌で、僕が話を切ろうとすると、慌ててサキは僕の声を遮った。
「それでね、それでね。」
二度言う、それが時間を延長するおまじない。
結局日は暮れて、真っ暗になって・・・。
サキの言葉を思い出していた。きっとずっと魔法の言葉。
「実はね、私、透明人間になれるんだよ。」
僕も思わず口に出す、
「透明人間になれるんだよ。」
一人暮らしの部屋は、よりいっそう寂しく狭かった。
サキを探しに行きたかった。だけど、それが無駄なことだってことくらい分かっていた。それに、探す当てが全く無かった。
僕は、ネジが外れてぐらぐらになった椅子に力なく腰掛ける。きいっという怪しい音が鳴って、椅子は揺れた。
机の上は綺麗に片付いていて、隅っこに小さな紙が置いてあった。僕はゆっくりとその紙を手に取り、開いた。
「話したいことがあります。」
それはサキの字だった。僕とサキが付き合うことになった日にサキからもらった、呼び出しの手紙。
想いが巡って、同じところをぐるぐると回った。好きだといってくれたサキ、ありがとうと言って泣いたサキ、透明人間になれるんだよ、と笑って言ったサキ・・・。
紙に書かれた文字が、みるみるうちに涙で滲んでいった。
まだまだ、思い出が足りないと思っていた。僕は、単純にサキといることしかできなかったから。でも、悲しくなるには十分だった。悲しみに暮れて、涙を流すには十分すぎた。
僕は、泣いた。
まだ死んだわけじゃないだろ、と自分を叱って、涙は流さずにいたのに。だけど、止まらなかった。
不意打ちだった。
こんなに悲しくなって、息が詰まって、全部消したくなるくらい苦しいなんて、僕には耐えられなかった。
サキにもう一度会いたい。
このまま、さよならだなんて辛すぎる。
サキが僕にかけた魔法が解け始めていた。僕を惑わしたのは、あの言葉だった。
「実はね、私、透明人間になれるんだよ。」
サキはいなくなったんじゃない、どこかに行ったんじゃない。透明人間になっただけだ。ずっと、傍にいる。隣にいる。そんな幻想にすがっていた自分に気付いた。
僕は精一杯、弱々しい手で涙を拭った。
僕は心を落ち着けて、そして深呼吸した。
サキが透明人間になってしまって、本当に消え去ってしまう前に、僕は走り出す。
「探しに行くよ。」
僕は大声で言った。
「すぐに、探しに行く。」