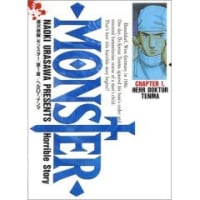13
サキの居場所は意外にも簡単に見つかった。
南ヶ丘病院という文字を見つけたのは、無造作に教官室の担任の机の上に置いてあった一枚のプリントだった。
担任の先生が、何度か病院に見舞いに行っていることは知っていた。だが、そのことは生徒には教えないで欲しいとサキの両親が頼んだらしい。僕にさえも、どこにサキが入院しているのか教えてくれなかった。
居場所を知った次の日、僕は学校を休んだ。それはもちろん、サキに会いに行くためだ。
きっと、サキは喜んでくれる、そんな気持ちが僕を突き動かせた。
僕は学校とは正反対の道を、いつもなら授業を受けている時間に早足で歩いた。
気持ちは怖ろしいほど焦っていた。
急がないと・・・。
心臓の鼓動はみるみるうちに早くなっていった。
「リョウスケ。」
僕の足を止めたのは、背後から聞こえてきた僕を呼ぶ声だった。ドキッとして振り返ってみると、そこにはクラスメイトの健司の姿があった。
「ケンジ・・・?」
思わず僕は声を漏らす。
「何やってんだよ、学校があるだろ。」
僕は健司の目を見ずにつぶやく。
「それは、こっちのセリフだよ。」
すぐに健司の言葉が返ってきた。彼の目は鋭く、僕の顔をキッと睨んでいた。
「どこに行くつもりだ?」
健司は僕に尋ねる。
「どこだって、いいだろ。」
投げ捨てるように僕は言う。無視して僕は後ろを向いた。そして足を進めた。
「行ったって無駄だぞ。」
大きな声で健司は叫んだ。僕はそれでも足を進める。
「リョウスケ!!」
健司が叫ぶ。だが、健司の言葉も聞こえないくらい、僕はサキの事で頭が一杯だった。
早く会いたい、それが約束だから。
健司の言葉はそんな僕には届かなかった。
「サキは死んだんだ。」
僕に届くような大声が響いた。僕と健司の距離は、その言葉がギリギリ届くほどだった。僕は足を止めた。
「死んだんだよ。」
僕は振り返る、そして健司に近付く。
「何だと。」
僕は声にならない声を絞り出した。
「サキが死んだって、今、連絡があった。」
真剣な表情で、健司は言った。
「嘘だ。」
咄嗟に出ていた言葉は、僕を落ち着かせるためのギリギリの言葉だった。健司の目が少し悲しく光って、それでもしっかり見開いて僕を見る。
「嘘じゃない。」
健司は苦しそうに言葉を吐き出した。
「今、校長がクラスに説明しに来た。」
冷静に健司は説明する。
「サキの親も、今学校に来てる。」
僕は、自分の体が震え出していることに気付いた。
「サキの母さんが、リョウスケに会いたいって言ってる。」
淡々と健司は話した。
「行こう。」
健司が手を差し出した。だけど僕は、体が動かなかった。
「嘘だ。」
それしか、僕の口からは出てこなかった。
「しっかりしろ、リョウスケ。」
健司が僕の肩を掴んだ。でも、僕はリョウスケの手を突き放した。
きっと、健司は知ってたんだろう。僕がサキと付き合い始めて、健司と遊ぶことは全くなくなったから。どれだけ僕がサキに夢中で、どれだけ大事だったのかを。
あれから僕は健司の遊びの誘いを断り続け、学校以外で会うこともなくなった。
それでも健司は何も言わなかった。
きっと、健司は変わってしまった僕のことを嫌いになってしまっただろう、とずっと思っていた。友達じゃなくなったとばかり思っていた。だけど、きっと健司は一番僕を心配してくれていたんだ。
だけど、その優しさも、今の僕には届かなかった。
「放って置いてくれ。」
僕は叫んだ。健司の言葉を理解しても、それを信じたくなかった。僕はもう一度走り出そうとしたが、僕の手を健司が掴んで前に進めなかった。
「放せよ。」
健司の目を見ずに言う。
「落ち着け、リョウスケ。」
必死に叫ぶ健司の言葉も、僕には何の意味も持たない。
「どこに行くんだよ。」
健司が僕の手を放して言う。
「サキに会いに行く。」
何のためらいもなく、僕は答える。そして、健司から目をそらした。
「そんなことしても、きっとサキは喜ばないよ。」
健司の言葉に、僕の足は止まる。
「サ・・・、、、」
声が震える。喋りたくても、うまく言葉が出ない。健司は伸ばした手を下ろして、僕を見た。
「サキとさ、約束したんだよ。」
どんどん震えが酷くなって、情けない声が僕の口から溢れた。
「サキがいなくなったら、すぐに探しに行くって。」
目が涙で潤む。
「分かってた。」
すうっと息を吸い込んで、震える声を落ち着かせてしゃべった。
「こんな日が来るって分かってた、ずっと前から。」
また僕は逃げようとしている。そのことに気付いたから、僕の頭は少しだけ状況を理解した。
「サキとの約束、守れなかったな。」
自然と溢れ出る涙を拭うこともせずに、僕はぼんやりとつぶやく。
健司はかける言葉が見つからないのか、ただ黙り込んでしまった。
不意に襲ってきた後悔と悲しみ。息をすることが精一杯になるくらい、僕は苦しくなった。
「大丈夫か?リョウスケ。」
健司が僕に言う。
「ああ、大丈夫だ。」
大丈夫なわけなかったけど、僕は裏腹な言葉を吐き出した。
「ごめん、一人にさせてくれ。」
僕は健司に言った。健司は心配そうな顔をしながら、僕を見つめる。
「分かった・・・だけど。」
健司はちょっと俯いて、そして再び僕を見た。
「これからは何かあったら、すぐに俺に相談しろよ。」
そう言って、ゆっくり健司は僕から遠ざかって行った。それ以上、何も言わずに。
中学生の頃、僕には気軽に話し合える友達がいなかった。遊んでいる時間がなかったし、友達を作っている余裕なんてなかった。学校にいる間も塾でもずっと勉強して、そして朝は仕事に没頭する。
だから、高校に入って出来た友達にも、僕は素直な気持ちを打ち明けれなかった。
だけど、今考えたら、僕はたくさんの人に恵まれていた。美鈴やサキだけじゃない。もっと、友達にすがって生きてけば良かった。
誰にも何も相談せずに、自分で抱え込むよりも先に。
健司の優しさが、ちょっとだけ僕の痛みを和らげた。それでも、真実を知ることが怖くて、学校に行けなかった。
僕はそれから、家に篭ってしまった。
数日後。サキの葬式は行われた。
だけど、僕は出席しなかった。
サキの死を理解できてないわけではなかった。でも、ほんの少しの何かが、それを拒否していた。だからこそ、葬式に出ることはできなかった。
いつか、後悔することは分かっていても、サキの最期を見届けることはできなかった。
何故だろう。あんなに覚悟していて、あんなに分かっていたのに。初めから、サキが死ぬってこと、分かっていたのに。それなのに、涙は止まらなかったし、ずっと眠れない日々が続いた。
何もする気に、ならなかった。
暗闇の中の生活は続く。
誰も入り込むことができない世界に、埋もれる。死んだように生きた。
無意味という色に毎日は染まっていく。
ただ何の引っかかりも、救いもないまま僕は不登校になってしまった。
逃げて逃げて、それでも心の変化はなく。苦しみを飲み込んで、また今日も泣いている。
壁に頭をぶつけても、痛みが跳ね返ってこない。
何かを吐き出しても、全部をからっぽにしても、また悲しみで埋まっていった。
繰り返しの日々、それでも生きた。
明日世界が終わってしまうことを願って、硬直して自分を殴れない手で今を生き延びた。
サキの夢ばっかり見るから、僕は眠るのをやめた。頭が割れるように痛くなったら、意識を飛ばすように僕は眠った。目覚めて体を起こそうとすると、体をうまくコントロールできずにその場に倒れ込んだ。
こんな生活がいつまで続くんだろうと、僕は何度か考えた。
でも、立ち上がることはしなかった。
カーテンを開けて、外を見ても、この部屋の世界となんら変わることがない。そこに、サキがいないから、どこにいたって同じだ。
何も起こらない、不気味な生活は続く。
夏がやってきた。陽の光で、ちょっとだけ僕の中の世界が明るくなった。
夏が終わると、長い夜がやってくる。それが分かりきっていた今年の夏は、恐ろしいほど凍り付いていて、暑さもまるで感じなかった。
太陽は心の奥までは照らしてくれなかったし、暇な長い夏は、この胸の孤独を無情に膨らますばかりだった。通り雨が降った日は、遠くで揺れる陽炎を眺め、晴天の日は、遠くでぼやける蜃気楼をぼんやり眺めた。
不規則に通り過ぎる人の流れは、まだこの世界が回っている紛れもない証拠になっていて、止まりきっている自分の世界との矛盾に頭を痛めつけられる。
ただ、意味も無く進み続ける時計の針と、カレンダーの日付だけが、僕を狂わせた。
誰もいない部屋の中で、僕は見上げた。今日は何日なのか、何曜日なのか、そんなことは今の自分には何の意味も持たないことだったが、ただ一つだけ心に引っかかることがあった。
僕は思い出した。
明日が、サキの誕生日だということに。
もう何も考えられなくなった頭で僕は考えた。遠い過去のことのように思い出される去年の夏のこと、あの日に誓った約束・・・そして変わってしまった自分のことを。
サキに会いたい、だけど会えない。
おかしくなっていく自分を、しだいに僕は見失っていく。もうすぐサキの誕生日がやって来る。
日が暮れて、翌日。
「何も聞かずに、僕をもう一度あの場所へ連れて行ってください。」
それは、僕が斉藤に言う、最後のワガママだった。
「お願いします。」
僕の気持ちが斉藤に届いたのか、はたまた斉藤がすべてを悟ったのか、すぐに彼は駆けつけてくれた。
僕は車に飛び乗った。
デカイ音を立てて、バスのエンジンがかかる。
去年はサキと二人だったバスの席は、寂しく広かった。僕は助手席から後ろを振り返った。サキの姿なんてあるはずないのに、僕はそこに誰かを探していた。
あの日の思い出は、幻のようにフラッシュバックされていた。
「真実を受け止めるのは、辛いだろう。」
ハンドルを握りながら、斉藤は僕に言った。僕は何も答えられなかった。
「俺は、お前が心配だ。」
ぼそっと彼はつぶやく。僕が何かに追われ、そして何かから逃げようとしていること、斉藤にはすべてバレていたんだと気付く。
山道を砂利を踏みながら進んでいくバスは、ガタガタ大きく揺れた。
「今なら、まだ引き返せるぞ。」
説得するかのように、斉藤は僕に言った。
結局、全部自分のためだった。辿ってきた道をもう一度確かめようとしていることも、自分の後姿の幻を必死で追いかけようとしていることも。
真実を受け止めるのが怖くて、まだ僕は過去にすがっている。
サキはもうこの世にいないというのに。
僕は「お願いします。」を繰り返した。
「連れて行って下さい。」
頭を大きく下げる。
もう、僕が普通じゃなくなっていること、斉藤は気付いている。だけど、引き返すことなく、バスはどんどん進んでいった。
サキと一緒だったあの日はあっという間だった時間が、無限に長く感じる。
「あそこにキジがいたんですよ。」
僕は指差して言った。
「それが、すごく綺麗で。」
無理に僕は微笑む。チクリと胸が痛む。
「斉藤さんも見ていましたか?」
僕の声は、バスの中にむなしく響いた。斉藤は何も答えずに、悲しそうな顔を浮かべながら、ハンドルを切った。
無意識に自分が涙を流していたことも、笑顔が引きつっていた事も、斉藤に見られてしまっていた。
バスは僕を乗せて、あの場所へと進んでいく・・・。
サキの居場所は意外にも簡単に見つかった。
南ヶ丘病院という文字を見つけたのは、無造作に教官室の担任の机の上に置いてあった一枚のプリントだった。
担任の先生が、何度か病院に見舞いに行っていることは知っていた。だが、そのことは生徒には教えないで欲しいとサキの両親が頼んだらしい。僕にさえも、どこにサキが入院しているのか教えてくれなかった。
居場所を知った次の日、僕は学校を休んだ。それはもちろん、サキに会いに行くためだ。
きっと、サキは喜んでくれる、そんな気持ちが僕を突き動かせた。
僕は学校とは正反対の道を、いつもなら授業を受けている時間に早足で歩いた。
気持ちは怖ろしいほど焦っていた。
急がないと・・・。
心臓の鼓動はみるみるうちに早くなっていった。
「リョウスケ。」
僕の足を止めたのは、背後から聞こえてきた僕を呼ぶ声だった。ドキッとして振り返ってみると、そこにはクラスメイトの健司の姿があった。
「ケンジ・・・?」
思わず僕は声を漏らす。
「何やってんだよ、学校があるだろ。」
僕は健司の目を見ずにつぶやく。
「それは、こっちのセリフだよ。」
すぐに健司の言葉が返ってきた。彼の目は鋭く、僕の顔をキッと睨んでいた。
「どこに行くつもりだ?」
健司は僕に尋ねる。
「どこだって、いいだろ。」
投げ捨てるように僕は言う。無視して僕は後ろを向いた。そして足を進めた。
「行ったって無駄だぞ。」
大きな声で健司は叫んだ。僕はそれでも足を進める。
「リョウスケ!!」
健司が叫ぶ。だが、健司の言葉も聞こえないくらい、僕はサキの事で頭が一杯だった。
早く会いたい、それが約束だから。
健司の言葉はそんな僕には届かなかった。
「サキは死んだんだ。」
僕に届くような大声が響いた。僕と健司の距離は、その言葉がギリギリ届くほどだった。僕は足を止めた。
「死んだんだよ。」
僕は振り返る、そして健司に近付く。
「何だと。」
僕は声にならない声を絞り出した。
「サキが死んだって、今、連絡があった。」
真剣な表情で、健司は言った。
「嘘だ。」
咄嗟に出ていた言葉は、僕を落ち着かせるためのギリギリの言葉だった。健司の目が少し悲しく光って、それでもしっかり見開いて僕を見る。
「嘘じゃない。」
健司は苦しそうに言葉を吐き出した。
「今、校長がクラスに説明しに来た。」
冷静に健司は説明する。
「サキの親も、今学校に来てる。」
僕は、自分の体が震え出していることに気付いた。
「サキの母さんが、リョウスケに会いたいって言ってる。」
淡々と健司は話した。
「行こう。」
健司が手を差し出した。だけど僕は、体が動かなかった。
「嘘だ。」
それしか、僕の口からは出てこなかった。
「しっかりしろ、リョウスケ。」
健司が僕の肩を掴んだ。でも、僕はリョウスケの手を突き放した。
きっと、健司は知ってたんだろう。僕がサキと付き合い始めて、健司と遊ぶことは全くなくなったから。どれだけ僕がサキに夢中で、どれだけ大事だったのかを。
あれから僕は健司の遊びの誘いを断り続け、学校以外で会うこともなくなった。
それでも健司は何も言わなかった。
きっと、健司は変わってしまった僕のことを嫌いになってしまっただろう、とずっと思っていた。友達じゃなくなったとばかり思っていた。だけど、きっと健司は一番僕を心配してくれていたんだ。
だけど、その優しさも、今の僕には届かなかった。
「放って置いてくれ。」
僕は叫んだ。健司の言葉を理解しても、それを信じたくなかった。僕はもう一度走り出そうとしたが、僕の手を健司が掴んで前に進めなかった。
「放せよ。」
健司の目を見ずに言う。
「落ち着け、リョウスケ。」
必死に叫ぶ健司の言葉も、僕には何の意味も持たない。
「どこに行くんだよ。」
健司が僕の手を放して言う。
「サキに会いに行く。」
何のためらいもなく、僕は答える。そして、健司から目をそらした。
「そんなことしても、きっとサキは喜ばないよ。」
健司の言葉に、僕の足は止まる。
「サ・・・、、、」
声が震える。喋りたくても、うまく言葉が出ない。健司は伸ばした手を下ろして、僕を見た。
「サキとさ、約束したんだよ。」
どんどん震えが酷くなって、情けない声が僕の口から溢れた。
「サキがいなくなったら、すぐに探しに行くって。」
目が涙で潤む。
「分かってた。」
すうっと息を吸い込んで、震える声を落ち着かせてしゃべった。
「こんな日が来るって分かってた、ずっと前から。」
また僕は逃げようとしている。そのことに気付いたから、僕の頭は少しだけ状況を理解した。
「サキとの約束、守れなかったな。」
自然と溢れ出る涙を拭うこともせずに、僕はぼんやりとつぶやく。
健司はかける言葉が見つからないのか、ただ黙り込んでしまった。
不意に襲ってきた後悔と悲しみ。息をすることが精一杯になるくらい、僕は苦しくなった。
「大丈夫か?リョウスケ。」
健司が僕に言う。
「ああ、大丈夫だ。」
大丈夫なわけなかったけど、僕は裏腹な言葉を吐き出した。
「ごめん、一人にさせてくれ。」
僕は健司に言った。健司は心配そうな顔をしながら、僕を見つめる。
「分かった・・・だけど。」
健司はちょっと俯いて、そして再び僕を見た。
「これからは何かあったら、すぐに俺に相談しろよ。」
そう言って、ゆっくり健司は僕から遠ざかって行った。それ以上、何も言わずに。
中学生の頃、僕には気軽に話し合える友達がいなかった。遊んでいる時間がなかったし、友達を作っている余裕なんてなかった。学校にいる間も塾でもずっと勉強して、そして朝は仕事に没頭する。
だから、高校に入って出来た友達にも、僕は素直な気持ちを打ち明けれなかった。
だけど、今考えたら、僕はたくさんの人に恵まれていた。美鈴やサキだけじゃない。もっと、友達にすがって生きてけば良かった。
誰にも何も相談せずに、自分で抱え込むよりも先に。
健司の優しさが、ちょっとだけ僕の痛みを和らげた。それでも、真実を知ることが怖くて、学校に行けなかった。
僕はそれから、家に篭ってしまった。
数日後。サキの葬式は行われた。
だけど、僕は出席しなかった。
サキの死を理解できてないわけではなかった。でも、ほんの少しの何かが、それを拒否していた。だからこそ、葬式に出ることはできなかった。
いつか、後悔することは分かっていても、サキの最期を見届けることはできなかった。
何故だろう。あんなに覚悟していて、あんなに分かっていたのに。初めから、サキが死ぬってこと、分かっていたのに。それなのに、涙は止まらなかったし、ずっと眠れない日々が続いた。
何もする気に、ならなかった。
暗闇の中の生活は続く。
誰も入り込むことができない世界に、埋もれる。死んだように生きた。
無意味という色に毎日は染まっていく。
ただ何の引っかかりも、救いもないまま僕は不登校になってしまった。
逃げて逃げて、それでも心の変化はなく。苦しみを飲み込んで、また今日も泣いている。
壁に頭をぶつけても、痛みが跳ね返ってこない。
何かを吐き出しても、全部をからっぽにしても、また悲しみで埋まっていった。
繰り返しの日々、それでも生きた。
明日世界が終わってしまうことを願って、硬直して自分を殴れない手で今を生き延びた。
サキの夢ばっかり見るから、僕は眠るのをやめた。頭が割れるように痛くなったら、意識を飛ばすように僕は眠った。目覚めて体を起こそうとすると、体をうまくコントロールできずにその場に倒れ込んだ。
こんな生活がいつまで続くんだろうと、僕は何度か考えた。
でも、立ち上がることはしなかった。
カーテンを開けて、外を見ても、この部屋の世界となんら変わることがない。そこに、サキがいないから、どこにいたって同じだ。
何も起こらない、不気味な生活は続く。
夏がやってきた。陽の光で、ちょっとだけ僕の中の世界が明るくなった。
夏が終わると、長い夜がやってくる。それが分かりきっていた今年の夏は、恐ろしいほど凍り付いていて、暑さもまるで感じなかった。
太陽は心の奥までは照らしてくれなかったし、暇な長い夏は、この胸の孤独を無情に膨らますばかりだった。通り雨が降った日は、遠くで揺れる陽炎を眺め、晴天の日は、遠くでぼやける蜃気楼をぼんやり眺めた。
不規則に通り過ぎる人の流れは、まだこの世界が回っている紛れもない証拠になっていて、止まりきっている自分の世界との矛盾に頭を痛めつけられる。
ただ、意味も無く進み続ける時計の針と、カレンダーの日付だけが、僕を狂わせた。
誰もいない部屋の中で、僕は見上げた。今日は何日なのか、何曜日なのか、そんなことは今の自分には何の意味も持たないことだったが、ただ一つだけ心に引っかかることがあった。
僕は思い出した。
明日が、サキの誕生日だということに。
もう何も考えられなくなった頭で僕は考えた。遠い過去のことのように思い出される去年の夏のこと、あの日に誓った約束・・・そして変わってしまった自分のことを。
サキに会いたい、だけど会えない。
おかしくなっていく自分を、しだいに僕は見失っていく。もうすぐサキの誕生日がやって来る。
日が暮れて、翌日。
「何も聞かずに、僕をもう一度あの場所へ連れて行ってください。」
それは、僕が斉藤に言う、最後のワガママだった。
「お願いします。」
僕の気持ちが斉藤に届いたのか、はたまた斉藤がすべてを悟ったのか、すぐに彼は駆けつけてくれた。
僕は車に飛び乗った。
デカイ音を立てて、バスのエンジンがかかる。
去年はサキと二人だったバスの席は、寂しく広かった。僕は助手席から後ろを振り返った。サキの姿なんてあるはずないのに、僕はそこに誰かを探していた。
あの日の思い出は、幻のようにフラッシュバックされていた。
「真実を受け止めるのは、辛いだろう。」
ハンドルを握りながら、斉藤は僕に言った。僕は何も答えられなかった。
「俺は、お前が心配だ。」
ぼそっと彼はつぶやく。僕が何かに追われ、そして何かから逃げようとしていること、斉藤にはすべてバレていたんだと気付く。
山道を砂利を踏みながら進んでいくバスは、ガタガタ大きく揺れた。
「今なら、まだ引き返せるぞ。」
説得するかのように、斉藤は僕に言った。
結局、全部自分のためだった。辿ってきた道をもう一度確かめようとしていることも、自分の後姿の幻を必死で追いかけようとしていることも。
真実を受け止めるのが怖くて、まだ僕は過去にすがっている。
サキはもうこの世にいないというのに。
僕は「お願いします。」を繰り返した。
「連れて行って下さい。」
頭を大きく下げる。
もう、僕が普通じゃなくなっていること、斉藤は気付いている。だけど、引き返すことなく、バスはどんどん進んでいった。
サキと一緒だったあの日はあっという間だった時間が、無限に長く感じる。
「あそこにキジがいたんですよ。」
僕は指差して言った。
「それが、すごく綺麗で。」
無理に僕は微笑む。チクリと胸が痛む。
「斉藤さんも見ていましたか?」
僕の声は、バスの中にむなしく響いた。斉藤は何も答えずに、悲しそうな顔を浮かべながら、ハンドルを切った。
無意識に自分が涙を流していたことも、笑顔が引きつっていた事も、斉藤に見られてしまっていた。
バスは僕を乗せて、あの場所へと進んでいく・・・。