場六の手七(ばろくのてしち)
水戸黄門に出てくる“風車の弥七”のことではありません。
もちろん“うっかり八兵衛”とは、全く関係ありません。
・・・すっきりしたところで、説明に入りましょう。
子供の頃、花札をした。
おばあちゃんもお母ちゃんもお父ちゃんも僕も四角い座布団を挟んで熱くなった。
2人で行う時は、場八の手十。
3人で行う時は、場六の手七。
4人で行う時は、場八の手五。
・・・だった。
3人の場合は場六の手七で、こうやった・・・。
まず親が、すべての花札を切って、各人に裏向けに手札を7枚、場に表向けに6枚セットし、残りの多くの札を裏向けで中央に置く(山)。
場に6枚、手札に7枚だから・・・ばろくのてしち。
各人順番に山から一枚札をとる。
その札と場にある札が同種の札だと、場からその札をとって自分のものとして、自分の前に置く(手札とは別とする、この時手札は1枚減ることになる)。
各人順番に山から一枚札をとったとき、その札と同種の札が場にない時は、その取った札は場に置いておく。(手札は減らない。)
この作業をすべての人の手札が無くなるまで行う。
最後に、すべての取り札の組み合わせを考える。
花札の一枚一枚には、点数があった。
0点、5点、10点、20点の4種類。
派手で綺麗な絵柄は点数が高かった。
勝敗は、取った札の総点数だけではなく、“役(やく)”の点数のやりとりの結果、最終的な順位が決まった。
役には以下のものがった。
赤タン 10点
青タン 10点
猪鹿蝶 10点
梅松桜 20点
月見に一杯 10点
花見に一杯 10点
ふじ 20点
きり 20点
他
青タンは、殴られた時できる青タンではない。
青色の短冊がついた札3枚(5点×3枚)が揃ったときの役である。
青タンの役点は10点だから、3枚の15点と合わせて25点と計算した。
結果の総合点を書き、そのゲームを数回戦行い順位を決めた。
これは龍神の方式ではないと思うけど、我が家だけのルールだったのか???
このルールは全国的なのか?
花札ゲーム現代版こいこいの遊び方というサイトはあるが、ゲーム方式がやや異なった。
そこには、手八の場八(2人)と書かれていた。
花合わせというゲームもあり、どうもこのことのようだ。
いったい花札とは何なんだ?
花札は江戸時代にできたようだ。
南蛮から伝わったカルタ(トランプ)と、日本古来のかるたがいつの間にか合体してできたようだ。
ハーフだね。
なんか古めかしくて、綺麗で、あやしい雰囲気のゲームだよね。
“おいちょかぶ”なんてやらなかったけど、やくざ映画の世界だね。
うちでは、アメちゃんかみかんを賭けてやるんだけど、この時は親も子もやくざになったね。
でも、その中から親子愛は生まれたんだよね。
僕は、今も時々娘達と花札をやっている。
ああ、脈々と受け継がれていく伝統の誇り。
電灯のほこりじゃないよ。
場六の手七・・・やっとるか? 龍神村!
水戸黄門に出てくる“風車の弥七”のことではありません。
もちろん“うっかり八兵衛”とは、全く関係ありません。
・・・すっきりしたところで、説明に入りましょう。
子供の頃、花札をした。
おばあちゃんもお母ちゃんもお父ちゃんも僕も四角い座布団を挟んで熱くなった。
2人で行う時は、場八の手十。
3人で行う時は、場六の手七。
4人で行う時は、場八の手五。
・・・だった。
3人の場合は場六の手七で、こうやった・・・。
まず親が、すべての花札を切って、各人に裏向けに手札を7枚、場に表向けに6枚セットし、残りの多くの札を裏向けで中央に置く(山)。
場に6枚、手札に7枚だから・・・ばろくのてしち。
各人順番に山から一枚札をとる。
その札と場にある札が同種の札だと、場からその札をとって自分のものとして、自分の前に置く(手札とは別とする、この時手札は1枚減ることになる)。
各人順番に山から一枚札をとったとき、その札と同種の札が場にない時は、その取った札は場に置いておく。(手札は減らない。)
この作業をすべての人の手札が無くなるまで行う。
最後に、すべての取り札の組み合わせを考える。
花札の一枚一枚には、点数があった。
0点、5点、10点、20点の4種類。
派手で綺麗な絵柄は点数が高かった。
勝敗は、取った札の総点数だけではなく、“役(やく)”の点数のやりとりの結果、最終的な順位が決まった。
役には以下のものがった。
赤タン 10点
青タン 10点
猪鹿蝶 10点
梅松桜 20点
月見に一杯 10点
花見に一杯 10点
ふじ 20点
きり 20点
他
青タンは、殴られた時できる青タンではない。
青色の短冊がついた札3枚(5点×3枚)が揃ったときの役である。
青タンの役点は10点だから、3枚の15点と合わせて25点と計算した。
結果の総合点を書き、そのゲームを数回戦行い順位を決めた。
これは龍神の方式ではないと思うけど、我が家だけのルールだったのか???
このルールは全国的なのか?
花札ゲーム現代版こいこいの遊び方というサイトはあるが、ゲーム方式がやや異なった。
そこには、手八の場八(2人)と書かれていた。
花合わせというゲームもあり、どうもこのことのようだ。
いったい花札とは何なんだ?
花札は江戸時代にできたようだ。
南蛮から伝わったカルタ(トランプ)と、日本古来のかるたがいつの間にか合体してできたようだ。
ハーフだね。
なんか古めかしくて、綺麗で、あやしい雰囲気のゲームだよね。
“おいちょかぶ”なんてやらなかったけど、やくざ映画の世界だね。
うちでは、アメちゃんかみかんを賭けてやるんだけど、この時は親も子もやくざになったね。
でも、その中から親子愛は生まれたんだよね。
僕は、今も時々娘達と花札をやっている。
ああ、脈々と受け継がれていく伝統の誇り。
電灯のほこりじゃないよ。
場六の手七・・・やっとるか? 龍神村!



















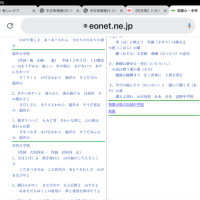
掲載から、ずいぶん時間が経ってのコメントなので、届くかは分かりませんが。
生まれは福岡は久留米です。
私の場合、場から言うのではなく、手から言う
手七の場六、手五の場八、などと言いました。
梅松桜、松キリ坊主、月見て花見て、雨で流れて
一杯出来ず。など行っていました。
青短、赤短、七短、十短などもありましたね。
幻の役みたいにして。
と、正月暇だったので、兄貴と子どもの頃の話しで、
盛り上がってました。