<序歌>
おーとばいにまたがり自在漂う月光孤洋海に佇む
小声でトツトツと喋るともなく話す話すともなくしゃべる寡黙な男よ
女知らずから女知る寒き夜病い畏れて友と海で洗うマラの冷たさよ
声上げてみな笑うなか恥じらうように笑顔で応じる黒ジャンの詩人よ
幸喜孤洋は居心地が悪そうに生きていたように思う。他人に対するとき、身体を前に屈めて座る。自然な姿勢なのか構えの姿勢なのかわからない。相手の顔をみつめるというよりは、じっと話を聞くという態度である。自分から話すというより、他人の話を聞くことで関わろうとする。
自分を、先に、主張することの恥じらい
現実世界で生きる時の孤洋には、そんな感性があったように思う。
初めて孤洋に会ったのは、宮城英定氏の家であった。1970年代の半ば頃であったと思う。何かの用事で、当時浦添市茶山団地に住んでいた宮城英定氏の家を訪ねると、ちょうど、孤洋がいた。個人誌『神経』という雑誌を出して、それを持ってきていた。寡黙な青年だなという印象があった。もちろん初対面だったから、お互いに寡黙であったと思う。宮城英定氏は、中央高校のときの教え子で今は詩を書いていると紹介した。その時であったか、あとで知ることになったのか定かではないが、孤洋は村で起こった強盗・強姦事件の犯人に仕立てられた苦い経験を持っており、その暴力と戦っているということを知った。そのあと、孤洋からは『神経』や詩集を送って貰ったり、最初の詩集『一人の舗石』の書評を頼まれ、書いたりした。
孤洋とは、宮城英定さんの自宅や何かの会合をきっかけにして会うという感じのつき合い方であった。寡黙な青年だが、あるとき、たしか新城兵一氏の詩集の出版会を那覇市安里の「芭蕉」という居酒屋で行ったとき、既に酔いの境地にいた孤洋が声を張り上げているのに遭遇したことがあった。そのとき意外な感じがしたが、これが孤洋だなと思った。その内容はもうはっきりとおぼえていないが、秘かに学んでいた清田政信や新城らを前にして緊張していたのかも知れない。「まあまあ、孤洋よ、余り気負わないで生きろ」、とかなんとか僕は言ったと思う。彼のこの酔ったときの声は、他人に幸喜孤洋は恐いなという印象を与えていたらしい。風情が丸刈り、黒の皮ジャンなので、一見チンピラ風という印象を与えていたせいか、「幸喜孤洋が酒を飲むと恐くなる」という声を聞くのを耳にしたことがあった。そんなとき僕は「違うんだよ、孤洋は本質的に優しい奴なんだよ」と弁護していたのを思い出す。 那覇市安里三叉路近くにあった泡盛居酒屋「芭蕉」は「詩・批評」同人の会合をよくやったところである。
それから何年たったろうか。1994年12月に、新城兵一氏の発案で、たちあげた「北村透谷を読む会」に誘われて参加したときに孤洋もいた。月一回、中城村伊集の井口千賀子宅で行われたこの会(たまに、鍼灸師をしていた、ましき・みちこさんの店でやったこともあった。彼女はこの年の8月に『猫のいる風景』という詩集を出していた。)は、透谷を読んで語りあうというものであったが、僕は、それほど、透谷に興味を持って参加しなかった。透谷を読むというよりは、「会話する場所を楽しむ」という態度をとった。初めて参加するために、会合する場所を尋ねて迷っていると、孤洋が外灯の下で待っていた。まったく久しぶりだった。彼も僕もお互いに歳月の変化を回避できない姿をみた。
「おい、孤洋、元気か」というと、ついてこい、という感じで、ハンドルの高いオートバイに跨り、10秒ぐらいで行ける井口宅に案内した。
孤洋はそのころ、あまり詩を書いてなかったと思う。沈黙する期間が続いていた。しかし、彼だけではない。詩と時代が剥離して、詩はますます詩の根拠を喪い、詩の修辞化が進行していた。詩の書き方や読み方の柔軟性を持たないと時代性へ対応が困難であった。というより、自分の言葉が古典化、陳腐化していってるなという危機感、空虚感が書き手の内面を通過していた。書く必然が希薄になり、いわゆる重たい詩は敬遠された。
清田や新城や幸喜には<村>のイメージがあるが、僕には無かった。それは、かれらが<農>の家系にあり、共同体としての<村>との確執や思念を言語に注入しているのに比べて、僕はそういう農の家系ではなく、もともと料亭経営を失敗した馴れの果て、無産者、プロレタリアートの家系だった。農の季節は我が家には無かった。左官や沖仲仕して一家を支える我が父は子に引き継ぐべきものを持ってなかった。だから、僕には<村>のイメージは出自から生まれてくるものではなく、言葉でイメージしていくようなものであった。といっても母方の実家は農家であったから全く無縁というわけではない。
<村>としての共同体への視線は、この沖縄に生きるものに課された課題であるけれども、その向き合いかたで、自ずから文体が決まってしまうということがある。清田、新城、孤洋が苦悩し、その文体から紡ぎあげた言語は沖縄、島、村といった風土と対峙する詩(文学)の確執を掬いあげ、戦後の抽象と暗喩を根源的に表現したと思う。文学(詩)の自立と共同体との確執というテーマはいまや古典であるだろうか。その苦悩の遺伝子は絶えたか、それとも耐えてるか。
孤洋と僕は同世代である。言語の使い方が違うのは、農と無農の違いでもあるだけではなく、彼にふりかかった<事件>とそこで見たものの違いと言えばそうなる。詩は言葉に過ぎないけれども、言葉の視えない力に誘惑された世代だ。我々は言葉を求めて、様々な事を考え、読み、ののしりあい、傷つきあい、熱病のように詩をめぐって論争し時間を消費した。それは、祭の後のようにとか、潮が引いたようにとかいう言い方が許されるなら、そのように今はあるのかも知れない。
孤洋の詩作品は長い。一編の詩を書くのになぜこれほどの行を積まねばならないのか。孤洋の詩は本質的に意味の詩である。その分析についてはルサンチマンとか悲壮美とか、幾多の人が書くであろうから、僕は触れないが、これは村で被疑者に仕立てられた固有体験と個が孤立する魂のなせるワザだと思いたい。修辞ではなく、自分の内面から湧き出る魂の声だ。そして、それは、かれの資質的な感受性と結びついてしまった。
時代を読みとる新しい言説の確立が求められている。このことについて、新城も僕も肯定的であったが、孤洋は否定的で、透谷会で、議論したことがあった。この考えが、彼には今までやってきた思想を捨てることに映ったらしい。とくに思想的血縁である新城氏に強く食ってかかっていた。
「新城もダメになりましたねえ。いままでの新城さんはどこにいったんですか。」
それは逆に孤洋の現在であった。孤洋が確執する村(国家)との対峙。孤洋の言葉の背後には、ふるさとの村での強姦事件の犯人に仕立てあげた共同体の暴力と闇との戦いがどっかりと存在している。孤洋にとって詩は戦いの拠点であった。孤洋は自らの苦い経験の痛みと「るさんちまん」を「自閉の情念」で突き抜けようとした。そこには孤独な痛みからくる叫びと淋しい抒情をともなった雰囲気が漂っていた。
あき缶に育てたひな鳥を
他人の空に解き放ち
無口な少年が
吹き散らすタンポポの穂は
いま どこの
幻野を流れているのだろう
(終曲のために<第三の歌>)
野辺の帰りの
すみれだけが
小雨に揺れて
ひっそりと美しかった
おれたちの青春 サラバ!
知の頂で
刀の鞘ばっかりを抜ぎ捨てた
おれたちの青年 サラバ!
(終曲のために<第四の歌>)
ひたすら問う
不安に傾く肩先から
どっしりと落ちる夕日の意味を
真っ赤に燃え滅ぶ血の理由を
すべてに背いて 世界にそむかれ
ほそぼそとたどりつく
ひとりの境地
(終曲のために<第七の歌>)
されば今夜は
係累たちのもどかしき罵声に
口つむぎ 我を忘れに
目のきつい少女のいる街へゆこう
街の空白に身をゆだね
強烈な酒の濃度に染まればよい
詩なんかよりうまい酒を
ランボーの著書にナイフが刺さったぜ!
(終曲のために<第八の歌>)
ああ、先に逝っちまった幸喜孤洋よ。僕は君の通夜に思い募って、君が好きだった森田童子の歌を録音して流したね。
センチな僕は最後にやはり森田童子を聴かせたかったんだ。聴いていたかい。
そんな僕は今、バッハの「マタイ受難曲」を聞いているよ。僕らは魂を鎮めながら、まだ生きなければならないのだよ。
※孤洋というペンネームは「太平洋ひとりぽっち」からとった、という。
(幸喜孤洋追悼集『いまを病む無明の時』(こよう会、1999年)に書いた「逝っちまった孤洋」に加筆訂正)
幸喜孤洋(こうき・こよう)
1950年9月 沖縄県具志川市(現うるま市)に生まれる。本名、幸喜克範(こうき・かつのり)。
1969年 国際大学(現在の沖縄国際大学の前身、コザ市にあった)国文学科入学
1970年 学生運動に参加
1972年 詩誌『神経』創刊
1973年 国際大学中退
1982年 第1詩集『一人の舗石』(矢立出版)
1984年 第2詩集『牢獄』(一風堂)
1990年 第3詩集『幸喜孤洋詩集』(脈発行所)
1998年2月 死去(享年47歳)


左の写真。(左から)清田政信、松原敏夫、泉見享、幸喜孤洋、勝連敏男(松原敏夫詩集『那覇午前零時』出版記念会で)
右の写真。(左から)ましき・みちこ、井口千賀子、新城兵一、幸喜孤洋(北村透谷を読む会で)
(拡大するには画像をクリックしてください)
















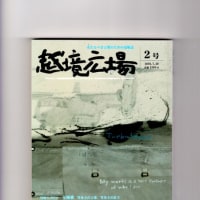
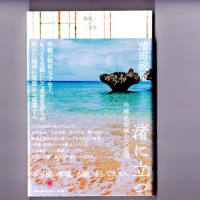
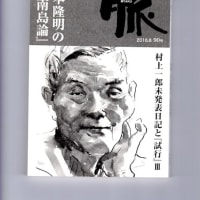
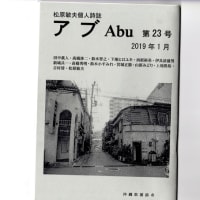
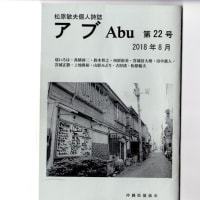
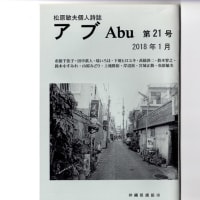
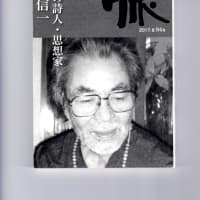
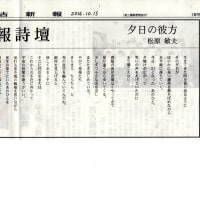
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます