黒田喜夫が沖縄の詩や詩人たちと関わり書き始めたのは、いつ頃からであろうか。著作から辿ると、『詩と反詩』(1968)に収録された「現代詩・状況の底部へ」(現代詩手帖、一九六六、一~十)に「萌芽のきらめき」があって『詩・現実』2号をとりあげ、東風平恵典の詩や清田政信の詩と評論「詩的断層Ⅱ」に言及しているから、それを嚆矢とみていいかもしれない。
「沖縄という地にあって、なお変革の精神と詩の精神がともにあり得るような視点をあくまで創ってゆこ うとする志向と、しかも一方で、大衆の自然発生(と疑似反体制)に加担することで詩の自立を阻まれるのをあくまでも拒否する志向とが、分裂したまま、しかし、分裂そのものがひとつにあるような世界として現れている。」
と書いている。「変革の精神と詩の精神がともにある」とはたしかに六十年代の詩の思想の傾向であった。三派全学連や全共闘運動の状況やらの〈大きな物語〉が詩(文学)意識を刺激していたし、沖縄においてはさらに復帰運動と変革をめざす学生運動が戦後の大きな闘争の形として文学や思想のことばにも影響を与えていた。沖縄戦後文学を牽引するかのようにあった『琉大文学』出身の世代が詩の同人誌『詩・現実』を創刊し活動開始したことは詩を書くものにとってエポック的な事件であったし、沖縄で文学(詩)するものはその活動を注目していたにちがいない。
清田政信はすでに1963年に詩集『遠い朝・眼の歩み』(詩学社)を出している。黒田喜夫がそれに眼を通していたかはわからない。黒田喜夫は一九七〇年に清田が出した『光と風の対話』や一九七三年に勝連敏男が出した『島の棘はやわらかく』の解説を、また「言葉の存在へ―裂ける村恋い」(一九七一・四、掲載誌不詳、『一人の彼方へ』所収)で清田政信について書いている。黒田喜夫は本土詩人でもっとも沖縄の詩に関わった詩人といっていいかもしれない。
清田は「黒田喜夫論―破局を超える視点」(『琉大文学』3巻8号、1967年12月)、をはじめ、「黒田喜夫論Ⅱ―歌と原郷」(1977年、現代詩手帖1977年2月号)、黒田喜夫論Ⅲ―沈黙の顕示」(「詩・現実」12号、1980年3月)、「黒田喜夫と石原吉郎―風土と沈黙」(琉球新報1972年?)とけっこう書いている。清田政信は黒田喜夫が自らの詩法に影響を与えたとも語っており、東京に行って、直接黒田喜夫に会ったりしている。
最初の「黒田喜夫論」で清田は、黒田喜夫が「死にいたる飢餓」で書いた東北農村の最底辺層にあって「飢餓病」を強いられた「あんにや」の存在にふれながら
「………日本の農民は初めて自らの疎外の生活史を最も高い言語水準として、黒田喜夫の詩にその実現された成果をみることができるわけだ」
と書いた。日本の戦後詩で村や辺境を詩のステージに押し上げたのは、たしかに黒田喜夫であった。戦後の復興期から高度経済成長、東京中心の都市文化の拡大、地方(村)から東京への人口流入が続き、村の若者が「東京へ東京へ」と流れる日本社会の流動があり、村や地方は〈辺境〉という地位にますます追いやられた。「東京」「都会」という語彙や風景を歌う歌謡曲が多数作られ、ラジオやテレビで流れて、〈東京主義〉というべき現象が踊っていた。地方(辺境)で文学意識をもつものは益々東京が産出する文学を中心とみなす習性を持ってしまった。戦後日本近代の先端、戦後資本主義のエナジーを集中して膨張した大東京がつくる意識と生産物の風景を背景に詩の言葉も対応していく必要性があったのであるが、都市の流民を市民という階層に変貌させた資本主義の無意識の戦略に抗しがたい結果となったのではないか。民衆の前近代意識(共同体意識)を喚起し〈夢のコンミューン〉を構築するために地方の労働運動(三池炭鉱争議)に参加して運動をしたが、戦後日本社会の行方を感受した谷川雁は、「東京へいくな ふるさとを創れ」と詠いつつ、ついに「詩は滅んだ」と宣言するしかなかった。谷川雁の方法に対して、貧農出自の黒田喜夫は、その村や民衆の最底辺にある疎外の民の負の極地から思想を築いていった。谷川雁の村や民衆へのまなざしは美しいのだが、黒田にとっての村は苦い味のする場所であった。
『脈』誌の原稿依頼を受けてから、黒田喜夫の著作に向かったら、黒い箱に入った初期の『詩と反詩』以降、ぼくはそれほど読んでこなかったことを痛感した。清田政信の黒田喜夫論を読んで充足したわけではないが、しんに取り組んで読もうとしてこなかった。清水昶と「日本的自然」と「ナショナリズム」についての論争があったのは知っていた。そのころ清水昶の書くものには、ぼくも「おや?」という感じを抱いていたし、やはりそうか、その方向へいったか、という奇妙な納得したのを憶えている。清水昶は、都市市民社会の見方に否定と肯定の混在があったが、土着的な観点からみていた初期の見方を段々と弱めて肯定のほうに強めていったと想われた。つまり下層日本人たちが、高度経済成長によって作られた都市社会の虚構の豊かさを無邪気に享受する流れを肯定する〈自然〉に視点を向けていった。高層ビルや巨大な駅やきらびやかな店や通りに〈一億総中流民〉が瀰漫する都市風俗に抗しがたくその流れを受容するしかなかった。だが黒田喜夫の場合、こういうプチ・ブルジョア意識が受容できないし、そういう意識によって国家の支配体制が覆い隠され、民衆から遠くにあるように見せかけられているとみなしていた。つまり近代日本の現在への批判精神を失ってはならぬという思想を持ち続けていた。七〇年代から始まった日本総中流化時代は、九〇年代バブル崩壊後、総崩れて、少子化、高齢化、IT技術の進歩、ネット社会、非正規雇用増大を生みだし、そしていま階級分化が進んだ格差拡大社会となっている。この状況は文学や思想に新たな問いを投げかけてきた。
今回改めて黒田喜夫という詩人の全体像をつかもうとあれこれ読んでみた。『詩と反詩』以降の詩論・評論を読みあさったのだが、『一人の彼方へ』(1979)にいちばんひかれた。歌謡論といえばまず吉本隆明の『初期歌謡論』がある。吉本の読み方は記紀歌謡、万葉集、古今集、新古今集を繙きながらの、歌の発生、和歌成立と歌人の思想や感性や韻律への歌謡論である。黒田喜夫の場合は記紀歌謡(宮廷歌謡)を通して古代ヤマト王権、天皇制国家成立とその支配をあぶり出して弧状列島日本(島尾敏雄流にいうとヤポネシア)の衆夷との関係をさぐっていくという「歌(短歌)の読み方」がある。なるほど、こういう読み方もあるのか、という独特さがある。短歌というものを表象だけで読むのではなくその歌形の彼方にあるもの、みえなくなっているものを読む、という詩想がある。日頃我々は詩(歌)を読んだり、書いたりしているが、歌(詩)の根底に横たわっている歴史性、その彼方にある起源というものに思いをはせることは殆どなく、現在の形式としての詩(短歌)を疑ったりしていない。できあいの形式にのって、自分の詩作を吐き出しているだけだ。その土台の上で、読んだり読まれているとみなしている。
『一人の彼方へ』に出てくるのは、短歌というものが、古代大和王朝への〈供儀〉として取り込まれ、記紀歌謡を介して発展してきた〈ヤマト歌〉という読み方である。つまり短歌という形式をヤマト王権、古代天皇制国家ができる頃の弧状列島に生存した衆夷のうたが収束された超時間性から見つめ直すことである。ならばそれは現在にあってもなお、歌の彼方にひろがるものであり、闇のかなたに葬られた声なき歌(詩)の言葉として掬いあげなければならない、そのための展開として東北出身の寺山修司の短歌や東北の民謡とともに北辺に伝わる譚話や史書を開いて、かつて古代ヤマト王権にまつろわず反抗し征服された衆夷である原東北あるいはアイヌの歌を引き出して、日本の現在において異化し、天皇制国家の支配と対峙する、という読み方となっている。
「衆夷の世界としての山野の、化外の呪力。それは統べられた世界に措定されることで実在――即ち強烈な不在に架かって生々しく、それ自体は、存在の恐怖と歓喜の統べられざる自然・身体への血を流す倒立であり、身体すれすれに、いや、そのただなかへ逆映する負の全体を負う。それは目くらむ懸崖をなすはるかな未生の「私」だ。だが、支配の天蓋をつくる呪法は、山野の呪力、衆夷の呪力を制し簒奪することで高みに登る。民人の祟りのちから、呪うちからの禁止簒奪としての呪法であり、民びとの呪殺のまじないの封じ様から異族(民びと)の地神、来迎神への表象性の簒奪まで、根の国神系、海童神系、所謂高天原系三層の基底を統べた日本神話(記紀)と以後の律令王朝の史的記述などはとりもなおさずその証にほかならず、つまり根源としての衆夷から発して衆夷を滅し追うことに終わる支配呪法のうちでは………」(鎮まざる地の歌、『一人の彼方へ』)
「いうまでもなく、いまわれわれにおいて亡滅するものがあるとすれば、それは「日本(国家)ではなく、「日本人」ではなく「日本の民」なのだ。いや「日本の民」でさえなく「日本の底の民」である、「日本(国家)」という共同の観念規範の根もとの、統べられた世界の底の、亡滅することで異民となるものである。」(土着と亡滅、『一人の彼方へ』)
「………照射されて浮きあがるのは、しかも地の絶えざる無声のうたなのであり、そこにいわば、「ヤマト歌」の統合のうえの高みを、地の南辺と北辺から衆夷のうたの現在にわたる生死の身体ではさみ、存在しているもののすがたが時に現れているわけだ。ーその地のうえの鎮まりえない断声・無声は「私」のものであり、その一人の彼方へ、想われるのは、「日本」自己同一的観念の統べられた擬調和の歌ではなく、われわれの、弧状列島の衆夷の感性の多様性ともえあがるそのコンミューンである。」(歌と郷Ⅲ、『一人の彼方へ』)
『一人の彼方へ』の文体は硬質である。詩的思想、詩的批評の濃淡が奥深い。この批評文の粘着的な文体は黒田喜夫的であるし、まるで詩をかいているのではないかという感じさえ抱かせる。藤井貞和はそれを「黒田詩学」と呼んでいる。古代天皇制国家がいかに列島を制して、化外を支配し呪力を簒奪していったかを歌(短歌)を追うことで述べる。東北がまさにそうであると寺山修司の短歌を例にして究めていく。読んでいくと、なるほど、まさにそうであったろうと思わせる。繰り返すようだが、「一人の彼方」とは、まだ見出されない、列島の歴史の内実を、民衆の、なお統べられなかったころの衆夷の、身体や呪力を詠った歌を見出していくことであろう。そういう亡滅のうたが底流に流れているだろうし、必ずやそれは、現在にあっても、どこかに出没する、と解している。黒田喜夫的思考は古代から続くまだ未生の、化外の、超時間としての共同性の根底を顕在させる方法といえる。その方法で、弧状日本列島のなかにある、大和王権に統べられざる空間、それはいまや幻の空間、幻の土地、時勢をおしてもなお現在に残存するであろう、非支配圏の言葉、とくに〈うた〉としてみることをとっている。そういう考えはユングの「集団的無意識」「元型」という考えにも通底するように想われるが、ここではふれるゆとりがない。
その方法を延ばして、沖縄の古謡、神歌、とくに宮古島の村落創成のニーリやアーグをとりあげ、古代天皇制国家への〈供儀〉から外れた化外、衆夷、異族としての南島のウタが存在することを述べ、ヤマト天皇制国家と相対するものとして書いている。どういうウタか、これも紙幅の都合上、あげることは出来ないが、黒田喜夫だけでなく吉本隆明や藤井貞和が南島歌謡に着目して、思想の可能性を書いた詩人がいたことを知悉しつつ逆に我々の痛い欠落を自覚しなければならない。すでに、数々採録されて出ている「南島歌謡集」を、地元である我々沖縄の詩の書き手はそんなに読んでいない。というかそういう地点にまったく無自覚である。せいぜい『おもろさうし』くらいではないか。本土の詩人や学者が琉球・沖縄の古謡、民俗、宗教、言語をあばいて様々に言及した、その研究成果を現在の地点で読んでいるだけで、自ら手を出して根源的な詩的思考を創造していない。これは怠慢であるし、惰性である。吉本隆明はこういった。
「わたしは、沖縄や琉球出身の研究者たちが、本土の研究者の学風の口まねと、うけ売りばかりやって、ひとつもそこからはみだそうとしないのを読むと、むかむかしてきてしかたがない。」((異族の論理、「文芸」1969年12月号)
特に研究者になる必要はないが、自戒をふくめて、残念ながらいまでもそういう傾向にあることを認めざるを得ない。といって、本土をすべて拒否せよ、というのではない。かつて祖国復帰へとなだれこんでいったあの運動過程で、〈日本的なもの〉への憧憬と同化の実践がいろんな形で行われたし、流暢な日本語や日本的な教養を身につけることに努めたり、はたまた日本的風俗(ほとんどそれは東京中心の文化、映画や歌謡曲やテレビやらでみる日本人の姿)への同化志向で、日本人化を図ったものが多かった。東京で流行したものを、すぐに取り入れて身につけたり、言葉にしたり、日本人と沖縄人との差を無化しようと志向した。これは、実は、明治近代以降の沖縄でなされてきた習癖でもあり、いちはやく取り入れた当時の知識人、教育者、文化人らがそうであった。土着的なもの=沖縄的なものを卑下し、亡滅するように働いていたし、そこから劣等意識や差意識やらが強くなり、近代化意識を実践するものたちの土着文化への差別意識があった。戦後も土着的なものを醜悪なもの、廃棄すべきものとしての習癖が続いた。
思い出す光景がある。ぼくが学生の頃(60年代)、戦前から新聞記者をしていた父をもつ友人がいた。那覇市首里にあった彼の家に遊びにいったときのことである。その父はもう退職して家にいるのが常であったが、ラジオを聞くのが楽しみであった。特に音楽を聴くのが好きで、そういう番組を聴いていたが、あるとき、三線の音色と沖縄民謡が流れてくると、「ちぇ、土人の歌だ」と吐き捨てるように言って、チャンネルを切り替えたのである。友人によるとNHKの「のど自慢大会」は好きで毎週聞いているらしかった。知識人ともいえる新聞記者が地元の民謡がかかってきたら「土人の歌だ」と切り捨てるようにチャンネルを変えるその心理には、沖縄近代のヤマト日本への憧憬と地元蔑視の感覚があったことはいうまでもない。また二千年代に入った頃であるが、職場の仕事関係で、沖縄の昔の写真ー大正時代に外国人が写した写真―をみるときがあったが、同僚の中年の沖縄女性が「あらぁ、いやだ!土人みたい!」と叫んだのである。みると、その写真には沖縄の古い風景があり、肌の黒い沖縄人が貧困(ヒンスー)な身なりの姿で写っていたのである。彼女は地元の大学を嫌って本土の私立大学を出ていた。「あらぁ、いやだ!土人みたい!」と反応するそこにも、いわゆる教養ある近代沖縄人の地元蔑視が続いているといわなければならない。
復帰運動は一種の民族運動であったが、日本というクニは帰るべき祖国であったか。いや本当は描いたというか夢見た祖国とは現にある日本というクニではなく、もうひとつのクニではなかったか。たとえば『一人の彼方へ』で黒田喜夫が引用した、ぼくも気に入った文章がある。
「………おもたいくびきをかける古代国家成立のうらがはに、もうひとつの国がよりそって、それをささえてゐる。農夫の腕は目のまへのやせた田をたがやしながら、まなうらに泛かぶ彼岸の畑に鋤をふるってゐた」(鈴村和成「異同考」、評論集『異文』所収)
まさしく〈もうひとつの国〉、〈まなうらに浮かぶ彼岸の畑〉をめざすとするなら、そのクニを造る、構築すべきクニとして、沖縄の運動家や知識人はたえず問い続けるべきであった。吉本隆明の「異族の論理」から影響を受けて編み出した沖縄異族論や反復帰論にその萌芽があるが、しかし「異族」「独立」「しまくとぅば」「伝統芸能」を持ち上げるだけでは根源的な説得力をもたない。そういう知識人や学者、文化人がいう言説は経済生活者の視点からみる現実論がないのが欠点である。民族感情、沖縄ナショナリズムをふるって、異族論やあるいは滅ぼされた140年前の琉球国を持ち出してヤマト・日本対沖縄・琉球という構図の喧伝や「琉球王朝」といった自画自賛する復古調をみかけるが、なにか歪で狭隘な回帰心が鼻についてしょうがない。沖縄民衆運動を語るシンポジウムで〈自分は首里出身で家系は士族で氏(うじ)はM氏である〉と故意に誇らしげに自己紹介する講師がいるこの二千年代現在の歪な沖縄言論の現実。身分制の意識を温存している彼らは首里城の幻の国王にいまだに拝謁しているのだろうか。
復帰後、いわゆる〈ナイチャー〉が多く住みついた沖縄社会の変容という現実がある。この移住という人の移動は琉球・沖縄島嶼の歴史に繰り返されたことであり、特別視することではない。3万年前からあったかもしれない。外来縄文人が住みついて狩猟を求めて移動したあとに、別の外来人がやってきて定住したかもしれない。ウチナーンチュの先祖は港川人であるのか。彼らはどこからやってきたのか。彼らが沖縄島にやってきて、そのまま、いわゆる先住民となったのかは定かではない。琉球人は九州からやってきたという説もあるし、中国からの移住人=久米村人が住みついて混血化しているし、とにかく移住、流出、混血を繰り返したのは歴史的な事実である。純粋な琉球人=ウチナーンチュはいないとみたほうがいい。
羽地朝秀や伊波普猷がとなえた「日琉同祖論」は否定されるべき考えだろうか。ぼくには、琉球・沖縄は日琉同祖の要素もあるし、そうでない要素もあるとみなしたほうがストンとくる。血や身体の人類学的、生物学的、考古学的研究の成果もみなければならない。琉球・沖縄にある〈沖縄的なもの〉=言語や習俗や神話や様式やらには、〈日本的なもの〉だけでなく〈中国的なもの〉〈南方的なもの〉の形跡が多い。もし独自の琉球・沖縄を探すとすれば、グスク時代以前までさかのぼって〈原沖縄=原琉球〉の事物をさがさなければならない。
先の鈴村の文章に相対するような、たとえば吉本隆明の次の言い方をとりだしてみる。
「ある支配的な共同体というのは、それ以前に存在する共同体なり、国家なりの、観念的な、それから土台的な核になっている構造を、自らの共同体あるいは国家の権力構造の中に、摂り入れていくということなんです。特に古代ではそういうことをしないと、以前に存在していた共同体に対して、次にそれを包括的に支配しようとする共同体が、包括するとか支配するとかいうことが出来ないのです。」(吉本隆明「世界―民族―国家」空間と沖縄、『全南島論』所収)
ある共同体が前に存在した共同体=国家の構造を戦略的に摂り入れて支配するという巧妙な力学をあばいていると想われるが、黒田喜夫はそうは見ず、古代におけるダイナミックな事例を指摘して、衆夷(前の共同体)を「亡滅」と位置づける。
「………滅びうるもの――わが弧状列島の民の実在。異民・衆夷・毛人・すべての日本土人。私である彼方。滅びうるものにしてわが反回帰的志向において滅びざるもの。その私の現存により支配に対し、まつろわずに滅びざるもの―。」(土着と亡滅、「『一人の彼方へ』」
こういう語り方にぼくは〈滅びの旋律〉というものを感じる。滅んだものへの抒情の美があるのだ。支配王権に決して服さない、遠くにあって、滅びながら滅びない旋律。それはまつろわずに滅ぼされた者達からの、遠い呼び声となって、〈私である彼方〉へ共鳴してやってくる、その声たちの旋律を聞くことなのだ。藤井貞和の次の文章をみつけた。
「亡滅こそ、黒田氏からあたえられる重要な鍵であって、それは亡滅させられた深い怨念の土着だと言おうか。…(略)……記紀歌謡は大部分、宮廷歌謡としてある。それのうえに広範な古代歌謡(古代的な村落共同体の歌謡類を中心にした―)の亡滅を読みとることができるのではなかろうか。」(藤井貞和「古代詩の方へ―黒田喜夫『一人の彼方へ』ノート」、『甦る詩学』所収)
藤井貞和は南島歌謡類を多く読み込んで、『古日本文学発生論』や『甦る詩学』で詩の起源、発生論を遠くまで展開してみせた学者、詩人である。この「亡滅」という不穏な思考は黒田喜夫の基本的な考えにあり、統べられた民の自己同一化を図るクニには必ず〈亡滅させられたもの〉があるとの固い信念があることを読みといている。
わが沖縄においても首里王府が編纂した『おもろさうし』が宮廷歌謡集としてあるが、それから除外された〈怨念の土着〉が琉球国が成立する時代にあったであろう。『おもろさうし』にある神歌、歌謡を読めば首里王権への供儀としての歌謡がほとんどであることはすぐわかる。『おもろさうし』に採録されなかった琉球弧の地方歌謡を集めた『南島歌謡大成』(外間守善・新里幸昭、ほか)は、すぐれた業績であるが、個人的には、まだなお、明らかになっていない琉球国成立より前のグスク時代よりさらに前の〈原沖縄=原琉球の歌〉が存在したと想う。それは亡滅しているから、黒田喜夫のように〈私である彼方〉で感受するしかなく、われわれの現在の詩や歌のなかに無声、無音でありながらも確かに存在するとみなすしかない。
「亡滅という契機をもっての想像力化により、短歌定型の響き合わせの調律の供儀性として表象される〈死せる共同体〉の無時間性の潜在を、〈詩とはまた根源としての衆夷のうた〉であるものの生成の時間へと、先ずそこで逆に奪い返すこと。」(黒田喜夫「精神の定型と関係主体」、『同時代批評1』1980・6、『人はなぜ詩に囚われるか』所収)
黒田喜夫の亡滅した衆夷や土着や共同体へのまなざしからくる〈詩(歌)の奪還〉という言説はなにかドラマチックな響きがある。
注:『脈』102号(特集 黒田喜夫と南島)-- 20191年8月発行--から転載)















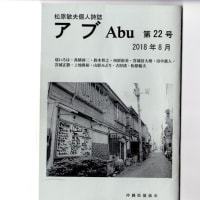
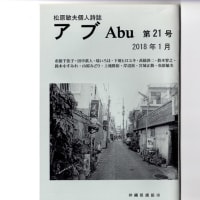



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます