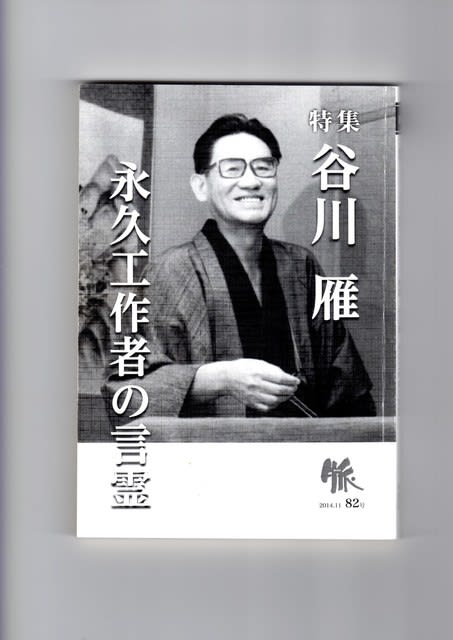
沖縄での、ある夜の会合の終わる頃、「では、さらばじゃ!」と谷川雁は丸いバッグを肩にかけ、いなせな格好をして、芯の入った声で、居酒屋を先に出ていった。すると、沖縄のある女流詩人が、ほれぼれとした表情で見送っていた。その女流詩人は酒のはいった会合の途中で谷川雁に「おめえの詩は帰る場所のない男を見破らずに、ただ女の愛を弄んでいるから駄目な詩だ」と批判されたが逆にうれしそうな顔で返した。「女にやさしくない男はつまらない男です……イメージから変われ、って女がいいそうな、男が変わることを求めた言葉じゃないですか。……」。
こういう記憶の情景がふっと湧いてくる。だが細部がはっきりしない。こういう会話が実際にあったか。記憶の錯誤かもしれない。……
しかし、たしかに谷川雁は沖縄にきたことがあった。当時那覇市若狭に居酒屋「ゆうな」という店があって、そこで小さな歓迎会があった。今は池間島にひきこもる伊良波盛男氏に声かけられて参加したのだった。いつだったか定かでない。70年代の後半だったか……。歯切れのいいしゃべり方だった。論理的な明晰さで会話をさばく。声も大きかった。
「では、さらばじゃ」なんて、ウチナーの男は〈ふつう〉いわない。谷川雁の潔い、男性的、武士のような闊達な声。しゃべり方も、口ごもった、歯切れの悪いしゃべり方ではなく、自信たっぷりというか、響き渡るような、口語的でなく、文語的な、しゃべりかただった。そこがその女流詩人をほれぼれとさせたのだろう。これが谷川雁という男だ、と感じさせた。
ああ、これが日本語だ、日本人だ。日本の詩人だ。羨望と拒否的な心情がたちあがった。ちぇ、なんともかっこいいぜ。だがな、悪いけど、おれは高倉健さんが好きなんだ、あの、ぼくとつな、押し出すような声で、すまなさそうな、しゃべり方だよ。あれがいいんだ。世の中から逸脱、疎外、追放されたようなはぐれ男の哀愁、うだつがあがらないが、影のように粋に生きている、そんな男。高倉健。そんな男にほれるぜ。雁さんよ。
谷川雁は目立つように中心にいなければすまない感じの人だったのではないか。いさぎよい男の姿。そこがある時期の女性のハートをひきつけたのか。心とはいわない。ハートだ。そして饒舌なレトリックだ。……
昔からの印象。すごい、かっこいい詩句を書いたな! 谷川雁のイメージはそれだ。 かっこいい!だがくせ者だね。とまたくる。いろいろ物議をかもす。伝説化していった詩人。「瞬間の王は死んだ」か。……うーむ。なるほど実に潔い。
ぼくのもと職場の上司に、雁と同じくらいの年齢の陸軍士官学校卒がいたが、かれは、出征するまえに戦争が終わったので、手柄(武勲)をあげるまえに戦争が終わったことを、非常に残念がっていた。その勢いをもって戦後の社会で、ある法人組織のある部の長となったら、軍隊命令調で、同期の世代の部下職員をあつかっていた。その職員たちは戦中の名残を持っていたから、軍隊の命令を聞くような忠義の格好で服従していた。実に哀れな情景を何度もみせられた。戦後の戦中世代の出世主義者のなかには無反省のまま暴君的に振る舞って残念をみたす、こういう人が多くいたのではないか。谷川雁も砲兵の所属で実戦にでるまえに戦争が終わった。
丸山真男のように戦後民主主義、近代主義を手放しで受け入れた学者とはちがって、共産党(除名されたが)や労働組合、組織活動の渦中で自己を実践した谷川雁にとって戦中はどうだったか。
鶴見俊輔がいうように谷川雁は幕末に生まれておけばよかった。維新の志士になったはずだ。理念にまっしぐら。邁進。しかし谷川雁は民衆だったろうか。鍬の一本でも手に握って汗水たらして血豆がでるくらい、土にふったことがあったろうか。精神的知的階級を構築しながら民衆を扇動しただけの言動家、詩人だったのか。谷川雁の詩のフレーズを声に出して読んでみればわかる。まさに指導者、扇動家のロマン的口調である。
おれの作った臭い旋律のまま待っていた
南の辺塞よ
しずくを垂れている癩の都から
今夜おれは帰ってきた
びろう樹の舌先割れた詩人どもの
木綿糸より弱い抽象を
すみれの大地ぐるみ斬ってきた
優しい蛮刀で一片ずつ
(帰館)
海べにうまれた愚かな思想 なんでもない花
おれたちは流れにさからって進撃する
蛙よ 勇ましく鳴くときがきた
頭蓋の窪地に緑の野砲をひっぱりあげろ
(おれは砲兵)
おれは大地の商人になろう
きのこを売ろう あくまでにがい茶を
色のひとつ足らぬ虹を
(商人)
おれは村を知り 道を知り
灰色の時を知ったった
明るくもなく 暗くもない
ふりつむ雪の宵のような光のなかで
おのれを断罪し 処刑することを知った
(或る光栄)
〈おれ〉という人称指示語のなんとも行動的な勇ましさ、格好つけ。しかし、うまい。暗喩が詩的現実となった傑作の詩句たち。読者の読み方でいろんなことを喚起させる。行動派詩人の言葉だ。「大地の商人」を冗談で不動産屋のことかと訊いた人がいたが、「なろう」「売ろう」「きのこ」「にがい茶」「色の足らぬ虹」……とはなにか。「おれは大地の商人になろう」は「おれたちは大地の商人になろう」にならなければならないのだ。谷川雁が大衆に向けたものへの言葉なら。
「大衆に向かっては断乎たる知識人であり、知識人に対しては鋭い大衆である」
(工作者の死体に萌えるもの)
という工作者の思想は、知識人は大衆を拒否せよ、大衆は知識人を拒否せよ、といっているのではないのだ。自立して相互に扇動しあえ、ということなのだ。つまり刺激的で相互に喝破しあう関係を構築せよということだ。曲解が許されれば、だ。
もう時の彼方の言葉を、思想の古典として読むしかないのも否定できない。プロレタリアート、鉱夫、農民、民衆はいまどこにいるのか。大衆はどこにいるのか。
戦後を生きた谷川雁の私史。戦時、砲兵、戦後共産党入党、オルグ活動、離党(除名)、60年安保、三池炭鉱労働運動(大正行動隊)、サークル活動、65年上京、筆を折る、66年小企業設立、80年代、十代の会、宮沢賢治に関する文章、……死という図式がある。それまで書いたものは詩集や散文で掲載されているが、燦然とした古典であるといっていいだろうか。時代が読者であるからして、時の言葉が古くなっていくのは宿命的でもある。
ぼくが60年代に谷川雁の詩に出会ったとき、もう書かない詩人だった。「瞬間の王は死んだ」という名セリフを残して、さっそうと詩の世界から去った詩人。その後をれんれんとして歩むものは、谷川雁とはちがうぞ、といった案配で、文学の世界をとらえていたといってもいい。労働運動、革命運動と連動した雁の言葉を、社会主義リアリズム文学との区別さえつかなかった。文学は政治とはちがう道だという観念が芽生え、それにひきずられ、ほんとの文学、文学らしい文学に傾倒していた。文学雑読の道を歩いていた。
闘争の詩には、農民、プロレタリアートの覚醒、革命運動の挫折を歌ってはならない矜恃があったかもしれない。
「谷川の詩の特色は意味空間にあるのではなく、いわば詩行のつながりの中の、突出した一行のもつ破壊的なイメージの美や論理にあるように思う。だからたとえば全体の詩の印象はうすれても、その一行だけがなまなましく意識の底にこびりついているというように記憶される。」(北川透「夢みられたコンミューン―谷川雁の詩の世界」)
「谷川は自己の内なる私有意識、自我を処刑するにふさわしい場のイメージとして《村》を求めたのであり、それはまた別にいえば、《村》を夢みることによって、自我処刑の責苦に耐えるのである。」(同)
「故郷からの家出人であるプロレタリアートの感情の底にひそんでいるこの心の破片と記憶をよみがえらせることによって、新しい連帯の基礎にすることができる――彼の夢は論理の翼を与えられて一気に走り抜けたといえる。(同)
「彼の詩はある頂点までのぼりつめていたといえる……」(同)
思潮社の現代詩文庫『谷川雁詩集』の解説にあった北川透の、この「谷川雁論」は谷川雁の詩への理解の手引きでもあった。現在でも、もっともすぐれた論である。(しかし、北川透は谷川雁が死ぬまで一度も直接会ったことがない、という)。なるほど、その一行だけが生々しく意識のそこにこびりつく。いい言い方だ。よくわかる。私的所有を否定した虚構を連帯に結びつける。民衆の原像。被差別民と労働者、農民。前プロレタリアートの感情。東洋的な村落共同体。そこから導き出した思想の造型は谷川雁独特のものである。ゆえに谷川雁は先駆者の姿、さすがと思わせる。
政治と思想の論理を基底にした詩作。前プロレタリアートの原感情で夢見られた幻の村、コンミューン。闘って勝つための戦略を練る意図がありありだ。詩も負けることが嫌いなんだ。もちろんそれはだれもそうだが、資質的なものもある。
コンミューンをいかに仮構していくか。その基底にあるのが、アジア的共同体(村)にある沈黙の感情域=原感情である。という発見は詩的感性と思想的感性が合体して編み出したものと思う。
こう書いてきて、いま自分が書いている、やっている詩との、ひどいギャップを感じている。ぼくはどこかで、戦後においては<もはや時代が読者である>と書いた。自らが持っている意識や感覚がずれている、通じなくなっている……ということはよく経験する。この時代がいいのか悪いのか。そういう紋切り調ではいえない。いいところもあれば悪いところもある。少なくともいい時代ではある。過去の時代に比べれば……と思う。今の時代が昔に比べて悪くなっている、という人がいるのは信用できない。経済的に豊かになっている。便利になっている。自由になっている、医療も発達している、権威が弱くなっている、民主主義の三昧世のなか……だが反面、壊れたものが、こうこう、ある。……そういうところがある。……そこは平均的、一般的にいうしかない。
当時(60年代)に谷川雁詩集を読むことと現在とで、こんなにちがうのはなにか。言葉が熱くなっているのに、一方では冷めている。谷川雁のフレーズはなにかの行動、思想的雰囲気のある環境で読むとすばらしい「詩のナツメロ」のようにやってくると思うのはぼくだけだろうか。 そうだ。谷川雁は「なつめろ」になっているのだ。
「谷川雁の言葉たちは、読む者になにか恋情の告白めいたことを強いる。田舎者というより、田舎武士まいた剛毅な観念の運動が燃えるような色どりのメタフォアに仕上げられて迫ってくる。」(黒田喜夫「谷川雁詩集から」)
「彼の詩の美と力強さは根源的なエネルギーにふれている美と力強さだが、彼はそのエネルギーを、出発点ではなく帰着点であるかのようにうたっている。私の中のひとりの日本農民の裔は、谷川の燃えるようなよびかけに、われわれの真実はそんなに美しくはないと答える。」(同)
「近代主義はただ踏みこえた石にすぎないとは、彼の決然とした宣言だが、それを踏みこえることができるのは美しい比喩によってであろうか。」(同)
黒田喜夫のなんという皮肉な評価であることか。近代労働者の末裔でもない谷川雁が、対象の出自階級、つまり農民、鉱夫、プロレタリアートを歌う。そこには美しい自然へ対するがごとく、階級に対している。そこを貧農出身の黒田喜夫は見抜いている。そんなに美しくはない、と。実際の泥土のような労働、汗水の労働をしたことのない知的インテリが農民や労働者の根底にあるものをつかんでいるとして歌うとはどういうことか。心情のエネルギーをつかんで歌うだけで終わりか。
戦後の農民はほとんどが農地改革によって地主の解体によって小作農から土地所有者へとなった。戦前の農民と戦後の農民の質的変化がある。小作農家としての被搾取民の意識は地主、あるいは支配者に対抗する階級としてあった。村落共同体(村)で関係を築き、共同のよしみで仲間意識があった。農民にとって、自然の風景は、作物が実るかどうかの気象が気になる場所である。四季が美しいとかなんとかは二の次だ。日本的抒情は生活感覚を問わないで遠くから風景を眺めた都市民の感覚や心情にすぎない。ふるさとを美しく歌うことができるのは限られている。悲しいかな、常民は支配者が右にしろといえば従うしかない。権力を持たないし、権力には無欲だからだ。
村は閉鎖的な空間だ。村に生まれのものが、自分の言葉をもって生きようとすると、共同体の桎梏に対峙していかねばならない。詩を書くことは裏切りとなる。黒田喜夫はそこを詩と反詩という切り口で村を幻視化してあばいてみせた。
乱暴な言い方になるが歴史学は権力者(支配者階級)についての学であり、民俗学は被支配者階級の、農民、民衆についての学である。とみることはできないか。とにかく世を支配しようと動き、権力争い、支配者にのしあがろうとして、戦や殺戮をくりかえし、民衆を道連れにする階層のものたち。なぜこういう権力好きなやつらが出て世を闊歩するのか。人間というものが国家や社会を作った理由はこういう欲望をみたすためにあるのか。国家は廃止できないものなのか。一方自然と繰り返しの習俗で生きることを強いられた農民(民衆)、常民がいる。歴史に出てくる人物や時代事項で世の中の流れをくくってしまうのはなんとも苛立たしい。歴史を支えていたのは常民の力であったことを忘却してはならない。お城を実際に築いたのは租税労働化された農民や雇われ労働者(人夫)の力であって、殿様や支配階級そのものではない。思考転換しないといけない。
谷川雁は柳田国男を評価していたようだ。常民、民衆の心情の域にある村の原感情をすくいとる方法として民俗学に接したからにちがいない。民衆を知るには歴史学ではできない。 しかし、遅かったのではないか。近代の時点で武士の視点で一揆が起こると期待していたのか。
谷川雁の書評の仕方には谷川雁らしい特徴がある。たとえば、『鮎川信夫全詩集』の書評。1965年11月、朝日ジャーナル。
「詩がほろんだことを知らぬ人が多い。いま書かれている作品のすべては、詩がほろんだことのおどろきと安心、詩が生まれないことへの失望と居直りを、詩のかたちで表現したものという袋のなかに入れてしまうことができる。もちろん、そのなかにはある快感をさそうものがないわけではない。しかし、それはついに詩ではない。」
わかります。この詩論の主張。ポレミックな言辞。この書評文に違和感があるのは、書評でありながら、鮎川信夫の詩の言葉にひとことも触れないで、鮎川信夫の詩的活動、戦後詩への「荒地」の影響を記述しているところだ。作品にふれずに書くことに差異を禁じ得ない。おそらくこういう書き方が谷川雁の対象へのやりかたであろう。真正面からみるのではなく、ちょっとずらした角度から切り込む。対象をだしにしながら、自分の知識や思想を披露するやりかたがある。
吉本隆明編の『ナショナリズム』に対してもそうだ。自分の知識と思想の披露をする。戦略的といえば戦略的だが、まず対峙する自分の言葉(意見)を出さなければならぬということなのだろう。おべっかは使わない。否定と肯定なんてものではない。そんなものに意味があるとは思っていない。
以後の谷川雁の文章で安心して読めるものは『宮沢賢治紀行』と『ものがたり交響』、『ものがたり考』だと個人的には思う。大人の世界はつまらないので、子供の世界にシフトしていった時期の表現活動の産物だ。童話の世界に起死回生をみたような感じだ。大人を組織しようとするのはつまらなく徒労が多い。世界は子供だとするのは、ぼくにも共感させるものがある。
「教えるとは共に希望を語ること。学ぶとは誠実を胸に刻むこと」(アラゴン)
この引用は『谷川雁の仕事Ⅱ』の「編集余滴」から拾った。革命と教育は似ているようで非なるものである。理念をおしつけるものは教育ではない。〈希望〉という人間にとって最後の言辞をうしなってはならない。それは革命ごっこではできない。
革命運動が大人の世界の物語であるなら、童話は子供の世界の物語である。そこには自由な連想が羽ばたいている。うっとおしい固定した大人の社会関係がない。宮沢賢治の童話を作品ごとにとりあげて、解釈を述するやりかたに、谷川雁は生き生きしていると私には思える。
谷川雁は、夢で詩を書く詩人だったのだから、その夢がなくなったら書かないはずだとだれも思う。「谷川雁詩集」が1960年1月に発行されたのは偶然か戦略か。この時期の安保闘争に出されたのは運命だった。のちのサークル村運動。三池闘争、大正行動隊の運動。沈黙。……
ところが、また詩集をだしている。1985年に『海としての信濃』だ。この詩集のあとがきは長い。まるで自己韜晦を縫うような、あとがきらしからぬ、知的、暗喩的な文章がつらなる。谷川雁は、一時代のみごとな閃光。ぼくからいわせると「戦後詩はナツメロ」のフレーズをかくもみごとに残した詩人だ。が、この『海としての信濃』は詩的言語の抽象と緊張がものたりない。あの雁詩を知っているものは、肩すかしを食わされたような気分じゃないか。
詩は弱音を吐かない。ぼくのように、中也や朔太郎に詩を感じるものは、雁のような、剛毅な、かっこいい詩にあこがれると同時に、ボロがぽろぽろでてくる弱い人間に毒づく詩を好んで読んだり書いたりする。 これもまた事実。
谷川雁が1995年に亡くなったとき、沖縄の詩人同士の間で、その事実を語りあおうとするひとは皆無であった。谷川雁は、あの宣言の詩人で終わっていた。清田政信が「谷川雁論」を書いているが、これとて1968年、「詩・現実」5号である。そのあとの谷川雁は語られることはなかった。もちろん、存在だけはかぶさっていた。情念の断言と饒舌の美学。暗喩の詩人。……もはや幻の遠い詩人だった。「東京へいくな ふるさとをつくれ」というフレーズは、ここ沖縄では特別なフレーズとして響いてくる。就職のため東京へいかない若者が多い。就職してもUターンしてくる。競争社会のヤマトとの心理的差異に耐えられず帰ってくる、と沖縄の教育者や行政者が分析するが、そんなものは信じない方がいい。帰ってくるものは、生きる場所としての価値が東京にはないことに気づいているからなのだ。生きる価値のないところに長くいる必要はない。 脱出も運命。帰郷も運命なのだ。
荒川洋治の「谷川雁へいくな」という文章が響く。(谷川雁の仕事Ⅱ付録・河出書房新社)
「谷川雁の詩の美質は好戦性にある。革命幻想があったからそうなのではない。好きも嫌いもない。「男性日本語」の古層にある好戦的な性格を体現したからである。」
これはよくわかる。その好戦性は実際の戦争に参加しそこねたものの残滓心情として戦後にあったにちがいない。その男性心情がやりきれないのは、血と殺戮のリアリズムをのけてロマンチスズムに塗られていることだ。かれの詩のなかに流れるロマンチシズムに対して鮎川信夫が「日本ロマン派の戦後版だよ」といったゆえんが理解できる。谷川雁の詩は「たたかう男の詩」として読まれたのだ。「連帯を求めて孤立を恐れず」というフレーズのように。
谷川雁の書いたものは、男性的だし、負けた場所がないし、つねに前へ前へ、根へ、根へである。なにかあると思っている。挫折があるが挫折がない。男性詩人なのである。近代詩や現代詩のひ弱な、泣きべそかいている詩は好きじゃないのだ。
「瞬間の王は死んだ」、こんな詩人は忘れろ、といったが、かれは筆を折ったわけではなかった。
「「谷川雁は筆を折った」と何度か書かれて、そのままにしてきた。あらたまった決意をしたわけではないが、ほぼ事実に近い。厳密に訂正しようとすれば、それを書かねばならなくなる。おおげさに言わなくとも、書くよろこびがないから書かない。なぜ、ないのか。読んでほしいと思う顔が浮かんでこないだけのことである。書くという作業は自分自身のためにする行為だから、そのゆえに現実または架空の相手がいる。現実の相手も、気体にまで昇華しておかねばならない。だが、いつのまにか受け手を活性化する気持ちを失った。」(谷川雁「『神話ごっこ』の十五年」―『意識の海のものがたりへ』、日本エディタースクール出版部、1983、初出『毎日新聞』1981・9・5、夕刊)
谷川雁が語りかける相手というのは、松本健一によれば「『工作者』が組織した大正行動隊の依拠すべき地方、漁民、山村民、鉱夫などの革命の砦としての生活民」(「谷川雁 革命伝説」)だった、という。エコノミックアニマルのネクタイ野郎達ではなかった。サラリーマンには革命は無縁だ。
松本健一の『谷川雁革命伝説』は甘いとらえ方である。このひとも好戦的な美の論者のように思える。
「どうして雁はああ、ポーズをつくるのが好きなのかねえ、と兄の谷川健一さんがいった。」(松本健一「『谷川雁の仕事』にふれて」)という。それは「武装」と松本健一はいう。……ぼくは谷川雁という人間がようやくわかってきた。
詩にするほどの境涯や経験や生き方や意志がないものたちが詩を書くことじたいむなしい。安定と平和と無危険と中産と無境涯で詩が書かれることが信じがたい。 名のある現在の詩人達が、どこかの大学の教師になりすましているのが多い。これが戦後詩のなれの果てだ。
「段々と降りてゆく」よりほかないのだ。飛躍は主観的には生まれない。下部へ、下部へ、根へ根へ、花咲かぬ処へ、暗闇のみちるところへ、そこに万有の母がある。存在の原点がある。初発のエネルギイがある。」(原点が存在する)
じつに美しい。革命運動経験のないものにとっても、このフレーズは思想言語の感応として憎いほど官能的だ。とりこにさせる。時代が空虚になびいているとしてもだ。とくにこの沖縄のいまの現実には反基地運動の表層の闘争がやむをえず花を咲かせているが、しかし、やがてくるだろう。下部と根へ向かうべき時が。
(「脈」82号 2014/11 に書いたものを一部訂正して再掲載)











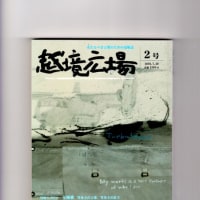
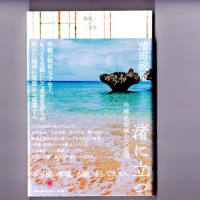
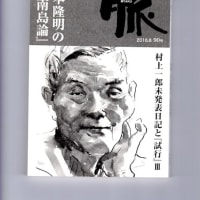
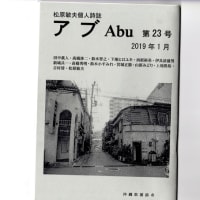
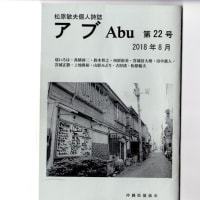
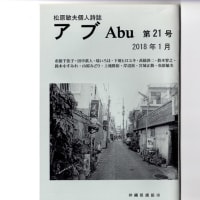
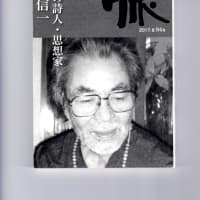
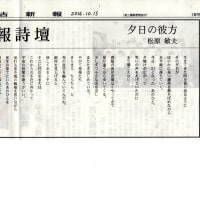

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます