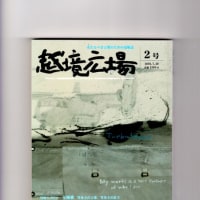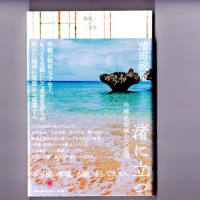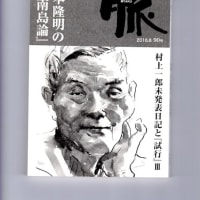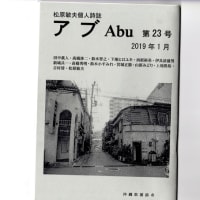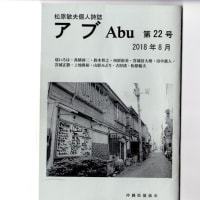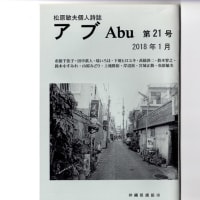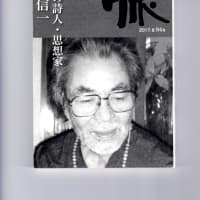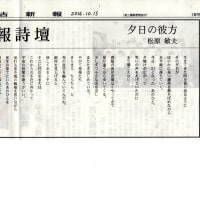新しいウイルスの流行が世界を一変させ、つねに〈感染リスク警戒〉を強いられ、経験したことのない日常生活にあるなか、比屋根薫氏から『琉球的思考の花歌』という分厚い本が送られてきた。ページ数も多く装丁が立派な本だ。平敷武蕉が出した『文学批評の音域と思想』について中里友豪が出版祝賀会で「まくらになるような本」と形容した分厚い立派な本をみて、びっくりした時があったが、比屋根のこの本をみたときも批評家はどうしてこんな立派な本を出すのか不思議な思いと同時と執念のような思いに耽ってしまった。書いたものや、発言の内容がすべてだ、なにも立派な本にしなくていい、というのが評論、批評に対する私の思いがある。それは偏見であることはわかっている。比屋根のこの本は、おそらく最初で最後の著作だという決意でだしたのだろう、と勝手に想像してしまった。
なにしろ五十年間の思索を書き継いできたものを一冊にした著作である。思索の足跡を年月順に配列しているので、比屋根薫という批評家の思惟の足跡を読むことができる。そこには生の行程と時代体験と他者の言説や表現にかかわる思索の姿があり、時代の思想を追及したまじめな努力家、相当な勉強家であったんだなと感心するとともにその継続に敬意を表したくなった。コロナ禍の最中であるが、今年は東京オリンピック開催でにぎわうだろうが、来年は沖縄復帰50年という節目であり、そろそろマスコミ、言論界で特集やトピックやら騒々しくなることが予想されるから、50年に流れてきた思想世界の捉えなおし、再検討のきっかけになるものであればいいと思うし、そういう読み方をしたいと思う。
比屋根は私と同じ団塊の世代である。さらに言えば「全共闘世代」である。この称し方は彼がその世代を存在証明的にあるいは時代体験を故意にだしてそう称している感じがあるから、同時代を生きたものとしてかれの言説の罠にはいってしまうのを厭わずにつきあう読書となった。もはや昭和時代の学生運動の遺物的歴史としてみられるこの時代的世代はいまなお元気であることを身体と思考に鞭打って這いつくばりながら語らねばならない心意気をもたねばなるまい。この本には、そんな同世代のヨシミを感じつつ時代の言葉を読むという読書の快楽が潜んでいる。そして一方では、この世代はいま生存の過程で不可避の健康喪失と死へ傾斜する時間にあり、現役から段々と下りていく年代である。団塊から団死の世代、と揶揄的にいっておこうか。
砂川哲雄が最近の詩集『とぅもーる幻想』で書いた詩編のひとつはわれわれの生的状況の現在を表出している。
きょうもまた近しいひとの訃報が届いた
ひとひらの枯葉が落ちるように
たしかに老いはじめたものたちの
身近になりつつある死
未知の世界から
無言の声が告知する
おまえたちのいのちも
けしてそう長くはないよ
(残照)
こういう迫りくる老いと死の心境詩がぐっとくるのが団塊の世代の現実である。死は身近になりつつあるし、君らも長くはないよ、という「告知」の言葉は「そうだね」と実感するものがある。しかし響いてくるのは社会の現在と自分の現在は同時ではないということだ。この世代、ぼやぼやしていたら、忘れ去られ、はじかれ、消されてしまう。常に声を上げるように心がけておくことが肝要だ。と思いつつも私のような気の弱いものは、こういう現在の流れとズレが強くなってくるのも事実だ。自己のおかれた私的な状況と社会や思想の流動と乖離がでてくるのは仕方のないことである。迫りくるものは生理の宿命だから抵抗してもどうにもならないが、終活がまじかになっているわけだし、もういまさらなんやかんやいう場合じゃないのだというのもたしかだが、ただ「老いの志の気概」があるうちに始末をつけておくのも悪くはないなという気がするのもたしかだ。
全共闘世代あたりといえば、ほかに高良勉、仲里効、仲本瑩、又吉栄喜、大城貞俊、上地隆裕、仲里哲雄、矢口哲男、安里昌夫、髙橋渉二、上地昇、松島朝義、宮城秀一、西銘郁和、砂川哲雄、ローゼル川田、高嶺剛、石川為丸、……といった面々も浮かぶ。本土では佐々木幹郎、荒川洋治、稲川方人、竹田青嗣、笠井潔、中上健次、村上春樹、加藤典洋、村上龍、高橋秀明、神山睦美、佐藤泰志、橋爪大三郎など(知っている名前だけあげたが)が浮かぶ。学生運動したかどうかにかかわらず、全共闘世代とひとくくりにするのは、セクト、ノンセクト、ノンポリ、政治(革命)運動家などと区切らなくとも時代の渦のなかで青春を過ごしたという意味でいっている。全共闘世代と呼ばれることを好む人もいれば嫌う人もいることはわかっている。しかし、青春時代がその時代であったということは質を抜きにして共通するものが確実にあったはずである。この同時代の者たちがどんなことを考え、どんなことを書き、なにをやっているかに関心を寄せるのは、世代的共有でむすぶ甘いガラスの絆があるからである。それで今みんなどうしているのか。
ひと息ごとに遠のいてゆく歩道の経線を追い
同志の死を報じた新聞を抱え急ぐ
黙然と秋の日射しの距離を測っている
休日の公園の小砂利は
力なく広がり 午後
ふとぼくは耳元の声を聞いたようだーなにをしている? いま
(佐々木幹郎「死者の鞭」、『死者の鞭ー1967~1970』所収)
久しぶりに佐々木幹郎の半世紀前の初期詩集を読んで、この詩に詠みこんだ1967年10月羽田闘争の死者は時代の死者であり、われわれの世代の死者でもあったことを改めて思い出した。あの時代の死者から「なにをしている? いま」とささやかれる「死者の鞭」は強迫観念のように続くのだが、しかし、それから70年代、80年代、90年代、2000年代、10年代という時代の推移と世界や社会の変化と世代の年齢の重ねに対応せざるをえないし、身体的衰弱に抗しながら、培ったその精神の思考をなお根っこに隠しながら、いまあの時代の行動と存在と空気を想起し苦々しい回帰のように佇む姿がある。われわれは、あとにきた世代に時代を譲り、世界や社会の変化の貌をみつめながら「思考を続けること」、それに加えて「表現を続けること」こそが、課せられていると思うようにしよう。
比屋根薫の、この著作も半世紀の時間の思考を積み重ねながらできあがったものである。
比屋根はデビュー作である「沖縄・琉球の問題とは何かー「さまよえる琉球人」に就いての諸注」(沖縄タイムス、1970・12・16、17)をひっさげて沖縄タイムスにのりこみ、川満信一に会って、新聞掲載を頼み込んだとき、彼に「なにがやりたいの?」と聞かれて、「小説を書きたい」といったらしいが、その初志を貫徹実行すべきであったのではないだろうか。しかし小説を書くまえに、批評という思考の快楽に手を染めて、それにひきづられて抜けきれなかった。結局、「文芸批評」や「思想批評」に専念して、その道を歩き続けてしまった。これはやりたいことから方向性を転じた、つまり方針転換であった。それを今どう思っているのだろうか。なぜそういうかは、比屋根の感性はもともと文学的感性をもっている人だなと思えるからである。その感性は批評文やエッセイの随所に貌を表しているところみてもわかる。小説を書くことを封印して、文学作品を書く行為から離れて状況や思想に関わりすぎてしまった。経験上いえることだが、批評にうつつをぬかすと作品が書けなくなることがよくある。とはいっても、文学創造の欲望を文芸批評で果たしてきたから、結果、オーライといえばいいか。彼がかつて『琉大文学』に大城立裕批判の「亜熱帯の方法的制覇」(1971)を発表したのを読んだとき、元気な文芸批評家が出てきたなと内心喜悦したものだ。なにしろ清田政信以来、文学状況に対する批判的言辞を表明したひとが少数だったからである。
この著作で、はじめに感じたのは「琉球的思考」といういいかたである。思考の基点と方向性を指していると思うが、ほんとは「琉球というアポリア」を超えたいのではないか。でなければ「世界的思考」「世界の存在的思想」を求めてきたことのあるはずである比屋根薫自身にみえかくれする、世界をとらえる方法としての「現象学的思考」がおかしくなるというものである。比屋根が本気で「琉球意識」をアイデンティティ主義のようにもっているとは思えない。いや、そうみるのは、あるいは誤解か。かれが吉本隆明の「異族の論理」や島尾敏雄の「ヤポネシア論」「琉球弧」や新川明の「反復帰論」に異常なほど関心を寄せ、いや関心どころか、自分の思考、思想の礎にしている、しようとしているところをみれば、あるいは、本気でいっているかもしれない。
「琉球的思考」にはそれらの思想の継承、深化された自己表出が課題として付されている。それをかれは追い続けてきた。「琉球的思考」という題名にいちゃもんをつけるつもりはない。比屋根が若い時から、読書家であり、広い知識や思想の所有、批評意識の強さなどに私は足元に及ばないから、対峙するつもりはない。私はただの文学主義者にすぎない。文学的言語、文学・芸術表現的思考、反定型好みの立場で文学作品や状況や思想をみてやっているだけのポンコツ素浪人だ。だから、勝手な感想をいうのは著作全般をとおしての印象であるから誤読があったとしてもご容赦ねがいたい。
比屋根は、「琉球的思考」は「沖縄で生まれ」「私が琉球だから」という。それは、決定的であるようにみえて弱すぎる。土着思想とたいした違いがないからだ。土着は無意識の思想と変わりない。しかしナショナリストになっては困るから、比屋根は、そこはちゃんと「距離感」を心得ている。高良勉のようにヤポネシア論や琉球弧を思考方法に取り入れ、その思想に同化する地点から沖縄ナショナリズム的な方法で書く地点に陥ってはいない。ナショナリズムにならない、ナショナリズムを拒否してたつ新たな思想というものを全共闘世代は持っていたはずである。では彼は学生運動のどの地点にたって思考を開始したのだろうか。全共闘の流れが比屋根にたしかにあるが、彼自身が、セクトや革命組織に入って運動していたのではなく、偶然に東京にいて、そのときの新左翼学生運動の沖縄闘争の現場に遭遇して、その運動の流れに参加して行動したために警察に逮捕され留置場に拘束されたが、懲りずに以後運動に参加してきたという経験があることは彼が何度も書いているので、そういう人間であることを前提にして尋ねているだけである。彼は、いわゆる革命運動家から言わすれば「ノンセクト・ラジカル」の部類であったのだろう。
セクトに入って実際の運動をしたかどうかはどうでもいい。そのとき、おそらく新左翼学生運動は「沖縄闘争」「沖縄奪還」とか「沖縄解放」とかスローガンにしていたはずだ。全共闘運動は当初は大学改革、授業料値上阻止、といった現実的なキャンパス闘争だったが、やがて政治的な命題を帯びてキャンパスを越えて「反体制」「反安保」「革命闘争」に拡大していった活動でもあった。そこにマルクスもゲバラも毛沢東もレーニンもサルトルも一緒くたにして未分化のまま、反体制、反帝国主義、反資本主義、階級廃絶の革命思想に費やされた。既成左翼やスターリニズムは前衛性を標榜しながら停滞に気づかず、大衆運動を党勢力の拡大の目的に利用することしか考えていなかったし、反体制を体制化しようとする位置をとりつつ、新左翼運動に「過激派」「トロッキスト」というレッテルをはることで組織防衛するのに邁進していたから、60年安保からさらに進んで旧左翼神話は完全に崩壊したといっていい。ところが新左翼運動も、思想のゲバルト運動に転化し、エスカレートして、戦術上の過激化、拡大、分裂を繰り返して、ついには内ゲバの死闘をするまでになって自壊してしまった。1972年2月の連合赤軍のあさま山荘事件は日本の革命運動の終焉の姿であった。熱狂が覚め、追い詰められたものの手段はテロリズムであったが、テロリズムは敗北の火花に過ぎなかった。この辺の経緯は関連する書物や映像に詳しいので、これ以上はいうことはない。ここで文学主義の立場から言いたいのは、テロルは現実化するよりも想像力の世界での表出がふさわしかったということだ。日本主義者の文学者三島由紀夫もそこを誤って、日本的想像を現実化、実践する逆の道をとってしまった。ま、そこが言行一致という武士道精神、日本主義のなれの果てだったかもしれない。饒舌はそれぐらいにしておこう。
沖縄に生まれたものが「自覚する存在」というものに、「沖縄人」とか「琉球人」とかがある。「南島人」とかはさすがにない。この「沖縄人」とか「琉球人」とかいういい方は他郷とのちがいからあるものだが、琉球人を展示した人類館問題に象徴される近代日本での同化過程で差別の歴史と経験から沖縄人にはヤマト(日本)に対する特殊な心理や感情が働くものとして形成され、日本社会で異化される存在であることを意識させられてきた。ところが近年は逆に先に自身を様々な場面で沖縄アイデンティティ意識で語るようなシーンを多く見るようになってきた。比屋根薫がいう「沖縄で生まれ」「私が琉球だから」という発想や自覚も「沖縄人」意識、「琉球人」意識を媒介にしているからだが、しかし、かれはそれを自分のアイデンティティにしようとしているようには思えないから、だからこそ、現在飛び交う啓蒙的な沖縄アイデンティティ主義、しまくとぅば復興ブーム(沖縄文化主義的な匂いを感じるが)への言及をすべきだろうが、それをあまり語っていないのはどうしてなのか。反復帰思想の精髄が大衆に理解されずに、ムーブメントになれないのはなぜなんだとぼやく前に「沖縄アイデンティティ」「しまくとぅば運動」を彼なりに思想的に対峙した本当の言説を出すべきではないか。そうならないのは島尾敏雄の「琉球弧」や沖縄文化主義思想の轡に追従するからか。
首里城再建に対して、少数の意識家の言論を除いて反基地や平和、民主主義の運動に情熱を燃やす沖縄運動家たちが内実に無言でいるのは解せない。それどころか、首里城再建にまつわる〈手放しの首里城賛美の沖縄的状況〉に加担する傾向がある。強固な身分差別を敷いた封建制度で貧しい琉球の民を搾取支配し、血なまぐさい権力争いを繰り返してきた琉球(首里)王権国家の内実の不問、薩摩藩支配の苦渋の歴史、近代、沖縄戦、米軍支配を経て、中国文化の影響を受けたきんきらきんの赤いお城が復元されて、これが沖縄の文化だ、シンボルだ、象徴だ、宝だ、誇りだ、琉球王朝だ、この邦はすごいぞ、沖縄・琉球………とかとか観光文化コピー語で語られる首里城(平和の象徴という著名人もいることに驚いた)というものに、われわれの意識の中の〈なにか〉が収斂され歪曲されている現実に違和感はないのか。観光目玉に活用され観光経済が豊かになるのはいいわけだし、建築文化の姿をみせることに活用されることもいいことだ。しかし身近の内なる歴史や国家を問わない都合のいい「琉球・沖縄イメージ生成への無自覚な邁進」(沖縄志向主義)という印象があってじれったいのだ。
この五十年を回顧してみる。かつて盛んにいわれた沖縄の知識人、文化人、教育者をはじめとした各界が悲願した、本土並みへの引き上げ、沖縄人の「劣等意識」「被害者意識」の解消が根強くあったが、彼らとは別に、若い民衆の側の自主的な上昇志向(がんばる精神)の実践によってそれは超克されてしまった感がある。例をいえば、具志堅用高の世界チャンピオン、甲子園での豊見城高校、沖縄水産高校の活躍からついに沖縄尚学の優勝(初の全国制覇)や興南高校の春夏連覇、安室奈美恵やスピード、仲間由紀恵、新垣結衣、GACT等の芸能界での活躍、ほか各界の若者の活躍が、いかに沖縄人、沖縄県民の劣等意識、被害者意識を克服させたかは多くの人が感じていることである。そのことを書いている人が多いから多くはいわない。ただ復帰以後の、本土化過程で、いまや沖縄は自立経済の問題を別にして〈ほとんど本土並みになった〉ことを確認することだし、もはや本土コンプレックスは表面上ないといえよう。そのプロセスは沖縄アイデンティティを言い出して鼓舞するまえに、その世界で頑張る、活躍することだった。このことはかつて米須興文が、沖縄人が沖縄という場所の文化意識から「日本のなかの文化創造者」になることが必要なことだ、といったことに通じる。
「………自我否定的なパターンに陥ることなく………(略)………明日の日本文化創造の作業へ積極的に参加することである。沖縄人が受けついできた象徴体系を死滅させることなく日本の全体的な体系の中で生きのびさせ、新しい体系の創造に貢献させることである。日本文化と沖縄文化を同時に自己のものとして認識し、さらにその認識の先端で新しい文化創造のために未来へ向けて実存の第一歩をふみだすことなしに沖縄人の主体性の確立は望まれないであろう。」(米須興文「文化的視点からの日本復帰」―叢書わが沖縄第6巻「沖縄の思想」木耳社)
谷川健一編による『叢書わが沖縄―「沖縄の思想」』は復帰後の沖縄がいかにあるべきかをテーマに1970年12月に出されたものだが、(新川明、川満信一、岡本恵徳らの刺激的な文章も入っている)状況がホットな時期だけに「これからの沖縄への思考」が表出され注目されていた本である。米須の主張は両義性をうちだしているし、復帰の受容感を前提に思考を前に進める姿勢がある。
旧世代が心理や感情に埋め込んでいた〈劣等感〉〈差異意識〉を復帰後世代がそれほど持たずに、日本のカルチュア界やスポーツ界に自然に参加し、結果を出している。そして現在も続いている。彼らは沖縄人だからという意識を前もって所有して頑張っていた(る)のではない。本土(日本)の文化、スポーツのステージに普通に参加してその同次元で頑張ったということだ。その快挙や活動を沖縄県民が〈沖縄人〉としての活躍として(同化)して、フイーバーするのは自由勝手でいいし、そうあるのは当然である。感情と精神は属性から自然にでてくるものだからである。しかし、はっきり言えばかれらの活躍は実際は個人の活躍なのだ。個人として頑張ったのだ。共同体意識で個人の活躍を自己同化するのは別次元のことである。個人の活躍=共同体出身の活躍とみるのはあって当然であるし自然であるが、個人で頑張ったということがまず前提である。共同体に属する前に〈個人〉というものが存在するからだ。安室奈美恵がシングルマザーの母との生活で地域共同体のなかでいろんな境遇にあったことは知る人ぞ知ることである。彼女が才能で頑張って芸能界のスーパースターにのしあがったのは、共同体のなかでの、その逆境をばねに個人の頑張りで成功したからである。彼女は沖縄人だから頑張ろうとする精神でいたのではない。
スポーツで勝利を得たもの(たち)が、ときどき口にする「沖縄の代表として頑張る、沖縄のために頑張った」とか「沖縄県民が応援してくれた、その応援のおかげで勝利を手にした、感謝したい」という優等生的な言葉は、〈郷土意識〉からであって、知識人がいう歴史をかぶせた〈沖縄人意識〉とは異なるものである。知識人のいうそれは、歴史や政治的な負の意味を持たせていうが、かれらにはそういう意識は薄いだろう。いや、ほとんどないといっていい。あるのは郷土意識、県民意識という単純なものである。沖縄人と日本人、その間にある歴史的、政治的な問題、ましてや異族という意識はない。その辺は、おそらくこれから復帰50周年に向けて新聞社や研究者などが県民意識の調査をするだろうから、その結果を待ちたい。
復帰年生まれが50歳になる。かれらもすでに中高年である。昭和も平成も終わり令和の新時代がやってきて、復帰前のあんやたんを知る旧世代はだんだんといなくなる。沖縄社会の人口構造も大きく変容している。沖縄本島の中南部地域は、県外、離島から流入した人々が多く移住して住んでおり、一種の近代都市としての体裁がある。しかし、その都市のなかの個人は生れ落ちてからのそれぞれの出自の運命とか境遇の歴史に呪縛された物語を生きている。都市や近代の共同体はそういうさまざまな個人を包摂してうごめいている。
本土の経済、文化、スポーツ、情報、システム、風俗等がすっかり定着し、その環境で育った世代が「しまくとぅば」なんか使わずに、共通語としての日本語を自然に使うし、本土との往来も自然にやるし、そういう傾向から、もはや日本人であるということに疑念をいだく世代はもうほとんどいなくなっている。沖縄人は日本人じゃない、日本人と沖縄人は異族だ、という旧世代の主張(思想)は復帰50年後の現在には、むなしく響く。やはりいま沖縄人は「沖縄人であって日本人」なのだ。では沖縄人=日本人なのか、というとそこまではいってないかもしれない。その間にはやはり間隙がある。沖縄人であって日本人でもあるとしかいいようがない間隙だ。この「も」が微妙に揺れ動くのが沖縄人の現在である。ある沖縄人(ウチナーンチュ)が本土からきた人に名前や言葉づかいや感覚のちがいで「ヤマトンチュ」とか「ナイチャー」とか本土人=日本人として意識することがあるのは事実である。それもなんとなく出てくる。その間隙は感覚的でもあるし、潜在する意識や感情のズレが噴出するときでもある。そんなときに文化や習性や言語の差異が出るだろう。しかし、これも微妙である。その差異は個人的なものである場合もあるからだ。同じ沖縄内でもシマ(地域)が違えば習慣やことばの違いがでてくるし、同じ共同体に生活していても、考え方が個人的なものとして、差異が出てきて対立することがある。地域のちがい、家系のちがい、性のちがいでもでてくる。その間隙は匂いのようにあって根深いものがある。
コロナ流行で延期された東京オリンピックが今年開催する動きになっている状況であるが、オリンピックやサッカーやラグビーのワールドカップなどの世界大会、WBC世界野球大会があると、沖縄人も日本国代表の選手を屈折や違和感なく自然に応援する。沖縄人か日本人かをことさら思うまでもなく、われわれは生まれた時から日本人だという意識を自然に持っている世代が圧倒的になっている現状で、政治を持ちこんで、反復帰だ、独立だ、反ヤマトだ、というのはもはや時代にそぐわない。かつての時代は「あんやたん」でしかないのだ。現政権の構造的差別がどうのこうのいっても、そんなこと気にしないし自然に応援して日本選手(チーム)の勝敗に歓喜したり悔しがったりする。大衆は普通に生活ができ、生活を楽しめればいいわけだし、「物呉ゆすど我あ御主」という沖縄俚諺は批判されるものでもないし否定されるものでもない。私自身もスポーツをテレビ観戦することが好きでよくみるのだが、県選手、県勢チーム、日本チーム、日本選手が勝利するところをみると内心喜んだりする。
しんに問題にすべきは社会の中の現実にある問題を本当の問題としてみるべきだ、というのがポンコツ素浪人の意見である。差別の問題でも政治的な意味での差別よりもっと深刻な人間社会の偏見と差別の問題がある。貧困、犯罪、障害者の問題、ジェンダーの問題、少子化、医療・介護、高齢化の問題、社会病理の問題もある。こういう生活社会にある問題がしんの問題である。政治の問題は全面の問題ではない。全く問題がないとはいわない。辺野古移転基地問題も重要な問題である。しかし日々の生活、社会のリアルに生きる大衆にとって深刻さの認識度は低い。団塊世代の井上陽水は、「テレビで誰かが国の将来の問題を深刻にしゃべっている。問題は今日の雨。傘がない」と歌った。今日明日の生活に懸命な大衆にとって政治の問題は小さい、と誰かがいったが、そのとおりだと思う。誰かが、それは思想の問題ではないといえば、私はそんな思想というものはつまらないと言い返すだろう。
吉本隆明が大衆の原像を思想の基点に据え、縦横化、縦深化しとらえ、言語論、幻想論、心的現象論を展開したのは、マルクス主義的な思考ではなく自らの自立の思想(思考)で課題を徹底したからである。つまり、大衆の現在を素手でみることで人間の現在の根源を把握し、本質的な問題を俎上にのせて思考したからである。なかでも私が強く関心を持ったのは『心的現象論序説』、『心的現象論本論』である。この著作は、とても難解で私自身も何度も読解に挑戦しているが、なかなかである。吉本の思想はほんとうに先をいっていたんだなと思う。そして、これだけはいえると思う。これまで誰もやらなかった、人間の、存在と関係にかかわって発生する心や意識の世界=心的現象を読み解くことに挑んだ普遍的な、まさしく重要な〈世界思想〉であるということである。もっといえば、われわれが読んだり書いたりする言語の幻想活動としての詩や文学の究極は、必ずや吉本隆明が追求した「心的現象論」の課題にいきつくといっても過言ではない。
「どんなことも、知的な孤独を体験しないで、できることなどない」
(『心的現象論序説』、全著作集のためのあとがき)
という吉本の言葉には思想家の覚悟がある。
「花歌」という題名に、竹中労の『汝、花を武器とせよ』を想起した。どちらにも「花」という語彙があるが、違うのは、竹中労の「花」は社会の底辺に生きる女たちである。比屋根薫の花歌は喜納昌吉の「花」のように綺麗すぎる。汚れがない。なにしろ、かれには「思想」が大事だからだ。思想と関係ない底辺の女たちや民衆は相手じゃないんだろう。下層民衆のアナーキー性(なんならアナーキズムといってもいい)に思想の根拠をみるべきものがある、と私は思っている。花はきれいな土壌で咲くものより、汚れ、疎外された場所の土壌に咲く花がいちばん美しい。花歌にはその匂いがなければならない。(竹中労が絶賛していた民謡歌手嘉手刈林昌の愛弟子大城美佐子が亡くなったからか、NHKの特番で「夢幻琉球ー大城美佐子の世界」が放映された。高嶺剛が作ったものだった。フランスのパリで撮ったもので、なかなか面白かった。それにローゼル川田が高嶺の映画『夢幻琉球つるヘンリー』に出演していたのを知ってびっくりした。これまでみていなかったので、なおさらびっくりだった。ああ、そうか、出ていたのか。感慨深くなった………)
比屋根もパリに一年ぐらい住んでいたらしいが、この本には、パリでのことがあまり書かれていないことが物足りなかった。屋根裏部屋でじっと住んでいたのか、ただ、パリにいただけだったのか。なにをそこでみたのか、なにをしたのか、だれに会ったのか。その姿があまり出てこないのが惜しい。比屋根にとってパリとは、外国とはなんだったのか。
沖縄の作家(大城立裕、崎山多美、目取真俊ら)への言及が多々あるが、東峰夫に言及するのがあまりないのはどうしたのか。これは比屋根が文学作品を政治的、思想的、状況的な意義の側面から読もうとする習性があるからだろう。そういう傾向のあるひとがほかにも多いから困ったものだ。その習性はまちがっていないが、つまらない。東峰夫はまさしく沖縄人の、沖縄的な意識と感性と習性の生き様をもって、ヤマト(東京)での底辺社会を生活していた。私は東峰夫にもアナーキー性をみるものである。東峰夫は権力や権威が大嫌いな作家である。かれの作品を読むと共感がしきりとでてくる。社会の底辺に棲む〈小さき者たち〉に軸を据えながらの文学は沖縄文学の傍流ではなく本流でなければならない。そういう意味で私は亡くなった啓蒙主義的作家大城立裕の小説のなかでは「カクテルパーティー」や「琉球処分」などよりも、小さき者たちを描いた「芝居の神様」という短編にいちばん心を寄せるものである。沖縄イクサが始まるときの沖縄民衆のある一家を描いた「亀甲墓」もいい作品ではある。
この著作で気付いたことは、本格的な「論」がないことだ。マルクス、ヘーゲル、現象学、フォイエルバッハ、吉本隆明、島尾敏雄、川満信一、新川明からよく学んだようだが、ならば「吉本隆明論」や「新川明論」、「川満信一論」を展開しなかったのが、物足りない。たしかにBzに引っ掛けたものはある。しかし、あれだけの読書をしているならば、特に吉本隆明についての彼なりの、まとまった論があってもいいのではないか。評論家の段階に終始しないで、彼自身が影響を受けた思想家についてまとめた、〈彼自身の論〉があってもいいのはないか。
「沖縄の思想とは、反復帰論にきまっている。」(まえがき)
と書いているところを読んでから
「川満さん、わたしたちはあなたの思想的営為の結晶である『沖縄・根からの問いー共生への渇望』『沖縄・自立と共生の思想―「未来の縄文」へ架ける橋』をたたき台にし、島尾さんが目をみはるような言説を展開する心意気で、やがて川満さんをおびやかすほどの力をつけるよう研鑽を積み、後に続くつもりです」
(空虚な現在に生きる、オキナワ状況88同時代のメッセージ、現代思想としての〈南島〉、1988・5・2)
この箇所を読んで笑ってしまった。1988年からほとんど変わってないと思えたからである。いまなお「沖縄の思想は反復帰論に決まっている」といってしまっちゃあ、どうしようもねえじゃないか。ほとんど停滞しているじゃないか。50年もたつんだぜ、50年も。まだ反復帰論なんかいっているのかよ。比屋根に染み付いた、その依存思想はまったく困ったもんだぜ。せいぜいそこから出現したのは独立論ぐらいのものじゃないか。独立論にしても、かつての琉球王国(国家)を根拠に併合だの植民地化からの脱却だのといっているにすぎない。沖縄の未来は琉球王国への回帰でも琉球共和国でもないのだ。むしろ私は日本国でもない琉球国でもない、非在の、もうひとつのクニをほそぼそと夢みたい。私自身の描くクニ、社会だ。それは想像力の、文学的存在になるかもしれないが、そういう妄念はもっておきたい。私は国とか国家というものになじめない。そこには共同体維持に必然化する権力のいびつな姿ができるからだ。これは逸脱好みのポンコツ素浪人のたわごととして無視してかまわない。個人的にいうなら個人が同次元にある共同体が好きだ。それはすでに川満信一の「琉球共和社会憲法」に一部出ているが、未完、未成の思想の遊びとして読むと面白い。それに仏教的な慈悲思想から編み出した共生思想が根にあって、われわれの地平的な思考を超えている。
異族論、ヤポネシア論、反復帰論、ポストモダン、現象学、「琉球的思考」、エロス、欲望といった思想的、哲学的語彙、言説が躍っている、この著作は、文学的思考と思想的思考が融合したり乖離したりしているが、ほんとは、やがてむすびついて比屋根自身の言葉、思想で語っていく方向性がみえてよいのだ。しかしなにか別の方角にスキゾしてしまっているように思えてしかたない。先行者の思想や思考に依存して脱けていないがゆえに物たりない。吉本隆明に与那国島で「そろそろ自分の頭で考えたらどうだ」といわれたらしいが、吉本の厳しい貴重なアドバイスを肝に銘じて腰をすえて自分の言葉を創造してくるべきだった。今後、比屋根自身のパンセとコギトが花開いて実を結ぶのは、来るだろうか。
沖縄でパンセとコギトを構築するには、沖縄という地の場所で佇み、ひとりで歩き、うつむきながら状況を見渡すなかで、感じ取る感受性の痛みと表出の言葉をときに静かにときに荒々しく吐き出して、なおその言葉の導火線に復讐され、夕暮れの海辺で朝の来るのをまつ。そのときには砂を噛むような〈ひとりの彼方〉を内域とともに遡行して自らの孤独なる個人性の言葉から少数の言葉を探し出すことだ。われわれには空虚な声ばかりがあるかもしれない。それを承知で現在と自らを交差させて、そこにみえるものとみえざるものとを双方向をもって対峙させながらみずからのパンセとコギトを生み出すこと。依拠するものに呪縛されている自分を解体して、歴史も営みも心的なものも明らかにすること。それしかない。やがてくる倒れるかもしれない日の時まで佇むしかないのだ。これはわれわれの詩的レジェンド、清田政信から学んだことだ。
「沖縄の思想とは、反復帰論にきまっている。…略……これがわれわれの最深で最前線の沖縄の思想である。」(まえがき)
「………沖縄の思想の根本的な組み替えとはなにか。反国家、反近代、反資本主義、反権力というわれわれの時代のアポリアがこれらのキーワードの錯誤のイメージに規定されていたことを本質転換すること、これである。」(同)
「新川の反復帰論は、まずやり残した近代をなしとげた後に(それが反国家の凶区である沖縄の反逆ということである)、それでも必要ならば独立の課題が日程にのぼるだろうなかば無意識のヴィジョンがかくされている。…略……とまれ、たくさんの修正必要部分があり、多くの異論があるにしても、反復帰論は沖縄の自立の思想的拠点なのである。その精髄は自由な自己決定ということである。もうおわかりであろう、自由も自己決定も近代が打ち立てた思考なのだということを。」(同)
「反復帰論は沖縄の自立の思想的拠点である。まだ一般意志を形成することができない反復帰論がいまだに生きているのは、その精髄が自由と自己決定の思想だからである。そしてそれは近代が打ち立てた思考であることを君の詩は同意してくれるだろう。しかし、反国家、反権力、反資本主義、反近代の思考を捨てることはできるだろうか。」(あとがき、空無化するラディカリズムが終わる夏、『あすら』57号、2019・8・28)
比屋根が好きな「反復帰論」思想に近代の終焉としての永劫回帰をみる過程に「反国家」「国家への反逆」を語ると解釈するなら、「反国家」思想をなぜ「無国家」思想へと進むべきとみないのか。新川明の「反復帰論」思想の生成に大沢正道の「アナーキズム」思想の影響があることは新川自身がいっているのだが、国家廃絶の絶対自由を志向するアナーキズムが「無国家」へいくためにはまずは「反国家」であらねばならないのは当然であるとしてもその先にあるものを語らねばならない。もっとも新川には「社会的自治の最高の発現」としての構想がある。そういう意味では、新川明の反復帰論を「ひとまず反国家」とみるが、それはいずれにしろ過程の思想でしかない。共同幻想の構築である「国家」を個の自立思想=個人幻想で超えるためには相当の苦難を払うことも覚悟すべきだ。日本の近代国家は個人を中途半端に仕立て上げ、集団=共同体のなかに収斂して、半端な個人にしている。半分は国家所属、あるいは民族個人として仕立て上げる。だから個人はいつでも個人でありながら、ある時期に容易に国家主義や民族主義に転がったりする。比屋根がいう近代の個人の欲望、エロスを徹底化したうえで、先にある資本主義の姿にみえるものは何であるかをみるとき、かれのいう永遠回帰というものが現実の政治と対峙したときに、おそらく人間の欲望は国家に同調し愚劣に個人を抹殺し、簡単にファシズムに陥る危険性がともなうのではないか。いまや、情報化社会の渦のなかで、ネット社会の氾濫する時代に、共同幻想や個的幻想の格闘がいかに現出し、自己存在を、自己の思考をいかにたたせるかを問うべきである。個人の存在が世界のすみに隠れるようにあったとしても、国家の管理情報システムはすみずみまで行き届き、個人が今何しているか、今どこにいるのか、わかるような仕組みができている。デジタル庁創設はその管理システムを拡大加速するだろう。AI技術が人間の知能を超え、人工衛星監視によって地上社会の隅々が国家管理されている現実では、個人の存在は危ういものであるといわねばならない。
「反復帰」「独立論」は「異族論」で根拠化されている。比屋根は、それに賛成なのだろうか。「沖縄の思想の根本的な組み替え」が「反復帰論」に収斂され、「自立の思想的拠点」とのたまうが、それしかないのだろうか。なんともさみしい。復帰後思想の生成を「反復帰論」に依存しすぎるのではないか。川満信一が「反復帰論は、いまさらどうだっていいんだよ」というのは当たっている。川満は仏教思想で現在をこえる思想を形成しつつある。かれの仏教思想への知識は広くて深い。川満は遠い所へ行っている。我々は、川満という仏陀の手のひらの上で呻吟しているだけかもしれない。おそらく自己決定の自由論も個人的なものと共同体的なものに分裂している日本的近代においては公益が優先して、個人の存在を希薄化するのに鈍感になる、それに抗する欲望を圧倒することが想定できる。
「反復帰論の核心は生の自己決定という精神の火柱のことであり、現在、反国家、反権力の思考ではそれを実現する ことではできない。」(文芸時評・反復帰論の精神の火柱、沖縄タイムス、2005年5月2日)
生の自己決定、とはなにをいっているのだろうか。比屋根の文章、見方で推定するしかないが、ここで言っていることは「反復帰論」は政治のことではなく、自己決定する個人の自由の問題であると解釈しているようにみえる。「自立の思想的拠点」というのは、そういうことなのだろうと理解するが、ここには比屋根の近代に依拠した思想性があると思われる。近代が与えた欲望とエロスの自由な発露を肯定しているようにみえるから、そういう地点での「反復帰論」思想の理解がある。しかし、これはかれの新川思想への好意的、依存的な理解という印象をぬぐえない。
新川明の「沖縄『独立論』のこと」(1997年)にある「国家を相対化し」「社会的自治の最高の発現形態」を目指すという論理は一見聞こえがいい。私には集団思考に依拠する思想は、権力支配構造を必然的に発生させると思われるから、思想的レトリックとして認めても社会的自治を構築し維持していくために組織が権力化し政治化する、新しい国家の発生と思えるから、一線を画すしかない。
個人からみる国家は、一国のなかにおいて多様性、個人性、その発露の自由、公平、公正、平等、差別なき社会を絶対的に保証するものとして妄想されなければならない。そうでない国家はごめんこうむりたい。
川満信一は書いている。
「………『未来の縄文』としたのは、中央集権国家の終焉を促し、その後の国家なき社会を、自由に構想していくためのバイタリティを夢見たためである。」(川満信一『沖縄・自立と共生の思想』―「未来の縄文」へ架ける橋、あとがき)
私は〈国家終焉〉の後に〈国家なき社会〉、つまり〈無国家社会〉を夢想する川満の〈未来の縄文〉思想に共感する。ついでに〈反権力〉を〈無権力〉にする思想を加えたらなおいい。新川の〈反国家〉=〈反復帰論〉は中途に固着した〈過程の思想〉として理解するしかない。
「未来の縄文」に触発されたら、沖縄の古琉球、グスク時代の歴史論なぞ話にならない。一万八千年前の港川原人や二万二千年前の八重山白保洞人といった先史時代の人骨が発掘され、この島嶼沖縄、小さな島々の遥か彼方に原琉球の人々がいたことに思いをはせると、まさに国家のない時代への、ロマン的心情が沸き起こる。これもポンコツ素浪人のたわごとと無視してかまわない。
「原風景というものがもしあるとするなら、わたしはそれを、〈個〉の時間と〈歴史〉の時間とがお互いを照射しつつ交叉する場所に設定しなければならぬ(それを方法といっても論理、あるいは知といってもいい、深層自体がそれを内知させるのだ)。」(アジア的風景 個の時間と歴史の時間の交叉)1986・8・23沖縄タイムス)
外国をめぐってきて気づいた比屋根のこういう言い方には私も同感である。原風景には何事もない平和な甘いノスタルジーだけがあるのはない。個と個が生まれ立っている歴史が交差する地点に自己存在があるのはたしかだ。比屋根にとって、それは外国でみつけることはできなかった。出自としての琉球、沖縄でなければならなかった。「あい、やっぱり、わんねぇ、ウチナーやっさあ!」だったわけだ。ところが、私の場合、そういう存在であることを知ったうえで、自分のみじめさと絶望さえ思った。琉球、沖縄のなかでさえ、貧しい歴史と貧しい出自と貧しい経済を自覚したら、〈私〉はこの世に茫然と佇んでいる空虚な自分をみつけるしかなかった。「島惑い」は個人化して内面に渦巻いていた。そして、〈自分惑い〉さえ潜在化してしまった。それを超克するために〈文学〉〈知〉に頼るような生き方を課そうとしていたことを思い出す。文学ではシュルレアリスムの考えに接近して、既成の自分を解体して、新たな自己を創造する方法にのめりこんだ。すると土着や風土や歴史から離脱していく。あるのは現在の素手の個人である。個の内面に文学・芸術的な豊饒な土壌があるというシュルレアリスムは〈芸術革命の孤独〉を介して、新たな人間理解に役立った。旗手アンドレ・ブルトンのフロイド、ランボー、ロートレアモン、ルヴェルディ、トロッキーや、人間の狂気と夢と無意識を援用し、自動速記、言語の偶然と衝突、超現実主義手法で顕在化する異様、異形、異端なるものの生成、そういう方法が人間の内面を創造的に開示する、というシュルレアリスムの文学、芸術観は魅力的だった。俗な文学者から「ひねくれもの」が好む文学・芸術とみるむきもあるが、ポンコツ素浪人の私には創造意欲を掻き立てるには天下一品だ。以来、心理学、哲学、宗教、精神医学などにも関心を持つようになったが、さらに数年前から私は越境してみんなから100周遅れて歴史、民俗学、考古学の現実的な知に接近している。「沖縄人はどこから来たか」「日本人はどこからきたか」などの考古学、人類学的視点にも関心を寄せている。最近読んだ沖縄歴史の本で、三山統一し第一尚氏をうち立てた尚巴志が本土倭寇系の人物である、との史資料を活用した史論や(折口信夫がかつて九州渡来の系統ではないかと言ったことがある)、現在まで流布している琉球・沖縄歴史学は奄美や先島(宮古、八重山、与那国)を軽視した「沖縄本島中心史観だ」という批判など、歴史の読み直しがあったりして、わくわくしている。島嶼である琉球・沖縄の、定説化された歴史や文化の言説は読み直しや問われるべき多くの課題があるらしいのだ。
この50年間の日本社会、沖縄社会が、高度資本主義、消費資本主義、金融資本主義、欲望とエロスの勝利にあることを比屋根自身何度もいっているから、ならば、その現在の沖縄社会の時点で、〈琉球的思考〉を深めてほしい。それには、思想の観念性からではなく、底辺にある現実に視点を移して、そこに広がっている、琉球的、沖縄的、オキナワ的な重層化したものを素材に自立思考を進めてほしい。日本的なもの=天皇制という解釈であれば、沖縄的なもの=琉球王国という定型になるだけだ。沖縄学の大家伊波普猷は琉球史とその事物(おもろさうし、神歌、祭儀、古歌謡など)を収集、発掘、記述することに一生を費やした。日琉同祖を語りながら近代日本と沖縄の裂け目と位相に苦悩した伊波の〈島惑い〉はそこからくる。この執念ともいうべき学者の愛憎は揺れていた。
柳田国男や折口信夫による沖縄には日本の古層がみつかるとした日本民俗学や古代学への収斂、弥生時代に成立した天皇制を相対化する沖縄古層の見方を編み出した吉本隆明の「異族の論理」(異族論ではない)、島尾敏雄の琉球弧論、岡本太郎の芸術的直観力による沖縄文化論、竹中労の沖縄底辺民衆の実像、谷川健一の先島から照射した沖縄、南島論、その他の学者、研究者、ジャーナリストやらに先行され、琉球、沖縄を吸収され、解釈を産出され、量産される琉球、沖縄イメージに、飛びつき、それに自分を同化する、怠慢、怠惰な己をこそ、われわれは恥じるべきといえよう。知的な孤独が足りないのだ。自戒をこめていっておきたい。近代だ、欲望だ、エロスだ、そんな時代だ、と浮かれるにはまだ早い。
(詩誌『アブ』第26号、2021年3月発行 より転載)