いやはや、お疲れモードが続く・・・
先日は県理学療法士会・県作業療法士会、
そして県医療ソーシャルワーカー会との交流会に出かけた。
略して3団体交流会。
そのまんまだが・・・(汗)
この交流会は毎年行われている。
話し合うのは、各団体の年毎の取り組み。
そして会を担当する士会から、情報提供。
今年は医療ソーシャルワーカー士会。
略してMSW士会。
今年の情報提供、それは・・・
「県の緩和ケア総合推進時事業の取り組み」について。
これは出ない訳にはいかない。
いいたいことがありすぎる(汗)
情報交換の後、県の医療対策課の方から情報提供。
まず、制度上の側面を話される。
即ち、本人・家族の側面と医療提供者側の側面。
その後に「癌対策基本法」の話になる。
それを受けて、我が県の取り組みの話。
さらに、今後の課題と提言。
緩和ケアアドバイザーとしての看護師取り組みと、
緩和リハビリテーションに対する療法士の役割と期待を話された。
その中には、県の未定稿であるが、と前置きされた上で紹介。
「緩和ケアを推進していく上での課題と今後の方向性について」
である。
この担当官の方は。緩和リハビリテーション、それ自体も最近知って、
さらにそれに取り組んでいるセラピストがいることを知った、
とのこと。
この未定稿で書かれているセラピストへの期待。
それは・・・
「緩和ケアを推進するスタッフ
(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士)
の養成が必要である」
#改行;Life
と記載されている。
他にもあるのだが、これほどセラピストへの期待も膨れているのだ。
で、質疑となり、質問というより現場からの報告をした。
まず、私が特養・訪問・通所で働いていること。
そして、介護保険の中で「ガン末期」が加わったが、
要介護認定において「要支援」など、
軽度要介護状態で判定されやすいこと。
まず、申請で一ヶ月かかるということ。
ガン末期の方に「一ヶ月」は貴重である。
ムザムザと見過ごしていいのか?といってみる。
軽度要介護となると、福祉用具は給付対象にならず、
また、「介護予防」対象になりかねない事実。
そして、よしんば要介護状態になっても、
今度は保険者側の綱引きがあるという事実。
即ち、ガン末期など医療の度合いが高い方は、
介護保険でなく医療保険で行うべきという意見が通達される。
せっかくケアマネージャーさんが整えてくれたのにだ。
これはガン末期だけでなく、難病指定された方多くに見られる。
ケアマネさんが手配してくれたのに、
医療にマネジメントが戻るのだ。
そして、頼りの「在宅支援診療所」も機能しているとは言い難い。
そして、施設ではやはり立ちはだかる介護職の医療行為。
これを言い出すと長くなるので、指摘するにとどめた。
そして、ご家族さんとの関係。
「生活がすでにリスクである」と知っているご家族さん。
「迷い」があるご家族さん。
「生活がすでにリスクである」と認められないご家族さん。
そんなご家族さんの話をして、
当のご本人さんのケア・支援の話をする。
それは数冊の本の紹介をした。
ご自分の職業を続けるために医療を使った、
「いのちの授業 がんと闘った大瀬校長の六年間」
神奈川新聞報道部 新潮文庫 平成19年9月初版
とにかく「治療」にこだわった、
「31歳ガン漂流」奥山貴宏 著 ポプラ社 05年8月第5刷
続編に「32歳ガン漂流Evolution」牧野出版
「33歳ガン漂流LaST eXIT」もある。
そして、闘うのではなくその最後のストーリを、
教えてくれる徳永進先生の本。
今回持って行ったのは「野の道往診」だ。
これらの本から、生活の差異は人の数ほどあり、
生活の質なんて「QOL」の一言では済ませられないという事実。
その質を決めるのは、他でもない、本人さんであるということを!
そして、それを支えるスタッフのこれからとして、
押川真喜子氏の「在宅で死ぬということ」。
文芸春秋からの出版だ。
押川氏の本を通して、今現在のスタッフの苦悩、
ケアするものをケアするシステムのあり方を問う。
そして、理学療法士・作業療法士のやるべきことは何か?
それはやるべきことはたくさんある!と発言した。
その方は、ガン患者でもなく、終末期の患者でもなく、
死ぬまで生きていらっしゃるという事実と、それに添うスタッフの役目、
それを話してきた。
どんな状態になろうとも、
私たちはあなたをささえますよ・・・
そういうメッセージが必要では?
なんて話して帰ってきた。
もう一人OTの方が、オピオイドについての提言をする。
これらを踏まえて県の方も、
「緩和ケアの研修会」を近いうちに開催したい、
それはコメディカル用のものも早急に・・・
ということだった。
高齢化社会は多死社会でもある。
これを支える社会保障。
さて、これから県の取り組みも始まる・・・
先日は県理学療法士会・県作業療法士会、
そして県医療ソーシャルワーカー会との交流会に出かけた。
略して3団体交流会。
そのまんまだが・・・(汗)
この交流会は毎年行われている。
話し合うのは、各団体の年毎の取り組み。
そして会を担当する士会から、情報提供。
今年は医療ソーシャルワーカー士会。
略してMSW士会。
今年の情報提供、それは・・・
「県の緩和ケア総合推進時事業の取り組み」について。
これは出ない訳にはいかない。
いいたいことがありすぎる(汗)
情報交換の後、県の医療対策課の方から情報提供。
まず、制度上の側面を話される。
即ち、本人・家族の側面と医療提供者側の側面。
その後に「癌対策基本法」の話になる。
それを受けて、我が県の取り組みの話。
さらに、今後の課題と提言。
緩和ケアアドバイザーとしての看護師取り組みと、
緩和リハビリテーションに対する療法士の役割と期待を話された。
その中には、県の未定稿であるが、と前置きされた上で紹介。
「緩和ケアを推進していく上での課題と今後の方向性について」
である。
この担当官の方は。緩和リハビリテーション、それ自体も最近知って、
さらにそれに取り組んでいるセラピストがいることを知った、
とのこと。
この未定稿で書かれているセラピストへの期待。
それは・・・
「緩和ケアを推進するスタッフ
(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士)
の養成が必要である」
#改行;Life
と記載されている。
他にもあるのだが、これほどセラピストへの期待も膨れているのだ。
で、質疑となり、質問というより現場からの報告をした。
まず、私が特養・訪問・通所で働いていること。
そして、介護保険の中で「ガン末期」が加わったが、
要介護認定において「要支援」など、
軽度要介護状態で判定されやすいこと。
まず、申請で一ヶ月かかるということ。
ガン末期の方に「一ヶ月」は貴重である。
ムザムザと見過ごしていいのか?といってみる。
軽度要介護となると、福祉用具は給付対象にならず、
また、「介護予防」対象になりかねない事実。
そして、よしんば要介護状態になっても、
今度は保険者側の綱引きがあるという事実。
即ち、ガン末期など医療の度合いが高い方は、
介護保険でなく医療保険で行うべきという意見が通達される。
せっかくケアマネージャーさんが整えてくれたのにだ。
これはガン末期だけでなく、難病指定された方多くに見られる。
ケアマネさんが手配してくれたのに、
医療にマネジメントが戻るのだ。
そして、頼りの「在宅支援診療所」も機能しているとは言い難い。
そして、施設ではやはり立ちはだかる介護職の医療行為。
これを言い出すと長くなるので、指摘するにとどめた。
そして、ご家族さんとの関係。
「生活がすでにリスクである」と知っているご家族さん。
「迷い」があるご家族さん。
「生活がすでにリスクである」と認められないご家族さん。
そんなご家族さんの話をして、
当のご本人さんのケア・支援の話をする。
それは数冊の本の紹介をした。
ご自分の職業を続けるために医療を使った、
「いのちの授業 がんと闘った大瀬校長の六年間」
神奈川新聞報道部 新潮文庫 平成19年9月初版
とにかく「治療」にこだわった、
「31歳ガン漂流」奥山貴宏 著 ポプラ社 05年8月第5刷
続編に「32歳ガン漂流Evolution」牧野出版
「33歳ガン漂流LaST eXIT」もある。
そして、闘うのではなくその最後のストーリを、
教えてくれる徳永進先生の本。
今回持って行ったのは「野の道往診」だ。
これらの本から、生活の差異は人の数ほどあり、
生活の質なんて「QOL」の一言では済ませられないという事実。
その質を決めるのは、他でもない、本人さんであるということを!
そして、それを支えるスタッフのこれからとして、
押川真喜子氏の「在宅で死ぬということ」。
文芸春秋からの出版だ。
押川氏の本を通して、今現在のスタッフの苦悩、
ケアするものをケアするシステムのあり方を問う。
そして、理学療法士・作業療法士のやるべきことは何か?
それはやるべきことはたくさんある!と発言した。
その方は、ガン患者でもなく、終末期の患者でもなく、
死ぬまで生きていらっしゃるという事実と、それに添うスタッフの役目、
それを話してきた。
どんな状態になろうとも、
私たちはあなたをささえますよ・・・
そういうメッセージが必要では?
なんて話して帰ってきた。
もう一人OTの方が、オピオイドについての提言をする。
これらを踏まえて県の方も、
「緩和ケアの研修会」を近いうちに開催したい、
それはコメディカル用のものも早急に・・・
ということだった。
高齢化社会は多死社会でもある。
これを支える社会保障。
さて、これから県の取り組みも始まる・・・


















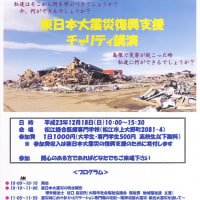
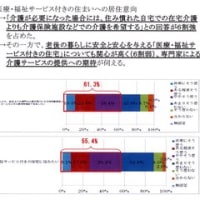
癌の患者さんの現実は、病状の変化の早いことに尽きると思います。
介護保険での申請主義では、日常生活用具にしろ、支給や貸与が後手後手に回るケースが多いのでは?
(義父を見ていての実感です)
「要介護」のケアの質が置いてきぼりになっていて、
なんのための「介護」保険でしょう。
どだい、普通の介護保険の対象疾患と癌の場合を一緒にするのは無理があると思いますね。
そういう現実をふまえても、今は介護保険でやっていくしかない、というのなら、
その部分を補う配慮が欲しいものです。
なかなか、難しいですが・・・。
介護予防対象高齢者・介護保険、在宅医療、
ターミナルケア・緩和ケア、終末期医療・・・
余りに制度が細切れで、どうしてもたらいまわし、
という個人的な想いを持っています。