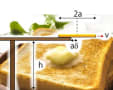「IH調理器とガスコンロ」でも書いたが、先日、2010年製の古いIH調理器が壊れたので、ヤフオクで中古のIHを落札した。 その間、1998年製の古いカセットコンロを復活させたら、火を消し忘れるという大チョンボを犯し、火事になる寸前だった。 そこで、ガスコンロをしまい、壊れた筈のIH調理器の電源をダメ元で押してみると復活したではないか。 これと同じような事が、タブレットでも起きたのだ。 昨年の6月 . . . 本文を読む
数学はよく”厄介すぎて偏狭的だ”と揶揄される所がある。果たしてそうだろうか? 確かに、数学という抽象的で難解な領域に閉じこもり、偏屈になりすぎてる部分もなくはない。しかし、現代数学ほどグローバルで自由と創造とアイデアに育まれた学問も他にはない。 例えば、我らを取り囲む日常の仕組みは大半が数学的で記述できる。勿論、100%とは言えないが、それは我ら人類が数学を100%理解出 . . . 本文を読む
あるフォロワーのブログに、”新聞紙1枚あれば宇宙を超える”とあった。 記事を読んでみると、とても興味深かった。 そこで、前知識なしで問題です。ネットで検索しないで、直感でお答え下さい。 仮に、新聞紙1枚の厚さを0.1ミリとして、新聞紙を100回折り曲げたら、その厚さはどれくらいになるだろうか。 答えを次の中から選びなさい。 ①教室の天井ぐらい(約3m) ②学校の屋上ぐらい . . . 本文を読む
パターン→人類が発見した最も強力な近道である。 計算→ややこしい問題も計算と記号を使えば簡単になる。 言語→手に負えない問題は違う言葉で考えよう。 幾何学→遠い場所への距離を現地まで行かずに測る。 図解→”百聞は一見に如かず” 微分→変化する世界を理解する。 データ→全部を調べなくとも全てが解る。 確率 . . . 本文を読む
「ナッシュJrの驚異(後半)」では、多様体の”埋め込み”理論について書きました。 リーマン多様体をユークリッド空間(曲率ゼロの3次元空間)の中へ等長に埋め込んだのが天才ナッシュJrです。が当時、このテーマは未解決問題の1つとされてました。 この理論の流れとしては、ガウスの曲率→リーマン多様体→ナッシュの埋め込みと、その時代を代表する天才たちの見事な連携 . . . 本文を読む
「神は数学者か」(マリオ・リビオ著)では、人間の純粋な思考の産物である筈の数学が何故、宇宙構造や自然現象、遺伝の法則や株価の挙動などを説明するのに見事なまでに役に立っているのかと訴える。 創造主(神)は数学を元にこの世界を創ったのか?それとも人間が数学を作ったのか? だとしたら、数学者は神様なのか?それとも神が数学者なのか? 数学の”不条理な有効性の謎”に迫るとも言えるこ . . . 本文を読む
珍しい事だが、「無限級数の闇と謎」の記事にアクセスが集まっていた。 現実の世界では、1+2+3+4+・・・は無限大に発散する筈だが、”総和法”と呼ばれるトリックを使えば、1+2+3+4+・・・=−1/12になるというのは、よく知られた事である。 カラクリを説明すれば、数列の和である級数が収束する様に部分和をとり、その極限を取る事で(発散する筈の)級数の収束値( . . . 本文を読む
ガウスと言えば、自ら”黄金の定理”と自画自賛した「平方剰余の相互法則」に代表される整数論や”驚異の定理”と呼ばれた「ガウス曲率」に代表される曲面論(微分幾何学)。それに、ケレス惑星の発見を導いた「最小二乗法」に代表される本職の天文学に、「ガウス分布」へと繋がる測地学や確率論。 更に実験物理学者としてのガウスの地位を広く知らしめたウェーバーとの共同研 . . . 本文を読む
「中盤」では、リーマン多様体や”埋め込み”理論の説明が不足し、最後は解りづらかったかと。 そこで今日はその補足版として、ガウスの驚異の定理からリーマンの多様体、そしてナッシュの(多様体の)埋め込み理論までの流れを追ってみたいと思います。 特に、曲率→多様体→埋め込みの流れは、そのままガウス→リーマン→ナッシュと見事に継承されています . . . 本文を読む
「前半」では長々と、ジョン・ナッシュJrのゲーム理論の基本について述べました。後半では展開ゲームと囚人のジレンマについて詳しく述べるつもりでしたが、(少し脱線して)果たしてナッシュ博士は”キチガイに陥ったのか?”を検証したいと思う。 「ビューティフル・マインド」のモデルとなったナッシュも例外じゃないが、多くの人は(天才と聞けば)彼が遺した実績(特に、ナッシュの&rdquo . . . 本文を読む