
一昨日の日曜日は、三男「りゅう」の通う特別支援学校の運動会だった。
一応、早朝から弁当も作った。
特支援学校の運動会、それも肢体不自由の学校の運動会は、世間一般で言う「運動会」とは、ちょっと雰囲気も内容も違う。
全体にゆったりしていて間合いも長く、保護者や先生方の参加する種目のみが、一般的な運動会種目みたいな慌ただしさやちょっとした対抗意識が感じられる程度。
こういうのに慣れてしまうと、もう、あのけたたましい「通常の」運動会には馴染めないなぁ・・・なんて思ってしまうくらい、心地良く余裕で参加できる。
そんな中で、子どもたち一人一人は精一杯「その子らしさ」を見せながら、周りの雰囲気を和ませ笑いを誘い、でも、本人は淡々と「練習した」ようにコトを進める。
なんとも言えない解放感。
生徒代表の終わりの挨拶だって、「おわります」の一言が、こんなにも楽しく味わい深く聞けるのだ。
「お」
・
・
・
「わ」
・
・
・
「り」
・
・
・
・
「ま」
・
・
・
「ま」
(「ええっ」という温かい笑い)
・
・
「す!」
って感じで。
なんでも、すぐに終わらない、終わらせない。
到達点よりもプロセスが大事(という場合ばかりではないけども・・・)。
余分なこと、派生すること、自然発生的なこと、予想外のこと・・・
みんな楽しみ味わう。
それは「普通」の運動会でも、そうか?
今年も、りゅうは、ポーカー・フェイスで、参加していた。
玉入れの玉を数える「い~ち、にぃ~、さぁ~ん・・・・」は、数字好きらしくニヤニヤ顔で聞いていた。
先生方の種目は高等部の先生がダントツで1位。
校長先生(実は同級生)の挨拶は、相変わらず彼らしく、ちょっと早口で、聴く人のことを考えすぎるくらい考えながら、誠実な雰囲気をいっぱいに出していた。
帰る前に寄宿舎に立ち寄り、紙パンツと尿パットを届け、夏服のチェックをしてきた。
帰宅後、ネットで吉田秀和さん逝去を知った。
写真は、昼休みに担任のN先生と戯れる「りゅう」
一応、早朝から弁当も作った。
特支援学校の運動会、それも肢体不自由の学校の運動会は、世間一般で言う「運動会」とは、ちょっと雰囲気も内容も違う。
全体にゆったりしていて間合いも長く、保護者や先生方の参加する種目のみが、一般的な運動会種目みたいな慌ただしさやちょっとした対抗意識が感じられる程度。
こういうのに慣れてしまうと、もう、あのけたたましい「通常の」運動会には馴染めないなぁ・・・なんて思ってしまうくらい、心地良く余裕で参加できる。
そんな中で、子どもたち一人一人は精一杯「その子らしさ」を見せながら、周りの雰囲気を和ませ笑いを誘い、でも、本人は淡々と「練習した」ようにコトを進める。
なんとも言えない解放感。
生徒代表の終わりの挨拶だって、「おわります」の一言が、こんなにも楽しく味わい深く聞けるのだ。
「お」
・
・
・
「わ」
・
・
・
「り」
・
・
・
・
「ま」
・
・
・
「ま」
(「ええっ」という温かい笑い)
・
・
「す!」
って感じで。
なんでも、すぐに終わらない、終わらせない。
到達点よりもプロセスが大事(という場合ばかりではないけども・・・)。
余分なこと、派生すること、自然発生的なこと、予想外のこと・・・
みんな楽しみ味わう。
それは「普通」の運動会でも、そうか?
今年も、りゅうは、ポーカー・フェイスで、参加していた。
玉入れの玉を数える「い~ち、にぃ~、さぁ~ん・・・・」は、数字好きらしくニヤニヤ顔で聞いていた。
先生方の種目は高等部の先生がダントツで1位。
校長先生(実は同級生)の挨拶は、相変わらず彼らしく、ちょっと早口で、聴く人のことを考えすぎるくらい考えながら、誠実な雰囲気をいっぱいに出していた。
帰る前に寄宿舎に立ち寄り、紙パンツと尿パットを届け、夏服のチェックをしてきた。
帰宅後、ネットで吉田秀和さん逝去を知った。
写真は、昼休みに担任のN先生と戯れる「りゅう」












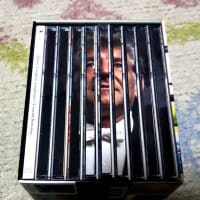

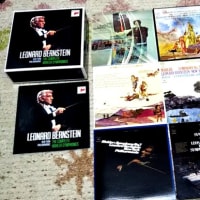
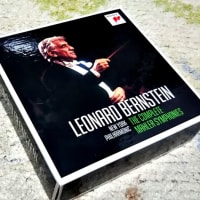

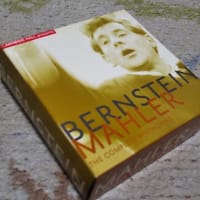

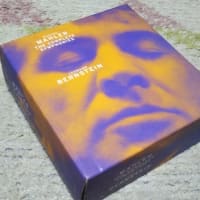

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます