
高速道路無料化実験がこの19日で終了だって。また、チンタラと国道を南下する日々が来るのか。まあ、それもいいのだけど、でも、あの山間部を一気に駆け抜ける爽快感はよかった。でも金払ってまで毎日走るほどでもないな。
ベートーヴェン/交響曲第8番
管弦楽:テレマン室内オーケストラ
指揮:延原武春
録音:2008年6月、大阪、いずみホール(ライヴ)
解説書に「クラシカル楽器による」とある。楽譜はベーレンライターではなくブライトコプフ版。そのせいか、音は古楽器味濃いが、聴こえてくる音符は昔なじみであり、ピリオド系あまり好きでない自分にとっても十分楽しめる演奏となっている。
テンポは速い。メトロノーム記号を遵守しているのかな?
とにかく第1楽章の冒頭から終楽章の最後まで、目を瞠っているうちに一気に聴き終えてしまう快活な演奏。喜びに溢れた演奏である。
金管の強奏にやや耳にきつい瞬間もあるがほとんど気にならず、逆に麗しい管のハーモニーに快感を憶える。第1楽章終結のムーディーな響きなどなかなかのもの。バロックティンパニの硬い音も程よくブレンドされて耳にやさしい。
津谷夏樹氏の解説に興味深いことが書かれていた。それによると第7も第8も、初演時は「大編成」(100人ほど)であったということ。そして、推測として「弦楽器にはアマチュアが参加し、強奏時には全員で、弱奏時には上位奏者のみで演奏するコンチェルト・グロッソ方式がとられた」ということだ。他ジャンルではあまり使用例のないfff(フォルテシシモ)やppp(ピアニシシモ)が多用されているのも、そういうことを裏付けるものだろうということだ。そして、延原氏は、「このダイナミックスを実現するために楽譜には無いコントラファゴットを加えている」。
日本のアーノンクール、ナニワのヴィンシャーマンと称される延原氏のアプローチは、ヘンにいじくりまわした感じの全く無い、すっきり活き活きモード全開の演奏であり、聴き終えたあとにもう一度最初から聴きたいと思わせる快感を伴っている。それを助長しているのが雰囲気たっぷりの録音であり、私は聖響さんのブラームスや(エイベックス以降の)ベートーヴェンも、こういう音で録っておればなぁ・・・と、つい思ってしまった。
彼は、1982年から「100人の第9」というのをやっている。オリジナル編成、オリジナル・テンポの取り組みとしては世界初であり、その演奏テープは、かつてガーディナーやホグウッドが参考にするために自国に持って帰ったりしていたという。

私は、一度だけナマでテレマン室内オーケストラを聴いた。
それは、ある小学校での「巡回公演」みたいなもの。浅井咲乃氏はじめ弦の主要メンバーとチェンバロの高田泰冶氏と共に、伊勢の地へやってきてくれたのだ。

ポピュラーなバロック名曲とストーロー笛のパフォーマンス(これ、最高!)、それに延原氏による絶妙なトークと楽器紹介によるものであったが、これがとてもよかった。よくアマチュア団体がやってくれる、同様な企画とは次元が違う面白さ、楽しさ、レヴェルの高さだった。
子どもたちを決して飽きさせないトーク。ちょっとでもざわつきがあると、「もう聴きたない?」と悪戯っぽく問いかけたり、ヴィヴァルディの「春」を、「これ、最初だけよく知られとるけど、そのあと、10分くらい続くねんで。がんばって聴いてみる?ムリやったらやめとくわ。」などと言われる。そうなると、当然「聴きたい」「聴きたい」の大合唱となる。
楽器紹介で奏でられた曲もパガニーニやバッハの無伴奏など、わずか数小節、数十秒の断片であっても、そのたびに会場中がうっとりとなった。
その小学校の生徒たちとのコラボもあったが、体育館がめったに味わえぬほどの一体感に包まれていた。

聴いている人みんなが音楽による「癒し」と「幸福感」に浸っていたと思う。まことにプロ集団であったと思う。今度は、ぜひ定期演奏会か「100人の第9」を聴いてみたいものだ。
ベートーヴェン/交響曲第8番
管弦楽:テレマン室内オーケストラ
指揮:延原武春
録音:2008年6月、大阪、いずみホール(ライヴ)
解説書に「クラシカル楽器による」とある。楽譜はベーレンライターではなくブライトコプフ版。そのせいか、音は古楽器味濃いが、聴こえてくる音符は昔なじみであり、ピリオド系あまり好きでない自分にとっても十分楽しめる演奏となっている。
テンポは速い。メトロノーム記号を遵守しているのかな?
とにかく第1楽章の冒頭から終楽章の最後まで、目を瞠っているうちに一気に聴き終えてしまう快活な演奏。喜びに溢れた演奏である。
金管の強奏にやや耳にきつい瞬間もあるがほとんど気にならず、逆に麗しい管のハーモニーに快感を憶える。第1楽章終結のムーディーな響きなどなかなかのもの。バロックティンパニの硬い音も程よくブレンドされて耳にやさしい。
津谷夏樹氏の解説に興味深いことが書かれていた。それによると第7も第8も、初演時は「大編成」(100人ほど)であったということ。そして、推測として「弦楽器にはアマチュアが参加し、強奏時には全員で、弱奏時には上位奏者のみで演奏するコンチェルト・グロッソ方式がとられた」ということだ。他ジャンルではあまり使用例のないfff(フォルテシシモ)やppp(ピアニシシモ)が多用されているのも、そういうことを裏付けるものだろうということだ。そして、延原氏は、「このダイナミックスを実現するために楽譜には無いコントラファゴットを加えている」。
日本のアーノンクール、ナニワのヴィンシャーマンと称される延原氏のアプローチは、ヘンにいじくりまわした感じの全く無い、すっきり活き活きモード全開の演奏であり、聴き終えたあとにもう一度最初から聴きたいと思わせる快感を伴っている。それを助長しているのが雰囲気たっぷりの録音であり、私は聖響さんのブラームスや(エイベックス以降の)ベートーヴェンも、こういう音で録っておればなぁ・・・と、つい思ってしまった。
彼は、1982年から「100人の第9」というのをやっている。オリジナル編成、オリジナル・テンポの取り組みとしては世界初であり、その演奏テープは、かつてガーディナーやホグウッドが参考にするために自国に持って帰ったりしていたという。

私は、一度だけナマでテレマン室内オーケストラを聴いた。
それは、ある小学校での「巡回公演」みたいなもの。浅井咲乃氏はじめ弦の主要メンバーとチェンバロの高田泰冶氏と共に、伊勢の地へやってきてくれたのだ。

ポピュラーなバロック名曲とストーロー笛のパフォーマンス(これ、最高!)、それに延原氏による絶妙なトークと楽器紹介によるものであったが、これがとてもよかった。よくアマチュア団体がやってくれる、同様な企画とは次元が違う面白さ、楽しさ、レヴェルの高さだった。
子どもたちを決して飽きさせないトーク。ちょっとでもざわつきがあると、「もう聴きたない?」と悪戯っぽく問いかけたり、ヴィヴァルディの「春」を、「これ、最初だけよく知られとるけど、そのあと、10分くらい続くねんで。がんばって聴いてみる?ムリやったらやめとくわ。」などと言われる。そうなると、当然「聴きたい」「聴きたい」の大合唱となる。
楽器紹介で奏でられた曲もパガニーニやバッハの無伴奏など、わずか数小節、数十秒の断片であっても、そのたびに会場中がうっとりとなった。
その小学校の生徒たちとのコラボもあったが、体育館がめったに味わえぬほどの一体感に包まれていた。

聴いている人みんなが音楽による「癒し」と「幸福感」に浸っていたと思う。まことにプロ集団であったと思う。今度は、ぜひ定期演奏会か「100人の第9」を聴いてみたいものだ。












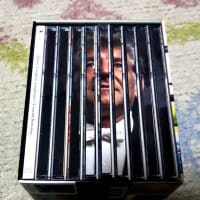

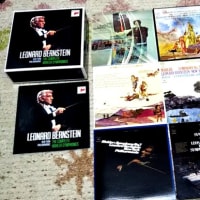
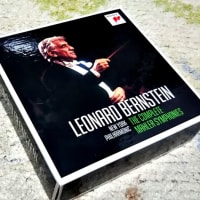

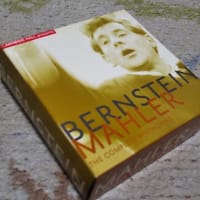

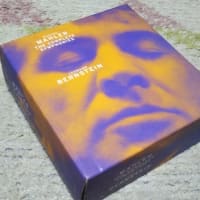

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます