今回の座禅は想像していたものと随分違いました。
お寺のようなところでやるものとばかり思っていましたが、普通の温泉宿の室内で畳の上です。部屋にはちゃんと暖房も入ります。私はかってにふきっさらしの板の間でやるものとばかり思い込んでいました。
座禅というと、ちょっとでもふらいついたり、妄想にふけっていると棒をもって見回っているお坊さんに背中を真っ赤になるまで叩かれるものとばかり思っていました。しかし、今回参加してみると、ずいぶん違っていました。座禅のおわりころになると順番に棒をもった人がまわりはじめます。なんと、うたれたくない人は、パスできるのです。強く打って欲しい人は合掌した手を高く挙げます。人によってはダウンを着込んでいる人もいるので、選べるようです。さらに学びになったのは、うたれても上手にたたかれるとほとんど痛くないということです。むしろ、座禅で体の感覚がこわばってしまっている筋肉をほぐしてくれて気持ちがいいのです。これは私のリフレームでした。もしかすると棒で叩くのは本当はこのため?
いつかテレビでみた激しい叩き方は、1、本来の凝りをほぐすという意味を忘れてしまって形式だけ間違って伝わっている、のか?2,実は見た目は痛そうだけど、叩かれている人は痛くない、のかもしれません。
じっさいに、ここで叩かれている音は木と木がぶつかりあうような激しい音ではあるので、はじめはビックリしました。
座禅も20分やっては40分の休憩をとる、といったサイクルです。
40分は元気があれば他の人と話をしていてもかまいませんし、寝たければ寝ていてもいいのです。また、もっと座禅を、という人は隣の部屋で休憩時間も座禅をくむことができます。
断食の方は、参加日から断食を始めます。前日の夕食は軽めにという指示があります。
私の場合は前日からほとんど何もたべませんでした。あまり食べる気がしなくなっていたということもあります。コーヒーばかり飲んでいました。夜にサラダだけを食べました。
2日目の昼には野菜ジュースがでますが、これが筆舌につくせぬ美味しさ!!!細胞にしみわたります。
3日目の昼に断食あけが始まります。
不思議と一度もおなかは空きませんでした。もともとお腹がすいていないときは食事をとらないようにしている生活だったのでなれていたのかもしれません。座禅中に食事の妄想はなかったし、食事の話をきいてもぜんぜん食欲がわいてこなかったのです。
3日目の昼に明けの食事をとります。
まず、250mlの水。
それから大根汁の汁だけと梅干し。
梅干しはたくさん取った方が宿便がよくとれるそうです。
もうこの2杯だけでお腹がいっぱいになってしまいました。
3日間でつらかったのはこの時間だけです。
食べることが逆に苦痛になっていました。
「周りのペースは気にせず、ゆっくり、ゆっくり食べていいから」などのアドバイスにしたがい、
大根汁をおかわりします。
ときどき、キャベツに味噌をつけてたべるのですが、なんと野菜の甘いこと。
ゆっくりと、ゆっくりと大根汁と梅干しをちびちび食べていたら、なんだかおなかが張ってきました。
きたかな? きたようです。
産まれる!
もうすでに食堂の大半の人はトイレとの往復が始まっています。
トイレにかけこむと、便意はあるものの、ぜんぜんでてきません。難産だなあ・・・
コロコロの固まり2つ程度で分娩停止中・・・
しかし。
しばらく頑張っていると、とつぜん5つ子くらいが産まれました。
3日間モノを食べていないのに君たちはいったいどこに隠れていたの?
(宿便は科学的根拠がないとされており内視鏡でも確認されないのですが、実際に目の前に産まれてくると、体のどこかにいたはずだろうと推測してしまいます。)
あとはびっくりするような大量の水がシャワーのようにとびだしてきました。
水に感じたのは、子どものころ、お腹をこわして下痢をしたときとそっくりだなあということでした。
もしかすると、子どもの下痢は治癒作用と同じなのかもしれません。
そこからは俄然、元気になりました。食欲が湧いてきました。
絶対無理だろうと思った、パンや果物も食べることができました。
もっとも、このあいだに4回くらいはトイレへの往復です。
平均して4、5回は往復するのが普通だそうです。
19回が記録だそうですが・・・
体はものすごく気持ちがいい。感覚が研ぎすまされ、野生な感じ。体が軽いのです。
体に良いなということが、明らかに感じとれます。
ちなみに体重は断食前後でほとんど変化なしでした。-250gあるかないか、程度です。
この断食法のベースは1700年前からインドに伝わる方法のようです。
まだまだ人間の体は謎が多いですね。
こうした経験知を宗教は上手にとりいれていますが、現代医学はまだ扱い方を知りません。
しかし、新しい分野を開拓してアップデートしていくのも現代医学は得意です。
漢方など、代替医療も分析されつつある時代です。
こうした絶食療法もとりいれられ、いつかは西洋医学、東洋医学、などなど、医学の知識・哲学的な派閥は一切なしで相互扶助型・患者中心型の医療乗り入れする時代を創っていきたいものです。(SUICAとPASMOだってお互いに乗り入れ可能なんですから(^o^))
お寺のようなところでやるものとばかり思っていましたが、普通の温泉宿の室内で畳の上です。部屋にはちゃんと暖房も入ります。私はかってにふきっさらしの板の間でやるものとばかり思い込んでいました。
座禅というと、ちょっとでもふらいついたり、妄想にふけっていると棒をもって見回っているお坊さんに背中を真っ赤になるまで叩かれるものとばかり思っていました。しかし、今回参加してみると、ずいぶん違っていました。座禅のおわりころになると順番に棒をもった人がまわりはじめます。なんと、うたれたくない人は、パスできるのです。強く打って欲しい人は合掌した手を高く挙げます。人によってはダウンを着込んでいる人もいるので、選べるようです。さらに学びになったのは、うたれても上手にたたかれるとほとんど痛くないということです。むしろ、座禅で体の感覚がこわばってしまっている筋肉をほぐしてくれて気持ちがいいのです。これは私のリフレームでした。もしかすると棒で叩くのは本当はこのため?
いつかテレビでみた激しい叩き方は、1、本来の凝りをほぐすという意味を忘れてしまって形式だけ間違って伝わっている、のか?2,実は見た目は痛そうだけど、叩かれている人は痛くない、のかもしれません。
じっさいに、ここで叩かれている音は木と木がぶつかりあうような激しい音ではあるので、はじめはビックリしました。
座禅も20分やっては40分の休憩をとる、といったサイクルです。
40分は元気があれば他の人と話をしていてもかまいませんし、寝たければ寝ていてもいいのです。また、もっと座禅を、という人は隣の部屋で休憩時間も座禅をくむことができます。
断食の方は、参加日から断食を始めます。前日の夕食は軽めにという指示があります。
私の場合は前日からほとんど何もたべませんでした。あまり食べる気がしなくなっていたということもあります。コーヒーばかり飲んでいました。夜にサラダだけを食べました。
2日目の昼には野菜ジュースがでますが、これが筆舌につくせぬ美味しさ!!!細胞にしみわたります。
3日目の昼に断食あけが始まります。
不思議と一度もおなかは空きませんでした。もともとお腹がすいていないときは食事をとらないようにしている生活だったのでなれていたのかもしれません。座禅中に食事の妄想はなかったし、食事の話をきいてもぜんぜん食欲がわいてこなかったのです。
3日目の昼に明けの食事をとります。
まず、250mlの水。
それから大根汁の汁だけと梅干し。
梅干しはたくさん取った方が宿便がよくとれるそうです。
もうこの2杯だけでお腹がいっぱいになってしまいました。
3日間でつらかったのはこの時間だけです。
食べることが逆に苦痛になっていました。
「周りのペースは気にせず、ゆっくり、ゆっくり食べていいから」などのアドバイスにしたがい、
大根汁をおかわりします。
ときどき、キャベツに味噌をつけてたべるのですが、なんと野菜の甘いこと。
ゆっくりと、ゆっくりと大根汁と梅干しをちびちび食べていたら、なんだかおなかが張ってきました。
きたかな? きたようです。
産まれる!
もうすでに食堂の大半の人はトイレとの往復が始まっています。
トイレにかけこむと、便意はあるものの、ぜんぜんでてきません。難産だなあ・・・
コロコロの固まり2つ程度で分娩停止中・・・
しかし。
しばらく頑張っていると、とつぜん5つ子くらいが産まれました。
3日間モノを食べていないのに君たちはいったいどこに隠れていたの?
(宿便は科学的根拠がないとされており内視鏡でも確認されないのですが、実際に目の前に産まれてくると、体のどこかにいたはずだろうと推測してしまいます。)
あとはびっくりするような大量の水がシャワーのようにとびだしてきました。
水に感じたのは、子どものころ、お腹をこわして下痢をしたときとそっくりだなあということでした。
もしかすると、子どもの下痢は治癒作用と同じなのかもしれません。
そこからは俄然、元気になりました。食欲が湧いてきました。
絶対無理だろうと思った、パンや果物も食べることができました。
もっとも、このあいだに4回くらいはトイレへの往復です。
平均して4、5回は往復するのが普通だそうです。
19回が記録だそうですが・・・
体はものすごく気持ちがいい。感覚が研ぎすまされ、野生な感じ。体が軽いのです。
体に良いなということが、明らかに感じとれます。
ちなみに体重は断食前後でほとんど変化なしでした。-250gあるかないか、程度です。
この断食法のベースは1700年前からインドに伝わる方法のようです。
まだまだ人間の体は謎が多いですね。
こうした経験知を宗教は上手にとりいれていますが、現代医学はまだ扱い方を知りません。
しかし、新しい分野を開拓してアップデートしていくのも現代医学は得意です。
漢方など、代替医療も分析されつつある時代です。
こうした絶食療法もとりいれられ、いつかは西洋医学、東洋医学、などなど、医学の知識・哲学的な派閥は一切なしで相互扶助型・患者中心型の医療乗り入れする時代を創っていきたいものです。(SUICAとPASMOだってお互いに乗り入れ可能なんですから(^o^))

















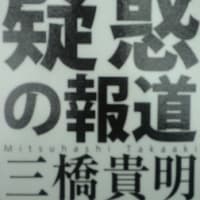
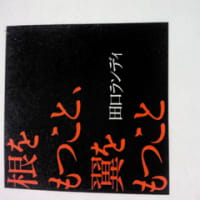

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます