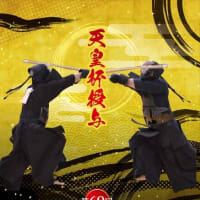今日も一日奈良の家にいました。
江戸時代の紙幣(今の1000円札、1万円札のような紙のお金)が出てきたので記事にしました。

左の2枚(左が表、右が裏)は大阪で一番の両替商「鴻池屋」の発行した藩札(はんさつ)、右の2枚(左が表、右が裏)は和州宇田(奈良県宇田)の吉野屋の発行した藩札です。
どちらも銀札といって、札に明記された銀と交換ができる、つまり兌換紙幣(だかんしへい)のようなものです。
左の札は銀十匁(ぎんじゅうもんめ)、右の札は銀一匁と交換ができるお札です。
※両替商は今の銀行のこと。 ※銀一匁は今の1500円くらいかな。
こういった藩札は各藩が許可した両替商が発行しました。
で、鴻池屋は両替の相場を幕府から任された十人両替(じゅうにんりょうがえ:幕府が認めた大阪の両替商10人で構成される組織)の中で最も大きな両替商でした。ちょっとした大名が束になってもかなわないくらいの資金力が有り、江戸後期には日本の藩の3分の1が鴻池屋からお金を借りていたとのことです。とんでもないお金持ちだったようですね。
※他の大きな両替商は…:大阪では加賀屋、天王寺屋など、江戸には三井、住友がありましたが、大阪に比べ規模はかなり小さかったようです。
江戸時代のお札と両替商について書きましたが、以前書いた➡銀行の地図記号も読んでもらえると面白いと思います。是非~
江戸時代の紙幣(今の1000円札、1万円札のような紙のお金)が出てきたので記事にしました。

左の2枚(左が表、右が裏)は大阪で一番の両替商「鴻池屋」の発行した藩札(はんさつ)、右の2枚(左が表、右が裏)は和州宇田(奈良県宇田)の吉野屋の発行した藩札です。
どちらも銀札といって、札に明記された銀と交換ができる、つまり兌換紙幣(だかんしへい)のようなものです。
左の札は銀十匁(ぎんじゅうもんめ)、右の札は銀一匁と交換ができるお札です。
※両替商は今の銀行のこと。 ※銀一匁は今の1500円くらいかな。
こういった藩札は各藩が許可した両替商が発行しました。
で、鴻池屋は両替の相場を幕府から任された十人両替(じゅうにんりょうがえ:幕府が認めた大阪の両替商10人で構成される組織)の中で最も大きな両替商でした。ちょっとした大名が束になってもかなわないくらいの資金力が有り、江戸後期には日本の藩の3分の1が鴻池屋からお金を借りていたとのことです。とんでもないお金持ちだったようですね。
※他の大きな両替商は…:大阪では加賀屋、天王寺屋など、江戸には三井、住友がありましたが、大阪に比べ規模はかなり小さかったようです。
江戸時代のお札と両替商について書きましたが、以前書いた➡銀行の地図記号も読んでもらえると面白いと思います。是非~