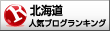野良猫みたいな男だから、気が変わったらふらっと、またどこかに出て行くはずだ。
今のところはおとなしく、わしの仕事を手伝ってくれている。
めし付き家(やさ)付き給料ナシで、お互い満足している。名前は岸元高志、ワルではない。
見掛けとは違い学もあるし紳士だ」
「ユニークな人なのね、小父さんの紹介の仕方のせいかも知れないけれど。でも見掛けだって素
敵な人に見えます。とても野良猫には見えません。
私のことはもう聞いているかも知れませんが、この家の娘で影山あやです」
あやは動じぬ視線を高志に投げた。
彼女のその言葉で3人はようやく、玄関口の立ち話しを切り上げて部屋の中に入った。
あやの足は三和土で佇み、居間で正座をし、流し場で井戸ポンプを漕ぎ、それからそっと襖を開
けて次の間に入り、最後の奥の間に辿り着くまでに10分以上を要した。
その間、鉄さんはストーブに火を入れ、高志は茶を入れる支度を整えた。
ようやく彼女が戻った時には、既に湯は沸き茶は淹れられていた。
卓袱台に着いた彼女は沈黙のまま茶をすすり、深く息を吐きようように、口を開いた。
「カレンダーはあの日のままだったのね。
何も変わっていない。時間が止まっていたみたい。私はずっとここにいたんだわ。
ねぇ鉄小父さん、私暫くここにいていいかしら」
鉄五郎はさして驚いた顔も見せずに言った。
「もちろん、いいに決まっているさ。ここはあやの家だ。わしは留守番をしているだけだから、
気の済むまでいたらいい」