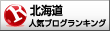それがあやの心を落ち着かせた。
しかしその直後に思いがけない激しい言葉が彼女を襲った。
「お姉ちゃんどうしてよ!」
マフラーを胸元で握った千恵の、まつ毛の長い黒い大きな眼から、みるみるうちに涙が溢れた。
「どうしてよ、私達が何か悪いことをしたの」
あやの息が詰まり、足元がぐらつくのを覚えた。言葉は一言も出てこない。
わずかに「ああっ」とも「ううっ」ともつかない呻きが漏れた。
「葉書きの一枚ぐらいくれてもいいじゃない」千恵は流れる涙を拭おうともせずに言った。
「ごめん、忘れていた訳じゃないの。赦して」
うろたえながらそれだけを言うのが、やっとだった。
言って仕舞うとあやは、しばし途方にくれ力が抜けていくのを覚えた。
「いったい自分は何をやってきたのだろう」
戸惑いと脱力感と慙悸の思いがごっちゃになって、胸の奥から湧き上がってきた。
「千恵、そんな風に言うものじゃないわ。あやお姉ちゃんがどんなに大変だったかなんて、私達
何も分からないんだから、お姉ちゃんが本当に私達のことを忘れる訳はないんだから。忘れていな
いからこそ便りを出せないってことだってあるでしょう。お前だって今にそうゆうこと分かるわ」
なだめるように言った清子の声も震えていた。
あやは今更ながら、ここに置き去りにした時間が消えず色褪せもせずに息づいていたことを知っ
た。生生しく甦る記憶の数々が、あやを襲いたじろがせた。
突然の出会いの中で互いにどんな言葉を交わし合ったのかも分からず、平静さを取り戻す間もな
いままに、結局あやは自分にとってはこの地のもう一つの家族の家を訪ねることになった。