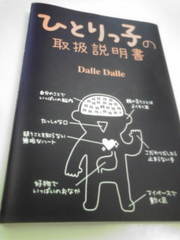先週の金曜日、美容院で髪を染めているときに読了。
約20年ぶりの竜馬だった。なぜか竜馬を読んだのが私は遅い。初回は27、8才で読んだ。
本来なら10代で出会いたかった本だ。
20代後半の読後感は、もっと早く読めば良かった、私には、もう志すという若さはない、と感じた。
今回は、残りの人生、まだ志すことはできるのではないか、という気になった。
眠っていた肉食性格が目覚めたような。
でも、若かったね、竜馬。若すぎたね。美容院の大きな鏡を前にして涙がつたいそうだった。
約20年ぶりの竜馬だった。なぜか竜馬を読んだのが私は遅い。初回は27、8才で読んだ。
本来なら10代で出会いたかった本だ。
20代後半の読後感は、もっと早く読めば良かった、私には、もう志すという若さはない、と感じた。
今回は、残りの人生、まだ志すことはできるのではないか、という気になった。
眠っていた肉食性格が目覚めたような。
でも、若かったね、竜馬。若すぎたね。美容院の大きな鏡を前にして涙がつたいそうだった。