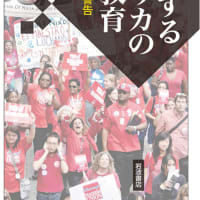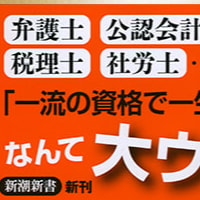「崩壊する日本の公教育」(2024鈴木大樹著)を読んだ。最近の教育に関する本としては最も共感し、驚きをもって勉強になった一冊である。
★「お客様を教育しなければならない」<つまり、「お客様」と化した生徒や保護者の要望に応えつつも、教育機関として生徒児童を指導しなければならない学校>この難解なジレンマ! このフレーズに、「思わず膝を叩く」想いがした。
現在、小学校を中心に先生のなり手が減少し、先生不足が深刻化している。また、せっかく教職試験に合格しても辞退する若者が急増しているそうである。
私の個人的な印象として、先生になりたくない理由は、長時間労働や給料の問題ではなく、モンスターペアレンツに代表する保護者との軋轢だと思っていた。また、そういう親を見た子供が、手出しできない教師をばかにする環境、教育実習などでみる手出しのできない無力で委縮した教師像に幻滅、そうやって教師をあきらめた若者が多いと思っていた。
現実には、そのことを含めて、政府による「新自由主義」的な教育改革が根本にあることを知った。著者は、自らが体験したアメリカの1980年代から90年代に進められた「新自由主義的な教育改革」が悲惨な結果を残しているにも関わらず、その失敗を日本が後追いし、現在、日本の教育が瀕死の状態にしていると述べている。
この「新自由主義的」という言葉がこの本で一つのキーワードになっている。「新自由主義」の主な特徴を調べてみると、
- 小さな政府: 政府の役割を最小限に抑え、規制緩和や民営化を推進
- 市場原理の重視: 市場の自由な競争を促進し、資源配分の効率化を目指す。
- 個人の責任: 個人の自己責任を強調し、社会福祉の縮小を主張する傾向がある。
- グローバル化の推進: 国境を越えた自由な貿易や投資を促進。
さらに、「新自由主義的教育」について調べてみると
- 教育の市場化: 学校間競争を促進し、教育サービスを市場原理に委ねる。
- 選択の自由の重視: 生徒や保護者の学校選択の自由を拡大する。
- 成果主義の導入: 教員の評価や学校運営において、学力テストなどの成果を重視する。
- 教育への公的支出の抑制: 教育予算を削減し、私立学校の役割を拡大する。
- 職業訓練の重視: 実践的な職業訓練を重視し、即戦力となる人材育成を目指す。
良いことだらけのようであるが、要するに学校を「塾化」させ、目に見える結果を出させる手段としての教育である。しかし、本来の「教育」、「子供を育てる」ということが、それでいいのか、また、その結果が現在どのような教育現場の風景となっているのかをこの本では警鐘している。
さて、お客様である生徒に遠慮する学校と教員は、失われた尊厳をどうやってとりもどすのか。
新自由主義的教育の解決策として、
1) サービス業に徹する。効率重視、マニュアル化、点数主義。見える結果のために働く。一定の効果を上げれば、だれからも文句が来ない。進学塾の在り方へ。
2)「ゼロトレランス」の名のもとに生徒指導をマニュアル化し、機械的に問題児を排除していく方向。「ゼロトレランス」とは、大きな秩序の乱れを引き起こさないよう、例えどんなに些細な学校規律からの逸脱段階で許さない厳格な制度指導方針のことである。極論を言えば、問題児は「別室指導」で、さらには、警察等関係機関との連携という名の引き渡し、つまり、排除する。アメリカでのゼロトレランスの実践では、拳銃所持やナイフ所持にいたらない小さな問題児も徹底的に排除し、学校も教師もそこに最大限の結果を出そうとする。しかし、ゼロトレランスによる生徒指導のマニュアル化や警察へのアウトソーシングが、教育であろうか、どこか、監獄のような息苦しさを感じさせる。それゆえ、多くの教師たちは、それが、教育なのだろうかという疑問に立ち止まり、苦しみ、落胆する。教育をあきらめる。教師をあきらめる。アメリカでは、公教育が破綻している。その破綻を日本が今追いかけている。

★人が人でなくなっていく教育現場
教師の体罰から子供たちを守るための行き過ぎた抑止の結果が、そんなものよりずっと恐ろしい、耐え難い傷を生徒たちに背負わせることになった。
つまり、教師たちは、「やんちゃな子」に対して、抑止力を失っている状態で、野放しにされた彼らにとって学校という環境が天国となる。やりたい放題になる。小学校では、まだ、「かわいい」らしいが、中学生になると、6年間やりたい放題の不良少年たちは、「性」も含めて、どれだけ同級生をいたぶっても自分たちに危害が及ばないことを知っているため、躊躇なく抵抗のできない生徒をおもちゃのように扱っていく。
個人的に学童の管理者から聞いた話であるが、小学校4年生の悪ガキが、指導員の指導に対して、「なら、殴ってみろ!殴ったら、お前をこの仕事から辞めさせるぞ!」と叫ぶ。指導員たちは、そうやって「おこり」もしなくなり、対応は管理者に任せ、管理者が怒るという繰り返しだそうである。
これも、個人的な経験だが、ある塾の教室で、なかなか英語の学力が伸びない中1生がいた。よく𠮟ることもあったが、学校の点数が、ぐっと伸び、「やったね!」と肩を叩いたら、「何触ってるんだ」という目でにらめ返してきた。数日後、親が、教室をやめると伝えてきた。塾では、「やめる」という手段があるので、尾を引くことはあまりないが、学校では、そうはいかないと想像する。
故に無法地帯と化した教室に平和を取り戻すためには、「ゼロトレランス」による生徒指導のマニュアルと警察による外部委託となるのであろう。
そこにある教室の平和は、あまりに冷たく、「『現場から心がなくなっていく』を通り越して、人が人でなくなっていく」ことになる。教師たちは、「働き方改革」で、給料を上げたり、長時間労働を是正したり、部活や残業を減らすことで教師としての「人」を手に入れるわけでないだろう。

★「教師という仕事が私を去っていった」
「教育現場から、創造性、イノベーションや学問の自由が失われていった。効率化の名の下に、教材も、アクティビティまでもが教育委員会が採択したパッケージで教師に配布されるようになり、教師によるオリジナルなテストは消え、生徒の評価は、数値化されくことで教師の手を離れていった。」教師の仕事は確実に減るであろう。だが、公教育として、それでいいのであろうか。
塾も同じような進化を遂げている。もう、教師は要らないので、教室と生徒・学生を管理するチューターがいるだけである。黙々とディスプレイの前で勉強する。「わからない」ので質問すると、「その科目のこの番号の講座をもう一度見なさい、1.5倍速で」などとなる。そこには、人と人の温かさはない。また、チューターという管理者(バイトの大学生の場合も多い)に「教える」経験はいらない。もし、これが、公教育の理想としたら、背筋が凍る。「ひと」がいない。「教師の本当の仕事」がない。
「教育とは、バケツを満たすことではなく、心に火をつけること」
日本の教育の現状を知るためには、多くの人に読んでもらいたい本である。

<ちょっと一言>
もう一点、個人的に思うことなのだが、この本では、「塾化」という点数主義、商業主義、マニュアル化などが批判される。多くの塾がその点は基本としながらも、教育には理想をもって子供たちと接して塾も多い。子供たちも、学校では、味わえない講師や塾生たちとの教育現場的な触れ合いを求め、通塾している。塾が好きだ、塾に行くのが楽しいという塾生は、そういう教えの場を求め、また、生き生きと授業を聞き、講師との、また、塾生同士でのワイワイと過ごしている環境を楽しく学んでいる。教室のあるべき姿がそこにある。(私の教室にはあった。)