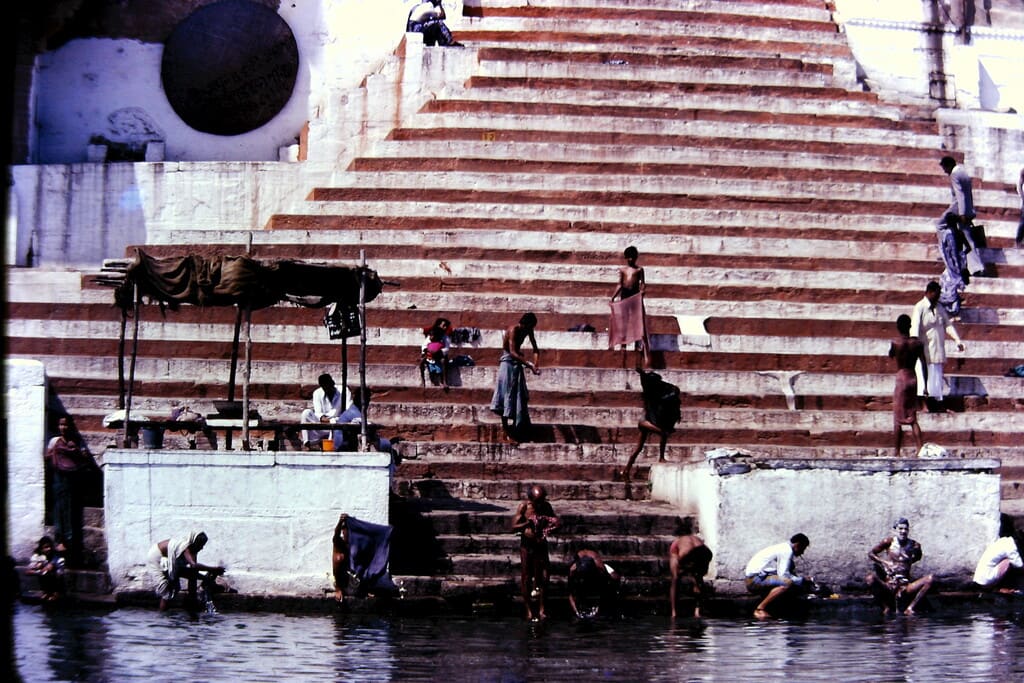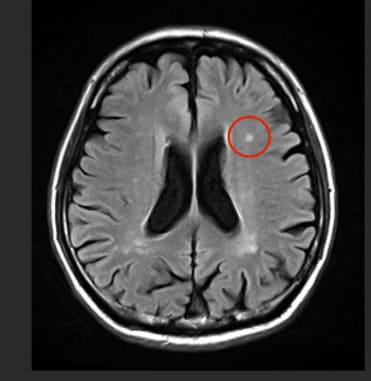妻が旧友と新年のお茶会へと小倉の繁華街へ赴く。次の日、悪寒のため仕事から早退、翌日発熱、かかりつけ医に受診する。インフルエンザA型と診断され、袋状の薬、イナビルをもらう。一回だけの吸入服用でおしまいという簡単便利な薬であった。

何度か高熱のため解熱剤を飲み、咳止めも多く服薬した。それから3日、ゆっくりと回復にむかった。その日の夜に今度は私が、悪寒におそわれる。うつされたか? とにかく眠ることにした。夜8時ころ床に就き、次の日の10時ころに目を覚ました。よく寝た。しかし、熱は38度前後あり、病院受診を決意する。かかりつけ医に電話すると発熱外来の予約はいっぱいであると告げられる。今日は、土曜日。午前中のみの受付か。妻のかかりつけ医の病院も予約をのぞくといっぱいであった。それでは、予約の要らない中規模病院の受診を考えたが、2時間も3時間も待たされるなら、それだけで病状悪化しそうなので、受診をやめて、自然治癒にかけることした。明日が日曜日で次の日が成人の日という祝日で火曜日まで待つのなら、回復しているかもしれないという淡い希望にかけてみた。ネットでもインフルは、り患してから2日以内に薬を飲むこで症状が和らぐとあり、病院にかかることで1日か2日回復が早まるとあった。もし症状が悪化したら救急車で搬送してもらおう。その可能性は少ないと思うけれども。娘の話によると、年末に孫の具合が悪くなり休日診療の小児科を受信しようとしたら4時間待ちと知らされて受診をあきらめたそうである。本当に具合が悪いのなら救急車でなければ受診さえもしてもらえないかもしれない、それが現実かもしれない。

軽く昼食をとって寝た。夕刻8時に目を覚ました。1日で20時間も寝たことになる。夕食を食べて、また、横になる。そんなに眠れるものなのかと思いつつ、また寝入ってしまった。起きると10時間寝ていた。2日で30時間寝たことになる。 体温は、37度台をあがったり下がったり、咳が時々出たり、鼻水も多少でそんなに深刻ではなかった。さらにまた寝る。午前中に2時間、午後から3時間と細切れだが、よく寝れる。
驚いたのは、あまりに長時間寝ていたので体が硬直して、足がのばせない状況におちいったことだ。いわゆる「拘縮」状態になった。自分で足をのばそうにも伸ばせない。足首を曲げようにもうまくいかない。「こうやって人は死んでいくのか」とついオーバーに思ってしまったが、渾身の力で足を延ばし、足を動かした。
ある記事で「1日安静にしていて失われた筋肉を回復するには約1週間、1週間の安静なら約1か月の回復期間が必要だ」「80代の高齢者は、1週間の入院で寝たきりになる」という記事を読んだ。恐ろしい。
3日間、昼も夜も寝て過ごし、3日目の夜は、さすがに寝つきが悪く、3時間ほど寝られない時間が過ぎた。寝られないかと思ったらまた、8時間ほど寝てしまい、起き上がった。熱を測ると36度7分、熱も下がり、回復した感じを体から受け取った。
TVでは、毎日インフル関連の番組やニュースをやっていたが、一番驚いたのは、あるクリニックでは、受診にファーストパスの制度を取り入れていたということである。お金を払えば、30分程度で受信できるというディズニーランドのファーストパスのような制度である。ディズニーも廃止したこの制度を医療の場で取り入れているのに違和感を覚えるというよりも怒りを感じてしまった。その番組では、ファーストパスを使っても1時間待たされたと言っていた。利用者がそれだけ多かったということだろうが、お金のない普通の人々はいったいどれほどの時間を待ったことであろうか。ひどいクリニックだ、そして、ひどい時代になったものだ。
さて、結局5日目で熱が下がりあと2日で感染させるリスクもなくなるらしい。これでよかったのだどうかわからないが、とにかく闘病終了である。
なんか、みんなに「ありがとう」と言いたくなってしまった。